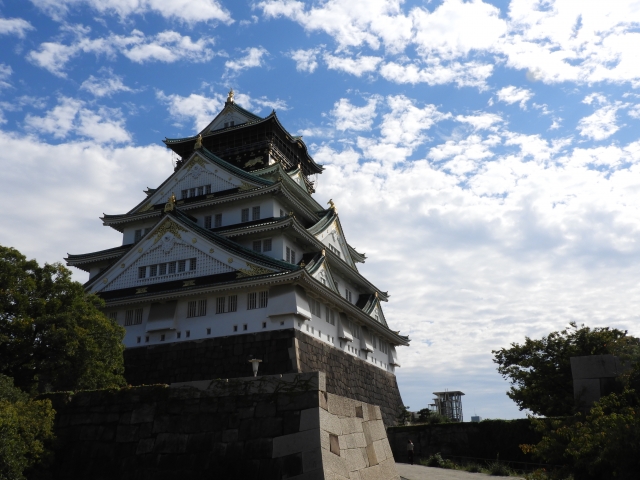鳴り響く武名
天皇方として兵をあげた正成は、500の手勢で赤坂の城にこもり、押し寄せた幕府の大軍を迎え撃つ。敵勢は30万とされているが、せいぜい数万と見るのが妥当。それでも100倍ほどの開きがある。「太平記」では、大石や熱湯を見舞うなど「三国志」顔負けの奇計を駆使したことになっているが、これは軍記ものによくあるパターンで、おそらく創作と見ていい。
とはいえ、これほどの兵力差がありながら数日にわたって城を持ちこたえたのは事実で、敵味方に楠木正成の名が知れ渡った。落城後は1年ほど行方をくらましたのち、再度挙兵。軍事の才にめぐまれていたのは間違いないようで、各地で幕府軍を翻弄した。笠置山が落ち、隠岐島(島根県)へ流されていた後醍醐の脱出に呼応するかたちで、こんどは同じ河内の千早城へ籠る。ここで3か月ものあいだ幕府軍と渡り合っているうちに、足利尊氏(当時は高氏)や新田義貞らおもだった御家人たちが寝返り、ついに鎌倉幕府は滅亡(1333)。正成は、都へもどる天皇の行列を先導するという栄誉を得たのだった。
みじかくも美しく燃え
こうして後醍醐の念願かない天皇親政の世が到来したものの、「建武の新政」とよばれるこの時代は、わずか3年しかつづかなかった。公家を中心とする体制に武士の不満が鬱積し、それに担がれるようにして足利尊氏が朝廷へ反旗をひるがえしたのである。このとき立ちふさがったのが正成で、鎌倉から京へ攻めのぼった足利方を撃退、尊氏たちは九州へ落ち延びることとなった。
おどろくのは、このとき、正成が朝廷に和議を説いたことである。尊氏はかならず再起してくるから、今のうちに関係を修復したほうがよいというのだ。相手のおそろしさを十分にわかっていたのだろうが、ふつう勝ちいくさの直後に言えることではない。まことに慧眼というほかなく、この一事をもってしても正成の非凡さがわかる。
だが、不幸にもというべきか必然的にというべきか、後醍醐方におなじような具眼の士はおらず、進言は容れられなかった。予想通り、九州で勢いを盛り返し攻め上ってきた足利方と激突したのが、名高い「湊川の戦い」(1336)。このときも正成は、一度都を捨て、敵方が入京したところで包囲するという策を献じたが、やはり採用されず、湊川(兵庫県)で激戦のすえ、戦死する。息子・正行(まさつら)との別離(「桜井の別れ」)、弟・正季(まさすえ)と、「七生報国」(七たび生まれ変わって国に尽くす)を誓い合っての自害など、よく知られたエピソードはこの時のものである。これらはそのまま事実とすることはできないが、日本史上、屈指の名場面と言っていい。いっぽう尊氏は正成の死を悼み、勇士として称賛を惜しまなかったとされる。これは、足利方の視点で書かれた「梅松論」という書物に記されている話だから、敵味方問わず正成の評価が高かった証左となるだろう。
戦前、「忠君愛国」の象徴とされていた反動か、現在の日本史は、どこか楠木正成という存在を扱いかねているように見える。が、筆者が彼の生き方を振りかえって感じるのは、忠や義といった理念ではなく、ひとりの人間として揺らぐことなき美しさである。正成が歴史の表舞台で活躍したのは、わずか5年。それでいて、これほどの足跡を残したのだから、感嘆するほかない。いま一度、光が当てられてしかるべき人物と思えてならないのである。
文/砂原浩太朗(すなはら・こうたろう)
小説家。1969年生まれ、兵庫県神戸市出身。早稲田大学第一文学部卒業。出版社勤務を経て、フリーのライター・編集・校正者に。2016年、「いのちがけ」で第2回「決戦!小説大賞」を受賞。著書に受賞作を第一章とする長編『いのちがけ 加賀百万石の礎』、共著『決戦!桶狭間』、『決戦!設楽原(したらがはら)』(いずれも講談社)がある。

『いのちがけ 加賀百万石の礎』(砂原浩太朗著、講談社)