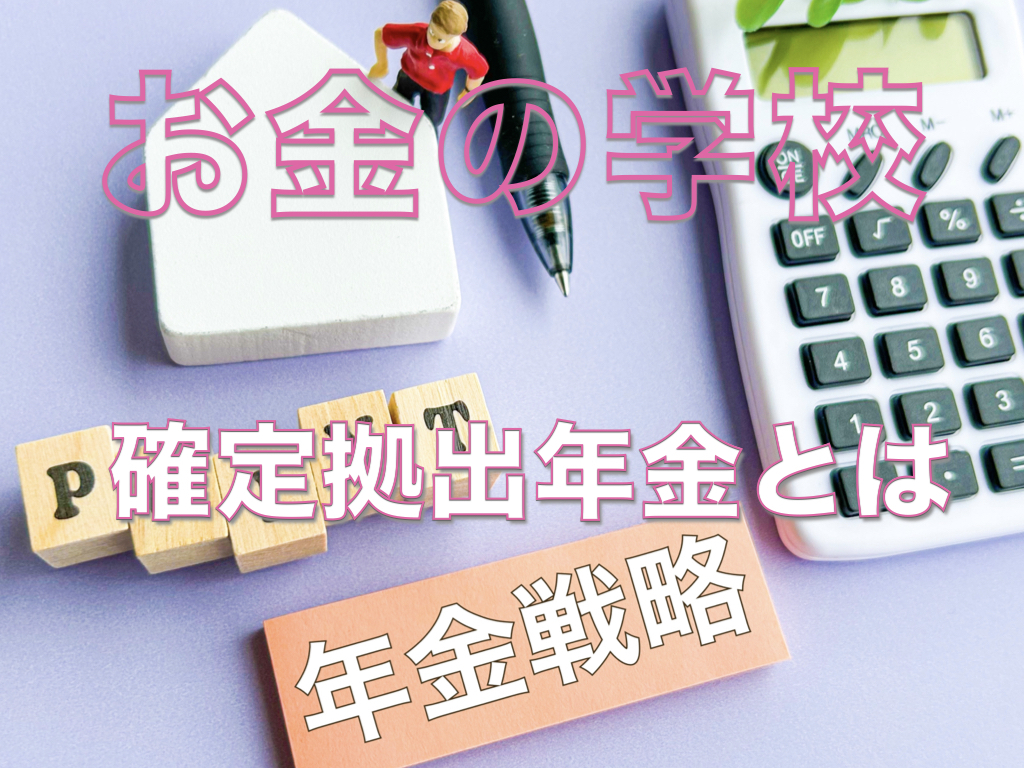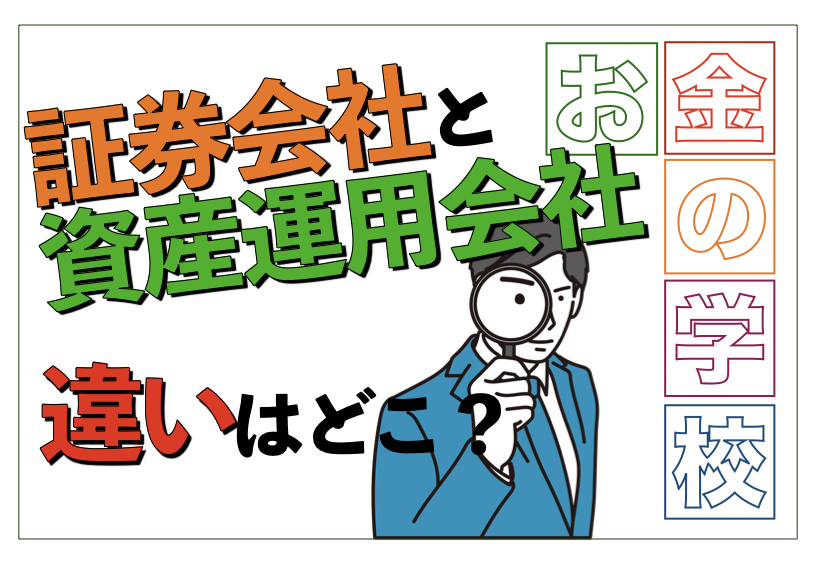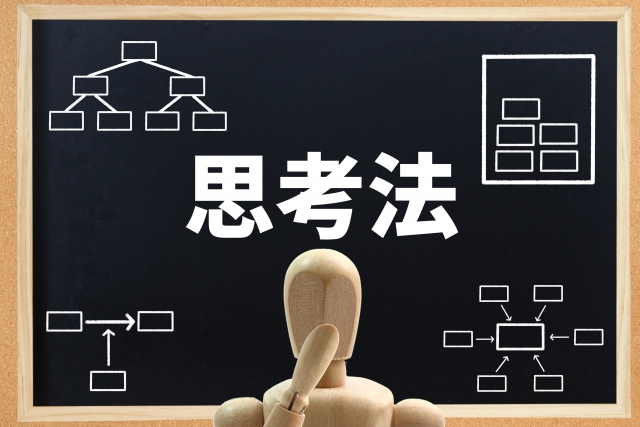超高齢化社会の日本では「介護」は多くの人にとって避けては通れないこととなっています。特に高齢の親や家族がいると「介護施設選び」や「介護費用」などに不安を感じる人も多いのではないでしょうか?
今回は、介護保険施設の仕組みや種類、費用、申請手続きまで、知っておきたい基礎知識について見ていきましょう。100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、ライフブック(R)を提唱する、独立系ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。
目次
介護保険施設とは? 仕組みと種類をわかりやすく解説
費用はいくらかかる? 介護保険施設の自己負担と補助制度
施設の種類と特徴を比較! どれを選べばいいか迷ったら
介護保険施設入所の流れと必要な準備
施設入所で知っておくべきトラブル防止ポイント
まとめ
介護保険施設とは? 仕組みと種類をわかりやすく解説
介護保険施設とは、公的な介護保険制度に基づいて提供される介護サービスを受けるための施設です。介護が必要な高齢者が安心して生活できるように、国や自治体が支援する仕組みになっています。介護保険施設は、費用の一部が介護保険から給付されるのが特徴です。
介護保険施設と民間施設の違いとは?
民間施設(有料老人ホームなど)は民間の企業が独自に運営しており、サービス内容や料金は施設ごとに異なります。一方で、介護保険施設は、介護保険法に基づく施設で、サービスの質や費用負担の仕組みが制度化されています。そのため、民間施設に比べて費用が抑えられる傾向があります。
介護保険施設は3つのサービスに分かれている
介護保険施設には、大きく分けて以下の3種類のサービスがあります。
1.特別養護老人ホーム(特養)
長期間にわたり介護が必要な高齢者向けの施設で、生活全般の支援を受けながら暮らすことができます。
2.介護老人保健施設(老健)
病院と在宅療養の中間的な位置づけの施設で、リハビリテーションや医療ケアを重視しています。基本的に在宅での生活に復帰することを前提としています。
3.介護療養型医療施設
医療的ケアが必要な要介護者向けの施設です。長期療養を目的とした医療体制が整っていることが特徴です。

介護保険施設を利用できる人の条件は? 要介護度との関係
介護保険施設を利用するには、「要介護認定」を受けている必要があります。利用可能な介護度は施設ごとに異なります。例えば、特養では原則として「要介護3」以上の認定が必要です。老健や療養型医療施設も「要介護1」以上が目安となっています。
費用はいくらかかる? 介護保険施設の自己負担と補助制度
介護保険施設は公的支援があるとはいえ、利用者にも一定の自己負担が求められます。では、その費用はどのように決まるのかを見ていきましょう。
1割〜3割の負担割合の決まり方とは?
介護保険サービスの自己負担割合は、所得に応じて1割、2割、3割のいずれかに設定されます。多くの人は1割負担ですが、一定以上の所得がある人は2割または3割負担となります。これは市町村が発行する「負担割合証」で確認できます。
「食費・居住費」はどう計算される?
介護保険が適用されるのは「介護サービス費」のみで、施設での食費や居住費(部屋代)は自己負担となります。これらの費用は施設の種類や地域、部屋のタイプ(個室・多床室)によって異なり、1日あたり数百円〜数千円の差が出ることもあります。
限度額認定制度や減免制度で負担を軽くできる?
所得が少ない人は「介護保険負担限度額認定制度」を利用することで、食費や居住費の負担が軽減されます。この制度を利用するには、市区町村の窓口での申請と「認定証」の取得が必要です。また、災害や生活困窮などの特別な事情がある場合には、さらに減免制度が適用されることもあります。
施設の種類と特徴を比較! どれを選べばいいか迷ったら
介護施設は多種多様で、それぞれに特徴や目的があります。入所者の介護状態や家庭の状況に応じて、入居する人に合った施設を選ぶことが大切です。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の特徴
特養は、身体的・精神的に要介護度の高い状態にある高齢者が、生涯にわたって入所できる施設です。費用も比較的安価で、入居待機者が多いのが現状です。医療的ケアが日常的に必要な重い病気がある場合は不向きです。
介護老人保健施設の役割とは?
老健は、病院を退院した後のリハビリテーションや、在宅生活への復帰を目指すための中間的な施設です。リハビリ専門のスタッフや医師が常駐しており、在宅生活への橋渡し的な役割を果たします。基本的には短期利用が前提になります。
介護療養型医療施設はどんな人向け?
療養型施設は、医療的ケアが日常的に必要な人に向いています。慢性疾患のある高齢者や、終末期医療が必要なケースが適しています。2024年度以降、介護医療院への移行が進められており、施設選びの際は最新情報を確認しましょう。
地域密着型施設やグループホームとの違いも解説
地域密着型施設(小規模多機能型居宅介護など)や認知症対応型グループホームは、要介護者が地域で自立した生活を続けるための支援を目的としています。少人数制で家庭的な雰囲気があり、スタッフも顔なじみになるなど、アットホームなケアが特徴です。
介護保険施設入所の流れと必要な準備
介護保険施設に入所するには、いくつかのステップを踏む必要があります。スムーズな入所のためにも、事前の準備が欠かせません。
要介護認定の申請から入所までのステップ
要介護認定の申請から入所までのおおまかなステップは、以下の通りです。
1.要介護認定の申請(市町村に申請)
2.認定調査・主治医意見書の提出
3.介護度の決定(審査会)
4.施設見学・申し込み
5.面談・契約・入所
入所を希望する場合、早めに動き出すことで希望に合った施設に入れる可能性が高まります。
必要な書類と窓口はどこ?
要介護認定の申請は、本人または家族が市町村の介護保険課などの窓口で行なうケースや、地域包括支援センターの支援を受けて申請するケースがあります。必要書類には「介護保険被保険者証」「印鑑」「申請書」などが含まれます。施設入所の際には、健康診断書や収入証明なども求められることがあります。
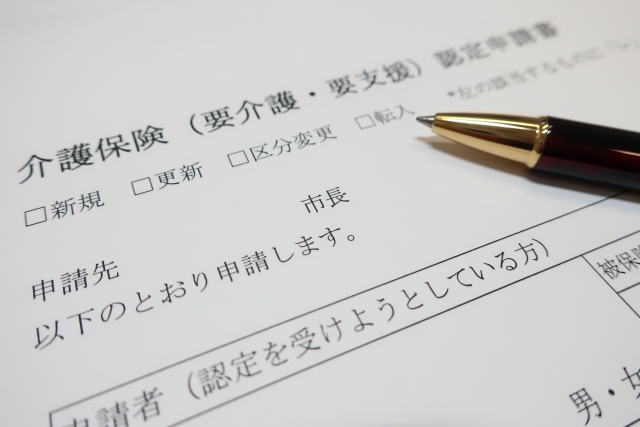
「要介護認定」が通るために知っておくべきこと
要介護認定は調査員との面談と主治医意見書で判断され、正確な介護状況を伝えることが重要です。家族が同席して、日常の介護の様子を詳細に補足することも認定に影響がありますので、できるだけ同席することをおすすめします。
施設入所で知っておくべきトラブル防止ポイント
入所後のトラブルを避けるためにも、事前に押さえておきたい注意点があります。
世帯分離と介護負担の関係とは?
親と同居していると、家族の所得が合算されて介護負担が重くなる場合があります。このようなケースでは、世帯分離を行なうことで、本人の所得に応じた軽減措置が受けられる可能性があります。
住所変更・住民票の扱いなど注意点
施設入所に伴い、住民票の移動が必要になる場合もあります。これにより、医療機関や介護サービスの提供地域が変わることがあるため、事前に施設や自治体に確認しましょう。
ケアマネジャーとの連携が成功のカギ
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、利用者に合った施設選びや手続きの相談役です。信頼できるケアマネジャーと連携することで、入所後の生活もスムーズになります。
まとめ
介護保険施設は、制度や種類、費用、手続きなど複雑な点も多く、正しい知識を持っておくことが大切です。早めの準備と専門家との連携を心がけることで、よりよい介護環境を整えていきましょう。
さまざまな金融商品や情報が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。ご自身のライフプランを考えるときには、生命保険や金融商品の販売をせずに中立的な立場からコンサルティングに徹する独立系のファイナンシャルプランナーへの相談をお勧めします。
●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/)
●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。
株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)