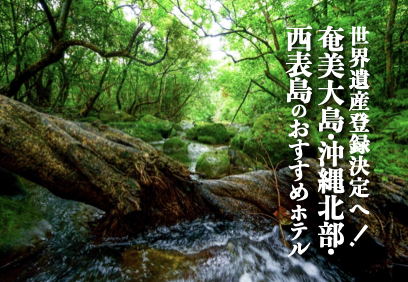大小約1万4000の島が寄り集まってできた国ニッポン。島から島へと渡る旅で見えてくるのは、多様な地域文化が織りなすわが国のかたち。日本そして世界に足を延ばす島旅の物語。
【風景】新島(東京都)
羽伏浦(はうしうら)のコーガ石(ガラス質の砂)

国土交通省の資料によれば、日本の島の数は1万4125(本州・北海道・四国・九州および沖縄本島を含む)。このうちの417が人の住んでいる島だ。
これら有人離島のすべてを半世紀にわたって旅してきたのが、島旅作家の斎藤潤さんである。斎藤さんを惹き付けてやまない島の魅力とは何だろうか。
【自然】礼文島(北海道)
固有種の宝庫「花の浮島」

「日本の原風景が今なお多く残っている点ですね。近年は文化的な均質化も進んでいますが、多くの離島は今も船に乗らないと行き来ができません。方言を筆頭に、本土では失われた風土性のようなものを肌で感じることができます」
観光情報を頼りに回る島旅もよいが、斎藤さんは自分流のテーマを持って訪ねることをすすめる。
「植物や地質のような自然でも、食べ物や行事、歴史や産業でもかまいません。日ごろ興味を持っている分野を切り口に歩くと、島の特徴がより見えやすくなります。そして発見も多いものです。
たとえば宗教や歴史に関心のある人なら、長崎県の島々がおすすめです。島ごとにある教会を訪ねると、キリスト教というものがどれだけ心の支えになってきたかがわかります。背景にある政治や時代状況も浮き彫りになります」
【歴史】端島(はしま)(長崎県)
世界文化遺産の旧炭鉱“軍艦島”

旅人が島に対してできること
離島は食の遺産の宝庫でもあるという。貧しい時代の象徴のように島の人が感じる食材は、普通は恥ずかしがって旅人には出さない。だが、こちらが関心を示すと味わうことができる場合もある。
「海産物や保存食に多いんですが、旅行者が興味を持ったことをきっかけに島の食文化としての再評価が進み、地域振興の新たな起爆剤になった食材もあります。
旅人は一方的に島から元気をもらって帰るわけではないのです。民俗学者の宮本常一も、旅人は古来、訪れた先に情報をもたらすメディアだったと書いています」
斎藤さんは、旅の本質は価値観の交流だという。好きなことを深掘りしながら、真の豊かさとは何かを島の人々と共に考える。離島の旅にはそんな贅沢さもある。
【食文化】樋島(ひのしま・熊本県)
限られた季節の珍味・ゴホンガゼ

【民族】悪石島(あくせきじま)(鹿児島県)
仮面の来訪神「ボゼ」信仰

島旅がより深まる斎藤さんの5つのアドバイス
1.乗船場のチラシを見逃すな
島に渡る乗船券売り場には、宿や店、ガイド個々が製作したチラシがある。行政の観光パンフレットには載っていない有益情報も。
2.肩からカメラを提げて歩く
島は生活圏。何者か判別のつきにくい格好で島を歩くと怪しまれることも。ハイキングの服装やカメラをぶら提げることをおすすめ。
3.町誌・村誌を閲覧する
図書館や宿にある町誌・村誌は島の情報の宝庫。地元の人ですら忘れている歴史や文化も多く記載され、会話のよい糸口になる。
4.自己紹介で「興味」を発信
自分が島に来た目的(探究テーマ)を宿や出会った人にさりげなくアピールしておくと、耳寄りな情報が飛び込んでくることも多い。
5.帰路は飛行機という手もあり
船の旅で実感できるのは島までの距離感と時間感覚。空路がある島ならぜひ帰路は飛行機で。島の形やスケールを視覚で実感できる。
解説 斎藤 潤さん(島旅作家・71歳)

さいとう・じゅん 昭和29年生まれ。東京大学文学部卒。月刊誌『旅』の編集に携わった後、文筆家に。日本の全有人離島を探訪。著書に『シニアのための島旅入門』(産業編集センター)など。
取材・文/鹿熊 勤 写真提供/斎藤 潤