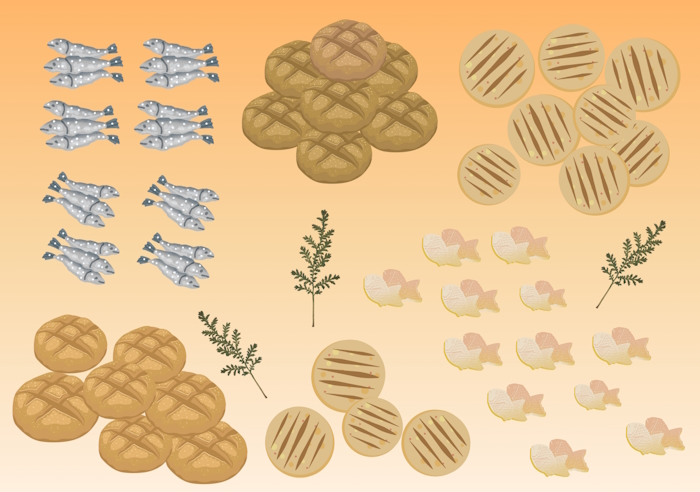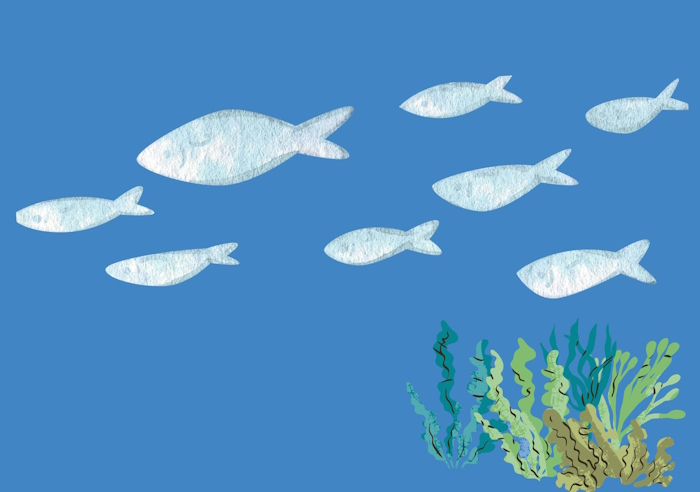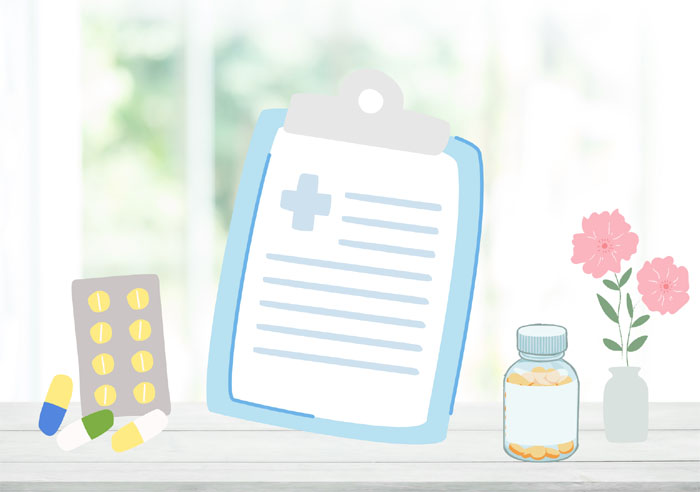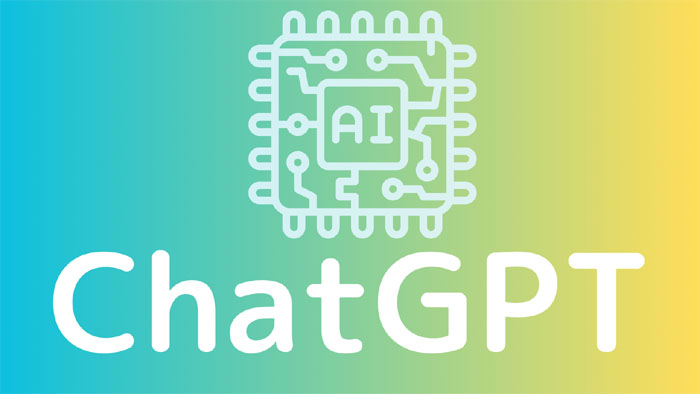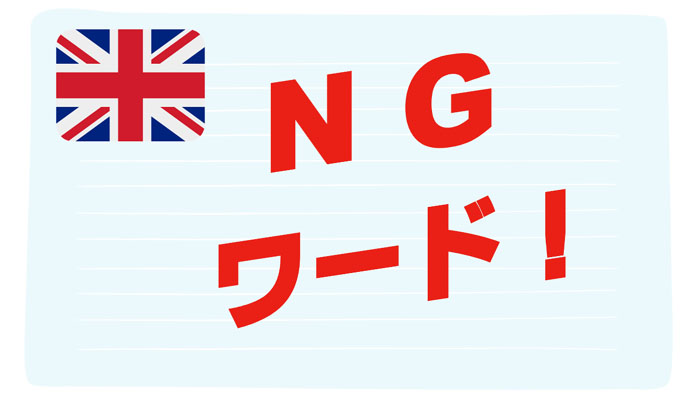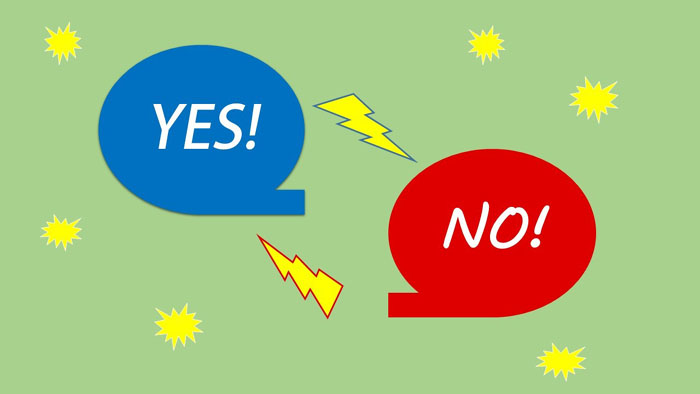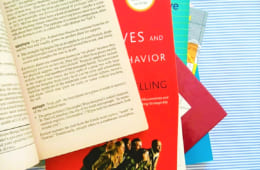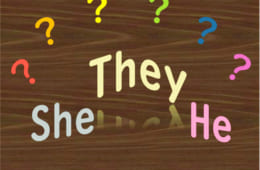文/晏生莉衣ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピックと、世界中から多くの外国人が日本を訪れる機会が続きます。楽しく有意義な国際交流が行われるよう願いを込めて、英語のトピックスや国際教養のエッセンスを紹介します。
* * *
これまで3回に渡り、ジェンダー ニュートラルな英語について紹介してきました。今回は、来年、東京でオリンピック、パラリンピックが開かれることから、オリンピックの第一公用語のフランス語を取り上げたいと思います。ノートルダム大聖堂の火災関連のニュースでは、現地の人々の話がフランス語のまま伝えられることも多くありました。
フランス語を少しでもかじったことのある方ならご存知だと思いますが、フランス語の名詞は基本的に男性名詞と女性名詞に分けられています。これはヨーロッパ言語に多くみられる特徴ですが、今回のレッスンでは話を広げずにフランス語に焦点を絞ることにします。
名詞が男性、女性に分かれているので、冠詞にも男性形と女性形がありますが、英語にはない部分冠詞というものも存在し、これにもまた男性形と女性形があります。英語はa(不定冠詞。母音の前ではan)かthe(定冠詞)しかないのに対し、フランス語の場合、単数形だけでも男性形が3つ(un、le、du)、女性形が3つ(une、la、de la)と、計6個あります。
フランス語のレッスンではないので詳しい文法の説明は省略しますが、冠詞をつけるルールは国の名前にもおよび、フランスは女性名詞でla France、日本は男性名詞でle Japon(ル・ジャポン)です。さらに、日本人は男性ならjaponais(ジャポネ)、女性は japonaise(ジャポネーズ)と、男性、女性で違う形を使い、それにつく形容詞も男性形、女性形に変化します。
フランス語はこのように、男性形(masculin)と女性形(féminin)という文法上の区別(genre)によってがんじがらめにしばられているような言語なので、これをジェンダー ニュートラルなものに変えるのは大変むずかしい、と言わなくてはなりません。フランスでは、人々は日々こうした言葉を使って生活していますから、家庭でも職場でも教育の場でも、自然と男女二分法が使われているわけで、現代の社会変化に合わせてジェンダーレスな言葉を使いなさいと言われたら、人々は話すことも書くこともできなくなってしまうでしょう。
では、「世界一美しい言語」と言われるフランス語は、この世の変化とは無縁で変わることがないのでしょうか。答えはOuiであり、Nonでもあります。
「女子10人+男子1人=男子チーム」という法則
フランスでも、社会の状況に適したフランス語を使おうとする動きは起きています。先に説明したような理由により、ジェンダー ニュートラルなものに変えるのは困難なことから、このところ活発化しているのが、できるだけ包括的な書き方を促進しようというムーヴメントです。フランス語では“l’écriture inclusive”と呼ばれています。(gender inclusiveについてはレッスン6で触れていますので、参考にしてください)
この流れをさかのぼると、2012年に発足したオランド政権によって、女性の権利省の復活や男女平等に関する総合的な法律の制定が行われ、2015年には、男女平等を担当する政府の評議会が、性別による差別のないパブリックコミュニケーションの実践ガイドを発表しました。それにもとづいて、2017年に、学習教材の専門出版社が “l’écriture inclusive”を導入した小学生向けの教材を初めて出版したのですが、これについて保守層から大反発が起き、包括的なフランス語への改革を巡って、教育の現場を巻き込む論争が開始されることになりました。
論争の背景には、フランス語が男女二分法による言語だという以外に、男性優先主義の象徴として批判が集中している文法があります。それは、「男女混在のグループの場合、主語は男性形を使う」という法則です。これに従うと、例えば学生10人のグループがあって、全員が女子学生なら、主語は「学生」の女性形の複数形(étudiantes)を使いますが、そのグループに1人でも男子が加われば、男性形の複数形(étudiants)を使うことになるのです。それがたとえ女子100人になっても、男子1人のために、主語は男性形を使います。
教材では、この法則を変えるために、主語は男性形と女性形を「・」(日本語で中黒(なかぐろ)と呼ばれる記号)を使って併記する方法を取り入れています。新しい発想なのでちょっとわかりにくいのですが、上記の「学生」を例にすると、単数形は“étudiant・e”、複数形は “etudiant・e・s” のように書きます。前回紹介した、見慣れない英語のジェンダー ニュートラル人称代名詞の数々の発案を連想させる、ユニークな試みです。
「フランス語の存続の危機」という批判と論争が始まる
これに対して、断固反対の意見をすぐさま表明したのが、フランス語の最高権威であるアカデミー・フランセーズでした。ブルボン朝ルイ13世の時代に設立された国立学術団体で、大半を男性メンバーで占める同アカデミーは、この新しい試みに対して、「フランス語は存続の危機にさらされている」という厳しい批判を行いました。
新たに発足したマクロン政権は女性差別の撤廃を掲げていますが、これについてはアカデミー・フランセーズに同調し、フィリップ首相は、政府文書や官庁での包括的なフランス語の使用を禁止すると発表しています。首相は説明として、「男性形は中性形として女性にも適応される」という趣旨の発言をしたのですが、これは、英語ではすでに使用されなくなった「総称としてのhe」と同様のロジックです(「総称としてのhe」についてはレッスン7参照)。

するとその翌月、全国の300名以上の公立小中校の先生たちが、「男性形優先の法則を自分たちは教えない」とするマニフェストを、署名入りで発表するという対抗措置に出ます。この法則は言語学的な理由によるものではなく、男性は女性より優れているとする概念から政治的な目的で17世紀に作られたものだとし、現代の価値観に反する文法を教えることはできない、と訴えたのです。そして、男女が混在する場合に男性形の主語を自動的に使うのではなく、多数を占める性別の形を使うか、当事者たちの合意によって選ぶことを代案として提案し、世界中のフランス語教師やフランス語を話す人々へ連帯を呼びかけて、変化を封じ込めようとする最高権力に真っ向からから挑みました。
「教室で教えていると、男の子たちは得意がり、女の子たちは下を向いてしまう。そんな光景を見たくないのです」── マニフェストには、先生たちのそうした思いが込められていました。
これらの教員たちの抗議活動は、賛成する学生や学者を始め、メディアや出版界も巻き込んで、包括的なフランス語への改革を求める多くの人たちの間にも広がっていきました。このマニフェストへの賛同を呼びかける嘆願書が推進派のフランス文学の教授によってインターネットに出されると、著名な執筆家や文化人、政治家を含む約3万3千人の署名が集まりました。
変化の兆しは英語、日本語と同じく、職業の名称から
それから1年以上が過ぎ――。アカデミー・フランセーズが、つい最近になって、ようやく譲歩の姿勢を見せました。現代の女性の役割と社会の変化を認めた上で、伝統を損なうとしてこれまで反対し続けてきた、職業の名称に女性形を加えることに「原則として支障はない」とする見解を、今年3月に出したのです。
フランス語では、「医師」(docteur、 médecin)、「作家」(écrivain)、「エンジニア」(ingénieur)など、男性形しかない職業の名称があります。日本語でもおなじみの「シェフ」(chef) は、料理長という意味だけでなく、組織のトップや指導者的なポジションを指すものですが、これにも男性形しかありません。
こうしたことは、以前のレッスンでも触れた、英語圏や日本の状況と似ているのですが、これらの職業や役職は伝統的に男性が就くものとされていたという時代背景がフランスにもあって、フランス語の番人として君臨するアカデミー・フランセーズは、過去に一部の職業の女性形を容認したことはあるものの、これらの職業については頑ななまでに男性形の使用しか認めていなかったのです。
伝統文化を重んじるフランスならではとも言えますが、これはさすがに旧態依然としているとされ、実際の社会では、男性形のみとする名称にeを付けて女性形にしたものが通称的に使われるケースも多々見られるようになっています。包括的なフランス語の推進派は、こうした職業名称の女性形についても正式に受け入れるように訴えていましたが、同アカデミーが、これについて、とうとう、ゴーサインを出したのです。
社会的変化に伴う英語や日本語での職業の改称と同様の取り組みが、フランス語でも始まったと言えます。ただ、英語がpolicemanからpolice officerに、日本語では「看護婦」が「看護師」へと、ジェンダー ニュートラルな名称に変えられたのに比べると(レッスン6参照)、フランスの場合は、男性形に加えて女性形の使用が容認されるという変更ですから、異質ではあります。男女二分法で成り立っているフランス語の性質上、こういう方法とならざるを得ないのでしょう。
小さな前進のようにも見えますが、アンシャン レジームを倒した市民の力が、再び、時代の変化を巡って勝利を勝ち取ったと、現代フランス語の歴史的な転換として注目を浴びることになりました。
包括的な方法として提案された「・」を使う男女形並列の新しい書き方や、男性形優先の法則の廃止については、同アカデミーも政府も反対姿勢を変えていないようですので、フランス社会では議論はこれからも続くことになります。フランス語の平等化についてはまだまだ様々な問題が指摘されていますが、それはまた別の機会に譲りたいと思います。
文・晏生莉衣(あんじょうまりい)
東京生まれ。コロンビア大学博士課程修了。教育学博士。二十年以上にわたり、海外で研究調査や国際協力活動に従事後、現在は日本人の国際コンピテンシー向上に関するアドバイザリーや平和構築・紛争解決の研究を行っている。