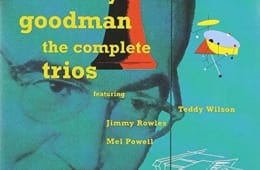文/後藤雅洋
ジャズの楽しさをもっともわかりやすく伝えてくれるミュージシャン、それが多くのファンに愛されたピアニスト、オスカー・ピーターソンです。
私もジャズを聴き始めたばかりのころ、彼の演奏を観ていっぺんでジャズの魅力に取りつかれました。心地よいリズムに乗った華麗な演奏テクニック。そして何より、ジャズだけがもつ独特の快適なスイング感が、ピーターソンのピアノからはダイレクトに伝わってきたのです。
このように多くのファンに親しまれているピーターソンですが、彼の演奏スタイルはバド・パウエルやビル・エヴァンスといった、同じように偉大なジャズ・ピアニストたちとは微妙に異なっていることを知ったのは、だいぶ経ってからのことでした。
といっても、ピーターソンのピアノ・スタイルはけっして異端ではありません。彼の奏法は深くジャズ・ピアノの伝統と結びついているのです。だからこそ、私を含め多くのファンは、ピーターソンの演奏から「ジャズの魅力」を感じ取るのです。
ジャズ・ピアノの歴史をひもとくと、その発端に、19世紀末から20世紀初頭にかけて流行った、ラグタイムというアメリカ独自の音楽があったことが書かれています。
ラグタイムは西欧音楽と黒人音楽が融合してできたという点でジャズと同じ構造を備えており、「ラグタイム王」の異名をとった作曲家兼演奏家スコット・ジョプリンもアフロ・アメリカンです。
日本で1974年に公開され大ヒットした、ポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード主演の映画『スティング』では、ラグタイムがじつに効果的に使われていました。主題歌「ジ・エンターテイナー」はスコット・ジョプリンが作曲した名曲で、この映画でラグタイムを知ったという方々もかなり多いようですね。じつをいうと、私もそのひとりなのです。
ラグタイムはきちんと書かれた譜面があり、即興的要素はほとんどないのでそのままでは「ジャズ」とはいえませんが、多くの黒人ピアニストたちがこれに改良を加え、しだいに「ジャズ・ピアノ」のスタイルが確立されていったのです。
その中でも注目すべきなのが、クラシック演奏家としても一流だった大ピアニスト、アート・テイタムです。面白いことに、「似ていない」と言ったバド・パウエルとオスカー・ピーターソンは、ともにテイタムの影響を受けているのですね。
いったいどういうことなのでしょう。ごく大まかに言ってしまうと、パウエルは「右手だけ」だったのに対し、ピーターソンは「両手を使った」から、というのがいちばんわかりやすい説明ではないでしょうか。
本来「両手を使って同時に多くの音が出せる」ことがピアノという楽器の最大の特徴であるとすれば、むしろ右手を強調したパウエル・スタイルのほうが、「ピアノ演奏としては」異端といえそうです。
それはさておき、パウエルは「モダン・ジャズ・ピアノの開祖」といわれるだけあって、テイタムのスタイルを「大幅に」改変しましたが、ピーターソンは「一時代前=スイング時代」のテイタム・スタイルを、巧みに「モダン・ジャズ・ピアノ」の中で生かしたといえると思います。
しかしそういうことができたのは、ピーターソンがアート・テイタム譲りの圧倒的な演奏技術を身につけていたからこそなのです。
誰にでも真似できるというわけではありません。実際、バド・パウエルの奏法に影響を受けた「パウエル派ピアニスト」は、ウィントン・ケリーはじめトミー・フラナガンやケニー・ドリュー、ソニー・クラークなど、じつに大勢いますが、ピーターソンの影響を受けたピアニストというと、ちょっとすぐには思いつきません。繰り返しますが、それは「テクニックの壁」が大きかったからなのです。
誤解を恐れずに言えば、パウエル派ピアニストの中には、クラシック・ファンの基準からみれば「ちょっと……」と思われてもしかたのないようなテクニックのジャズマンが少なからずいます。しかし急いで付け加えれば、その人たちもジャズ演奏家としてはけっして劣っているわけではないのです。その秘密は、もうおわかりですよね。そうです、「個性的表現」においてそれぞれ傑出した「独自性」を備えており、そのこと自体が「ジャズという音楽の価値観」としては正解なのでした。
要するに「味」の問題ですよね。私たちがジャズを楽しむとき、それと意識せず好ましいと思う要素が、それぞれのジャズマン特有の「味わい」なのです。これは必ずしも一般的な意味でいわれている「優れたテクニック」によって表現できるわけではありません。
■テクニックという〝味〟
さて、ここでパウエルとピーターソンの「違い」を浮き彫りにする、もうひとつの要素が登場しました。それは「文化背景」の問題です。
黒人ジャズマンと白人ジャズマンの演奏のテイストの違いは、わかりやすく「人種の違い」で説明されがちですが、厳密にいうと、それぞれのグループの文化背景が異なっているところから生まれているのです。
バド・パウエルは、ジャズの中心地ニューヨークのハーレム地区で育っています。他方、オスカー・ピーターソンはカナダ、ケベック州モントリオール出身。モントリオールといえば1976年にオリンピックが開かれたことぐらいしか私たちの記憶にありませんが、「北米のパリ」と呼ばれたこの都市はフランス語を話す人のほうが多く、文化的にはアメリカ合衆国とはかなり異なっているのです。人種差別もアメリカのようなことはありません。
一概にいえませんが、どちらかというと黒人ジャズマンは「味=個性で勝負」する傾向が強く、白人ジャズマンは「演奏技術」や「音楽性」と呼ばれる要素で自己表現するタイプが多いように思えます。
個性派黒人ピアニストの代表は、セロニアス・モンクでしょうね。誰が聴いてもモンクのピアノは「ユニーク」です。オスカー・ピーターソンは黒人ですが、アメリカ合衆国のブラック・ピープルたちとは生活環境・文化背景が異なっていることが影響しているのでしょうか、どちらかというと音楽的には「白っぽい」のですね。
ところで、ふつうの音楽ファンにとっていちばんわかりやすい要素って、なんだと思います? 私の場合は演奏技術でした。
ピアノにしろギターにしろ、「うまい人」の演奏はふつうにわかります。もちろんその音楽が好きかどうかは別問題ですが、どなたでも、引っかかったりつまずいたりする演奏と、滑らかでスムースな演奏の違いはわかるものです。要するに「この人アマチュアじゃない?」ってことぐらいは、誰でもわかるということですよね。
他方「味」とか「個性」と呼ばれている要素は、その音楽ジャンル特有の「聴きどころ」が摑めていないと、意外とわかりにくいものではないしょうか。具体的にいえば、私はセロニアス・モンクの演奏を最初に聴いたときには「なんかヘンだな」という印象しかもたなかったものです。もちろんジャズの面白さに開眼するにつれ、モンクの魅力もしだいに実感するようになりましたが、最初は不思議な感じしか受けませんでした。
こうした話をお聞きになれば、おのずとピーターソンの魅力の源泉が見えてきたのではないでしょうか。そうです、ピーターソンはジャズならではの聴きどころ、快適なスイング感を、誰にも真似できない高度なレベルで表現する演奏技術を身につけているのです。
ですから彼の演奏からは、さほどジャズという音楽ジャンルを聴き慣れていない方々でも、容易に「ジャズの魅力」を実感できるというわけなのですね。
ところで、この説明ではモンクの演奏技術には問題がある、あるいはピーターソンには個性が不足しているのでは? といった疑問が当然浮かんでくることと思います。どちらも違うのです。とくにピーターソンの場合は、彼の圧倒的なテクニック自体が、誰にも真似できない特有の個性となっているのです。
その証拠に、ちょっとジャズを聴き慣れてくれば、演奏を聴いただけでアルバム・ジャケットを見なくても「これはピーターソンのピアノだ」と、どなたでも聴き分けられるからです。
■ノーマン・グランツとの出会い
オスカー・ピーターソンは1925年(大正14年)に、前述したようにカナダのモントリオールで生まれました。世代的には26年生まれのトランペッター、マイルス・デイヴィスやテナー・サックス奏者ジョン・コルトレーンとほぼ同世代です。しかしカナダ生まれということと、〝ビ・バップ〟以前のピアノ奏法も取り入れた独自の演奏スタイルゆえ、合衆国の黒人ジャズマンたちとは微妙に違う道を歩むこととなりました。
なんといっても大きな出来事はヴァーヴ・レーベルのオーナー・プロデューサー、ノーマン・グランツとの出会いでしょう。
グランツは、JATP(ジャズ・アット・ザ・フィルハーモニック)という大物ジャズマンを多数擁した連続コンサートの企画者として有名ですが、彼がカナダを訪れた際、ピーターソンを見いだしたのです。いっぺんでピーターソンの才能に魅了されたグランツは、ピーターソンをJATPのメンバーに引き入れます。〝ビ・バップ〟真っ盛りの49年のことでした。
その後グランツは自身のプロデュースするレーベル(マーキュリー、クレフなど。のちにヴァーヴに統合)でピーターソンのレコーディングを大量に行なっているだけでなく、ピーターソンの個人マネジャー的な立場となり、長きにわたる親密な関係が続くこととなったのです。
実力あってのこととはいえ、アメリカ・ジャズ界に取り立てて人脈がなかったピーターソンにとって、これは大きなチャンスでした。
■キング・コールの影響も
グランツとピーターソンの関係はジャズ界でも特異といえますが、これはお互いにとってよいことだったと思います。
グランツという人はどちらかというと「旦那」的で、ピーターソンも自由に才能が発揮できたのですね。ピーターソンのいい意味でわかりやすく陽性な音楽性は、グランツの好みと見事一致していたのです。
こうした、ジャズマンとしてはかなり特別の待遇を得ていたピーターソンは、音楽的にも大きな特徴がありました。それは長期にわたって活躍したジャズマンにしては珍しく、好不調の波が少なく、また音楽的にもほとんど変化がないことです。このいい意味での「保守性」はグランツのジャズの好みとも一致しているのですね。
また、そのこととも関連しますが、ピーターソンはトリオ編成が多く、またサイドマンも比較的固定していました。59年から66年まで続いたレイ・ブラウンのベースとエド・シグペンのドラムスを従えたピアノ・トリオは「ザ・トリオ」とまでいわれてファンから親しまれていました。
しかしここにもピーターソンと、パウエルを祖とする「モダン・ジャズ・ピアノ」との境目というか微妙な違いが透けて見えます。それはピアノ・トリオの楽器編成です。
パウエルはたんにジャズ・ピアノのスタイルを一新しただけでなくその必然的結果として、ピアノ、ベース、ドラムスという現在では定番となっている「ピアノ・トリオ」の楽器編成を定型化しました。
パウエル以前のピアノ・トリオというと、日本ではポピュラー・ヴォーカリストとして有名なピアニスト、ナット・キング・コールが率いていたピアノ、ギター、ベースという編成ですが、面白いことにピーターソンも初期(51年頃)は、バーニー・ケッセルのギターにレイ・ブラウンのドラムスというように、キング・コール・トリオの楽器編成を踏襲しているのですね。
そして興味深いのはこのふたりは仲がよく、意外なことにピーターソンもまたキング・コールのようにヴォーカルも得意としていたのです。そしてあるとき、お互いに「私はヴォーカル専門」とキング・コールが、そして「じゃあ、僕はピアノに専念するよ」と言ったとか……。
ともあれ、ピーターソンはキング・コールのピアノ・スタイルの影響も受けているのです。そして彼らはともにポピュラーな人気を得ている。これは偶然とはいえないような気がします。
文/後藤雅洋
ごとう・まさひろ 1947年、東京生まれ。67年に東京・四谷にジャズ喫茶『いーぐる』を開店。店主として店に立ち続ける一方、ジャズ評論家として著作、講演など幅広く活動。

ジョン・コルトレーン|ジャズの究極にフォーカスし続けた求道者
アート・ブレイキー |燃えるドラムで世界を熱狂させたジャズの“親分”
チャーリー・パーカー|アドリブに命をかけたモダンジャズの創造主
オスカー・ピーターソン|圧倒的な演奏技術でジャズの魅力を伝えたピアニスト
ビル・エヴァンス|「ピアノ音楽としてのジャズ」を確立した鍵盤の詩人
モダン・ジャズ・カルテット(MJQ)|クラシックの香り漂う典雅な〝室内楽ジャズ〟
ジョン・コルトレーン|情念をも音楽の一部にして孤高の道を驀進した改革者
クリフォード・ブラウン|完璧なテクニックと最高の歌心で音楽を表現した努力の天才