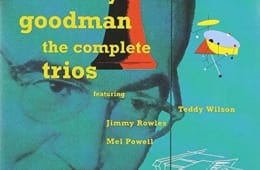文/後藤雅洋
ビル・エヴァンスの本名はウィリアム・ジョン・エヴァンスで、1929年(昭和4年)にニューヨークのすぐ隣、ニュージャージー州に生まれました。世代的にはモダン・ジャズの開祖、20年生まれの天才アルト・サックス奏者チャーリー・パーカーの一世代下。そして、のちにエヴァンスがサイドマンとして加わることになる26年生まれのトランペッター、マイルス・デイヴィスの弟分という立場です。
大方の白人ジャズ・ピアニストの経歴と同じように、エヴァンスもクラシック音楽から学び始めています。そのころのお気に入りはモーツァルトやベートーヴェンといったまさに王道路線。ジャズの中でも〝ピアノ〟という楽器は、クラシック音楽との縁がとりわけ深いともいえるのです。そしてこのことはエヴァンスの音楽の特徴とも関わっています。
この世代のジャズ・ミュージシャンのお定まりのように、エヴァンスもラジオでジャズに興味をもちました。エヴァンスのお気に入りは40年当時、幅広い人気を誇った白人バンド、トミー・ドーシーやハリー・ジェイムズ楽団でした。そして、兄のハリーがトランペット奏者として所属していた地方バンドで、10代のエヴァンスはジャズの演奏を始めます。まだ子供ですから当然アマチュアですよね。終戦の翌年46年にエヴァンスは大学に進み、クラシックのフルートとピアノを学びます。ジャズマンといえどもクラシック音楽の基礎知識は当然もっているのですね。
第2次世界大戦後は50年に起こった朝鮮戦争に象徴される東西対立がしだいに激しくなり、徴兵制も維持されていました。エヴァンスも51年に徴兵され、除隊したのは54年。この数年はちょうどジャズが〝ビ・バップ〟から〝ハード・バップ〟へと移行する期間で、いわば〝モダン・ジャズ黄金時代〟を迎えようとする揺籃期でした。そのまさに「何かが始まらんとする」55年にエヴァンスはようやくジャズの中心地ニューヨークに進出するのです。
56年にギター奏者マンデル・ロウの紹介でリヴァーサイド・レーベルと契約したエヴァンスは、この年に初リーダー作『ニュー・ジャズ・コンセプションズ』を吹き込みます。この演奏はエヴァンスのジャズ・ピアニストとしてのスタート地点を示す興味深いものです。当時のジャズ・ピアニストの常として、ビ・バップ・ピアノの開祖、バド・パウエルの築いた枠組みを踏襲しつつも、パウエルとは対照的な〝クール・ジャズ〟の創始者である白人ピアニスト、レニー・トリスターノの影響をも感じさせる斬新なスタイルは、いかにもアルバム・タイトルにふさわしいものといえそうです。
■新感覚にマイルスも注目
ある意味でパウエル的スタイルが類型化しつつあったこの時期、エヴァンスの「新感覚」は当時絶頂期を迎えていた〝ハード・バップ〟の先を予感させるもので、時代の動きに敏感なマイルスのアンテナに引っかかります。58年にはマイルスのグループに参加し、まさにジャズ・シーンの中央に登場することとなったのですね。
それにしても、ニューヨークに出てきて数年を経ずして当時の人気バンド、マイルス・グループに起用されたということは、エヴァンスの才能の輝きと同時に、マイルスの嗅覚の鋭さをも実感させるものです。というのも、当時は人種差別がまだ激しく、白人であるエヴァンスのサイドマン登用はかなり思い切ったものでもあったからです。
ふたりの出会いはジャズ界に大きな果実をもたらしました。59年に録音されたマイルスのジャズ史的名盤『カインド・オブ・ブルー』(コロンビア)は、エヴァンス抜きには成立しなかったでしょうし、エヴァンスもまた、当時のナンバー・ワン・ジャズ・グループで鍛えられた成果は名盤『ポートレイト・イン・ジャズ』(リヴァーサイド)に結実しています。この作品からベーシスト、スコット・ラファロを擁する名高い「エヴァンス・トリオ」が活動を開始したのです。
ところで、「モード・ジャズの先駆け」とも称されたマイルスの『カインド・オブ・ブルー』、そしてエヴァンスの『ポートレイト・イン・ジャズ』が吹き込まれた59年という年は、ジャズ史の「節目」でもあったようです。他にも、ジョン・コルトレーンの新生面を切り拓いた名盤『ジャイアント・ステップス』(アトランティック)や、〝フリー・ジャズ〟の記念碑的作品、オーネット・コールマンの『ジャズ来るべきもの』(アトランティック)が吹き込まれるなど、ジャズ・シーンは新たな時代を迎えたのです。
■トリオという特殊編成
ではエヴァンスは「ジャズ新時代」であった1960年代に何をなしたのでしょうか。それこそが「エヴァンス・トリオ」の業績なのです。
実際日本では多くのファンがいる「ピアノ・トリオ」という楽器編成は、じつはアメリカではそれほど一般的なジャズ・スタイルではなかったのです。おそらくそれは日米の国民性の違いに由来するのでしょう。島国日本は「わび・さび」といった渋めな魅力が受け入れられやすい。他方、多民族国家アメリカでは、動作・身ぶりも大仰でなければ他人に理解されにくく、ジャズも派手な音が出るトランペットやサックスのいない「ピアノ・トリオ」は、半ば冗談ですが「人件費をケチった」ジャズのように思われていたようです。
ピアノの名手でもあったデューク・エリントンも、ビッグ・バンド・リーダーとしての名声が第一で、同じくバンド・リーダーであるカウント・ベイシーのピアノも、ギター、ベース、ドラムスとのセットで「オール・アメリカン・リズム・セクション」の尊称を受けたように、世間では「ピアニスト」としての評価はどちらかというと二次的。当然ビッグ・バンドの縮小版であるスモール・コンボでも、トランペットあるいはサックスを擁する、少なくとも4人から7、8人編成が一般的なジャズの楽器編成だったのです。
ですから、40年代半ばに起こった〝ビ・バップ〟以前のジャズでは、ソロ・ピアノの名人、アート・テイタムのような例外はあったにしても、音としての派手さに欠けるピアノだけにスポットを当てるような楽器編成は珍しいものでした。あったとしても、日本ではポピュラー・シンガーとして知られたナット・キング・コール・トリオのように、ピアノ、ギター、ベースという、現代のピアノ・トリオとは少し違った楽器編成でした。つまりメロディ楽器(この組み合わせの場合は和音も出せますが)は、少なくとも2台必要ということでしょうか。ともあれ、アメリカでは「賑やかし」が大事なようですね。
■バド・パウエルの影響
こうした風潮に風穴を開けたのがバド・パウエルでした。かつてアート・テイタムがやったように、両手をフルに使えば和音もメロディも自在に駆使できるピアノの特性を、パウエルはあえて右手に集中し、力強いメロディ・ラインを浮き上がらせる「ビ・バップ・ピアノ」の奏法を開発したのです。
そしてギターの代わりにドラムスを入れた、現在の「ピアノ・トリオ」のスタイルを定着させたのがパウエルの偉大な功績なのです。パウエルの強力な右手の旋律はトランペットやサックスに対抗できるパワー、説得力をもっていたのですね。初期のビル・エヴァンスはじめ、50年代に登場した大多数のピアノ・トリオは、おおむねバド・パウエルの開発した「モダン・ピアノ」の演奏法を踏襲していたのです。
そのかわり、パウエル流のスタイルはどちらかというと「1番槍」を目指す騎馬武者のように、ピアニストが演奏の先頭に立って進み、ベースやドラムスはそれに付き従う「従者」のようなスタンスをとらざるをえません。ピアニストがリーダーなのですから、それも当然といえば当然なのですが……。
■3者協調型トリオの誕生
エヴァンスが手をつけたのはそこでした。3人ミュージシャンがいるのに、ピアニストだけが演奏のイニシアティヴを握るのは、もったいない。こうした状況に、まさにうってつけの人材が現れたのです。先進的発想と極め付きの演奏技術を身につけたベーシスト、スコット・ラファロです。彼は、リズムをキープしつつ演奏の見取り図ともいうべき「コード進行」を低音で指示するベーシストの役割にこだわらず、あたかもギターのように自在にメロディを奏でることでピアニストに音楽的刺激を与えたのです。
ミュージシャンがお互いの旋律によって音楽的刺激を受け、アイデアが閃く「インタープレイ」の誕生です。
しかし、自分の意思だけで即興演奏を行なういわゆる「アドリブ」に比べ、他人の出す音に瞬時に反応して即興演奏を行なうのはきわめて高度な音楽的センスが要求されます。エヴァンスはラファロとの出会いによってこうしたハイ・レベルの技術を己がものすると同時に、たったひとりで演奏を仕切る「パウエル型ピアノ・トリオ」からの脱却が図られたのです。もちろんこうした「全員参加型ピアノ・トリオ」の発想はドラムスのポール・モチアンにも及び、いわゆる「3者協調型ピアノ・トリオ」が誕生したのです。
その影響力は圧倒的で、以後現在に至るまで、キース・ジャレットやブラッド・メルドーなど、ほとんどのピアノ・トリオはエヴァンスが主導した「3者協調型ピアノ・トリオ」のスタイルを踏襲しています。エヴァンスが現代ジャズ・ピアノの先達だということが明瞭に示される例証ですね。
さて、それではピアニストとしてのエヴァンスの魅力はどこにあるのでしょうか。これも最初に説明したように「美しいメロディ」が最初にあるのは事実です。しかしそれが「飽きない」のはどうしてでしょうか? これこそがエヴァンスの魅力の秘密であると同時に、ジャズならではの「聴きどころ」なのです。
まずは「タッチ」です。ほんとうに不思議なことですが、トランペット、サックスなどと違い、ピアノという楽器は素人考えでは誰が弾こうが「出る音」は同じように思えるのですが、これが違うのですね。
結局、鍵盤を押さえるときの力加減というか勢いというか、それこそ微妙な「タッチ」の違いによって音色や力感がまったく別物に聴こえるのです。エヴァンスのタッチは繊細であると同時にきわめて力強く、その結果ピアノの音に明確な〝芯〟があるのです。これが心地よい。誤解を招くといけないので付け加えますが、それは「大きな音」とは違います。フォルテでなくとも、それこそピアニッシモでも彼の音はシャンと屹立しているのですね。
■独特の躍動的リズム
そのことと関連しますが、エヴァンスのリズム感は独特です。彼は白人ジャズ・ピアニストの特徴である拍子の頭に強拍がくるスタイルをとりつつも、それぞれの「拍」に対しては微妙に「遅れ気味」というか「もたれ気味」に乗ることによって、追い立てられるような緊張感、切迫感を伴ったドライヴ感を生み出しているのです。一聴して「エヴァンスだ」と聴き分けられるのは、じつは旋律ではなく彼独自のリズム感なのです。そして強力で〝芯〟のあるタッチがそのリズム感、躍動感をいやが上にも強調しているのです。
こうしたリズムに関わる要素はアップ・テンポの曲想で顕著ですが、エヴァンスの長所が浮き彫りになるスロー・バラードではどうなのでしょう。
優しく美しいメロディがきわめて印象的に心に残るのは、エヴァンスが紡ぎだす旋律には秘められた力強さと緊張感が潜んでいるからなのです。繊細さと力強さが同居した緊張感に満ちたタッチが生み出す、独特の躍動的リズムが彼の演奏を聴く快感に繫がり、「飽きない」秘密なのですね。
私たちは「意識としては」エヴァンスのメロディに魅せられているように感じていますが、実態は彼ならではのリズムの快楽、繊細な力強さが生み出すジャズ的スリルによって魅了されているのです。言い換えれば、ジャズを他の音楽と区別する最大の特徴、エヴァンスならではの「個性的表現」に魅了されているのですね。
文/後藤雅洋
ごとう・まさひろ 1947年、東京生まれ。67年に東京・四谷にジャズ喫茶『いーぐる』を開店。店主として店に立ち続ける一方、ジャズ評論家として著作、講演など幅広く活動。

ジョン・コルトレーン|ジャズの究極にフォーカスし続けた求道者
アート・ブレイキー |燃えるドラムで世界を熱狂させたジャズの“親分”
チャーリー・パーカー|アドリブに命をかけたモダンジャズの創造主
オスカー・ピーターソン|圧倒的な演奏技術でジャズの魅力を伝えたピアニスト
ビル・エヴァンス|「ピアノ音楽としてのジャズ」を確立した鍵盤の詩人
モダン・ジャズ・カルテット(MJQ)|クラシックの香り漂う典雅な〝室内楽ジャズ〟
ジョン・コルトレーン|情念をも音楽の一部にして孤高の道を驀進した改革者
クリフォード・ブラウン|完璧なテクニックと最高の歌心で音楽を表現した努力の天才