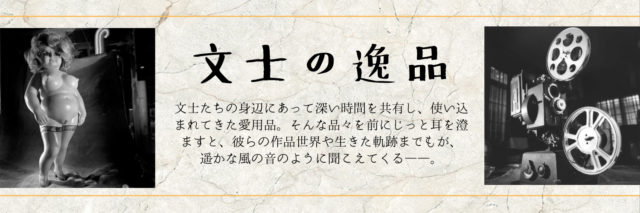
◎No.13:岡本かの子のロケット

岡本かの子のロケット(撮影/高橋昌嗣)
文/矢島裕紀彦
天真爛漫のナルシスト。自分の美貌を確信し、こんな台詞を吐く。パリにいたころ、フランス人は私を牡丹と呼びましたのよ--。それが岡本かの子だった。
だが、この自己陶酔あったればこそ、夫・一平の放蕩三昧や、夫公認の若い恋人・堀切重雄と夫との同居生活という、奇妙な魔窟のような時間をくぐり抜け得た。さらには、『母子叙情』『老妓抄』『家霊』といった豊満で妖しい唯美的作品の誕生にも、このナルシシズムは一役買っただろう。
東京・目黒区の日本近代文学館に残るかの子遺愛の品物の中に、直径2センチほどの小さなロケットがあった。金の縁取りの中央部、ガラスの向こうに収められているのは自らの肖像写真。かの子は何度となく、このロケットの中の自分に、いとおしむような言葉を投げかけたに違いない。
死に至る病の床についてのち、かの子は一度も鏡を見ることがなかった。自らが確信的に愛した「美貌」の中に、多少ともやつれや醜さを見いだすのを拒否して、かの子は完全なるナルシストを貫いたのである。
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。『サライ.jp』で「日めくり漱石」「漱石と明治人のことば」を連載した。
写真/高橋昌嗣
1967年桑沢デザイン研究所 グラフィックデザイン科卒業後、フリーカメラマンとなる。雑誌のグラビア、書籍の表紙などエディトリアルを中心に従事する。
※この記事は、雑誌『文藝春秋』の1997年7月号から2001年9月号に連載され、2001年9月に単行本化された『文士の逸品』を基に、出版元の文藝春秋の了解・協力を得て再掲載したものです。




































