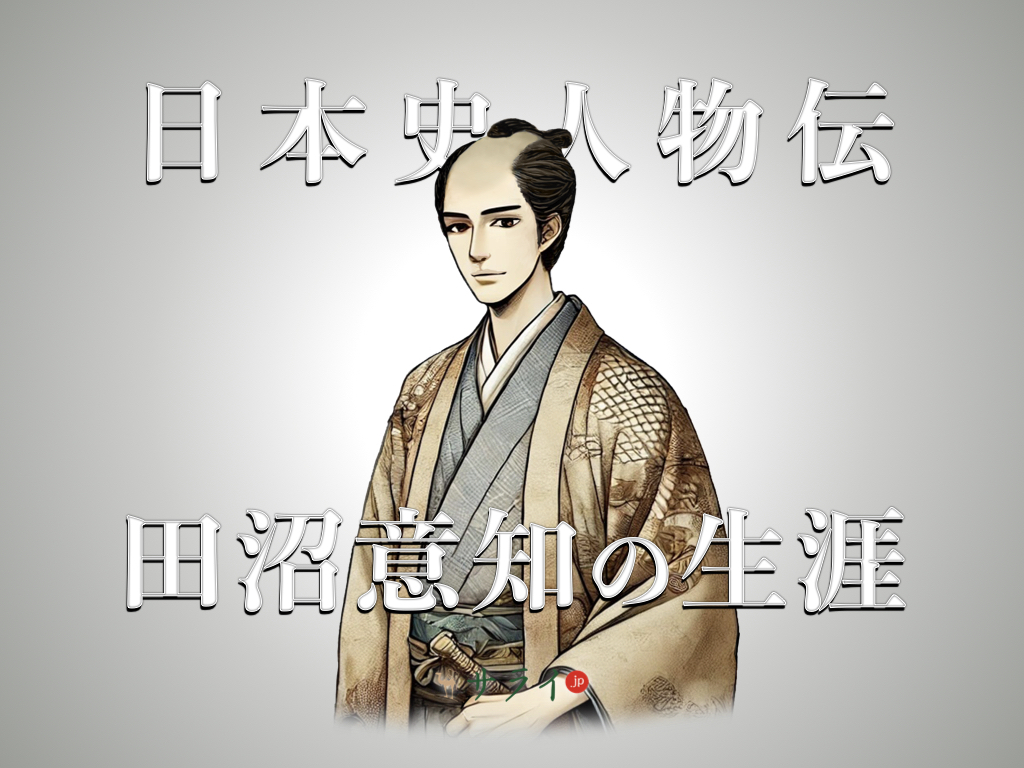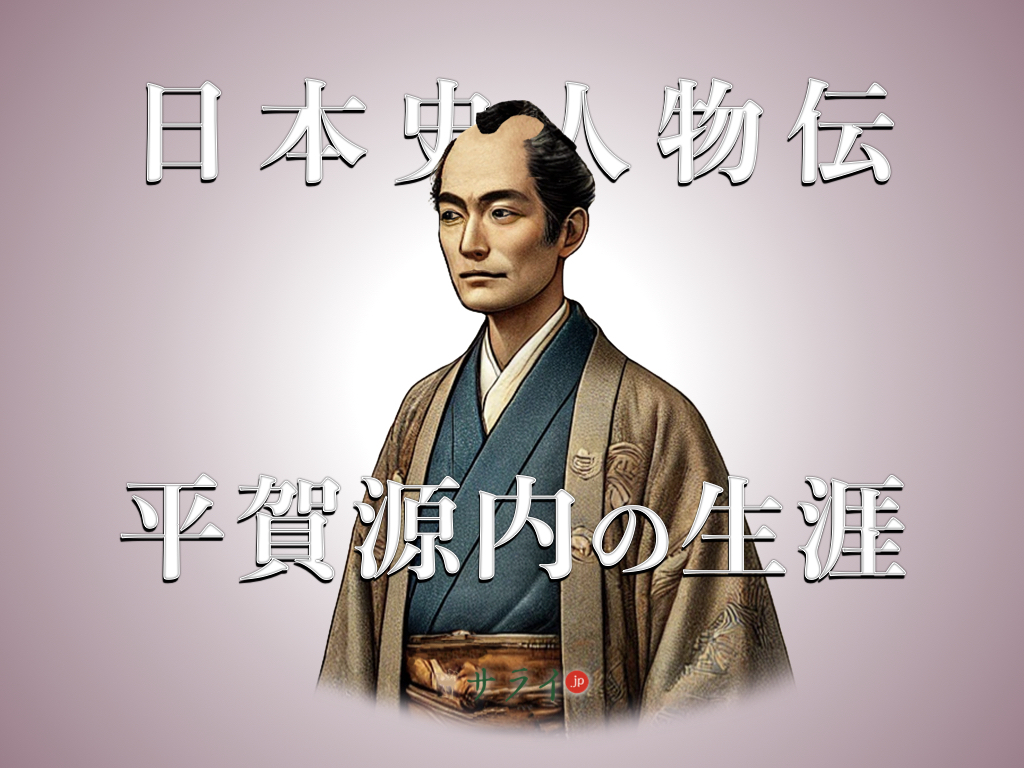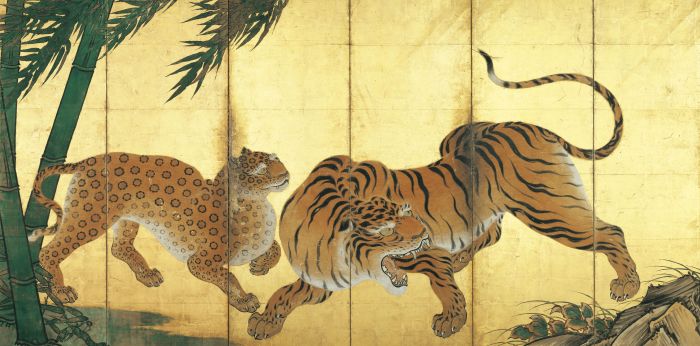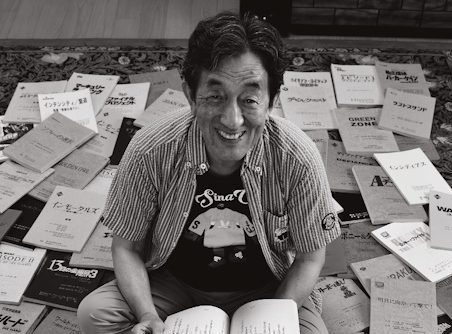はじめに-田沼意知とはどんな人物だったのか?
田沼意知(たぬま・おきとも)は、田沼意次(おきつぐ)の子です。田沼意次を知っていても、田沼意知のことはあまり知らない人も多いのではないでしょうか? 意知は、父・意次とともに田沼時代の政治を支えました。しかし、天明4年(1784)、江戸城中で佐野政言による刃傷事件に巻き込まれ、36歳で命を落とします。この事件は田沼時代終焉のきっかけともなり、彼の死は当時の世相に大きな影響を与えました。
では、実際の田沼意知とは、どのような人物だったのでしょうか? 史実をベースにしながら、紐解いていきましょう。
2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、明るい未来を信じるまっすぐな田沼家のプリンス(演:宮沢氷魚)として描かれます。

目次
はじめにー田沼意知とはどんな人物だったのか?
田沼意知の生きた時代
田沼意知の足跡と主な出来事
まとめ
田沼意知の生きた時代
田沼意知が生きた18世紀後半は、田沼意次による積極的な商業政策が進められていた時期です。重商主義を基調とした政策により、幕府財政の再建を図る一方で、賄賂の横行や都市民の不満が高まりました。天明の大飢饉や都市下層民の生活苦も重なり、田沼政権への批判が激化していた時期でもあります。
田沼意知の足跡と主な出来事
田沼意知の生年は寛延2年(1749)、没年は天明4年(1784)です。その生涯を出来事とともに紐解いていきましょう。
田沼意次の長男として誕生
寛延2年(1749)、意知は田沼意次と黒沢定紀の娘の子として、誕生します(※長男という説と次男という説あり)。幼名は、竜助でした。
明和元年(1764)1月には、10代将軍・徳川家治に仕え始めます。

若年寄となり、権勢を誇る
その後、父・意次の全盛期である天明元年(1781)に奏者番(そうしゃばん、江戸幕府の職名の一つ)に就任し、翌年には山城守の官位を授けられます。天明3年(1783)には若年寄に昇進し、父・意次とともに幕閣の要職を占めました。廩米(りんまい)五千俵を与えられたことも、当時の権勢の強さを物語っています。
【江戸城中で斬られる。次ページに続きます】