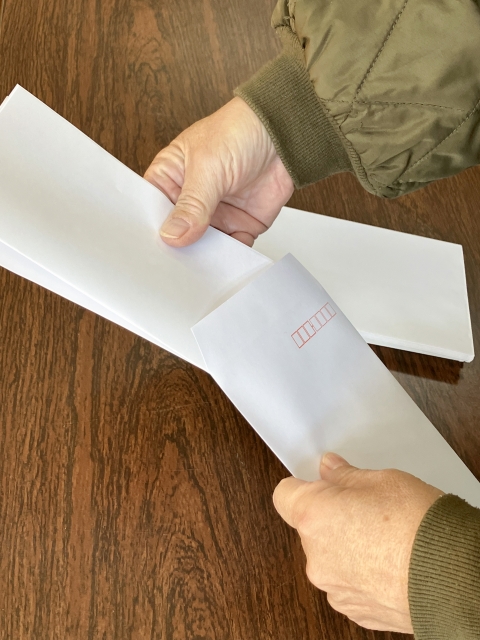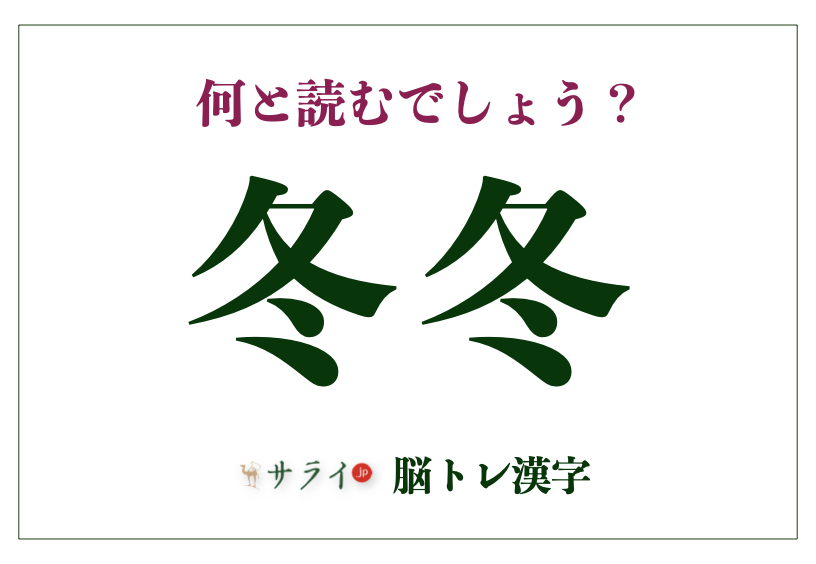取材・文/ふじのあやこ

一緒にいるときはその存在が当たり前で、家族がいることのありがたみを感じることは少ない。子の独立、死別、両親の離婚など、別々に暮らすようになってから、一緒に暮らせなくなってからわかる、家族のこと。過去と今の関係性の変化を当事者に語ってもらう。
*
株式会社アタムは、「子どものコミュニケーション能力に関する意識調査」(実施日:2025年6月26日~7月1日、有効回答数:中学生までの子どもがいる親493人(女性396人/男性97人)、インターネット調査)を実施。同調査にて、「子どもが普段よくコミュニケーションをとる場面」を聞いたところ、最も多かったのは「学校にいるとき(56.6%)」で、半数以上の回答が集まった。次に「習い事をしているとき(30.8%)」や「幼稚園・保育園にいるとき(25.2%)」という結果になっている。続いて、「子どものコミュニケーション能力を伸ばす方法」に対しては、1位は「親子でコミュニケーションをとる(25.6%)」、2位は「習い事をさせる(17.8%)」、3位は「家族以外との関わりを持つ(17.6%)」となっている。
今回お話を伺った史帆さん(仮名・45歳)は、小学校卒業間際のタイミングで家族との別居を選択し、中学から祖父母の家で暮らすことに。母親は月に1度は必ず史帆さんの元に会いに来ていた。【~その1~はこちら】
親よりも祖父母と一緒にいたかった
中学2年の3月頃に、父親の仕事の異動があり、頻繁に転勤がある部署ではなくなる。そのことで高校からは親子3人で再び暮らすことを提案されたという。しかし、史帆さんはこれを拒否する。
「両親が暮らしている場所は東京でした。だから、興味はありましたが、離れて暮らしていた3年間で私の生活も落ち着いていて、離れたくない思いが強かったんです。友人のことはもちろん、祖父母のことも大きかった。その3年の間に祖父が入退院を繰り返すようになっていて、1人で暮らすことが多くなった祖母を放っておけない思いがありました。
でも、祖父母への思いを伝えることはできませんでした。実の両親よりも祖父母を選ぶんだって思われたくなかったんです。だから、進学について考えていることがあると親を説得しました」
離れて暮らす間に父親に会うのは年に1~2度ほどだった。離れて暮らす前から、「父親は本音で話し合える関係ではなかった」と史帆さんは振り返る。
「一緒に暮らしていたときから、父親は私に対して何も言いませんでした。家に帰って来ても静かにテレビを見ながらご飯を食べて、母親が話しかけると答えるぐらい。家族3人は母親がいないと成立しないような感じだったんです。
それが離れて暮らしてからは、母親は月に1度は様子を見に来てくれていたけれど、父親はお正月やお盆などに大勢の中の1人として顔を合わせるだけ。特に会話はありません。父親も母親と同様に私が地元に残りたいと言ったときに反対はしませんでしたが、私の思いを尊重してくれていたというより、どうでもよかったという感じがしていました」
【父親からちゃんと愛されていた。次ページに続きます】