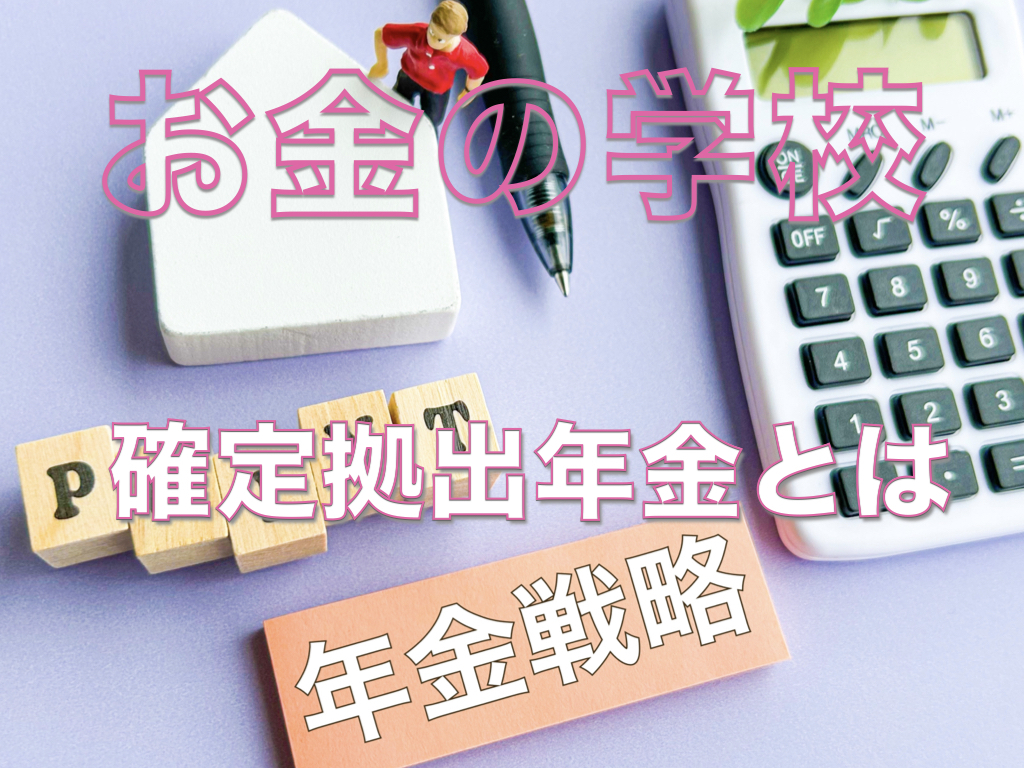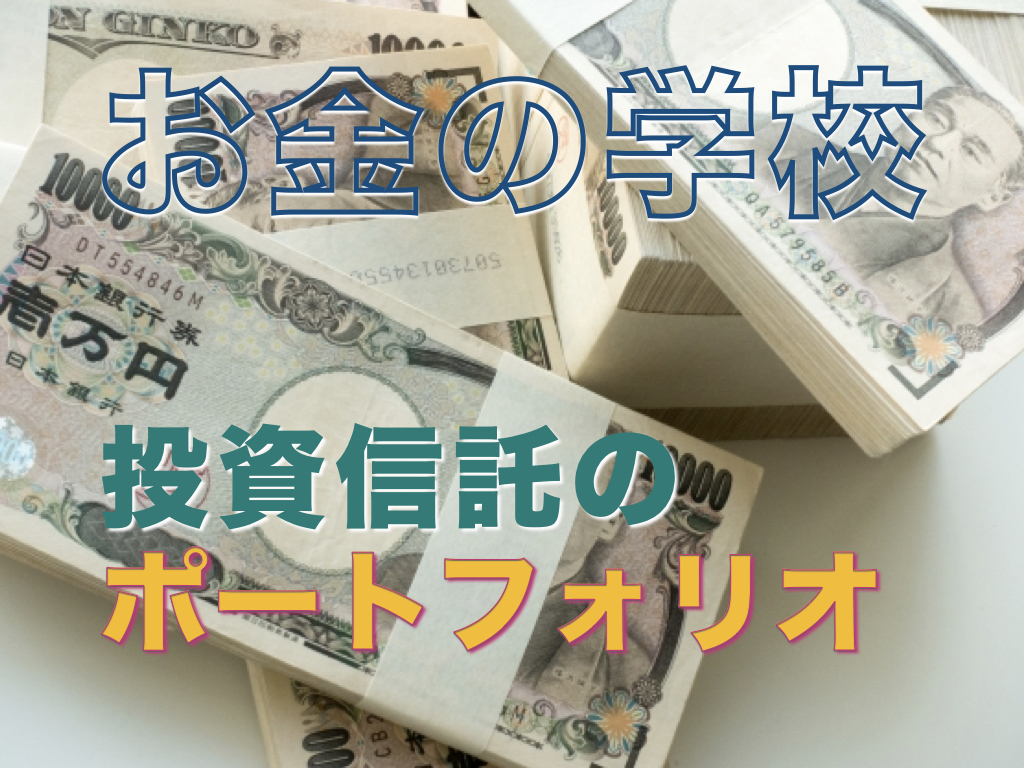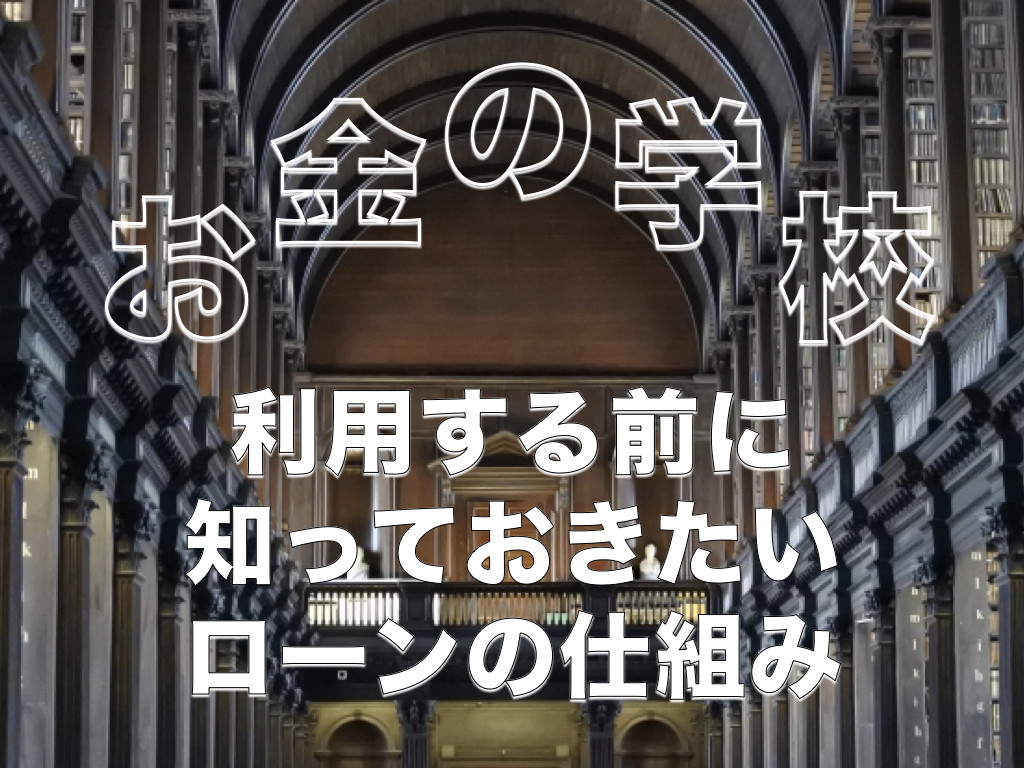近年、「空き家」について全国的に問題視されています。これは社会問題であり、老朽化した空き家が放置されることで、防災・防犯・衛生面などさまざまなリスクにさらされることになります。そうした問題に対処するために制定されたのが「空き家対策特別措置法」です。今回は、この法律の概要や改正ポイント、空き家を相続した際の注意点についてなどを見ていきましょう。
100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、ライフブック(R)を提唱する、独立系ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。

目次
空き家対策特別措置法とは何か?|わかりやすく解説
2023~2024年の改正ポイントとその影響
相続で空き家を取得した場合の注意点は?
特定空き家に認定されたらどうなる?
空き家対策に使える補助金・特別控除制度まとめ
まとめ
空き家対策特別措置法とは何か?|わかりやすく解説
まずは「空き家対策特別措置法」について見ていきましょう。
制度が誕生した背景と目的
「空き家対策特別措置法」は、正式には「空家等対策の推進に関する特別措置法」といい、2015年に施行されました。少子高齢化の影響で空き家が増加し、地域の景観悪化や災害時の倒壊リスク、不法侵入などのトラブルが増えて社会問題化していることが法律制定の背景となっています。
この法律は、空き家の適切な管理を促し、地域の安全や環境を守ることを目的としています。
「特定空き家」の定義とは?
この法律のキーワードとなるのが「特定空き家」という分類です。単なる空き家ではなく、以下のような条件を満たす空き家が「特定空き家」に指定されます。
・倒壊など著しく危険な状態
・衛生上有害な状態
・適切な管理がされておらず、著しく景観を損なっている
・周囲の生活環境の保全に悪影響を与えている
市区町村はこれらの空き家に対し、調査・指導・勧告・命令を行なうことができます。
なぜ今注目されているのか?
「空き家問題」が社会問題化していることに加え、2023年の改正により、管理不全な空き家にも行政が関与できるようになり、その対象が広がったことが注目を集める理由です。また、「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除されるなど、経済的な負担も大きくなるため、所有者にとっても軽視できない問題となっています。

2023~2024年の改正ポイントとその影響
2023~2024年の法改正のポイントやその影響について解説します。
何がどう変わったのか? 改正の概要
2023年の法改正では、これまで「特定空き家」に限られていた行政の対応範囲が拡大され「管理不全空き家」という新しい区分が追加されました。見た目には安全なように見えても、適切な管理が行なわれていない空き家に対しても、指導や勧告ができるようになったのです。
特定空き家の判断基準の厳格化
改正前は倒壊する恐れが明確でないと「特定空き家」には認定されませんでしたが、改正後は「周囲への悪影響」がより広く判断されるようになりました。たとえば、庭の草木が伸び放題で隣地へ侵入している場合なども対象となる可能性があります。
改正施行日と今後のスケジュール
改正法は2023年12月13日に公布され、段階的に施行が進んでいます。2024年4月以降は自治体ごとの条例整備が進み、より具体的な運用が始まっています。今後は、自治体の対応がますます厳格になると予想されています。
相続で空き家を取得した場合の注意点は?
空き家となっている家を相続して取得するケースもありますが、この場合の注意点はどのようなところにあるのでしょうか?
「相続放棄」しても空き家の管理責任は残る?
相続放棄は、その手続きに時間を要するため、相続放棄が正式に認められるまでは「管理義務」が残ります。この期間に放置していることで、思わぬ損害賠償などを求められる可能性もあります。相続放棄する予定でも、最低限の管理や報告は行なう必要があります。
登記未了の空き家がもたらすリスク
空き家の所有者が亡くなっても名義変更(相続登記)を行なっていない場合「所有者不明土地」として扱われ、自治体の対応が遅れたり、管理の責任が曖昧になったりすることで、親族間のトラブルや行政処分を受けるリスクが高まります。
2024年からは相続登記が義務化されており、正しく登記することが重要です。
特定空き家に認定されたらどうなる?
所有している空き家が特定空き家に認定された場合の影響や、行政の関与はどのようなものなのでしょうか?
固定資産税の軽減措置が解除される
住宅用地として固定資産税の軽減措置が適用されている土地は、固定資産税が土地の面積が200㎡未満の場合1/6、200㎡以上の場合1/3に軽減されます。しかし、特定空き家に「勧告」が出されるとこの軽減がなくなり、翌年度からは最大6倍近い税額が課されることになります。これは事実上の「経済的ペナルティ」といえます。
命令・行政代執行の流れ
勧告を無視し続けると、「命令」が出され、さらに従わなければ行政代執行(市町村が強制的に解体などを実施)に至ります。この際の費用はすべて所有者に請求されるため、大きな負担となります。
「勧告」を受けたら何をすべきか?
「勧告」を受けてしまった場合、すぐに専門家(不動産・行政書士など)に相談し、修繕や解体の可能性、売却・賃貸などの活用法を検討しましょう。また、自治体によっては改善に向けた相談窓口や補助制度もあります。

空き家対策に使える補助金・特別控除制度まとめ
空き家問題には処分だけでなく、対策のための補助金制度や特別控除などの支援策も用意されています。
解体費用やリフォームへの補助金
多くの自治体では、空き家解体費用やリフォームに対して補助金を設けています。たとえば、解体費用の一部(最大50万円~100万円)補助や、耐震改修費用の補助などです。補助金には予算枠と申請期限があるため、自治体の窓口で早めの確認が必要です。
空き家譲渡所得の「3,000万円特別控除」活用法
相続した空き家を一定の条件で売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。この制度を活用することで、売却益にかかる税金の負担を大きく減らすことが可能です。条件としては、被相続人が一人暮らしだったことや、譲渡期限などがあります。
各自治体の支援制度の調べ方
たとえば、「○○市 空き家 支援」などでインターネット検索すると、各自治体の支援制度が掲載されているページを見つけることができます。また、市役所の住宅政策課や空き家対策担当に問い合わせてみるのもいいでしょう。市区町村だけでなく、都道府県でも支援制度を準備しているケースもありますので、有効に活用しましょう。
まとめ
空き家は「放置しておけば問題ない」という時代はすでに終わりました。空き家所有者の責任は今後も重くなっていくことが予想されます。自分や家族の将来のためにも、早めの対策と正しい知識を持つことが重要なのです。
さまざまな金融商品が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。ご自身のライフプランを考えるときには、生命保険や金融商品の販売をせずに中立的な立場からコンサルティングに徹する独立系のファイナンシャルプランナーへの相談をお勧めします。
●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/)
●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。
株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)