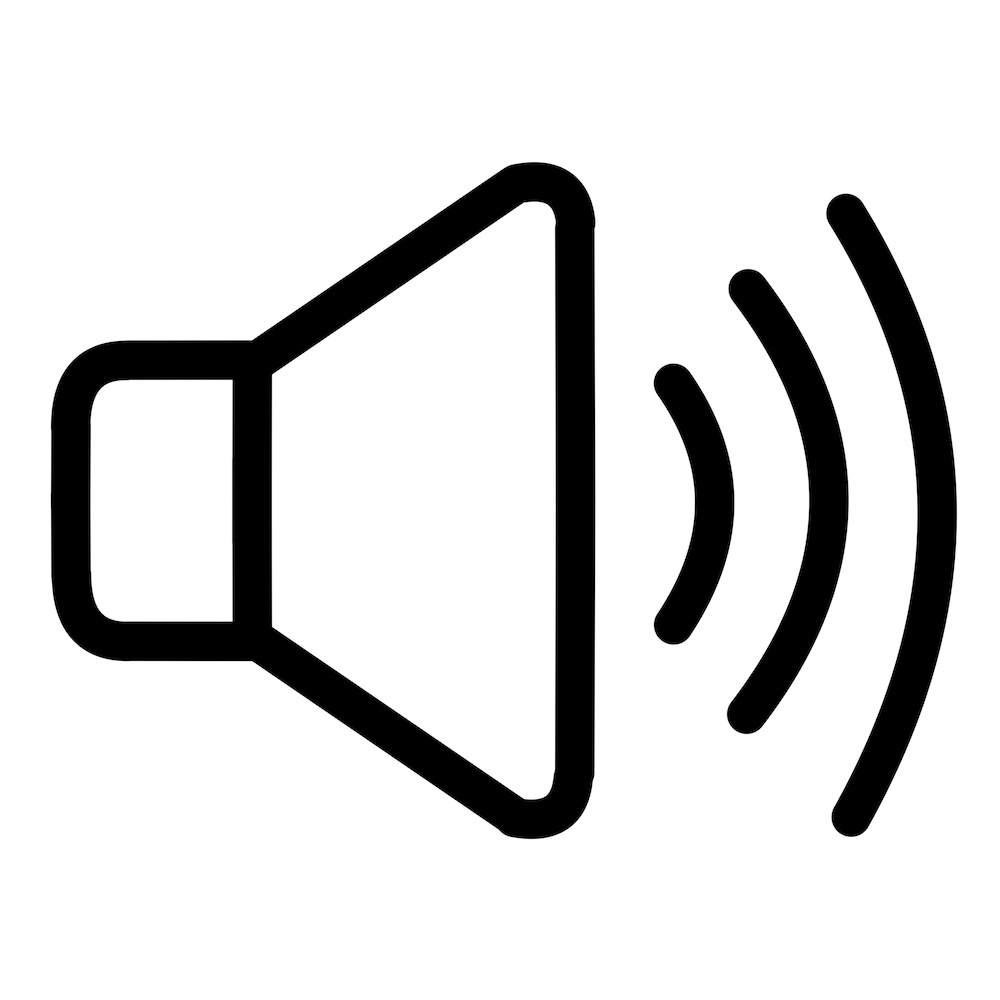文/砂原浩太朗(小説家)

晩年のクーデターで政敵を葬り、魏のなかで比肩する者なき実権をにぎった司馬懿仲達。が、みずからは臣下の地位を越えることなく生涯をおえる。彼の子や孫たちは、いかにして乱世を平定していったのか。
【前編はこちら】
司馬師登場
西暦251年、司馬懿が没し、長男の司馬師が跡を継ぐ。ときに44歳。司馬師は正妻が生んだ嫡子であり、はやくから後継者となることがきまっていた。家門の勢威を高めるべく三たび結婚を繰りかえすなど、一族のため生きることを運命づけられた人物といえよう。父の履歴をなぞるようにして昇進をかさねており、翌年には大将軍に任じられる。おなじ年、魏は諸葛恪(孔明の兄・瑾の子)ひきいる呉軍に大敗を喫したが、司馬師はみずからの責任であるとして諸将の罪を問わず、かえって人望をあつめた。すでに天下取りを視野に入れていたのだろう、目先の勝敗に一喜一憂するのでなく、有徳の士という評判を得ようとしたものと思われる。
254年、司馬師を除こうとする計画が露見し、背後にいたとされる皇帝・曹芳が廃位に追い込まれた。かわって帝位についたのは、文帝・曹丕の孫にあたる14歳の曹髦(そうぼう)。英明ではげしい気性の持ち主だったらしく、これがのちに悲劇を招く。
司馬家の側からすれば、みずからに害意をもつ皇帝などそのままにしておけぬのは当然だが、やはり反動は大きかった。翌年、軍事上の要衝たる寿春(安徽省)で司馬師の排斥をくわだてた反乱が起こる。眼病をわずらっていた司馬師は、みずから征討にむかい、鎮圧には成功したものの病が悪化、日を経ずして世を去った。父の跡を継いでわずか4年、48歳という働きざかりである。
司馬昭の活躍
司馬師には男子がなかったため、跡を継いだのは同母弟の司馬昭だった。兄より3歳年下の45歳で、残りの生涯を天下取りの地ならしについやすこととなる。
2年後の西暦257年、司馬氏の専横にたいして、またも反乱の火があがる。こたびの首謀者である諸葛誕は、孔明とおなじ一族につらなる人物。孔明が「龍」、呉につかえた兄の瑾が「虎」と評されているのにくらべると、魏の「狗(いぬ)」と称され分がわるいが、兵士たちの信頼も厚いひとかどの武人だった(諸葛恪および誕については、第1回後編参照)。この鎮圧に成功した司馬昭の勢威はもはや被いようもなく、危機感をおぼえた皇帝・曹髦は、みずから司馬一族の討伐をくわだてる。が、まともに従う家臣もないまま計画は洩れてしまった。結果、絶望した皇帝が奴隷をひきいて悲壮な突撃を敢行、乱戦の只中で討ち取られるという異様な事態が生じる(260)。ほとんど無謀というほかない振る舞いだが、英雄的気質をもつ曹髦は、魏王朝の衰退をだまって見ていることができなかったのだろう。
司馬昭は簒奪(さんだつ)の地ならしを慎重にすすめていたから、皇帝の命まで取る気はなかったはずである。あやうい局面だったが、直接の下手人に罪をかぶせるかたちで、どうにか切り抜ける。すでに、表立って司馬一族を糾弾する声はあがらなくなっていた。つづいて帝位につけた曹奐(曹操の孫にあたる)が、魏王朝最後の皇帝となる。
3年後、司馬昭はついに蜀の討伐へ着手する。当時、蜀では宦官の黄皓が国政を牛耳り、あきらかに衰退への道をたどっていた。名将・とう艾(とうがい。「とう」は登におおざと)や鍾会のはたらきで蜀は滅亡(第7回参照)、ついに三国の一角が崩れたのである。
これを見届けた司馬昭は、晋王の位へ就いたのち世を去った。西暦265年、55歳の死である。王は皇帝に次ぐ位だから、最後の布石というところだろう、司馬氏の天下は、もはや目前にせまっていた。むろん父や兄のはたらきあってのことだが、たった10年でその道すじを確固たるものとした司馬昭の功績は多大といわざるを得ない。筆者には、もっとクローズアップされてよい人物と思える。
【武帝・司馬炎~三国統一さる。次ページに続きます】