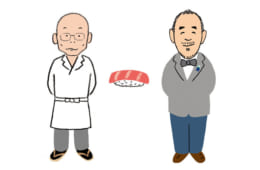写真・文/山本益博

大とろ(すきやばし次郎)
今から50年ほど前の東京の「握り鮨」には、季節がありました。例えば、こはだ。「しんこ」と呼ばれるこはだの幼魚がすし屋に登場するのが、秋風の立ち始める9月でした。そこから春の3月頃まで。こはだはしだいに大きくなって、「このしろ」と名前を変えるようになります。
こはだに代わって握られるのがあじで、あじは春から秋まで、夏が美味しい魚でした。くるまえびも夏が旬の海老でした。
ところが、流通が発達すると、毎日日本全国から築地に魚介が届くようになり、こはだもあじも一年中に握られるすし種になりました。便利な世の中ではありますが、季節感が乏しくなって昔ながらの「江戸前」の握り鮨ファンは寂しい限りですね。
「江戸前」の握り鮨の主役、まぐろは11月からが旬で、12月1月の真冬の津軽海峡で漁師が命懸けで獲ってきた本まぐろこそ、酢めしにぴたりとあって、「江戸前」の醍醐味が楽しめる握りと言えましょう。
そのほか、冬のすし種と言えば、忘れてならないのが、さばとはまぐり。さばは締めさばにして握るのですが、脂がのりすぎているさばは「みそ煮」こそ向いていますが、締めさばには適しません。もちろん、脂がなければ美味しくありません。そのころ合いを見つけるのが、難しい仕事です。この「締めさば」、鮨としては最も歴史あるすし種です。
はまぐりは冬の貝の横綱で、甘く煮含めてから握ります。「江戸前」のすし種としては、江戸時代からある古参格です。

さば(すきやばし次郎)

はまぐり(すきやばし次郎)