
約2年後に迫った、東京オリンピック・パラリンピック競技大会。スポーツが人間の営みであり、<人類がみずからの手で築き上げてきた有形・無形の成果の総体>(デジタル大辞泉)が文化であるとするならば、東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、文化の祭典という見方をすることもできます。そして、多くの外国人が訪れるであることを考えると、日本の文化や伝統を世界に伝える好機と捉えることもできます。
こうした趣旨を踏まえ、文化庁では次世代に向けたオリンピック・レガシー(有形無形の社会的遺産)を生み出す文化プログラムの周知と普及を目指し、日本各地の文化資源の発掘や発信、国際文化交流などをテーマにしたシンポジウム「Culture NIPPON シンポジウム」を全国4会場で開催します。
その第1回目が11月9日に、京都府の長岡京市で行なわれました。今年創設50周年を迎えた文化庁は、芸術文化の振興、文化財の保存・活用、国際文化交流の振興などの機能強化を目指し、10月から京都へ移転しました。そうしたことも関連してか、会場は多くの人で賑わいました。
イベント冒頭にはオープニングアクトとして、日本の最も古い伝統楽器である和太鼓で新しい音楽活動を行なう「倭太鼓 飛龍」と、いま注目を集めつつあるダンス&ラップユニット「FE OSAKA」が登場。和太鼓とストリートダンスが融合したパフォーマンスを披露しました。その後、村田善則文化庁次長、山内修一京都府副知事、「日本書紀によると、長岡京遷都は518年のことで、今年がちょうど1500年目。われわれはそうしたPRも行なっています」と中小路健吾長岡京市長が挨拶しました。

「スポーツの祭典は、文化の祭典!」をテーマにした「Culture NIPPON シンポジウム2018」が行なわれました

挨拶をする「倭太鼓 飛龍」の和太鼓と「FE OSAKA」のメンバー

「2020年の東京オリンピック・パラリンピックを、日本が誇る地域性豊かで多様な文化を発信する千載一遇のチャンスと捉え、全国津々浦々で文化プログラムを実施し、1人でも多くの方々に文化の素晴らしさや魅力を体験していただきたい」と意気込みを語る村田善則文化庁次長

「京都には有形無形の文化財がたくさんあり、その文化は、千年の長い歴史の中で独自に発展してきたというよりも、全国でそれぞれの地域で育まれている文化との融合によって京都の文化が創られてきました」と、周辺地域の関わりのなかで京都の文化があるなど、国際的な観点を含む交流をキーワードに挨拶をした山内修一京都府副知事

「日本書紀によると、長岡京遷都は518年のことで、今年がちょうど1500年目。また、2020年のNHK大河ドラマ『麒麟が来る』は明智光秀が主人公で、その娘細川ガラシャこと玉が細川忠興と結婚し、新婚時代を過ごしたのが長岡京市の勝竜寺城です」と長岡京市をPRする中小路健吾長岡京市長。
■それぞれの立場から、文化の力を提唱
その後の第一部では、ブリティッシュ・カウンシルの湯浅真奈美氏、俳優の辰巳琢郎氏、Deportare Partners 代表の為末大氏、社会福祉法人グローの田端一恵氏が、それぞれ立場からショートプレゼンテーションを行ないました。
湯浅氏からは、2012年ロンドンオリンピック・パラリンピックが文化の祭典としてオリンピックを捉える契機になったことが紹介され、さまざまな文化プログラムによって、英国の人々が、大会をホストすることを通じて、わくわくするイベントに参加すること目指したことが紹介されました。こうしたアプローチは、現在のIOC(国際オリンピック委員会)にも継承され、現在オリンピック・パラリンピックが文化の祭典でもあることの啓蒙活動につながっています。
京都に長く住む辰巳氏は、専門領域のひとつである「食」についてリラックスしたトーク。なかでも、魚食の習慣が減ってきていること、それに伴い漁業を中心とした特色豊かな地域文化が衰退していること、「知足」(満足すべき限度や、自分の本文を理解すること。『老子』三十三章)といった価値観の大切さなど、独自の視点からの憂い漂う語りには、多くの聴衆が耳を傾けていました。
日本でスポーツという言葉から連想されるのは、サッカー、野球、陸上競技などと思うが、スポーツ発祥の地とも言われる英国では、もう少し範囲の広い言葉であることを紹介したのが為末氏。「スポーツの語源には、日常から離れ、憂さを晴らすなどの意味もあり、初期のオリンピック選手は、詩を詠んだり、歌を歌い、完璧な人間、美しい人間を目指すという意味合いもあった」ことが紹介されました(「スポーツ」の起源について詳しくは、スポーツ庁のウェブサイトを)。そのうえで、スポーツと、文化やアートは離れておらず、その融合こそ、今後は考えていくことが大切ではないか、という提案がありました。また、障害者スポーツの大会がパラリンピックと呼ばれるようになったのは1964年の東京大会からで、ロンドン大会では「Unlimited(無限の、無制限の、果てしない、いっぱいの)」がテーマにして成功を収めたことを例に挙げながら、2020年の東京大会でも、日本の文化、ひいては日本とは? を発信する機会を得たので、何を伝えるのかが大事になるであろう、という視点が示されました。
ちなみに為末氏は、アスリートをサポートするうえでも、どんなメッセージを伝えるために競技に臨んでいるかを持とうということを提案しているそうです。そして、個人的な意見として従来の国別に競っていたオリンピック・パラリンピックに、難民やLGBTなどの自分らしさというアイデンティティーを問うケースが新しい動きとしてあることを紹介しました。
障害のある人の表現活動の紹介に核を置くことだけに留まらず、一般のアーティストの作品と共に並列して見せることで「人の持つ普遍的な表現の力」を感じてもらうことを狙いとした、ボーダレス・アートミュージアムNO-MA(滋賀県)の活動にも携わる田端氏は、「誰もが参加できる芸術活動の可能性」と題し、いくつかの作品を紹介しながら、プレゼンテーションを行ないました。会場から驚きとともに共感する反応があったのは、障害のある人の作品がきっかけとなり、困った行為と捉えられがちの行為が、別の目的のある行動であることが「発見」され、相互理解が深まった事例です。作品が新聞などで伝えられて理解が進むと、「あなた、アーティストなのだってね。多分アートの題材になるのだろうからどんどん見てください」と、それまではネガティブな目で見られていた行動が、温かい応援のまなざしに変わったとか。こうしたエピソードが各地で起き始めていることが、田端氏のを通じて伝えられ、アートや文化の持つ可能性について考えを深めるきっかけとなりました。

大会前の4年間から、さまざまな文化プログラムを英国全土で行ない、大会開催の約1か月前には「Once In A Lifetime(一生に一度きり)」というテーマで、ロンドン2012フェスティバルという祭典が行なわれたことなどを紹介した湯浅氏。「2020年の東京大会をホストする機会が、その後の日本、そしてその他の国々の社会に、大きな良い影響をもたらし、文化・芸術が大きく発展するということを期待しています」

「『食いしん坊万歳』というテレビ番組で3年間全国を回り、本当に日本の食はすごいと思いました。おいしいだけでなく、地方ならではの価値観がある。独自のものが、それぞれ素晴らしいことに改めて気付きました」と自身の経験を中心に、興味深い話を披露した辰巳氏。

「2020年には、同じ国だから応援しているということだけではく、女性が女性のアスリートを応援するなど、いろいろな軸で、あの人は自分の代理だという気分で応援するスタイルが広がるでしょう。国以外のもう一つのアイデンティティという軸で応援できるしくみを日本が用意できたとしたら、新しくて面白いのではないかと思っています」とアイデアを披露した為末氏。
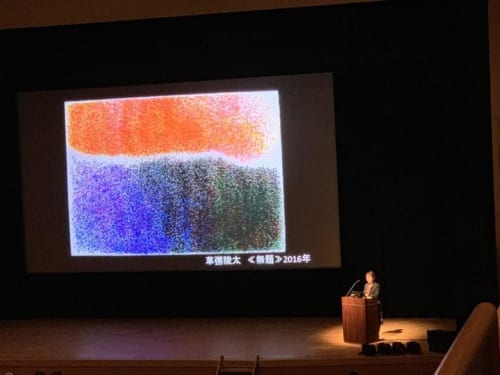
アールブリュットとは、既存のメソッドや流行に左右されず、自身の血から湧き上がるもので、衝動のままに独創的に表現された作品のこと。ボーダレス・アートミュージアムNO-MAは、この精神に触発をされて、現代アーティストなどプロの作品も含めた展覧会などの活動を行なっている、と話す田端氏。
■活発な議論が繰り広げられたシンポジウム
第二部は、モデレーターに日本文学研究者で国文学研究資料館長・東京大学名誉教授のロバート・キャンベル氏を迎え、村田氏、辰巳氏、為末氏、湯浅氏、田端氏のパネラーとともに「Culture NIPPON ~2020年とその先の未来へ向かって~」と題したパネルディスカッションを行ないました。
各パネラーからは、プレゼンテーションの補足や、より踏み込んだ意見などが披露され活発な議論が交わされました。たとえば、キャンベル氏は「私は文化庁の京都移転(2021年年度末までに実施予定)が発表されたとき、新聞に、ブエノスアイレスやロンドンなど、海外に移転したほうがいいのではないかということを7割は真面目に書きました。日本にいて外交広報するだけではなく、パートナーを世界中に作ったり、持続的な関係をつくっていくことも、これからの文化庁に求められる、一つの大きな役割だと思います」と意見すると、村田氏は「京都は常に文化的な発信を続けてきました。それは京都や日本国内にとどまらず、むしろ世界に向けていろいろなことを発信してきています。われわれとしては、閉じこもるのではなく、外に打って出るための移転ということも考える必要がある」など、議論は幅広い話題に及びました。

この「Culture NIPPONシンポジウム」は、12月10日(月)に第2回の東北大会(岩手県盛岡市)、1月20日(日)に第3回の中国・四国大会(徳島県徳島市・徳島県立21世紀館)、そして2月9日(土)には第4回東京大会(東京都江東区・ティアラこうとう江東公会堂大ホール)が行なわれます。京都大会の模様は、Culture NIPPON シンポジウム公式サイト(https://culture-nippon-s.com/)にも掲載予定です。

【Culture NIPPON シンポジウム2018関連記事】
※文学が繋ぐ人と人~Culture NIPPON シンポジウム 東京大会【参加者募集のお知らせ】
※文化庁主催「Culture NIPPON シンポジウム2018」京都大会が行なわれました
※文化庁主催「Culture NIPPON シンポジウム2018」東北大会が行なわれました
※文化庁主催「Culture NIPPON シンポジウム2018」中国・四国大会が行なわれました
※文化庁主催「Culture NIPPON シンポジウム2018」東京大会が行なわれました



































