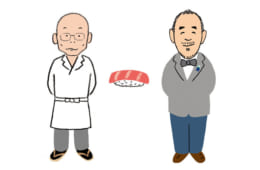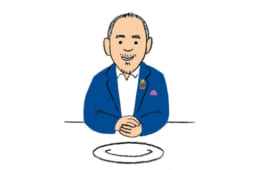文/山本益博

京都『浜作』の「鱧となすのお椀」【ひと皿の歳時記134】より
昔から日本料理は椀刺しが華と言われてきましたが、「椀刺し」とは、日本料理の要諦、「お椀」と「お造り」のこと。日本料理では「お椀」のお出汁と、「お造り」の庖丁が料理人のいちばんの腕の見せ所というわけです。
お出汁は、水をベースに昆布とおもに鰹節を煮出して作ります。料理屋は最上質の素材を使いながら、昆布にも鰹節にも偏らない、柔らかなまあるい「うまみ」を目指します。それには、豊かな経験と繊細な味覚が必要となります。
お造り、いわゆる刺身は、一度いのちを落とした魚が、料理人の庖丁の技術によって、いのちを蘇らせる調理と言ってよいでしょう。

元麻布「かんだ」の「紅葉鯛のお造り」【ひと皿の歳時記~第10回】より
懐石料理では、わずかな例外を除いて、お椀の前にお造りが出てきます。お造りでは鯛が一番の御馳走ですね。薬味はわさび、調味料は醤油。でも、この鯛をいただくのに、誰もがいつもするように、わさびを溶いた醤油に鯛の刺身をつけて食べては、鯛の本領を知ることはできません。
まず、鯛の刺身を一切れ、そのまま何もつけずにいただきます。こうすると、鯛の刺身の角の鋭い切れ味が分かり、庖丁の冴えが鯛のいのちを今一度蘇らせていることが舌の上から伝わってきます。外国人から見れば、魚の「切り身」にしか見えないものが、私たちには「刺身」と感じられる瞬間です。
その身をゆっくり噛んでゆくと、まず鯛の香りと甘みがにじみ出てきて、醤油をつけていただいたのでは決して分からない鯛の本性が姿を現します。しかし、このとき、同時に塩気、塩分が欲しいと舌と身体が要求しはじめます。そこで、箸の先に醤油をちょっとだけつけて口の中に含むと、突然、うま味が口の中で広がりはじめるのですね。二切れ目は鯛の身にわさびを載せていただき、そのあとは同じ要領で鯛を味わってゆきます。こうすることで、鯛は初めて成仏するのではないかしらん。
そして、いよいよ「お椀」の登場となります。このときに、私は次の儀式をおこなって、「お椀」をいただく万全の準備をします。前回、申し上げましたが、懐石料理で使う箸は、両方の先が細く、どちらを使ってもいいようになっています。一方を使い始めたら、もう一方は、本来は、神様が使う箸先ということになっています。でも、このとき、私は神様の許しを乞うて、箸先を返します。つまり、「お椀」を味わうのに、使っていない箸先でいただこうというもの。醤油がしみこんだ箸先を、微妙な加減のお出汁のなかにそのままつけ込みたくないのですね。
箸先を代えるばかりではありません。「お椀」が目の前に現れたら、一度ゆっくり深呼吸します。カウンターの先、目の前に板前さんがいても堂々と一呼吸します。こうすることで、心が鎮まり、お椀を味わう集中力が生まれるんですね。なぜ、そんなことをするのか、と問われれば、フランス料理や中国料理のようにバター、クリーム、油を一切使わずに調理した料理は、皿のほうから「美味しさ」は立ち上って来ず、こちらから「美味しさ」を探しにゆかなければならないからです。水が基本になっている料理とはそういうものなんですね。