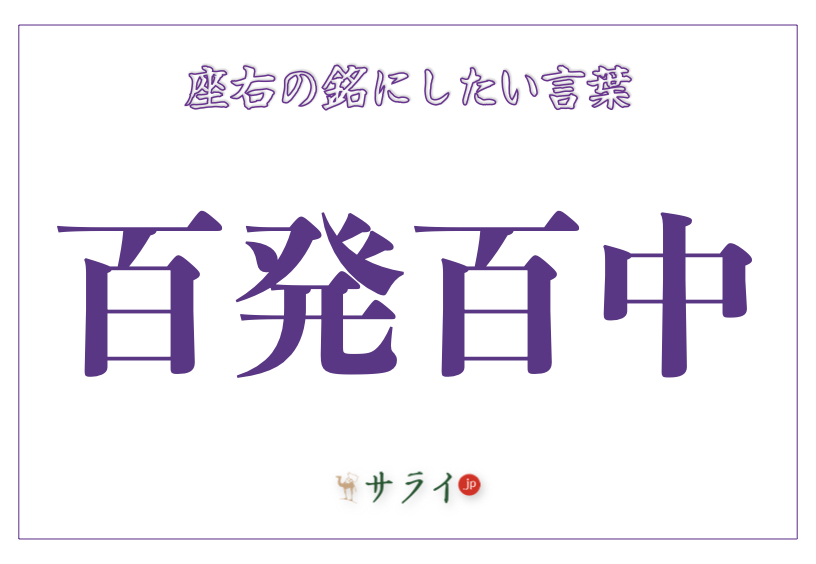伝兵衛蔵

九州新幹線の終着駅、鹿児島中央駅から鹿児島本線に乗り換えて約35分。鹿児島の本土西端にあるいちき串木野市。古くから遠洋マグロ漁業で栄えた港町で、日本有数の産出量を誇った金山の町としても知られる。
濵田酒造は、明治元年創業。本格芋焼酎『海童』、『赤兎馬』など伝統の銘柄で全国的な知名度を誇るが、ライチのような香りで一世を風靡した『だいやめ』、甘芳ばしい麦焼酎『うかぜ』、ボタニカルフレーバーの『CHILL GREEN(チルグリーン)』など、進取の酒を世に問う気鋭蔵の側面も持つ。
濵田酒造には、コンセプトの異なる3つの蔵がある。創業時からの伝統的な焼酎造りを守る「伝兵衛蔵」。鉱山の奥深くで焼酎を製造、貯蔵・熟成まで手がける「金山蔵」。新鋭の設備で革新の酒を生み出す「傳藏院蔵」。
まず訪れたのは市街地にある「伝兵衛蔵」。初代、濵田屋伝兵衛の名を冠し、伝統的な焼酎造りを今に守る蔵である。

蔵の中心部には、巨大な木桶の蒸留器が据えられている。樹齢80年以上のメアサ杉(蒲生(かもう)杉)と竹のタガのみを用い、釘や接着剤を用いずに手技で組み上げられたこの蒸留器は、現役で稼働している。焼酎造りの黎明には主流だった木桶蒸留器だが、現在では、作ることのできる職人は日本でひとりだけになっているという。
この木桶蒸留器で造られる本格芋焼酎が伝兵衛蔵の代表銘柄『伝(でん)』である。
商品開発研究室長の原健二郎さん(52歳)は次のように話す。
「木桶での蒸留は、木の香りが焼酎に移って、独自の味わいが出ます。また、隙間から呼吸のように空気が出入りする構造のため、口当たりが柔らかいまろやかな酒に仕上がるのです」
木桶と甕の呼吸が美酒を生む

木桶蒸留器のある、梁を巡らせた大きな部屋には、巨大な貯蔵甕が並ぶ。原さんが甕の上の木蓋を外し楷を入れると、甘みのある柔らかな香りが漂う。
「貯蔵には、主に江戸時代に作られた和甕を用いています。和甕にはミクロの穴が無数にあり、やはり木桶と同様、呼吸のように空気が循環します」
この伝兵衛蔵は、事前予約制で見学ができる。明治元年から今に続く焼酎造りの現場をぜひ目にしたい。

伝兵衛蔵

鹿児島県いちき串木野市湊町4-1
電話:0996・36・3131
定休日:水曜
営業時間:9時〜17時(売店)
交通:JR串木野駅より車で約10分
蔵見学は事前予約が必要。1日2回開催(11時〜、14時〜、所要時間約40分)。料金は20歳以上は数種類の銘柄の試飲付きで500円。オリジナルグッズのおみやげが付く。
金山蔵


いちき串木野市街から北東の山地に向かう。北薩火山群の西側にあたるこの一帯の地下には、大小約40本もの鉱脈が走っており、古くから日本有数の金山・銀山として開発されてきた。このうちの西山坑と呼ばれた鉱山跡を、焼酎の貯蔵や熟成などに利用しているのが濵田酒造の「金山蔵」である。
総延長120km、16層にもわたる広大な坑洞の2層目が仕込み蔵と焼酎の貯蔵庫になっている。
専用のトロッコに乗り込むと、汽笛を合図に走りだす。運転士の薩摩弁による軽妙なアナウンスを聞きながら、坑洞の入口から地下に向かって約700mの距離を8分ほどかけてゆっくり進む。手が触れるほどに近い安山岩の壁には、人の手でうがたれた跡が残る。所々に地下水が伝い、ときおり帯状の鉱脈の線も見える。とくに白みがかった部分には、金が多く含まれているのだという。
終着点でトロッコを降りると、ひんやりと肌寒いほどだ。坑洞内は通年、気温19℃前後に保たれていて、湿気も多い。この環境が、焼酎の熟成には最適なのだという。
四方に伸びる坑洞には、貯蔵甕が無数に並んでいる。甕の中は熟成中の焼酎で満ちており、かぐわしい香りが立ちこめている。

坑洞の奥には、木造の小さな仕込み場がある。ここでは、江戸期の製造方法であるどんぶり仕込みと、江戸期以前に用いられたというカブト釜式蒸留器を復元し、古来の焼酎造りに取り組んでいる。

トロッコ体験および蔵見学は事前予約制。限定の焼酎を購入すると、坑洞内で最長5年保存し、満期に発送してもらえるサービスもある。

金山蔵
鹿児島県いちき串木野市野下13665
電話:0996・21・2110
定休日:月曜~金曜(祝日は営業)
営業時間:10時~17時
交通:JR串木野駅より車で約10分
蔵見学は要事前予約。土曜・日曜・祝日の1日2回開催(11時~、14時~、所要時間約75分)。料金は試飲付き2500円(20歳以上)、試飲なし800円。試飲付きコースはおみやげ付き。
傳藏院蔵


最新鋭の設備による気鋭の酒
最後に訪れたのは「傳藏院蔵」。濵田酒造の主力銘柄のひとつ、芋焼酎『海童』をはじめ、フルーティな香りを追求した『だいやめ』や『CHILL GREEN』、4種の原酒を用いた麦焼酎『うかぜ』といった気鋭の商品までを生み出す革新の蔵である。
串木野港にほど近い平野部に位置し、西を見れば東シナ海が広がり、晴れた日には甑島(こしきじま)の島影が見える。隅々まで清潔に保たれた工場には、全自動で麹米の浸漬と水切りをする装置や、巨大な回転式自動製麹(せいぎく)機をはじめ、最新鋭の設備が揃う。
傳藏院蔵を除く2蔵は見学可能。焼酎の過去と未来を造り出す酒を、蔵を訪れ味わいたい。
傳藏院蔵

鹿児島県いちき串木野市西薩町17-7
撮影/宮地 工 写真提供/濵田酒造