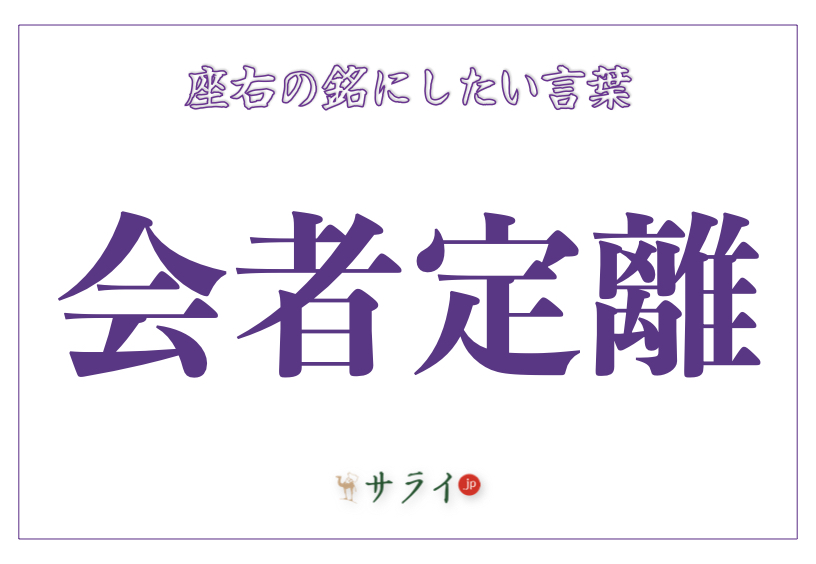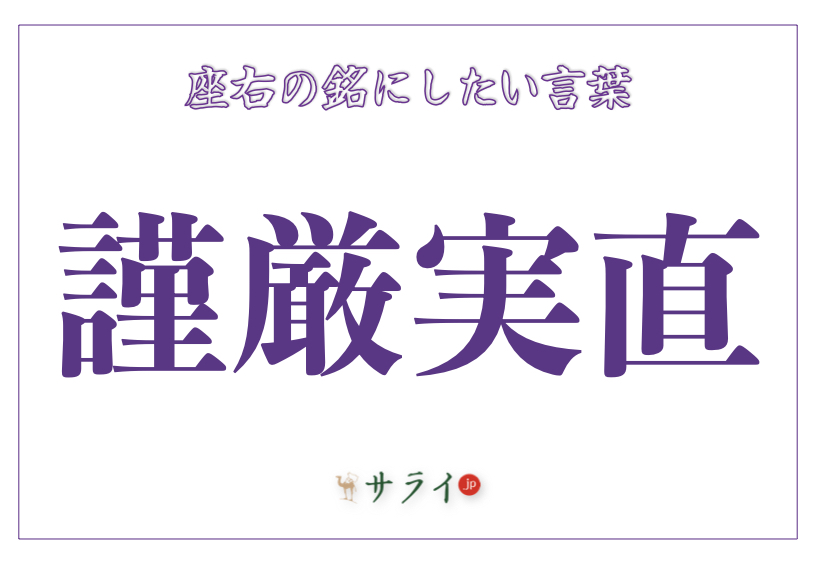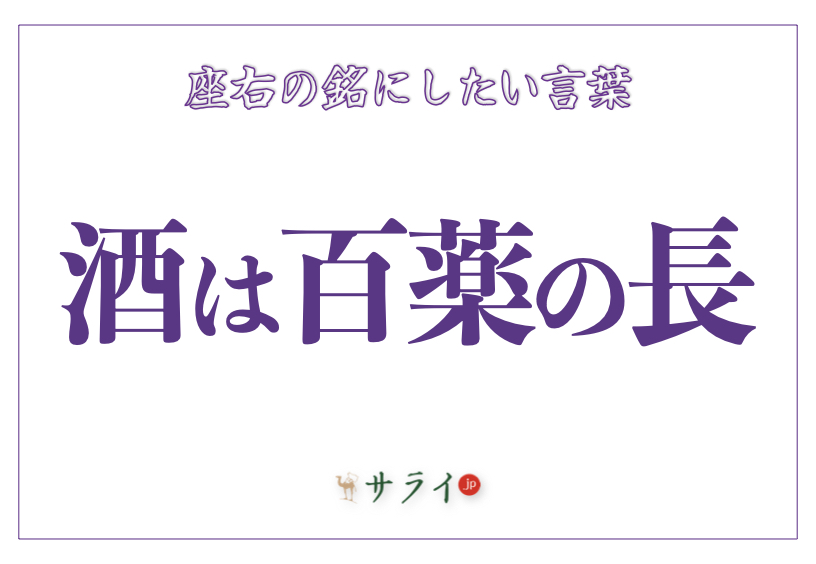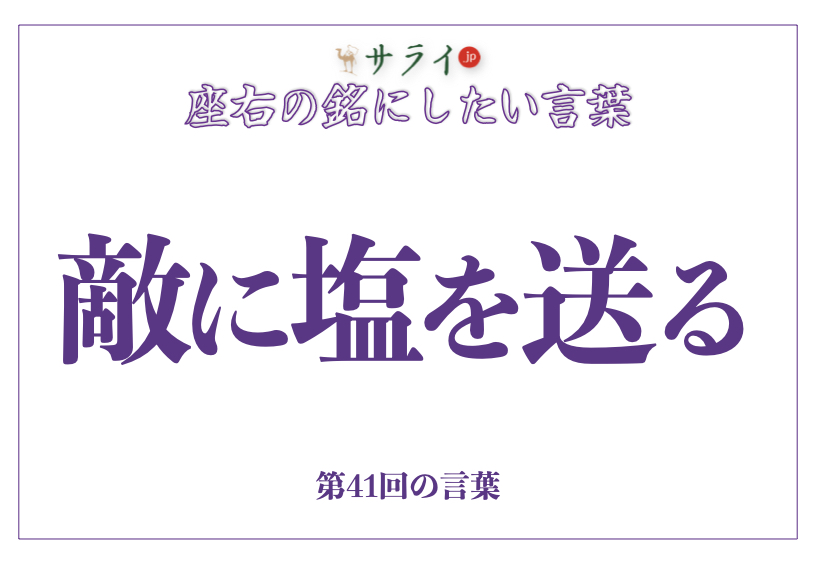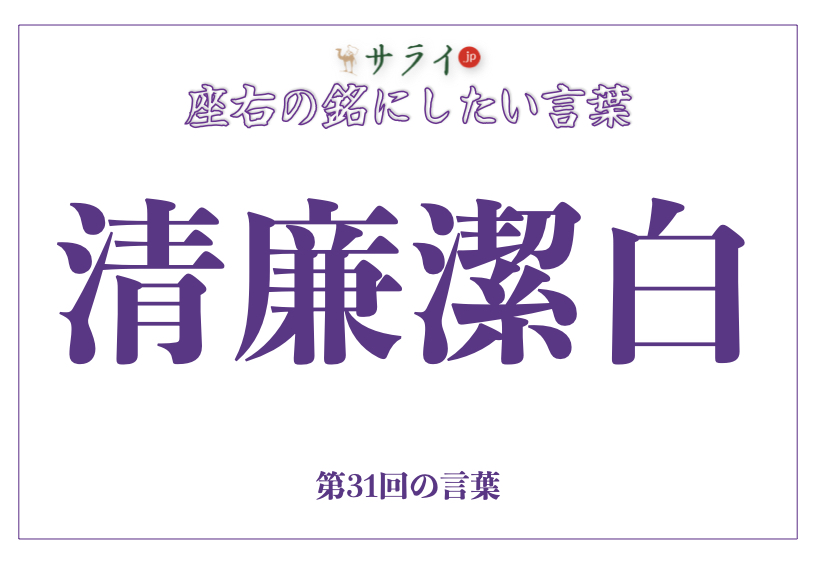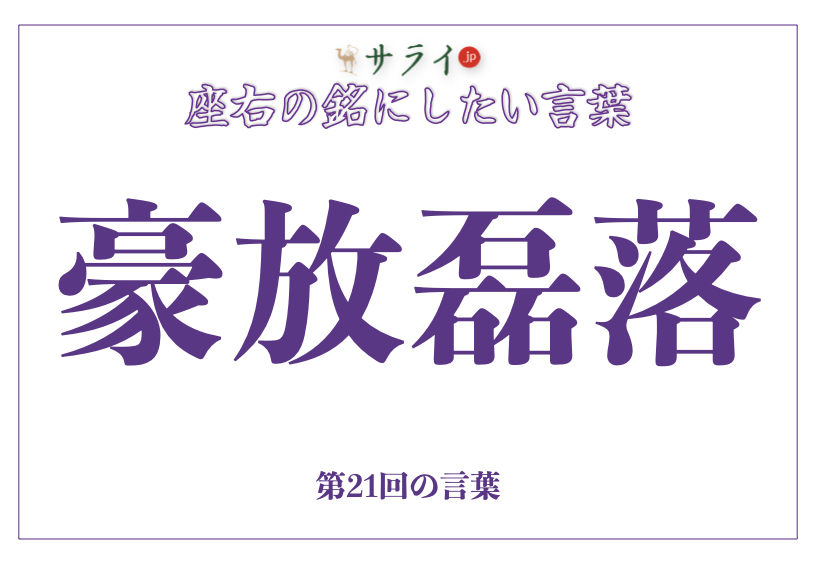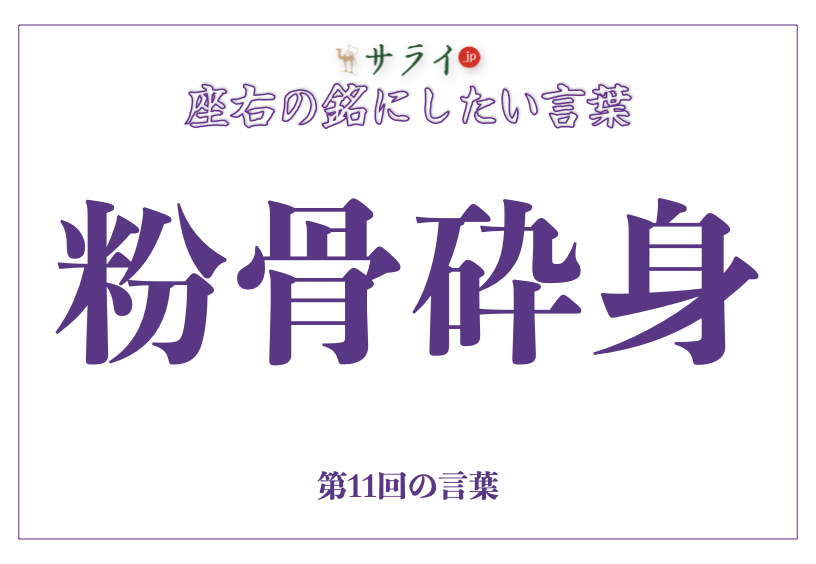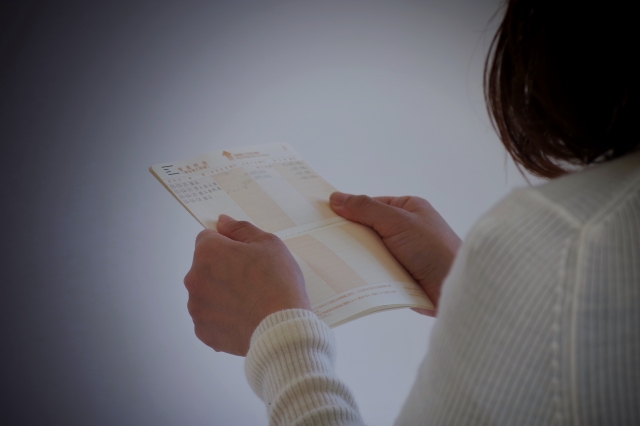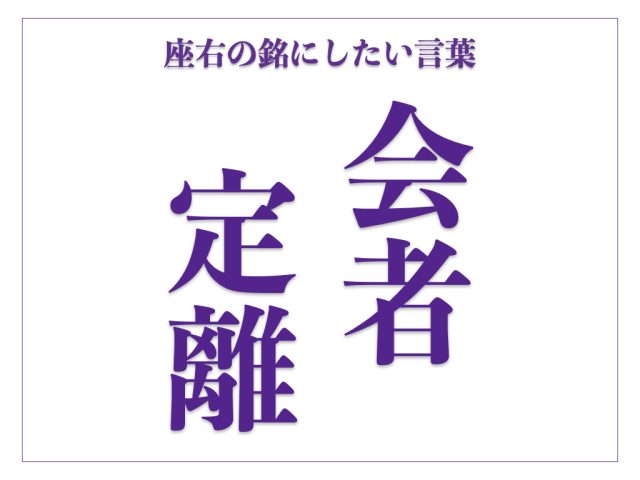
若き頃は、自分の生きる道、己のあるべき姿を思い描きながら、その目標を見失わないために格言、諺(ことわざ)、偉人たちが残した名言などを心に抱き、日々の生活を送っていたように思います。そうして半世紀以上を経て、己の人生を振り返った時、かつて思い描いていた姿とはかけ離れたものかもしれません。
しかし、人生折り返しと考えるならば、新たな「あるべき姿」を描き、生きることもできるようにも思います。そんな第二の人生のために、改めて座右の銘とする言葉を持つのはいかがでしょうか?
今回の座右の銘にしたい言葉は「会者定離(えしゃじょうり)」 をご紹介します。
目次
「会者定離」の意味
「会者定離」の由来
「会者定離」を座右の銘としてスピーチするなら
最後に
「会者定離」の意味
「会者定離」について、『⼩学館デジタル⼤辞泉』では、「会う者は必ず離れる運命にあるということ。人生の無常をいう語」とあります。
私たちは、この言葉を聞くと、どうしても「別れ」という側面を強く意識してしまいがちです。大切な人との別離、慣れ親しんだ場所からの退去、永遠ではない命。そう考えると、無常観や寂寥感に包まれてしまうかもしれません。
しかし、この言葉の本質は、もう少し深いところにあります。コインに裏と表があるように、「別れが必ず来る」ということは、裏を返せば、「だからこそ、出会いの瞬間や、共に過ごす『今』この時が、かけがえのない宝物なのだ」という真理を私たちに教えてくれているのです。
会社員時代、がむしゃらに働いていた頃には気づけなかった、何気ない日常の輝き。家族と食卓を囲む時間、友人と交わすたわいないおしゃべり、趣味に没頭する喜び。セカンドライフという新たなステージに立った今だからこそ、この「会者定離」の哲学が、日々の暮らしに深い彩りを与えてくれるのではないでしょうか。
「会者定離」の由来
この言葉の由来は、仏典の『遺教経(ゆいきょうぎょう)』の一節「世皆無常、会必有離」にあります。読み下すと「この世のものはすべて移ろいゆき、出会ったものは必ず別れる」と理解されます。
つまり、「生者必滅、会者定離(いきているものは必ず死に、出会った者とは必ず別れる)」という意味で、人生の儚さや変化の必然性を教えてくれます。
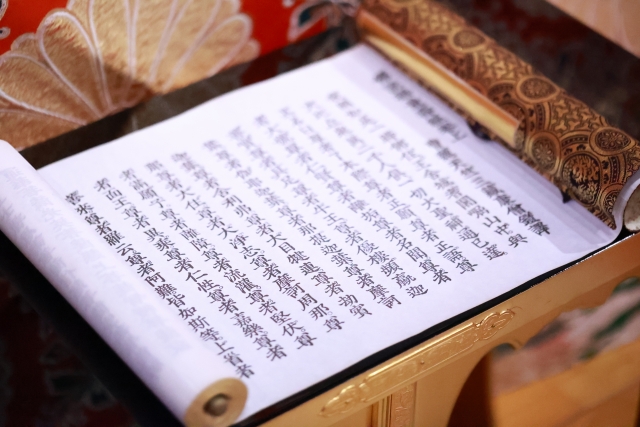
「会者定離」を座右の銘としてスピーチするなら
スピーチで「会者定離」を紹介する時には、聴く人の気持ちに寄り添いながら言葉の意味を丁寧に説明するとよいでしょう。難しい仏教用語なので、意味を噛み砕いて伝えることがポイントです。また、別れを単なる終わりとして捉えず、出会いの大切さを強調することで、聴衆の共感を得やすくなります。以下に「会者定離」を取り入れたスピーチの例をあげます。
「出会う」ための「別れ」の大切さを語るスピーチ例
私の座右の銘は「会者定離」という言葉です。出会った者とは、いつか必ず別れる運命にある、という意味ですね。
私は昨年、長年勤めた会社を定年退職いたしました。毎日顔を合わせていた同僚たちと会う機会も減り、一つの時代の終わりを感じたものです。また、大切に育ててきた子供たちもそれぞれ家庭を持ち、我が家から巣立っていきました。一つ、また一つと、別れを経験するたびに、寂しさを感じなかったと言えば嘘になります。
しかし、この「会者定離」という言葉を深く味わううちに、少し違う景色が見えてまいりました。別れがあるからこそ、一つ一つの出会いがどれほど奇跡的で、尊いものだったかに気づかされたのです。仕事に追われていた若い頃には、見過ごしてしまっていたかもしれません。
そして何より、別れは新しい出会いの始まりでもあります。こうして今、地域の皆様と新しいご縁をいただき、同じ時間を共有できている。これもまた、私がいくつかの「別れ」を経験してきたからこそ、たどり着けた新しい「出会い」なのだと感じております。
「会者定離」は、決して寂しいだけの言葉ではありません。別れがあるからこそ、今この瞬間を大切に生きようと思える。そして、これからの新しい出会いに、素直に心を開くことができる。そんな、人生の後半を豊かにしてくれる、温かい言葉だと、私は思っております。
最後に
時代を問わず、人との出会いと別れを重ねながら生きる私たち。「会者定離」はその歩みにやさしく寄り添い、人生を豊かに深めてくれる言葉です。
家族や友人との縁、仕事や地域のつながりなど、どれも一期一会。時には別れが訪れるかもしれませんが、その分、今この瞬間のご縁をより大切に、かけがえのないものとして受け止められるはずです。
●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com