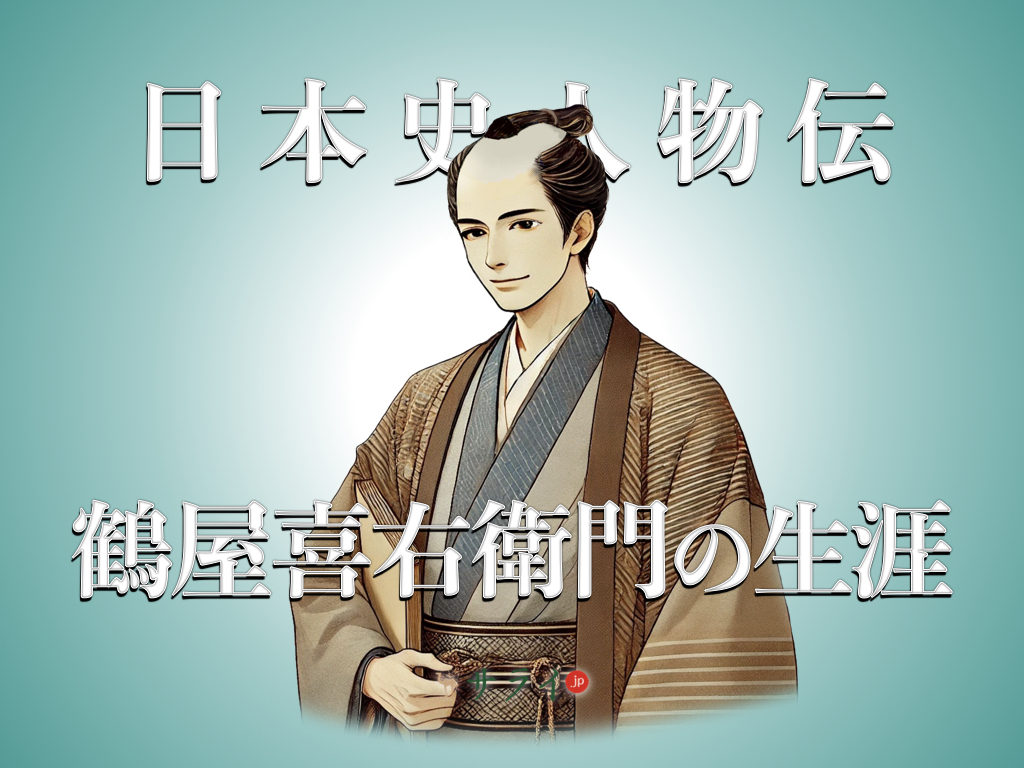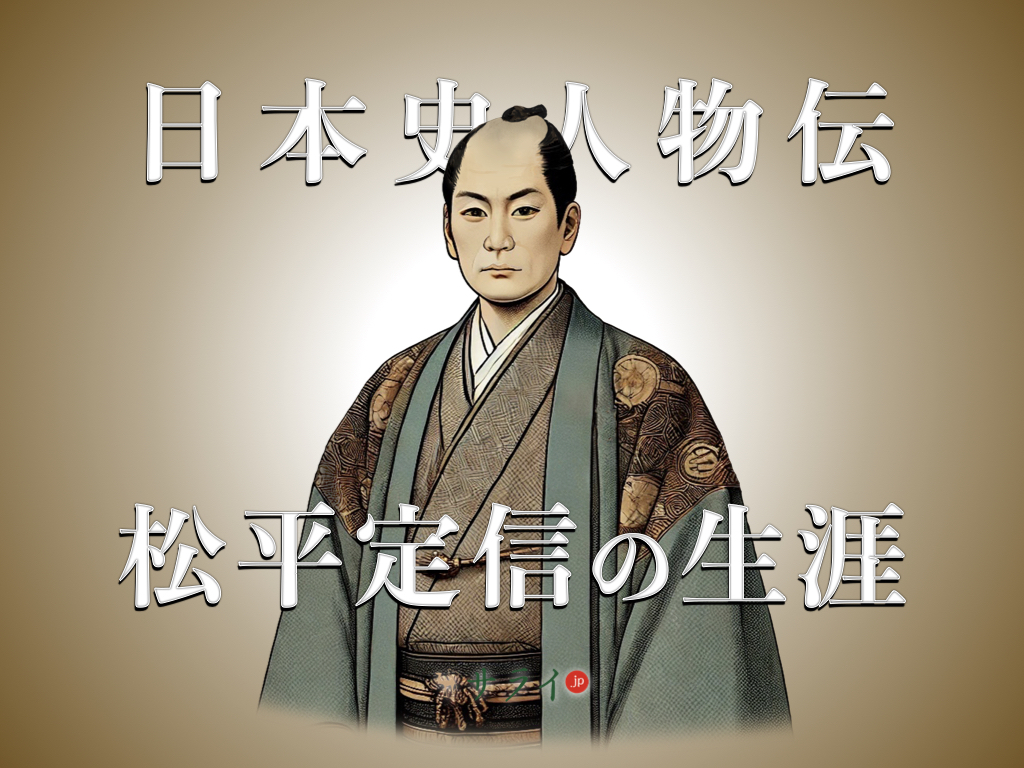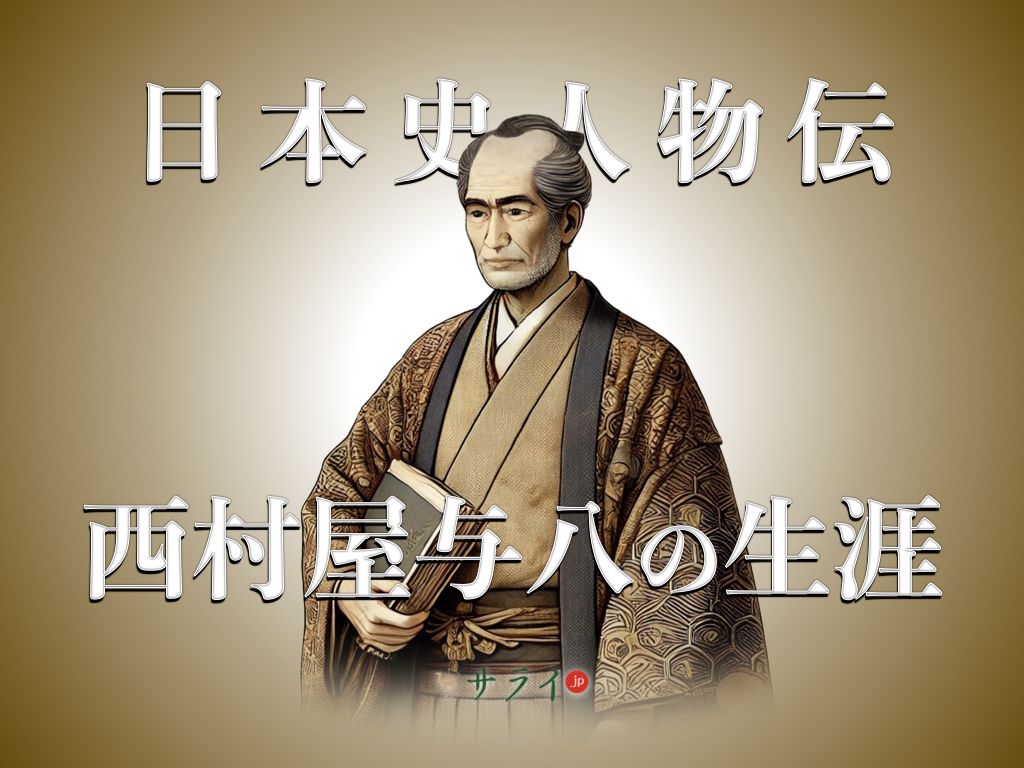はじめに-鶴屋喜右衛門とはどのような人物だったのか
鶴屋喜右衛門(つるや・きえもん) は、江戸時代を代表する地本問屋であり、日本の出版文化に多大な影響を与えた本屋です。京都を拠点にスタートしましたが、のちに江戸に進出。独自の地位を築きました。その出版活動は絵草紙や浄瑠璃本を中心に、錦絵や合巻など幅広いジャンルにわたりました。
そんな鶴屋喜右衛門ですが、実際にはどのような人物だったのでしょう。史実をベースに紐解きます。
2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、江戸市中の地本問屋のリーダー的存在の人物(演:風間俊介)として描かれます。

目次
はじめに-鶴屋喜右衛門とはどのような人物だったのか
鶴屋喜右衛門が生きた時代
鶴屋喜右衛門の生涯と主な出来事
まとめ
鶴屋喜右衛門が生きた時代
鶴屋喜右衛門が活躍したのは、江戸時代中期から後期にかけての時代です。この時代は、日本の出版文化が大衆化し、庶民の間で娯楽本や絵入り本が広く読まれるようになった時期でした。
江戸中期には、赤本や黒本などの簡易な娯楽本が普及し、これらを扱う地本問屋が急速に成長しました。一方で、江戸後期にかけては、黄表紙や合巻、錦絵といった高度な技術と芸術性を備えた出版物が登場し、出版業界がさらなる発展を遂げました。
鶴屋喜右衛門の生涯と主な出来事
鶴屋喜右衛門の生没年は不詳です。喜右衛門の出版人生について、見ていきましょう。
鶴屋喜右衛門の成長と発展
鶴屋喜右衛門は、寛永年間(1624~1644)に京都二条通寺町西入る町で開業。当初は絵草紙や浄瑠璃本を版元として扱い、江戸時代前期では第一の本屋でした。のちに店舗を二条寺町上る町に移し、明治時代まで存続しました。
万治年間(1658~1661)には江戸にも進出。江戸日本橋通油町(東京都中央区日本橋大伝馬町三丁目)に店を構えました。
この江戸店は、のちに京都店から独立。鶴屋喜右衛門の名は江戸出版界においても広く知られるようになりました。屋号は「仙鶴堂(せんかくどう)」といい、地本問屋の中でも一際目立つ存在となりました。
【『源氏物語』を翻案した合巻作品『偐紫田舎源氏』の成功。次ページに続きます】