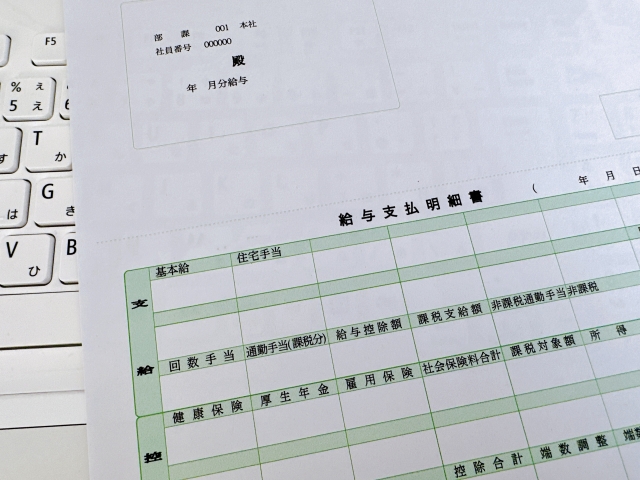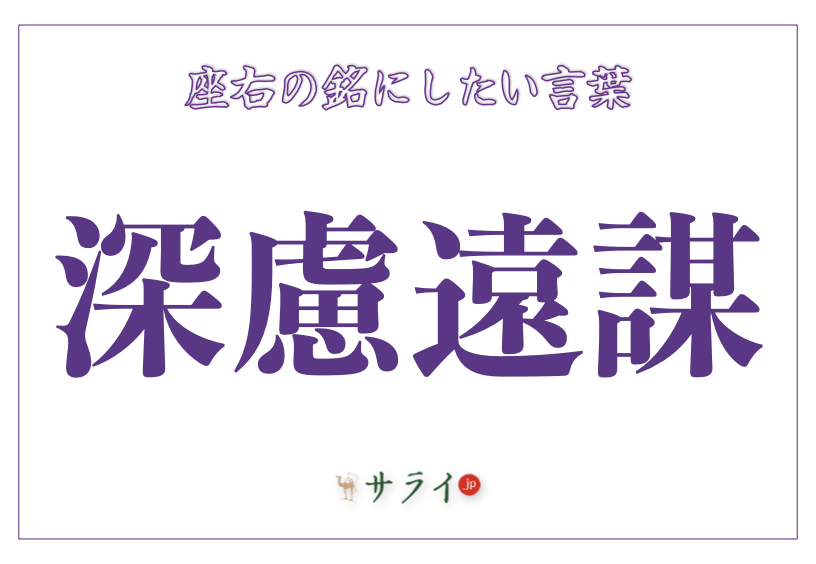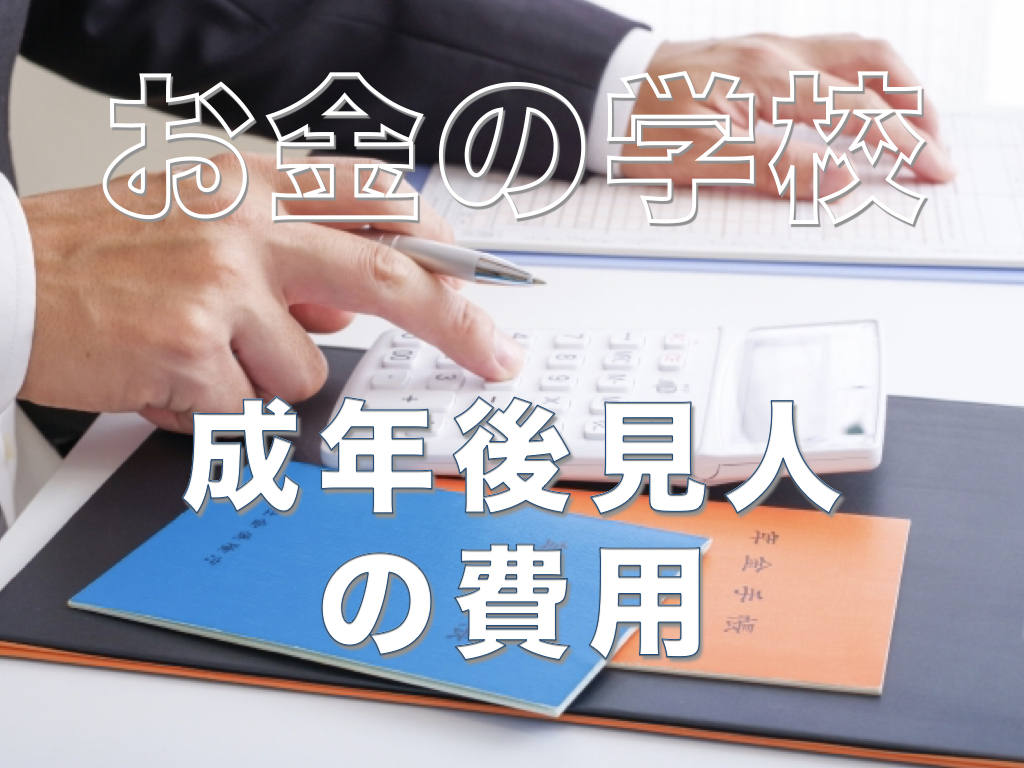マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の用語や問題を解説するシリーズ。
はじめに
「手塩にかけて育てた優秀な社員が、ある日突然、退職届を持ってきた……」多くの経営者や管理職が頭を悩ませる問題です。高い成果を出し、将来を期待していた人材ほど、評価や待遇への不満、成長機会の喪失などを理由に会社を去っていく傾向があります。なぜ、企業が最も失いたくないはずの優秀な人材から辞めていってしまうのでしょうか。
この記事では、優秀な社員が離職に至るメカニズムを解き明かし、彼らが定着し、活躍し続ける組織を作るための具体的な対処法を解説します。
なぜ社員は会社に所属し続けるのか?
そもそも、従業員はなぜ特定の会社で働き続けるのでしょうか。その理由は「給与が高い」「福利厚生が充実している」といった待遇面から、「仕事にやりがいを感じる」「尊敬できる仲間がいる」「自己成長につながる」「会社の社会的評価が高い」といったエンゲージメントに関わるものまで、人それぞれです。突き詰めると、従業員は「その会社に所属することで得られるメリット」が、他の選択肢よりも大きいと判断しているからこそ、そこに留まり続けるのです。
では、従業員の離職を防ぐためには、彼らが求めるメリットをすべて提供し続ければ良いのでしょうか。残念ながら、それは現実的ではありません。一人ひとり価値観が異なるため、すべての要求を満たすことは不可能です。また、業績にかかわらず給与や待遇を上げ続けることは、企業の持続可能性を脅かしかねません。
そこで重要になるのが、企業が持続的に提供可能で、かつ多くの従業員にとって本質的なメリットとなる要素です。それは「個人の成長」と「会社の成長」に他なりません。給与や待遇といった金銭的・物質的な報酬には限界がありますが、従業員一人ひとりが成長を実感でき、会社自体も社会からの評価を高めながら成長していく環境は、企業努力によって継続的に提供できます。優秀な社員が「この会社にいれば、自分も会社も成長できる」と感じられることこそ、離職を防ぐための最も強力な土台となるのです。
「任せる」と「放任」の違いが生む成長実感の欠如
優秀な社員が離職を考える大きな理由の一つに、「この会社にいても、これ以上成長できない」という停滞感があります。特に陥りがちなのが、優秀さを信頼するあまり、「彼(彼女)なら大丈夫だろう」と仕事を任せきりにしてしまう「放任マネジメント」です。
成長とは、出来なかったことが出来るようになることです。このプロセスには、「自分には何が足りないのか(課題の認識)」と「それを乗り越えるための挑戦(ストレッチな経験)」、そして「乗り越えられたという実感(成功体験と承認)」が必要です。しかし、優秀な社員に対して「彼は何でもできるから自由にやらせている」「期待の新人なので新規事業を丸ごと任せてみた」といった形で放任してしまうと、この成長のサイクルがうまく回りません。
上司からの適切なフィードバックや指摘がなければ、本人は自分の課題を客観的に認識する機会を失います。また、管理されないまま放置されると、たとえ困難な業務を乗り越えたとしても、その頑張りや成果が正当に評価・承認されているという実感を持ちにくくなります。結果として、「自分はただ放置されているだけではないか」「この会社は自分のキャリアを真剣に考えてくれていないのではないか」という不信感につながり、成長を実感できなくなってしまうのです。
もちろん、自ら課題を見つけ、改善を繰り返して成長していける自律的な人材もいます。しかし、そのような人材ほど、自身の市場価値を客観的に把握しており、「もっと成長できる環境」を常に探しています。彼らに対してこそ、現状に満足させるのではなく、一段上の視点から課題を提示し、より高い目標に挑戦させる積極的なマネジメントが不可欠です。
会社の「進行感」が帰属意識を左右する
個人の成長実感とともに、社員のエンゲージメントを支えるもう一つの柱が「会社の成長」です。自分が所属する会社が社会からどのような評価を受け、未来に向かってどのように進んでいるのか。この「進行感」は、従業員の帰属意識や働くモチベーションに大きな影響を与えます。
ここで言う「会社の成長」とは、単に売上や利益率の伸長だけを指すものではありません。もちろん、業績が好調であることは重要ですが、すべての企業が毎年急成長を遂げられるわけではないでしょう。大切なのは、自社が「社会に対してどのような価値を提供しようとしており、その結果としてどう評価されているのか」というストーリーを従業員と共有することです。
自分が社会的に価値のある企業の一員であるという誇りは、日々の業務に意味を与え、困難な状況を乗り越える力になります。逆に、会社の将来像が見えず、社会から取り残されているような閉塞感が蔓延すれば、優秀な社員ほど「この船に乗り続けていて大丈夫だろうか」と不安を感じ、より将来性のある企業へと移っていくでしょう。
公平性と納得感を蝕む組織の「不」の要素
どんなに成長機会があり、会社の将来性が有望であったとしても、日々の業務の中で「不公平感」や「不信感」が募れば、優秀な社員の心は離れていきます。特に注意すべきは、「ルールの不徹底」と「不透明な評価制度」です。
人は、同じルールを守る者同士でコミュニティへの所属意識を強く感じます。会社として定められたルールが形骸化し、守る人と守らない人がいる状況は、組織の一体感を著しく損ないます。特に真面目で成果意識の高い優秀な社員にとって、「自分はルールを遵守しているのに、なぜ守らない人が許されているのか」という状況は、強いストレスと不公平感を生み出します。こうした小さな不満の積み重ねが、「この会社は真面目に働く者が損をする場所だ」という認識につながり、離職の引き金となるのです。まずは、既存のルールを全員が徹底して守るという、当たり前の文化を醸成することが極めて重要です。
さらに、優秀な社員の離職に直結するのが、評価制度に対する不満です。評価制度が整っている状態とは、「どのような成果を出せば、どのような評価を受け、それがどう報酬に反映されるのか」が明確で、従業員が納得できる状態を指します。もし、「頑張っても頑張らなくても給与はほとんど変わらない」「評価基準が曖昧で、上司の感覚で全てが決まる」といった状態であれば、高い成果を出している優秀な社員ほど、自身の貢献が正当に評価されていないと感じ、強い不満を抱くことになります。
彼らは自身の市場価値を理解しているため、より公正な評価と報酬を提示する他社へ移ることに躊躇しません。これを防ぐためには、評価基準や目標設定のプロセスを透明化し、成果と評価、そして報酬が明確に連動する仕組みを構築・運用することが不可欠です。
まとめ:優秀な人材が輝き続ける組織へ
本記事では、優秀な社員が離職してしまうメカニズムを4つの視点から解説しました。
1.根本的な理由:社員は「個人の成長」と「会社の成長」を持続的なメリットとして求める。
2.成長実感の欠如:「任せる」と「放任」を混同し、適切なフィードバックと挑戦機会を与えられていない。
3.会社の停滞感:会社のビジョンや社会貢献性が共有されず、将来性が見えない。
4.公平性・納得感の欠如:ルールの不徹底や不透明な評価制度が、不公平感と不信感を生む。
これらの課題はすべて、組織のマネジメントによって改善することが可能です。もし、この記事を読んで心当たりがあると感じたならば、まずは明日からできることから始めてみてはいかがでしょうか。
一つひとつの小さな改善の積み重ねが、優秀な人材が「この会社で働き続けたい」と心から思える、強い組織を築き上げていくはずです。
識学総研:https://souken.shikigaku.jp
株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/