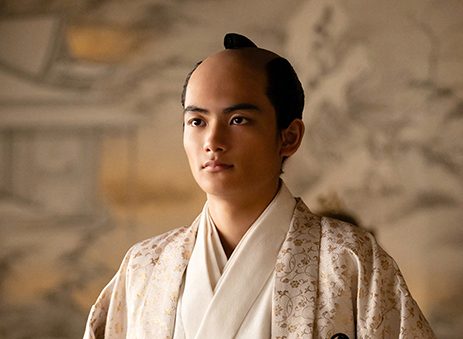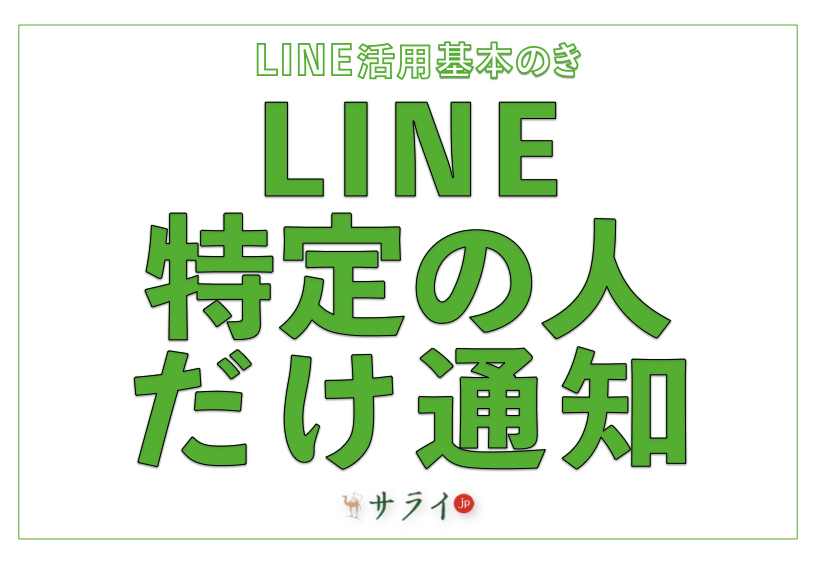ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)では、徳川治済(演・生田斗真)と松平定信(演・井上祐貴)の間で、俗に「尊号一件」と称される問題についてやりとりする場面が描かれました。
編集者A(以下A):松平定信と将軍徳川家斉(演・城桧吏)の関係が悪化する原因のひとつになる案件です。理解を深めるために当時の皇統の説明から入ります。『べらぼう』は明和9年(1772)の大火の場面からスタートしていますが、その直前の明和7年(1770)まで、在位していたのが後桜町天皇(117代)です。
I:現状で、わが国最後の女性天皇ですね。
A:後桜町天皇は譲位して甥の後桃園天皇(118代)が即位しますが、安永8年(1779)に崩御。この段階で即位したのが光格天皇です。光格天皇は、中御門天皇(114代)の弟宮閑院宮直仁親王の孫になります。
I:閑院宮直仁親王――典仁親王――光格天皇という流れですね。
A:劇中でやり取りされていたのは、光格天皇が、父である典仁親王に「太上天皇」の尊号を送りたいと幕府に諮ってきたことを定信が治済に報告した場面です。5代将軍徳川綱吉が母親である桂昌院を「従一位」の位につけたいと柳沢吉保に命じて工作する様が描かれた大河ドラマもありました。親に対する孝ということですが、江戸時代は、徳川家康が命じて定められた禁中並公家諸法度の第二条で、親王の序列は太政大臣、右大臣、左大臣より下と定められていました。つまり、光格天皇の父である典仁親王は、天皇の父であるにもかかわらず、序列としては太政大臣、左大臣、右大臣の下になる。そのため光格天皇は、父に太上天皇の尊号を奉りたいと希望されたということになります。
I:なるほど。そういえば、将軍徳川家斉の父一橋治済も将軍の父であるにもかかわらず、御三家当主の下座に控えていましたね。
A:その場面は、そうした状況を視聴者に視認させるためにあえてもうけた場面ではないかと思料します。そうしたことは今後の展開の中で出てくると思いますので、ここではみなまで言いません。
I:「天皇の父に太上天皇号を奉る」ということは先例があったのでしょうか。
A:源平の戦いが行なわれていた時期、高倉天皇(80代)の皇子に安徳天皇(81代)、守貞親王、後鳥羽天皇(82代)がいました。承久の乱で朝廷が混乱した後に、即位したのが守貞親王の皇子だった後堀河天皇(86代)です。このとき、守貞親王には、太上天皇の称号が与えられ、薨去後に「後高倉院」という院号まで贈られたのです。
I:なるほど。
A:南北朝時代の事例には歴史的に今日の話題にもつながっているので、深掘りしたいと思います。北朝第3代目の崇光(すこう)天皇は、足利尊氏と足利直義兄弟による争い(観応の擾乱)の余波で、退位を余儀なくされました。
I:足利尊氏が弟直義との抗争の難局を打開するために、自ら擁立した北朝の崇光天皇を退位させてまで、南朝と和解した「正平の一統」という事件ですね。
A:そうです。「足利尊氏ひどい!」という事件です。尊氏は、南朝との和議を受けて、直義を破りますが、用済みになった南朝とは破局します。怒った南朝側は、京都にいた光厳上皇、光明上皇、退位したばかりの崇光上皇を拉致して南朝の行宮に「軟禁」するのです。
I:冷静に聞くと、なんともめちゃくちゃな事件ですね。
A:南朝側に主だった皇族方を拉致された尊氏は、京都で難を逃れていた光厳上皇の第三皇子で崇光天皇の弟宮を擁立し即位させます(後光厳天皇)。和議の際に、尊氏は南朝側に「三種の神器」が渡るのを容認していましたから、後光厳天皇は、三種の神器もないイレギュラーな形での即位になったのです。
I:なるほど。
A:数年後に崇光天皇らは、京に戻りますが、本来北朝(持明院統)の正嫡の立場だった崇光天皇はその立場を回復することなく、皇統は崇光天皇の弟宮・後光厳天皇から後円融天皇、後小松天皇、称光天皇と続きます。この間、崇光天皇の第一皇子栄仁親王は、伏見宮をたてます。伏見宮は、栄仁親王、(治仁王)、貞成親王と続きます。
I:ここで称光天皇が崩御され、後継が途絶えるのですね。
A:そうです。皇統は、伏見宮貞成親王の皇子が後花園天皇として即位することでつながります。そして、伏見宮は後花園天皇の弟宮・貞常親王が継ぐのです。尊号の問題が持ち上がったのは、後花園天皇父である貞成親王。このころの歴史を専攻している方には、お馴染みですが、『看聞御記(かんもんぎょき)』という日記の筆者になります。
I:室町幕府第6代将軍で後に暗殺される足利義教のことを「万人恐怖」と記しているのが『看聞御記』ですね。この日記には、一緒に暮らしていた猫の記載もあるなど、猫好きにとっては、気になる親王ではあります(笑)。さて、この貞成親王には、どんな待遇が与えられたのでしょう。
A:生前に太上天皇の位を固辞したそうですが、薨去後に「後崇光院」の院号を追号されています。そして、貞成親王の皇子から皇統を継いだ、後花園天皇の流れが現代の皇室まで続くのです。天皇家の実家であること、正平の一統の際に理不尽な退位を迫られた崇光天皇の子孫であること、そうしたことが加味された結果なのかどうかはわかりませんが、伏見宮家当主は、室町、戦国、江戸時代を通じて、代々親王宣下をするなど、特別な待遇を与えられてきました。明治維新後は、江戸時代であれば、出家していたであろう皇子も新たに宮家を設立して、第二次大戦終戦後に臣籍降下する段階で十一宮家を数えていました。
I:皇位継承問題で、旧皇族の養子案というのがあるのですが、その対象である十一宮家はすべて伏見宮からの流れになります。もともと持明院統の正嫡だった崇光天皇、崇光天皇の第一皇子だった栄仁親王が立てた伏見宮という宮家、その宮家から皇統を継いだ後花園天皇。明治維新まで特別な宮家として代々親王宣下を受けた背景にはそうした歴史があるということですね。
A:「旧皇族の養子案」というのは、こうした歴史の流れを経たうえでの話ということになります。『べらぼう』の松平定信の「尊号一件」の話からかなり脱線しましたが、現代まで続く物語として触れてみました。
●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。
●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。
構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり