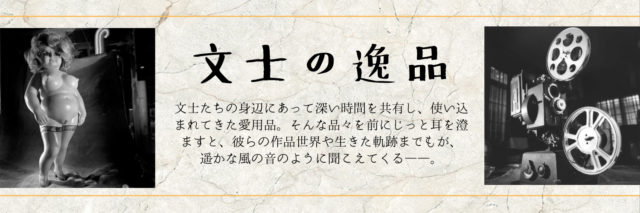
◎No.18:菊池寛の将棋駒

菊池寛の将棋駒(撮影/高橋昌嗣)
文/矢島裕紀彦
菊池寛は文壇屈指の将棋愛好家だった。1日数回、盤の前に座す。対する相手のない時は、ひとり古今の名局の棋譜をたどった。寛は綴る。
「凡(およ)そ、あらゆる勝負事の中で、将棋ほど、テキパキして居るものはないだろう。勝は飽くまで勝である。負は飽くまで負である。敵将を擒縛(きんばく)して後(のち)止(や)むのであるから、何等の妥協あるなしである」(『将棋の話』)
盤上に現れる潔いまでの明快さが、肌合いに合ったのだろう。寛は作家としても『恩讐の彼方に』や『父帰る』に見られる如く、作品に明晰なテーマを持たせることに主眼を置いていた。
長年使い込むうち、味わい深い飴色になった寛の駒が、東京都豊島区の菊池英樹氏のもとに残されていた。材は本黄楊(つげ)。小刀で彫り込んだ文字の上に漆を埋め込み、さらに丁寧に塗り重ね文字部分を盛り上げた「盛り上げ駒」。文壇の大御所と言われた人物に相応しい風格が漂う。
「人生は一局の棋なり 指し直す能(あた)はず」とは、寛の残した言葉。香川県高松市の菊池寛記念館の一室。擦り減って目盛りも霞んだ愛用の盤に駒を載せ、改めて噛みしめるはその至言。
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。『サライ.jp』で「日めくり漱石」「漱石と明治人のことば」を連載した。
写真/高橋昌嗣
1967年桑沢デザイン研究所 グラフィックデザイン科卒業後、フリーカメラマンとなる。雑誌のグラビア、書籍の表紙などエディトリアルを中心に従事する。
※この記事は、雑誌『文藝春秋』の1997年7月号から2001年9月号に連載され、2001年9月に単行本化された『文士の逸品』を基に、出版元の文藝春秋の了解・協力を得て再掲載したものです。




































