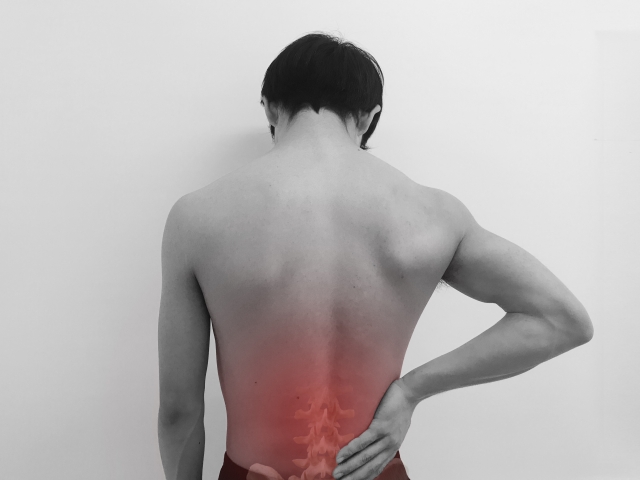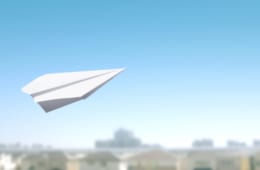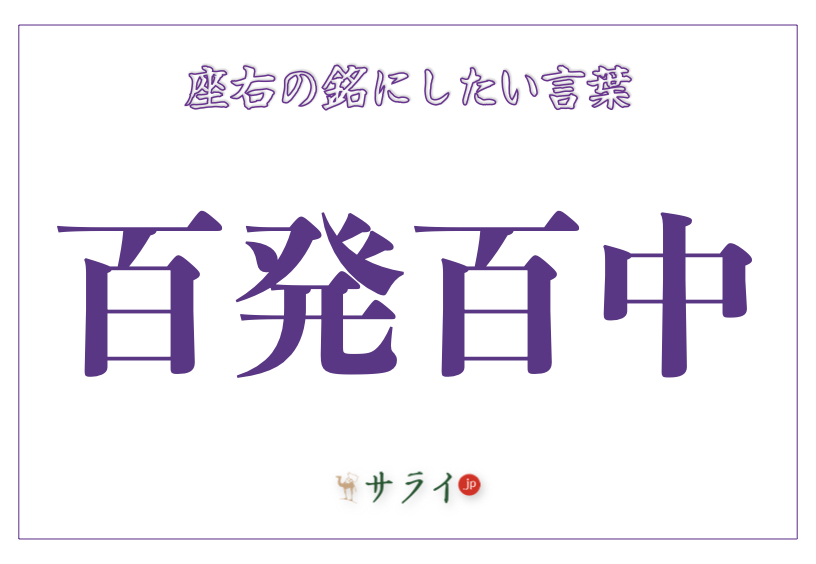文/印南敦史

実際にその痛みを抱えている当事者は別としても、「脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)」という病名を聞いてピンとくる人はそれほど多くないかもしれない。
では、それはどのような病気なのだろうか?
この問いに対し、『脊柱管狭窄症の痛み・しびれリセット法』(芳村憲泰 著、アスコム)の著者は次のように答えている。脊椎脊髄外科の専門医として、多くの患者さんの治療にあたってきたという人物である。
脊柱管狭窄症は、脊柱管という背骨の中にある神経の通り道が、老化による骨の変形によって狭くなり、神経が圧迫されることで引き起こされます。(本書「はじめに」より)
脊柱管が狭くなる大きな要因は、加齢に伴う体の変化だ。50歳を過ぎたあたりから少しずつ増え始め、高齢になるほど有病率が高まるという。
最新の研究では、50歳以上の10人に1人が脊柱管狭窄症といわれているらしい。つまり「ピンとくる人はそれほど多くない」どころか、サライ世代にとっては決して人ごとではないわけである。
ちなみに脊柱管狭窄症にしかほとんど見られない、特徴的な症状が2つあるのだという。それら2つの特徴にあてはまるかどうかで、脊柱管狭窄症なのか、それとも別の病気なのかが、かなりの精度で予測できるというのだ。
確認してみよう。
特徴(1) 足の痛み・しびれがあるか?
1つ目は、「太ももからふくらはぎにかけて、痛みやしびれがある」。脊柱管狭窄症に見られる、最大の特徴といってよいでしょう。(本書57ページより)
とはいっても、寝込んでしまうほどの激しい痛みやしびれではないようだ。一般的なのは、「電気がビリビリと走るような」「ズキズキ、ジンジンとした」「重だるいような違和感のある」痛み・しびれ。
ひどくなると足の甲にまで痛み・しびれが出る人もいるが、脊柱管狭窄症が原因で腕や手がしびれることはないという。この点も、症状を見極めるために役立ちそうだ。
特徴(2) 「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」が見られるか?
2つ目は、「歩くと痛みやしびれが強くなるが、少し休むと症状がおさまる」。この症状を、間欠性跛行と呼びます。(本書58ページより)
ある程度の時間、歩くと痛みやしびれが生じるということ。
そのため歩き続けることが難しくなるわけだが、しばらく座って休めば症状が軽くなり、ふたたび歩けるようになる。
それにしても、なぜこういったことが起こるのだろうか?
それは、歩くと腰がまっすぐになり、脊柱管が狭くなって、神経への圧迫が強くなるからです。
一方、しばらく休むと楽になるのは、前かがみの姿勢をとることで、一時的に脊柱管が広がり、神経への圧迫が減るからです。(本書59ページより)
したがって、自転車に乗ったり、スーパーのショッピングカートを押して歩いたりしても、痛みやしびれは出ない。前かがみの姿勢になり、脊柱管が広がるからだ。
また、「腰の痛みはあるけれど、太ももからふくらはぎにかけての痛み・しびれがない」場合は、脊柱管狭窄症の可能性は低いと考えられる。
さらにいえば、脊柱管狭窄症の症状は、長い年月を経て少しずつ進行するため、いきなり重症化することはまずないようだ。
どんな病気にも言えることですが、脊柱管狭窄症も早期発見・早期治療が何より大切です。早期に発見したからといって、必ず手術が必要ということではありません。(本書85ページより)
症状が軽い場合は、本書で紹介されている運動や、薬による治療を取り入れることで、進行を抑えることができるという。
いずれにしても重要なのは、少しでも異変を感じたら早めに専門医に相談すること。症状が出たら不安を感じて当然だが、早めに診断を受け、適切な対策をとるべきなのだ。
そうすれば、ふたたび快適な日常生活を送ることができるようになるのだから。
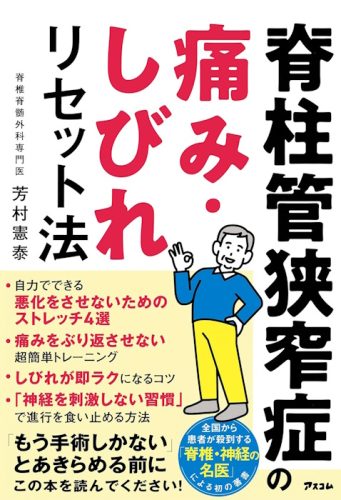
芳村憲泰 著
1650円
アスコム
文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。