文/鈴木拓也

今の日本では、「とても疲れている」と自覚する現役世代が増えている。
一般社団法人日本リカバリー協会の最新調査によれば、その割合はおよそ8割。1999年に行われた国の調査では約6割であったから、四半世紀で2割も増加した計算になる。
理由として、「ちゃんと休めていない」点を挙げるのは、同協会代表理事の片野秀樹さん。片野さんは、仕事が終わったオフタイムも、SNSを見続けたり、会社からのメールをチェックしたりなど、なにかと活動する人の多さを指摘。そうした過ごし方をしていれば、休養はとれないまま、疲労ばかりが蓄積すると警鐘を鳴らす。
片野さんは、現代人の疲れの対策を、著書『疲労学 毎日がんばるあなたのための』(東洋経済新報社 https://str.toyokeizai.net/books/9784492048016/)で説く。
今回は、本書の内容の一部を紹介しよう。
睡眠だけでは100%に回復できない
言うまでもなく、人間は活動しっぱなしで生きることはできない。必ず休養し、疲労からの回復をはかる必要がある。
片野さんは、これを充電池に例える。朝起きたとき、疲労がなく万全のコンディションだと100%の充電。これが日中の活動によって消耗していき、残量が20%くらいになったら疲労状態になる。そこで十分な休養をとることで、翌朝100%に戻る。正常であれば、このサイクルを繰り返す。
しかし、疲れている人だと、「休養しても50%程度しか充電できていない」状態に。疲れをうったえる約8割の人たちは、この負のサイクルに陥っているという。
こう聞くと、「夜、もっと寝なくては」と考えがちだが、睡眠だけではダメ。むしろ長すぎる睡眠時間は、筋量の低下という別の問題を生むというから厄介だ。
軽い負荷が活力を高める
そこで片野さんが提唱するのは、疲労の反対語である「活力」を加えることだ。実はこれが、効果的だという。
意外かもしれないが、活力は、「あえて軽い負荷」を加えることで高まるそうだ。負荷については、次のように書かれている。
できれば肉体的な負荷と精神的な負荷の両方をかけるといいでしょう。肉体的な負荷については、ウォーキングやヨガ、ストレッチ、犬の散歩といった軽い運動がおすすめです。どれも自分でペース配分でき、負荷としてちょうどいいですね。
もう一方の精神的な負荷ですが、(中略)少し難しい試験にチャレンジしたり、趣味の世界で何かを賞に応募したりするといったように、あくまでポジティブな負荷を課してみるのが大切です。(本書67pより)
このやり方を片野さんは「攻めの休養」と呼ぶ。ただしそれは、あくまでも仕事と関係なく、自分でやると決めたもので、楽しむ余裕があることなどが条件となる。
疲労の元凶はさまざまなストレス
そもそも疲労は、なぜ積み重なっていくのだろうか?
片野さんによれば、それはストレスだという。片野さんの提唱する休養学では、ストレスの定義は広範囲にわたり、寒暑、騒音、酒類、病原体なども含む。もちろん、仕事のプレッシャーや人間関係のトラブルもストレスである。それが適度であれば問題ないが、過剰になると疲労につながるため、日頃からコントロールする必要がある。
本書には、様々なストレスと対応策が記されているが、意外なのが「振動」によるストレス。乗り物に乗っているときは、常時振動(揺れ)が発生するが、無意識に足を踏ん張ってしまい、身体的なストレスになるという。
そこで、振動を少しでも緩和するため、乗る位置に注意するようアドバイスがある。例えば、電車だと車両の中央、飛行機だとできるだけ通路寄り、乗用車も後列なら真ん中がベストだという。乗用車は、車高が低いほうが振動は少ないため、選べるなら「セダンタイプ一択」だとも。
「のんびりする時間」を意識してつくる
疲労を抑えるにあたって、現代人が避けて通れないのが脳の使い方だ。
それにはまず、思考を司る前頭前野にあるワーキングメモリ・ネットワークとデフォルトモード・ネットワークという2つの神経網を理解する必要がある。簡単に言えば、前者は集中しながら浅く考える機能で、後者はぼんやりしつつ情報を整理する機能となる。
これまで人間は、この2つのネットワークを交互に働かせていた。だが現代人は、スマホとパソコンを使うことでワーキングメモリばかりを酷使しているという。こうなると脳への過負荷は避けられない。
そこで片野さんがすすめるのが、「定期的にぼんやり、のんびりする時間」の確保だ。要するに、集中して脳を使っている合間に、ぼんやりする(ただし眠らない)時間を設ける。ただし、スマホでゲームをしたり、SNSをチェックするのは、本人はぼんやりしているつもりでも、脳はフル稼働しているのでNG。あくまでもスマホ、パソコンは遠ざけるのがルールとなる。
くわえて、日常的に着る服や食べる物をある程度決めてしまうのも有効。「今日は何を着ようか」「晩御飯は何にしようか」と考えずに済むと、それだけデフォルトモードの時間が増えるからだ。さらに片野さんは、どうせやるなら良い習慣を根付かせるよう提案する。例えば、ある食事を続けたら体調が良くなったのであれば、その食事をルーティン化するというふうに。
このように本書には疲労を抑え活力を増す、とっておきの方法が数多く紹介されている。「最近、なんだか疲れ気味で」と悩んでいるなら、試してみるといいだろう。
【今日の健康に良い1冊】
『疲労学 毎日がんばるあなたのための』
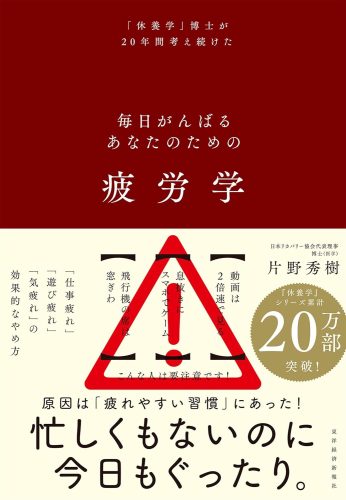
定価1760円
東洋経済新報社
文/鈴木拓也
老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライターとなる。趣味は神社仏閣・秘境めぐりで、撮った写真をInstagram(https://www.instagram.com/happysuzuki/)に掲載している。


































