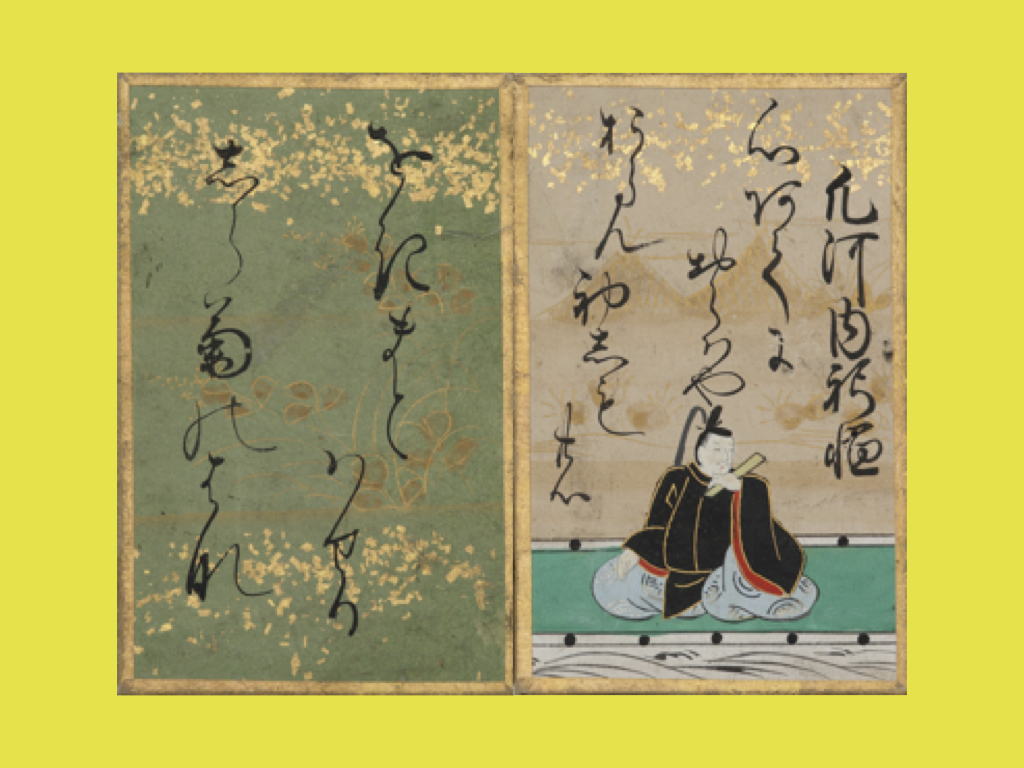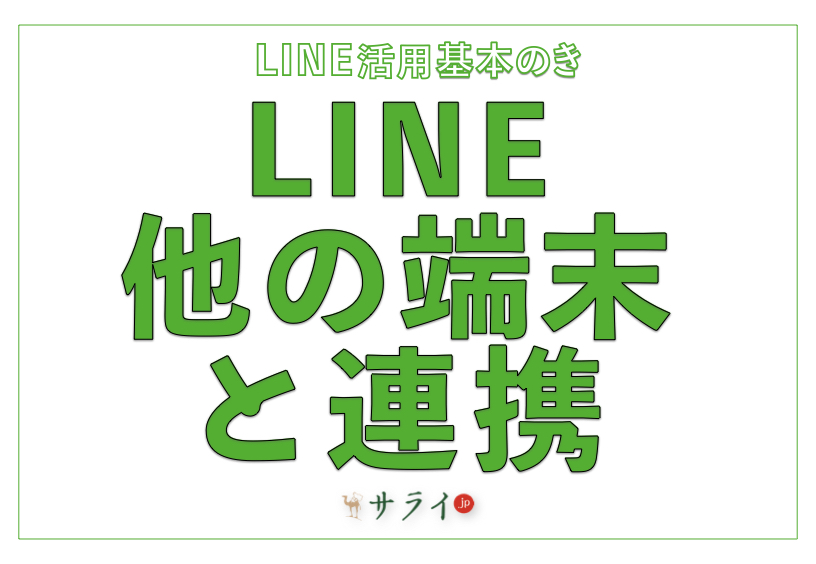文/鈴木拓也

シニア世代を中心に、罹患者が350万人を超えるといわれる脊柱管狭窄症。加齢や背骨の病気などで、背骨が変形したり、じん帯が厚くなることで脊柱管が狭くなって神経を圧迫して起こる病気だ。
歩くと足のしびれや痛みが始まり、歩き続けるのが辛くなるのが主な症状で、うつ症状が伴うこともある。
これを、「年のせいだとそのままにしたり、痛みを我慢したりしないことが大切」と唱えるのは、参宮橋脊椎外科病院の大堀靖夫院長。監修を務めた書籍『大丈夫!何とかなります 脊柱管狭窄症』(主婦の友社)は、脊柱管狭窄症の症状や間違いやすい病気、治療法、セルフケアと、患者が知るべきことがコンパクトにまとめられた好著だ。
今回は、本書を下敷きに、日々進歩している脊柱管狭窄症の治療法のあらましを紹介したい。
■保存療法
脊柱管狭窄症には、圧迫される部位によって「神経根型」、「馬尾型」、(神経根と馬尾の両方が圧迫される)「混合型」がある。
このうち神経根型は、薬物などを用いた保存療法で軽快することが多いが、どの型であれ、いきなり手術になることは少ない。たいがいは保存療法からスタートする。
「治療の最初に選ばれるのは、血流を改善する薬(血管拡張薬)であるプロスタグランジンE1製剤です。血管を広げる作用があり、血流が促進されると痛みやしびれがやわらぎ、間欠跛行の改善に役立ちます。
また痛みやしびれを抑える薬では、おもに非ステロイド系消炎鎮痛薬(NSAIDs)やプレガバリン(神経障害性疼痛治療薬)が処方されます」(本書90pより)
こうした薬を1か月ほど試してみて、効果が見られれば服用を続け、そうでなければ医師と相談して薬量を増やすか、別の薬へ切り替える。
これとは別に、すぐに痛みを止める作用がある神経ブロック療法、ストレッチや体操を行う運動療法、温熱や電気刺激による理学療法も取り入れることもある。
■手術
上記の保存療法を約3か月続けてもあまり改善が見られない場合、手術を検討することになる。
医療技術の進歩で、身体への負担を減らし、症状の大幅な改善が見込めるようになっているため、ひと昔に比べ手術を行うメリットは大きくなっている。また、かなりの高齢でも手術は可能であり、90代の方が手術によって症状が改善した例も、ふつうにあるという。
一方で、「症状が重い場合は、手術で圧迫を取り除いても、しびれなどが残る」こともあり、手術を選ばないという選択肢もありうる。また、内臓の病気をかかえていれば、手術の際にそれだけ身体に負担がかかる。そうしたことについては、医師とよく相談して決断したい。
■手術の種類
手術にも何種類かあるが、代表的なのが「椎弓部分切除」。狭窄を起こしている椎弓(脊柱管の後ろ側にある、上から見て羽のように広がった部分)の一部を削り、厚くなったじん帯をはがして神経への圧迫を取り除く(除圧)という手法。全身麻酔が必要となるが、翌日には自分の足で歩くことができ、入院期間は1週間程度ですむ。
この手術には、背中側を切開して行う従来の開放手術と、小さく切開して内視鏡と専用器具を使う内視鏡手術がある。後者が切開範囲が小さい(2cm程度)ため、筋肉への傷は小さく、より早く日常生活に復帰できるというメリットがある。しかし、これは内視鏡手術の修練を積んだ医師しか行えず、安全性や合併症のリスクの観点では開放型にも利がある。
このほか、内視鏡よりもさらに切開部分が小さい(8mm程度)PEL(経皮的内視鏡下脊柱管拡大術)や、局所麻酔で行うPELF(経皮的内視鏡下腰椎椎間孔拡大術)といった手術もある。
■手術の後
大堀院長は、手術したからといって「横になってばかりいるのは、早期回復のためにはむしろ逆効果になります」と、無理のない範囲で体を動かすようアドバイスする。これは、体力・筋力の低下を防ぐためであり、手術の翌日からリハビリと並行して歩き始めて問題ないという(しばらくの間は腰を守るためコルセット着用)。
ただし、寝返りを打とうとして不用意に腰をひねる、靴・靴下を履くときに深くかがむといった姿勢は、ご法度。理学療法士や看護師からの注意事項を守り、腰への無用の負担はかけないように心がける。
■手術する・しないにかかわらずNGな姿勢とは?
大堀院長は、手術をした後はもちろん、ふだんからなるべくしないほうがいい姿勢を、以下4つ挙げている。
・あぐら
腰が沈み、脊椎の自然な湾曲が保てず負担がかかる。なるべく避けるように。

・横向き寝で片肘をつく
絵で見るだけでも左右がアンバランスになるのがわかる姿勢。左右のゆがみにも注意。

・腹這い
あぐらと反対に、腰を前に湾曲させすぎる「反り腰」になる。あまり楽な姿勢とはいえない。

・物を拾う
体をやや前傾にするだけでもよくないのに、床に手が届くほどかがむのは大きな負担になるので避ける。

基本的に座っているときは「少しだけ胸を張り、『頭が天井から一本の糸でつり下げられているような』まっすぐ伸びた姿勢を保ちましょう」ともアドバイスがあり、そのための筋力づくりにストレッチと筋トレも取り上げられている。
* * *
脊柱管狭窄症は、放っておいて自然に治る病気ではなく、通常は徐々に進行する。大堀院長も、早めの治療が肝心と随所で力説するように、「おかしいな」と感じたら、すぐに受診し、適切な治療を受けるべきだろう。
【今日の健康に良い1冊】
『大丈夫!何とかなります 脊柱管狭窄症』
http://shufunotomo.hondana.jp/book/b370949.html
(大堀靖夫監修、本体1,000円+税、主婦の友社)
<
文/鈴木拓也
老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライター兼ボードゲーム制作者となる。趣味は散歩で、関西の神社仏閣を巡り歩いたり、南国の海辺をひたすら散策するなど、方々に出没している。