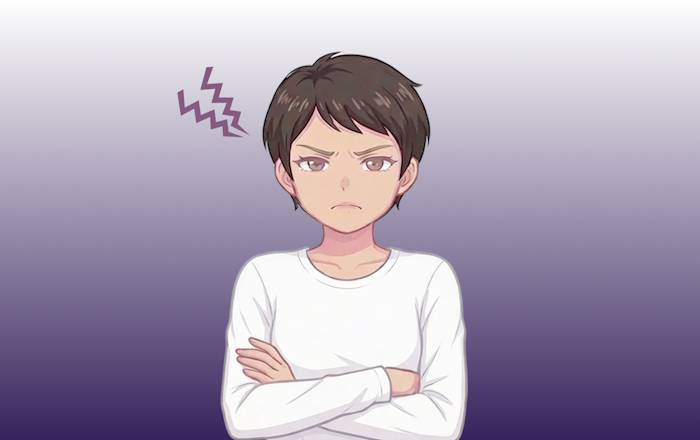幕末の文久2年(1862)に土佐藩の豪商の家に生を受け、維新や幾度もの戦争や災害を経て、昭和32年(1957)に齢94で鬼籍に入るまで、植物とともに生き、人生を存分に謳歌した牧野富太郎。
幼少期は体が弱く、育ててくれた祖母からは干した赤蛙を煮だしたものなどを疳(かん)の薬といって飲まされたと著書『草木とともに』の中で回顧している。
牧野富太郎に学ぶ長寿八訓
一つ、好きなことはとことん追求する
一つ、「老」を自ら避ける
一つ、いつも明るく笑顔でいる
一つ、ありきたりをありきたりと思わない
一つ、自然に親しみ、野山を歩く
一つ、煙草は吸わず、酒は嗜む程度に
一つ、滋養のあるものを食し、過食は避ける
一つ、コーヒーと甘味で心身の疲れをとる
好きなことはとことん追求する
そんな牧野が最晩年まで研究を続け、長寿を全うできたのには、いくつか理由がありそうだが、何をおいても好きなことを追求できたこと、に尽きるのではないか。嫌いなことを我慢しながら行なって精神をすり減らすのではなく、好きなことに没頭できる環境。牧野がこうした自由を享受できたのは、常に傍らにいて牧野を見守っていた妻の壽衛(すえ)の内助の功によるところが大きいだろう。待合茶屋を経営し、稼いだ金で練馬に家を建てて牧野の研究成果を守ったのも壽衛だった。
「老」を自ら避ける
牧野は最晩年になっても、自分を「老人」とは認めなかった。やはり著書の中で、《老人めくことが非常に嫌いだ》とはっきりと述べているように、自分のことを「翁」だとか「老」だとかいった言葉で表現しないように心がけていた。また、晩年まで視力が良かったことも自慢のひとつだった。裸眼でなんでも見ることができると著書の中で語っており、老いとは無縁の気持ちでいたようだ。
いつも明るく笑顔でいる
写真に撮られることが好きだったという牧野。今に残る写真の多くでも満面の笑顔を見せている。生来の陽気な気質もあいまって、牧野の幸せそうな笑顔は、周囲も楽しませたに違いない。
ありきたりをありきたりと思わない
牧野は、植物と向き合う時は、最敬礼の気持ちを持って接し、いつも正装をして出向いていったという。地方の珍しい植物ばかりではない。折に触れて市場にでかけていって、その頃流行している野菜や果物などを求めてきては、輪切りにするなどして標本を作っていたという。常に好奇心をもって、ありきたりの日常生活の中をも真剣な眼差しで覗き込んでいたのだ。
【長寿八訓の残り4つは、次ページに続きます】