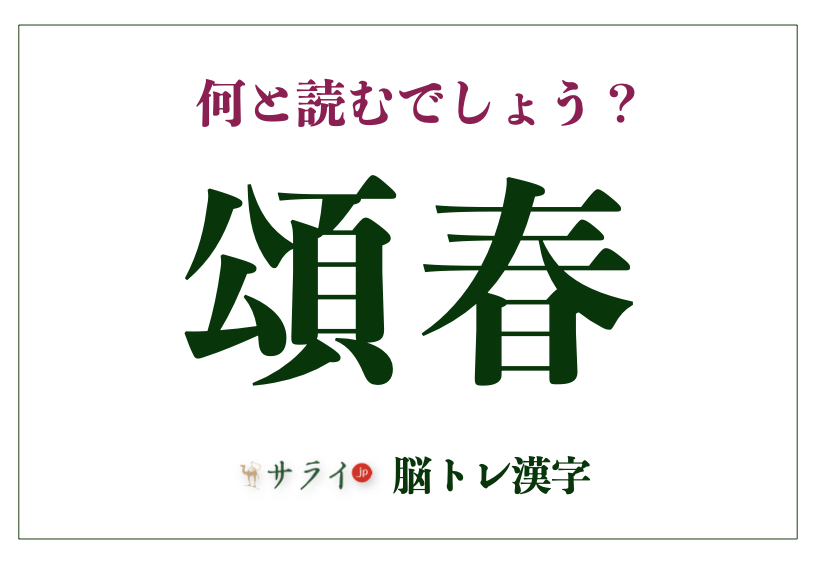負けても心くじけず
豊臣政権下で大名となった宗茂は、朝鮮出兵でもその勇猛ぶりを発揮する。とくに文禄の役では碧蹄館(へきていかん)の戦い(1593)で明と朝鮮の連合軍をしりぞけ、名をあげた。
が、秀吉の死により、世は徳川家康と石田三成の対立へと推移する。関ヶ原の戦いに際しては三成ひきいる西軍に加わり、東軍方の大津城を囲んで開城させた。が、周知のように西軍本隊は関ヶ原で敗北、宗茂は柳川へ帰還する。この途次、おなじく西軍に属して敗走する島津氏の軍勢に出会った。宗茂にとっては実父の仇である。この機を利用して討ち取っては、とすすめる家臣もいたが、宗茂は「勇士のする所にあらず」としりぞけた。のみならず、警戒を解くよう島津軍に使いをだすことまでしたという。
ちなみに、はるか後年、この折のことを徳川御三家(尾張・紀伊・水戸)のまえで話す機会があった。そのとき宗茂は、「大津城攻めのことを謀反という人がおりますが、謀反とは主君に背くことです。当時天下人だった豊臣家に届け出ておこなった戦ですから、謀反であるわけがございません」という趣旨のことを述べている。やはりどこか理屈っぽいところが面白いが、見事なまでに筋が通っている。そういう性質を持った人物と見ていいだろう。
西軍に加担した咎で所領を没収され、一介の浪人となった宗茂だが、その名声は高く、加賀の前田利長(利家の長男)などから召し抱えたいという申し出があった。が、それをことわり、上方で十数人の家臣と浪人ぐらしを送る。
この頃のこと、家臣たちが所用で不在にし、宗茂がひとり留守宅に残っていた。家臣らは、ほしいい(乾燥米)にするつもりで米を乾かしていたのだが、折あしく雨が降りだしてしまう。帰宅してみると、宗茂は書見中で雨に気づかず、ずぶ濡れになった米は使いものにならなくなっていた。が、家臣たちはかえって喜んだ。「ほしいいだの雨だのといった些事に気を取られるようでは、わが殿もこれまで。ご武運、いまだ尽きず」というわけである。
これは、作家の海音寺潮五郎が名著『武将列伝』(「立花一族」の項)で紹介している話で、柳川に伝承されているものだという。そのため、学術的な伝記ではまず採られていないが、滋味のあるエピソードだから、多くの小説などで繰りかえし描かれることとなった。筆者も宗茂といえば、まずこの挿話を思いだす。
旧領へ復帰した唯一の人
そして、たしかに武運は尽きていなかった。関ヶ原から6年後の慶長11(1606)年、宗茂は二代将軍秀忠から召しだされ、奥州で1万石を与えられたのである。のみならず、その4年後、加増をうけて3万石となり、ついに元和6(1620)年には、20年を経て旧領・柳川へ復帰、石高もかつてとほぼ同じ11万石の大名となった。秀忠からの寵愛ぶりがうかがえるが、これは三代家光の世になってもつづき、立花邸へお出ましの折には脇差を与えられ、また貴人のまえでも防寒用の頭巾を着用する許しを得たという。島原の乱(1637~38)にまで出陣した戦国の猛将は、栄誉に包まれたまま76歳で世を去った。
関ヶ原の敗将から返り咲いた大名は何人かいる。が、旧領へもどることができたのは、宗茂ただ一人である。その数奇さと満ち足りた晩年が、近年人気をあつめる理由なのかもしれない。
今ふうな表現になるが、筆者には、宗茂がきわめて健全な「自己肯定感」を持った人物だと思える。浪人中も読書や武芸に励み、弓術の免許まで得ている。先の見えない生活のなかで、たやすくできることではないだろう。前田や徳川が手を差しのべたくなるのも道理と感じられる。その精神を育んだのは、ふたりの父からうけた深い情愛――といえば、いささか小説的すぎるが、そう思いたい気もちが残るのもたしかである。
文/砂原浩太朗(すなはら・こうたろう)
小説家。1969年生まれ、兵庫県神戸市出身。早稲田大学第一文学部卒業。出版社勤務を経て、フリーのライター・編集・校正者に。2016年、「いのちがけ」で第2回「決戦!小説大賞」を受賞。著書に『いのちがけ 加賀百万石の礎』、『高瀬庄左衛門御留書』共著に『決戦!桶狭間』、『決戦!設楽原(したらがはら)』(いずれも講談社)がある。最新刊 『逆転の戦国史「天才」ではなかった信長、「叛臣」ではなかった光秀』 (小学館)が発売中。
「にっぽん歴史夜話」が単行本になりました!
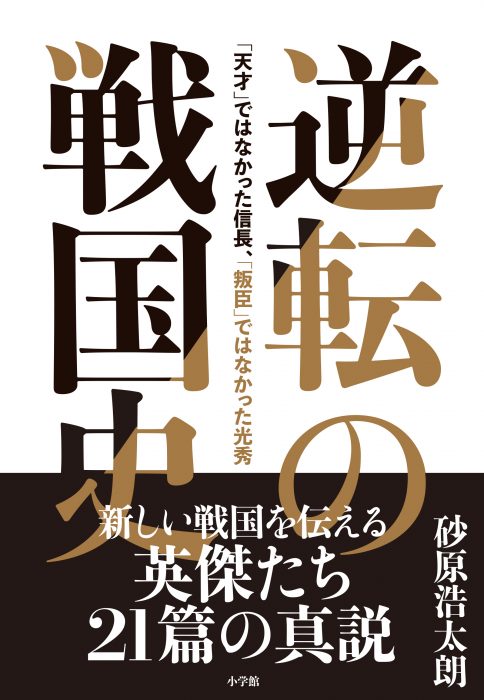
砂原浩太朗 著
小学館