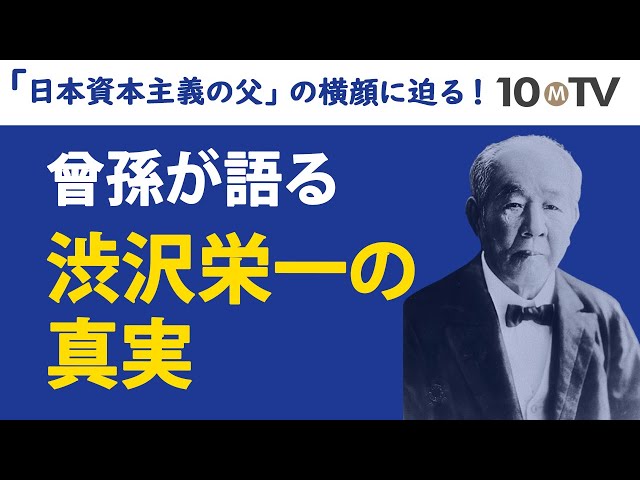「歌は世につれ」というように、音楽は常に時代性を色濃く表します。教養動画メディア「テンミニッツTV(https://10mtv.jp/lp/serai/)」での講義で、片山杜秀氏(慶應義塾大学法学部教授)は、次のように語ります。
「音楽は常に同時代的に社会に密着していて、後の時代に聴くときに、まさにそれがつくられ、演奏されていた時代のことを考えるのに、とても有力な材料になる」。つまり、クラシック音楽を知れば、生き生きとした「世界史の裏側」もわかるのです。
テンミニッツTVの片山杜秀氏の「クラシックで学ぶ世界史」講座では、全13話で、グレゴリオ聖歌からバッハ、モーツァルト、ベートーヴェンから、ワーグナー、国民楽派、マーラー、20世紀の音楽までを総覧していますが、ここでは、モーツァルトの時代をピックアップします。
18世紀後半、市民階級がさらに力を蓄えるにつれ、王侯貴族や教会などの旧勢力は弱体化し、お抱えの音楽家を雇用するゆとりを失い始めました。ヨーロッパ中に名前を知られた「神童モーツァルト」でさえ雇用する者がいないほど、それは深刻な変化だったといいます。はたして、どのような状況だったのか?
以下、教養動画メディア「テンミニッツTV(https://10mtv.jp/lp/serai/)」の提供で、片山杜秀氏の講義をお届けします。
※動画は、オンラインの教養講座「テンミニッツTV」(https://10mtv.jp/lp/serai/)からの提供です。
講師:片山杜秀(慶應義塾大学法学部教授/音楽評論家)
インタビュアー:川上達史(テンミニッツTV編集長)

「就職氷河期」にぶつかったモーツァルトの短い生涯
――先生は、モーツァルトについて非常に印象深い言葉を紹介していらっしゃいます。「モーツァルトは不安の時代の音楽家である」と。端的にいうと、時代が移り変わっていく中で、かわいそうなことに就職氷河期に当たってしまったのがモーツァルトであると、『ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる』の中でお書きになっています。
片山 そうですね。前回までの流れでいえば、教会や封建領主の強い時代が、絶対王政によって揺らぎ始める。国によって違いがあるので、中央に権力が集中して、教会の権力や封建領主の権力が弱っていくようなところもあれば、神聖ローマ帝国のように、なかなかそうでもなく、いつまでも割れているようなところもあるわけです。
そういう中で、イギリス発の産業革命は特に大きいわけですが、その手前でいわゆる商業革命的なことが起こります。いろんな品物が、大きな圏域で幅広く流通していくようになるのです。そういう時代になりますと、もちろん生産力も上がっていく。そして決定的には産業革命によって生産力が飛躍的に向上し、同じ時間と同じ労働力で10倍とか桁違いなかたちで、いろんな品物ができるようになっていきます。
こうなると、動く富も変わってくる。また、力を持ち始めるのは生産手段である工場などを持っているような人、それから、そういう品物を取り引きしている人になって、いわゆる商工業者がお金を持つようになります。その分、どこが没落するか。国によって違いがあり、封建領主でも相変わらずお金が集まるようなシステムでがんばっていたところもありますが、全体的には富が一般の市民の方にたくさん蓄積されることにより、教会や国王、封建領主たちが相対的に弱ってきます。
弱ってくるということは、王さまや貴族や教会ばっかりがたくさんお金を使って音楽家を雇う時代が終わり、その代わり市民相手に稼ぐのが当たり前になってくるのが、まさに18世紀の後半に起きることなのです。
旧体制の存続を信じて天才児の就職活動をした父レオポルド
――例えば、モーツァルトの場合、生まれたのが1756年で、亡くなったのが1791年ということですね。このあたりの微妙な差によって、この時代では非常に色が分かれてくるわけですね。
片山 そうですね。1789年がフランス革命の始まる年ですので、モーツァルトは、フランス革命が始まってから2年後に亡くなっています。つまり、あのような大革命が起きる前後の時代に生きていたわけです。モーツァルトの父親はレオポルト・モーツァルトといって、ザルツブルクの大司教に雇われた音楽家でした。彼はヨーロッパのアンシャンレジームが続くことを疑わず、自分の子も当然どこかの王様や大貴族、教会などでたくさんお金をもらえるようになるだろうと思って、一生懸命、息子の就職活動などをしたわけです。
――子どもの頃から非常に音楽的才能豊かで、神童といわれていた人でしたね。
片山 そうなのですね。「うちの息子は天才なんだから、当然たくさんのお金を出してくれる雇い口があるはずだ」。「ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトに頼れば、モーツァルト一族が安泰に暮らせるような成功は、当然得られるだろう」。こうしたことがレオポルト・モーツァルトにとっては当然の考え方だったわけです。
ところが、父親が信じていたような世界は、神童モーツァルトがだんだん青年になっていく中、どんどん壊れていく時代でした。モーツァルトがすごいことは皆が認めるのですが、すごいからといって、たくさんのお金を払って専属に雇いたがるような人が、だんだんいなくなっていました。
貴族専属からロンドン市民を相手にしたハイドン
片山 モーツァルトの先輩にハイドンという人がいました。彼が雇われたのは、ハプスブルク帝国の大貴族エステルハージ家でした。もともとはハンガリーの方でオスマン帝国と戦う際に最前線に立つような、「戦闘貴族」と呼ばれた陸軍軍帥的な家系です。ここに雇われ、専属のオーケストラを持って、エステルハージのファミリーのために懸命に作曲するのが、ハイドンの前半何十年かの音楽家人生でしたが、さしもの大貴族の家がやがて傾いてきます。
エステルハージ家ほどの、ハプスブルク帝国を代表する大貴族でさえ、その有様ですから、ハイドンより後のモーツァルトは悲惨なものです。
ハイドンはエステルハージ家の楽長として雇われ、専属のオーケストラを持ち、エステルハージ侯爵の趣味に合わせて曲をつくっていました。「今晩、こういうのをやるから、あんた、つくりなさい」と言われて交響曲をつくったりセレナーデをつくったり、「うちのオペラハウスでやるためのオペラを、あなた、早くつくりなさい」と言われたり、「これで一生、食いっぱぐれはない」と彼は思っていたでしょうが、ハイドンも最後は食いっぱぐれることになります。
音楽に理解のあるエステルハージ家の当主が死んでしまって、代替わりしたら、「もうお金がないし、私は父のように音楽の趣味はない。年金をあげるから、もう自立しなさい」と、クビを宣告されたのです。ハイドンは困ってロンドンで稼いだりしました。市民を相手に、一回一回の演奏会で稼ぐようになったりするわけですが、こういう時代がまさにモーツァルトの生きた時代なのです。
音楽家がフリーランスとして生きているスタイルの出現
片山 だから、モーツァルトの父親や兄の世代の人たちがすでにそうなっている中で、同じ人生行路を歩もうとしても無理です。これはモーツァルトが認められるか認められないかの問題じゃなくて、もう基盤自体がなくなっている。宮廷から市民にシフトしているわけです。
市民にシフトするために、モーツァルトは就職活動を途中で手放し、結局、最後はウィーンという大都会で、契約制の演奏会を開くようになります。市民に、今でいえば定期会員券、連続のチケットを買ってもらい、これで何回モーツァルトの演奏が聴ける、とする仕組みです。「ピアノ協奏曲を何曲、新作を何曲演奏します。その会場で聴く権利は、連続演奏会のチケットを買った、あなたのものです」みたいな感じです。
そうして稼いだり、また楽譜を出版したりします。当時の音楽家は皆楽譜を出版して、レッスンで「これを弾いてみましょう」と使うテキストにし、それで楽譜の印税なり出版料で稼ぎました。また、弟子をとって個人レッスンをつける先生になって稼ぎました。こうしたことを組み合わせて生きていくスタイルの出現が、まさにハイドンの時代からモーツァルトの時代にかけて、ちょうど起きたことなのです。
だからモーツァルトは、前半生においては「就職氷河期」ということが理解できず、おかしいと思いながらも就職活動をしていました。悪くいえば無駄に過ごした時期があったということです。その後、ようやく時代に合うかたちの生き方を見つけて、「じゃあ、契約して演奏会をやったり、オペラの注文とかをこなして、まとまったお金をもらえばいいんだ」ということで、一回一回の単発の仕事でやっていくようになったのですが、そういう人生の切り替えができたところで、モーツァルトは(亡くなってしまいます)。
不安定な雇用と、聴衆の「耳」の変化に応える努力
片山 もちろんモーツァルトも、ハプスブルクの宮廷音楽家としても契約していたわけですが、もう昔のハイドンやバッハやヘンデルの時代のように、そこにさえ契約しておけば食べられるというような時代ではなくなっていました。
――厳しいですね。
片山 仕事はちょっとしか来ないし、「お抱え」といっても、結構名誉職的なことでした。もちろん王族の音楽のお相手をするとか、そういう仕事はあっても、それだけで食べられることはありません。だから、たくさんやりながら、今でいうフリーランスのアーティストの生き方の原型のようなものができてきます。その端境期に後半生を置いたのがハイドンであり、全人生=端境期みたいな人がモーツァルトということになるわけです。
――そこが一種、モーツァルトの、美しいながらもはかなげで、不安な時代を象徴する曲になっていくわけですね。
片山 しかもモーツァルトの時代というのは、まだそうやって貴族や王様相手の仕事が残っていた。これはハイドンの交響曲などを順番に聞いていくと分かりますけれども、あくまでもエステルハージ侯爵のためにつくっている時の曲には、私どもが今の耳で聴いて、いわゆる覚えやすいキャッチーなメロディはあまりないのです。
――ハイドンは百何十曲もつくっていますけど。
片山 つまり王侯貴族というのは、やっぱりそれなりに耳が洗練されているのです。俗っぽいメロディには、「ああ、こんなのは民衆の聞いている音楽で、私どもの趣味ではありません」といった感じになる。そうすると、もうまさにカトリックの時代の教会音楽みたいなものですけれども、ちょっと知的に訓練された耳に「あ、ここの装飾が」とか、「ここのちょっとした音程の動きが、なかなかハイドン、よく工夫しましたね」みたいなところが勝負になってくるのです。
――通好みな感じというわけですね。
居眠りするロンドンの聴衆を驚かせた『驚愕』交響曲
片山 ところが、そういう世界が崩壊していって、代わりに成り上がりの市民が、「王侯貴族みたいな音楽を聞かせてくれ!」といったことを言い出します。でも、ハイドンがロンドンに行って演奏会をやると、王侯貴族の洗練された趣味に合わせた曲では、分からないので、みんな寝てしまうわけですよ。もうちょっとキャッチーな、みんなが覚えやすいメロディじゃないと、分からない。
そこで、ハイドンは市民に一所懸命合わせようとした。彼の一番有名な曲の中に『驚愕』という交響曲があります。なんでそういう名前が付いたかというと、「チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャーン、チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン、チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャーン、チャンチャンチャンチャンチャン、ブワーン!」とやったりする。
どうなっているかというと、そもそも「チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン」というのは、今、私が即興で口ずさむのにもすぐ思い出せるし、皆さんが口ずさめるような覚えやすい旋律なわけです。つまりキャッチー。これはもう、ロンドンの成り上がり市民の趣味に合わせたからで、とても覚えやすいメロディです。
その覚えやすいメロディを聞いても寝る人がいる。だから、ちょっとショックを与えないといけない。「ブワーン!」とやると、「あれ? あれ?」とか言って、「あ~やっていますね。ああ、ハイドン先生の音楽を聞いていたんだ。寝ていませんよ」となる。これがロンドン市民向けに、音楽がキャッチーなものに変わっていく流れです。
モーツァルトが晩年に受けた「軍楽」の影響
片山 モーツァルトの、例えば交響曲の40番や41番、オペラなら『ドン・ジョヴァンニ』や『魔笛』は歌いやすい。年齢を重ねれば重ねるほど、今聞いてもすぐ覚えるような、「タラター、タラター、タラタータ~」といったメロディになりますね。
――そうですね、きれいな旋律です。
片山 40番のような、すぐに歌えてしまうようなメロディが出てくるのは、モーツァルトの晩年(若い晩年ですが)になってからで、趣味が急に変わったからではありません。口ずさみやすいメロディがたくさん出てくるようになったのは、ウィーン市民の趣味に合わせているわけです。みんなに聞かせて、すぐ反応がある音楽じゃないといけないから大変でした。
だから、交響曲の第41番『ジュピター』なんて、「ジャン、ジャカジャン、ジャカジャン」ということで、あれは誰が聞いても軍隊行進曲ですよね。あれはオスマン帝国とちょうどまた戦争を始めた時につくっているので、つまり「軍楽」はやりです。できるだけキャッチーに、流行に合わせて、つくっているわけです。
オペラ『フィガロの結婚』にも、たくさん軍楽的な要素が出てきます。これも、当時のハプスブルク帝国がプロイセンとオスマン帝国に対抗して、軍の近代化を推し進めて、軍隊マーチというものが出てきた(もちろんその前のトルコ行進曲はやりもあります)流れです。どんどん国民国家的なものがつくられ、傭兵ではなく、もともとのネイティブな一般国民も軍隊に入れて、人数を多くしなくちゃいけなくなるのです。そういうことをやっているから、街中は軍楽というもので満ち満ちているわけです。そういう世俗的な要素をどんどん入れて、みんなの耳に馴染みのいいものをつくろうというのが、ハイドンの終わりの頃や、モーツァルトの終わりの頃なのです。
1話10分の動画で学べる「大人の教養講座」テンミニッツTVの詳しい情報はこちら
協力・動画提供/テンミニッツTV
https://10mtv.jp/lp/serai/