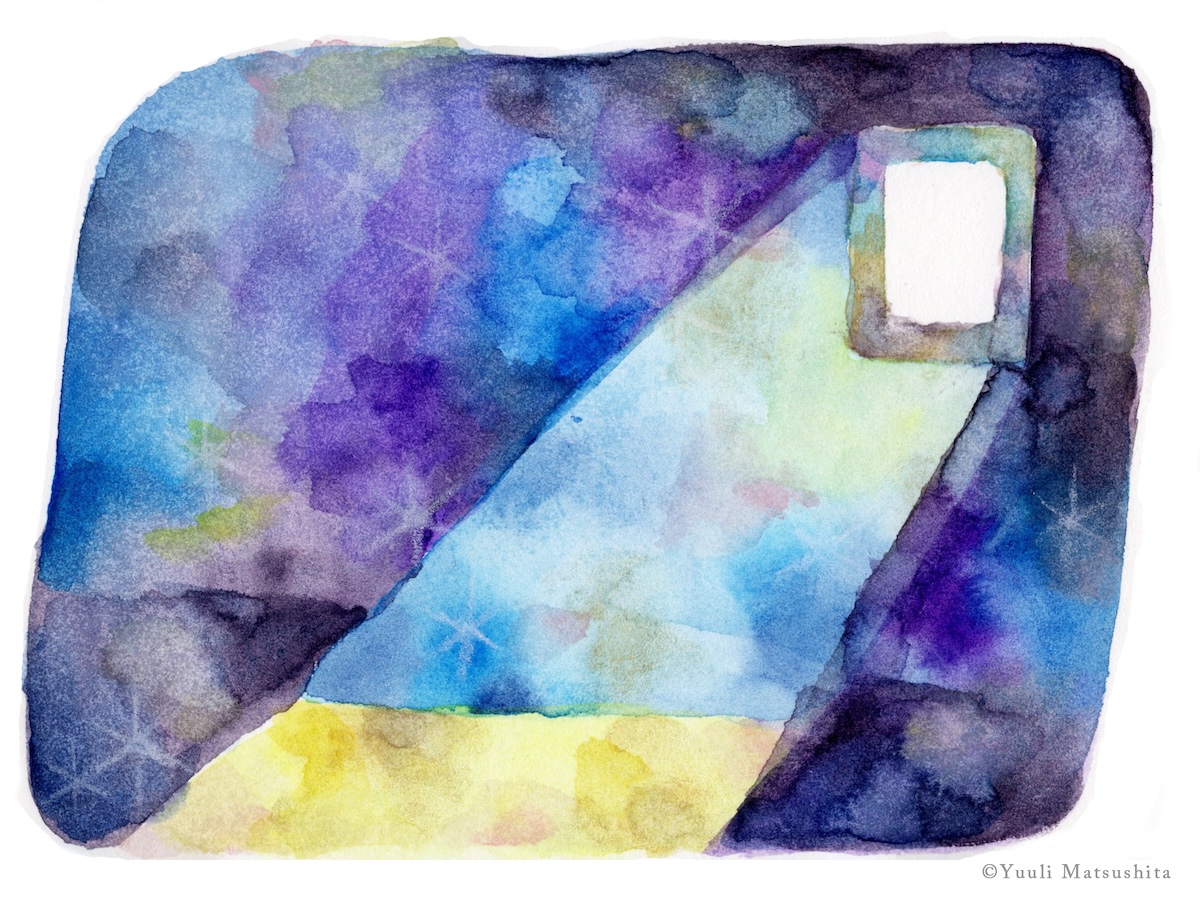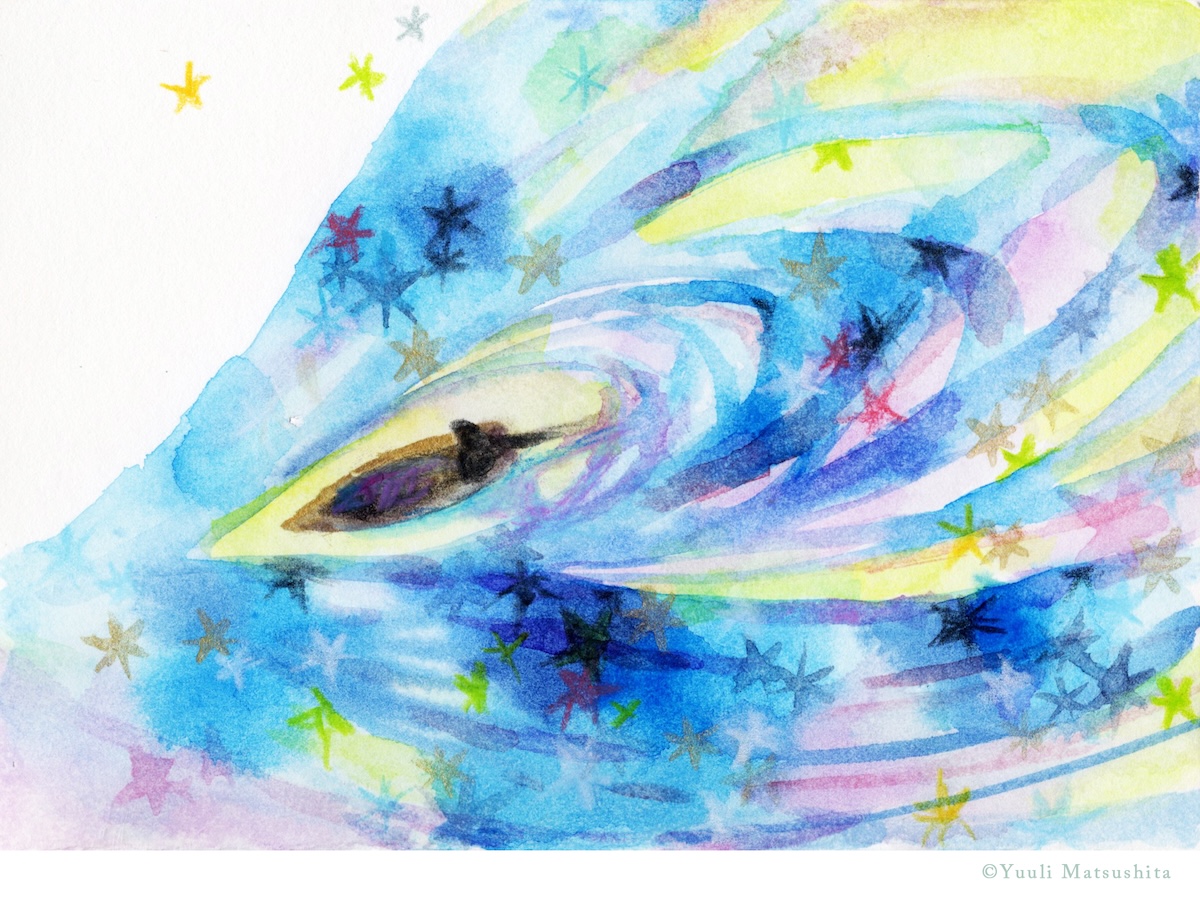秋の空気がすっと澄み、ふと気づけば日が短くなったことを感じる頃――それが「秋分(しゅうぶん)」です。昼と夜の長さがほぼ等しくなるこの節気は、自然と人の営みが調和する季節の分岐点。古くから続くお彼岸や旬の味覚を楽しむ文化が根づいています。
この記事では、2025年の秋分の日程をはじめ、秋分の行事や風習、季節の花や味覚まで、秋分をより豊かに感じるための知恵をご紹介します。
旧暦の第16番目の節気「秋分」について、下鴨神社京都学問所研究員である新木直安氏に紐解いていただきました。
秋分とは?|昼夜の長さが同じになる季節の節目
秋分は、昼と夜の長さが等しくなる特別な日。
太陽が真東から昇り、真西へと沈むこの日は、古代から自然と人の営みが調和する「季節の分かれ目」とされてきました。例年、秋分の日は9月22日または23日頃にあたり、2025年は【9月23日(火)】がその日に該当します。この日を境に昼の時間は短くなり、夜が徐々に長くなる「秋本番」へと移っていきます。
また、秋分の日を中心とした一週間が秋のお彼岸です。「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉が示すように、秋分の頃には日中の暑さも和らぎ始めます。空には秋雲が広がり、野には薄の穂が顔を出す……そんな本格的な秋が訪れる季節です。
七十二候で感じる秋分の息吹
「秋分」は二十四節気の第16番目で、例年9月23日〜10月7日ごろ。七十二候では以下のように分けられます。
■初候(9月23日〜9月27日頃)…雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)
夏の象徴だった雷が鳴りを潜め、秋の静けさが広がり始める頃。空に浮かぶ雲も、入道雲から鰯雲(いわしぐも)へと変わります。
■次候(9月28日〜10月2日頃)…蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)
虫たちが土の中へと潜り、戸口をふさいで冬支度を始めます。
■末候(10月3日〜10月7日頃)…水始涸(みずはじめてかるる)
田の水を抜き、いよいよ稲刈りの季節を迎える頃。たわわに実った稲穂が黄金色に輝き、秋の実りが最高潮に達します。
秋分を感じる和歌|言葉に映る秋分の情景
秋も半ばとなりました。皆さま、こんにちは。絵本作家のまつしたゆうりです。そろそろこの花の咲く季節かなと、今月は目にも鮮やかなこの歌をご紹介します。
道の辺の いちしの花の いちしろく 人皆知りぬ 我が恋妻は
(詠み人知らず『万葉集』2480)
《訳》道の辺に咲く彼岸花がハッキリと目立つように、皆が知ってしまった。私の愛しい恋妻のことを。
《詠み人》詠み人知らず。どんな人が詠んだかは分かっていませんが、「我が恋妻」とあるので恋する男性が詠んだものだと思われます。ストレートな感情表現にぐっときます。
『柿本人麻呂歌集』とは、『万葉集』に記載があるのみの現存しない歌集であり、当時大人気で超絶歌が上手かった宮廷歌人の柿本人麻呂が詠んだり集めたりした歌が載っているとされているものです。柿本人麻呂の詠む歌は、みんなが思いつかないような壮大でファンタジーな世界観が特徴。私の一推し歌人です!

黄色く色づく稲田の脇に、この真っ赤な花が咲き出すと「ああ、秋が来たなあ」と思うのではないでしょうか。彼岸花は、古くは「いちしの花」と呼ばれていました。「赤いのに『いちしろく』なの?」「赤なの? 白なの?」と思うかもしれませんが、「いちしろく」は「いちしろし」という言葉で「明白、はっきり」という意味。のちに濁って「いちじるし」となる言葉です。
『万葉集』の頃は彼岸花を指す「いちしの花」の音と、赤い色がハッキリしているところからも、よく「いちしの花の いちしろく」とセットのように詠まれています。
彼岸花は花期に葉が無い植物。スラリとした長い茎の上に赤い大きな花の塊というシルエットからも、花のみが印象に残りますよね。美しくも根に毒があるので、モグラなどの害獣予防のため田んぼの脇に植えられることが多かったそう。他に背の高い植物が無い場所に咲くことも、よりいっそう「目立つ」要因になっているのかなと。
そんな彼岸花のように「今、大好きな妻のことが皆に知られてしまった!」と男性が嘆く歌です。
当時は付き合っていることが周りに知られない方がいい、という風潮だったようで、まるで芸能人のようにお忍びで会う様子が数多く歌に詠まれています。
この歌もそんな様子が詠まれているとは思いますが、それだけじゃない感じがするなとも思っています。
たとえば、「大好きなものの価値を、自分だけが知っていたい」という独占欲のようなもの、皆様も持たれたことはありませんか?
「この素敵さを、自分だけが知っている」という、優越感。そんな「自分が独り占めしている」と思っていた妻の魅力を、みんなが知ってしまった。
その悔しさと、「どうだ素敵だろう、俺は知っていたけれどね」という誇らしさの、ないまぜのような気持ちにも思うのです。
知ってほしいけど、知られたくない……そんな相反する気持ちの間でもだもだするのは、人間の変わらない心の動きのひとつ。
独占したいけれど、魅力をシェアもしたい。生物としての本能と、集団で生きる人間の社会性との間で揺れる心はいつの時代も変わらないなあと、うまくコントロールできない心に滑稽さも含めて愛おしく思えてきます。
皆様はどう思われますか?
歌は自分の心を映す鏡のようなもの。そこに見えた誰かの心の動きは、本当は「あなたの丸裸の心」なのかもしれません。
(「秋分を感じる和歌」文/まつしたゆうり)
秋分に行われる行事とは?|祖先を敬い、実りに感謝する
秋分の日を中心としたこの時期には、日本人の精神文化を象徴する行事がいくつも行われます。ここでは、自然や祖先に心を向ける古来の慣習を紐解いていきましょう。
秋分の日と「お彼岸」
「お彼岸」は春と秋にあり、春分の日と秋分の日を中日(ちゅうにち)とした前後3日間の1週間のことです。お彼岸には、先祖を供養するためにお墓参りをする習わしがあります。二十四節気「秋分」の初日は「秋分の日」という国民の祝日であり、この日の目的は「祖先を敬い、亡くなった人を偲ぶこと」です。
「お彼岸」は日本独特の風習で、その歴史は古く、平安時代から存在していたといわれています。お彼岸の名の由来は、仏教において「先祖のいる悟りの世界」を彼岸と呼んだことです。また「彼岸」に対して、今私たちが生きている世界は「此岸(しがん)」と呼ばれます。
昼と夜の長さがほぼ同じになる秋分の日は、彼岸と此岸の距離が最も近く、祖先との交流に相応しい日と考えられてきました。そのため現在も先祖を敬い、感謝を伝える日として、この日にお墓参りに行ったり仏壇に手を合わせたりするなど、先祖の供養をしています。

秋分の日と春分の日の違いとは?
秋分の日も春分の日も、太陽が真東から上がって真西に沈み、昼と夜の時間がほぼ同じになるという点は変わりません。その大きな違いは季節です。秋分の日は、これから昼が短くなる、秋から冬への始まりの日にあたります。対して春分の日は、これから昼が長くなる、春から夏の始まりの日です。
また、秋分の日の目的が「祖先をうやまい、亡くなった人々を偲ぶこと」であるのに対して、春分の日の目的は「自然をたたえ、生物をいつくしむこと」とされます。どちらも季節の変わり目ではありますが、春は五穀豊穣を祈り、秋は収穫に感謝するという違いがみられます。
秋分に見頃を迎える花|季節の変わり目に咲く、静けさと彩り
秋分の頃、日本の自然は夏の名残を手放し、落ち着いた美しさへと移り変わります。そんな季節にふさわしく、目に映る花々も華やかさより「しみじみとした趣」が感じられるものばかり。野の花に秋の息吹を感じながら、今だけの情景を心に刻みましょう。
彼岸花(ひがんばな)
秋分の季節に咲く花の代表といえば、赤く独特な雰囲気を纏う、「彼岸花」です。墓地や田んぼの周り、あぜ道でよく見られます。「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」とも呼ばれる鮮やかな赤色の花は、1週間ほど咲くと、やがて葉になり、冬・春を経て、枯れます。

金木犀(きんもくせい)
秋分の頃、街角でふと香る甘くやわらかな香気……それが金木犀の花のしるしです。橙色の小さな花を枝いっぱいにつけ、その存在を香りで印象づける珍しい花木。古くは「桂花(けいか)」とも呼ばれ、中国から伝来したものとされます。
金木犀の香りは、懐かしさや郷愁を呼び起こすと言われ、日本の秋の風物詩として定着しました。この花が香ると、「秋が来た」と感じる方も多いのではないでしょうか?

秋分の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む
秋分を迎える頃、日本列島には実りの秋が訪れます。旬の食材や菓子を味わい、身体の内側から季節を感じてみましょう。
野菜|松茸(まつたけ)
秋分といえば、まず思い浮かぶのが松茸。「茸の王」とも称される香り高さは、『万葉集』でも歌われているほどです。土瓶蒸しや炊き込みご飯など、加熱しすぎず香りを生かす調理法がおすすめです。

魚|鯖(さば)
この時期、海の幸も豊かさを増します。なかでも秋鯖は、夏に蓄えた脂がのって旨味が凝縮。塩焼き、味噌煮、しめ鯖など、多彩な料理で楽しめるのも魅力です。
ちなみに「鯖」という漢字は、右側の「青(靑)」が旧字体ですが、「青」と「靑」どちらを使っても誤りではありません。秋の食卓に、栄養価の高い青魚を上手に取り入れて、健やかな体づくりを。
京菓子|おはぎ
秋分といえば、お彼岸の時期でもあります。この時季に親しまれているのが「おはぎ」。春は「牡丹餅(ぼたもち)」、秋は「御萩(おはぎ)」と、花にちなんだ名で呼び分けられています(諸説あり)。

まとめ
日が短くなり、空気に秋の澄んだ気配が漂いはじめる「秋分」。この節目は、自然の移ろいだけでなく、祖先を敬う心や季節の恵みに感謝する心を思い出させてくれます。
秋彼岸のお墓参り、ほのかに香る金木犀、そして実り豊かな旬の味覚──。秋分のひとときには、私たち日本人が古来から育んできた、自然と調和した暮らしの知恵が詰まっています。日々の暮らしに季節のリズムを取り入れながら、心と体を整えていきましょう。
●「和歌」部分執筆・絵/まつしたゆうり

絵本作家、イラストレーター。「心が旅する扉を描く」をテーマに柔らかで色彩豊かな作品を作る。共著『よみたい万葉集』(2015年/西日本出版社)、絵本『シマフクロウのかみさまがうたったはなし』(2014年/(公財)アイヌ文化財団)など。WEBサイト:https://www.yuuli.net/ インスタグラム:https://www.instagram.com/yuuli_official/
監修/新木直安(下鴨神社京都学問所研究員) HP:https://www.shimogamo-jinja.or.jp
協力/宝泉堂 古田三哉子 HP:https://housendo.com
インスタグラム:https://instagram.com/housendo.kyoto
構成/菅原喜子(京都メディアライン)HP:https://kyotomedialine.com Facebook