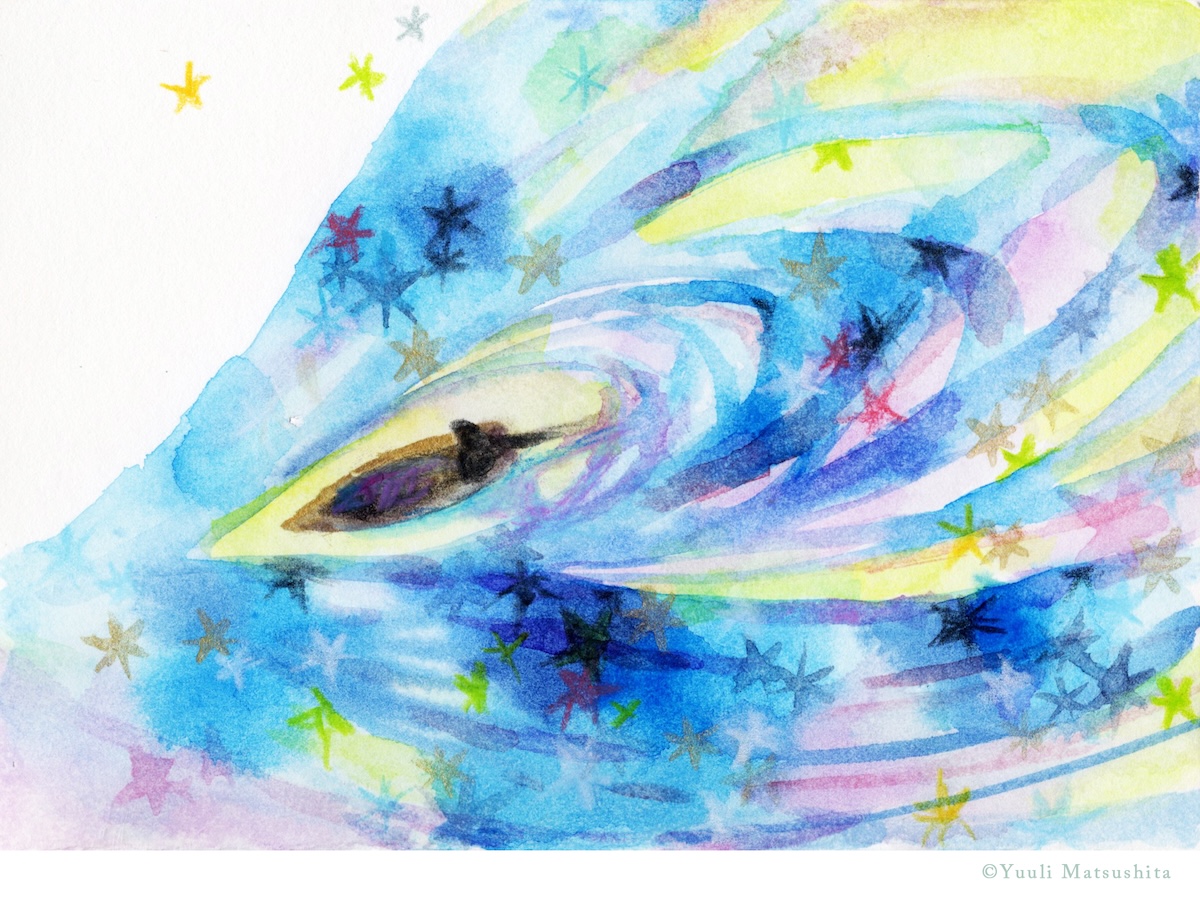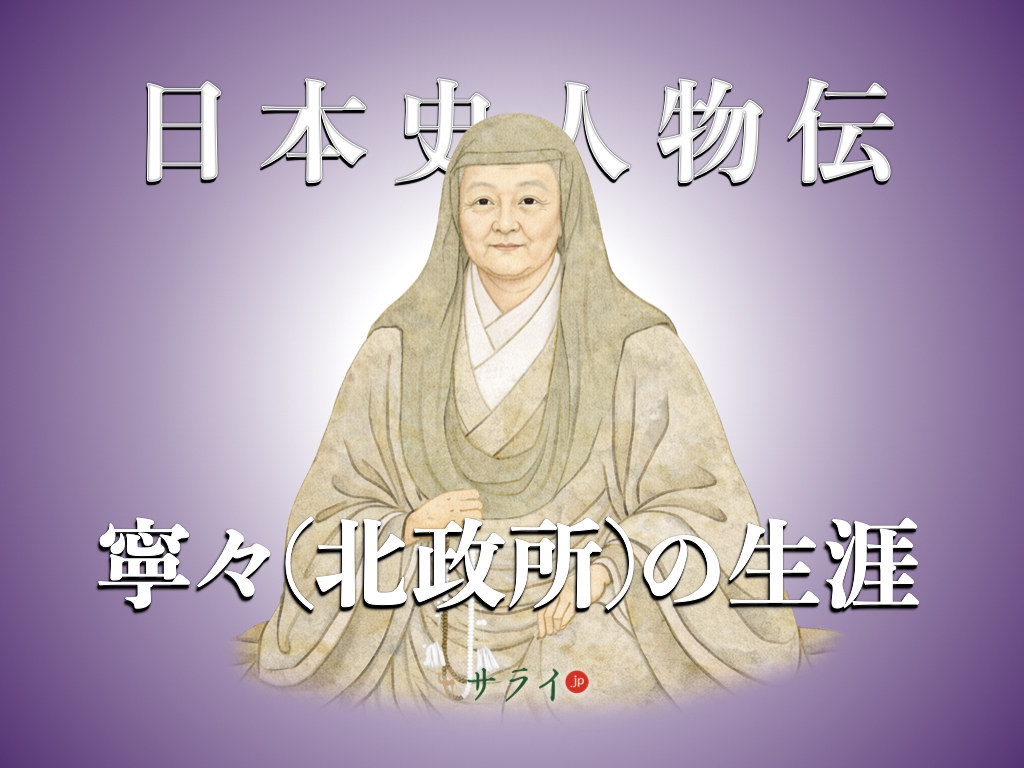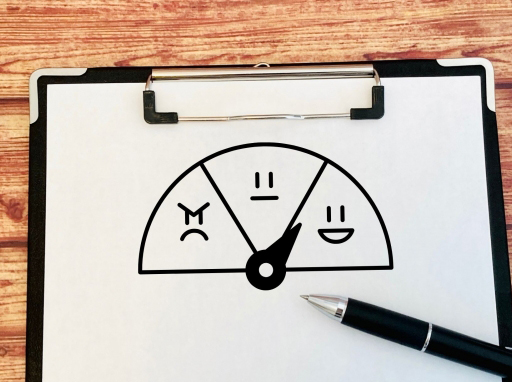秋も深まり、朝晩に肌寒さを覚える頃——季節は「寒露(かんろ)」を迎えます。草木に冷たい露が降り、月の光は明るみ、虫の声が秋の夜長を彩る時期。
古くから日本人は、自然の小さな変化に耳を澄まし、季節のうつろいを丁寧に感じ取ってきました。この記事では、寒露の意味や過ごし方、風習、旬の味覚、花々などを丁寧にご紹介します。暮らしの中にそっと季節を取り入れて、日々に風情を添えてみませんか?
旧暦の第17番目の節気「寒露」について、下鴨神社京都学問所研究員である新木直安氏に紐解いていただきました。
寒露とは?
「寒露」とは二十四節気のひとつで、2025年の寒露は【10月8日(水)】にあたります。字のごとく、草木に冷たい露が降りる時期。秋の長雨が終わり、空気が澄んで秋晴れが続く爽やかな季節の始まりでもあります。
七十二候で感じる寒露の息吹
「寒露」は二十四節気の第17番目で、例年10月8日〜10月22日ごろ。七十二候では以下のように分けられます。
初候(10月8日〜12日頃)…鴻雁来(こうがんきたる)
雁(かり)が北の国から渡ってくる頃。秋の深まりを告げる風物詩です。
次候(10月13日〜17日頃)…菊花開(きくのはなひらく)
菊の花が咲き始め、秋の趣がいっそう色濃くなります。
末候(10月18日〜22日頃)…蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)
この候の蟋蟀(きりぎりす)は、「コオロギ」もしくは「キリギリス」を指すといわれています。戸口に近づいて鳴く虫の声が、秋の夜長を静かに演出します。
寒露を感じる和歌|言葉に映る寒露の情景
皆さま、こんにちは。絵本作家のまつしたゆうりです。秋も深まるこの頃、今回は静寂かつ雄大なこの歌をご紹介します。
さ夜中と 夜は更けぬらし 雁が音の 聞こゆる空ゆ 月渡る見ゆ
(柿本人麻呂歌集『万葉集』1701)
《訳》夜は更けて、真夜中になったようだ。雁が鳴きながら渡っていく夜空を、月が渡っていくのが見える。
《詠み人》柿本人麻呂歌集(かきのもとのひとまろかしゅう)
柿本人麻呂は当時大人気で、超絶歌が上手かった宮廷歌人。天皇や皇子に捧げる公の場で詠まれた歌から、妻の死を嘆く個人的な歌まで幅広い歌が残っています(この歌も、弓削皇子に捧げたも歌3首のひとつだと推測されます)。その柿本人麻呂が詠んだり集めたりしたのが『柿本人麻呂歌集』。現在は『万葉集』に記載があるのみで現存していません。
柿本人麻呂の詠む歌は、みんなが思いつかないような壮大でファンタジーな世界観が特徴。私の一推し歌人です!

今年の十五夜は10月6日(旧暦8月15日)だったそう。皆さまは「夜渡る月」を見られましたか? 秋の半ばあたりは秋晴れの日も多く、月が美しく見える頃合いです。そんな頃合いに詠まれたんじゃないかな、というのが今回の歌。
「さ夜中」に「月が渡る」ということから、この月は満月前後の月だろうと推測します(満月は日没と共に昇り、夜中に天頂に達する)。わざわざ歌に詠むくらいなのだから、中途半端な月齢の月ではなく満月なのでは、と。
この歌が秋に詠まれていると分かるのは、「雁が音」をバックミュージックにしているから。「雁が音」とは、秋に最初にやってくる初雁の、初めの鳴き声のことなのだそう。
なのでここでは、十五夜の満月の日、待ちに待った初雁の切ない鳴き声を聴きながら、真夜中に空を渡っていく満月をながめているという、なんとも優雅なシーンが浮かびあがってきます。
この歌の素晴らしいところは、まず「真夜中」という真っ暗なシーンから始まり、そこに雁の切ない鳴き声が聴こえてくる。そして急に煌々と輝く満月が、のったりと優雅にその漆黒を渡ってゆくのが見えること。
この言葉の並びの妙による、シーンの浮き上がり方、描かれ方が本当に秀逸なんです! これぞ人麻呂様!! という、ダイナミックかつ細やかな計算の芸術品のような歌だなとときめきまくります(『柿本人麻呂歌集』なので、本人の作とは限らないのですが、「弓削皇子に捧げた」と歌詞にあるので、ご本人の歌であるかと!)。
こういう歌を知ると、本当に「言葉の順番」って大事だなあ、と思うんです。これ、逆から言ってたら本当につまんない歌になるんですよ。試しにやってみますね。
「月が渡っていくのが見えます、初雁の鳴き声がします、真夜中です」
こんな風に言われても、「で?」ってなりません?
「月」と言ってる時点で、大半の人が夜を想像するので、その時点でもう、最後の「真夜中」に何の意外性も無いんです。逆だと意味深に感じた「雁と月」のワードも、なんだか希薄に感じてしまう……。
こういうこと、日常でもありません? 例えばプラスの言葉とマイナスの言葉、どちらを先に言うかなんてたいした差じゃないと思ったら大間違い!
よく、「プラス→マイナス→プラス」と、前後をプラスの言葉で挟むといいよ、なんて言われたりもするように、何をどういう順番で言うかで、相手に受け取ってもらえるかが変わったり、話の伝わりやすさが変わってくる。
ほんのちょっとしたことなら、やらないよりやる方が絶対いいですよね!
ここで大事なのが「自分がどう思うか」ではなく「相手がどう思うか」に寄せること。それも自分の思い込みの中の推測でしかないけれど、まったくしない人よりは伝わるものが増えると思うのです。
伝わりやすい歌は、31文字の中で最大限工夫をして、相手に伝わる景色と想いを届けてくれている。長く歌い継がれてきた歌には、その工夫が絶対にある。
わたしたちも「相手に届けられる言葉の数は、本当はそんなに多くはない」と思って、ひと言でも、ひと言だからこそ、「わたしとあなたは、別の考え方をする人である」という前提のもとに、伝わる言葉を選んでいけたらいいですよね。
(「寒露を感じる和歌」文/まつしたゆうり)
寒露に行われる行事|五穀豊穣を神に捧げる感謝のとき
寒露の時期は、自然の恵みへの感謝が各地で形になる季節。秋の収穫を祝う行事が、日本各地の神社や地域行事として受け継がれています。澄んだ空の下、祈りと伝統が静かに息づくこの時期の行事をご紹介します。
神嘗祭(かんなめさい)|伊勢神宮で執り行われる五穀の感謝祭
寒露には、神宮(伊勢の神宮)にて、例年10月15日~17日に「神嘗祭」が行われます。「神嘗祭」はその年に収穫した新穀(しんこく)を天照大御神(あまてらすのおおみかみ)に捧げ、御恵みに感謝するお祭りです。天皇陛下は神宮に遥拝され、日本各地の神社でも神嘗祭遥拝式が斎行されます。
古来からお米を主食として生きてきた日本人にとって、「神嘗祭」は重要な祭儀であり、その伝統は今日にも受け継がれているのです。

えと祈願祭(崇敬者大祭)|下鴨神社で行われる年に一度の感謝祭
京都・下鴨神社では、えと祈願祭(崇敬者大祭)が行われます。豊かな秋の稔りを感謝する、年に一度のお祭りです。模擬店や福引き、舞楽の奉納などが行われ、境内は多くの参拝者で賑わいます。
スポーツの日|身体を動かして秋空を感じる祝日
寒露の時期にある祝日として「スポーツの日」が挙げられます。もともとは1964年の東京オリンピック開会式にちなんで「体育の日」と定められた祝日で、2000年からは10月の第2月曜日に変更されました。
この日は「スポーツに親しみ、健康な心身を培うこと」を目的とした国民の祝日です。秋の涼しい空気の中、体を動かすには絶好のタイミング。散歩や軽い運動でも、季節を楽しみながら心身を整えることができます。
寒露に見頃を迎える花
空気が澄み、草木に冷たい露が宿る寒露の頃。野山や庭先では、ひっそりと咲き誇る秋の花々が季節の深まりを静かに伝えます。この時期にしか味わえない、繊細で風情ある植物の魅力をご紹介します。
菊(きく)
寒露の花といえば、菊が代表的でしょう。奈良時代に中国から伝来し、やがて皇室の御紋に用いられるなど、日本文化を象徴する花となりました。
江戸時代の園芸ブームで品種改良が盛んに行われ、日本独自の多彩な菊が生み出されたそうです。大ぶりでたくさんの花びらを付ける菊や、小さく一重の風情ある野菊など豊富な種類が楽しめます。

藤袴(ふじばかま)
藤袴は、秋の七草のひとつ。淡い藤色の小さな花を袴(はかま)に見立てたことが名前の由来とされ、古くは『万葉集』や『源氏物語』にも登場する花です。
見た目の可憐さもさることながら、乾燥させると甘くほのかな桜餅のような香りを放つのが特徴。その芳香から中国では「香水蘭」や「蘭草」とも呼ばれ、古くからポプリや薬草としても親しまれてきました。

寒露の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む
秋が深まる寒露の時期は、季節の恵みが豊かな季節。野山や畑、海から届けられる旬の味覚をいただくことで、自然の移ろいを身体でも感じ取ることができます。この時期ならではの秋の味覚をご紹介しましょう。
果物|柿(かき)
寒露の頃に旬を迎える果物として、まず挙げられるのが柿です。ほんのりとした甘さと、柔らかな果肉は、どこか懐かしさを感じさせる秋の味覚。熟した柿はビタミンCが豊富で、風邪予防にも効果的とされます。
種類は大きく甘柿と渋柿に分かれますが、甘柿は渋柿の実を日本国内で品種改良し、生まれたものです。

魚|ししゃも
寒露の頃に味わいたい魚といえば、ししゃもが代表格。10月〜11月の季節になると、卵を蓄えるメスは「子持ちししゃも」と呼ばれます。
焼いて食べれば、濃厚で歯ごたえのある卵の食感を味わえるでしょう。丸ごと唐揚げやフライにするのもおすすめです。また、酢や柑橘類の調味料と相性がいいため、マリネにも向いています。
京菓子|初雁(はつかり)
寒露の時期、京都では「初雁」という上用饅頭をいただきます。その名のとおり、北国から飛来する雁の姿を模した焼き印があしらわれ、秋の訪れを告げる菓子として親しまれています。
材料には、つくね芋と上用粉が用いられ、しっとりとした口当たりと上品なこし餡の甘さが絶妙。古人が空を見上げて雁の飛来を感じたように、現代の私たちも、ひとつの菓子から季節の空気を感じ取ることができます。

写真提供/宝泉堂
まとめ
草木に露が降り、澄んだ冷たい空気が肌で感じられる「寒露」。秋になって日照時間が短くなるため、夜は時間が長くなる、いわゆる「秋の夜長」となります。空気が澄んでいるため、月や星がきれいに見えて、窓を開けると心地いい風が吹き込んでくるでしょう。涼やかな夜風に当たりながら、季節の移ろいを感じてみてはいかがでしょうか。
●「和歌」部分執筆・絵/まつしたゆうり

絵本作家、イラストレーター。「心が旅する扉を描く」をテーマに柔らかで色彩豊かな作品を作る。共著『よみたい万葉集』(2015年/西日本出版社)、絵本『シマフクロウのかみさまがうたったはなし』(2014年/(公財)アイヌ文化財団)など。WEBサイト:https://www.yuuli.net/ インスタグラム:https://www.instagram.com/yuuli_official/
監修/新木直安(下鴨神社京都学問所研究員) HP:https://www.shimogamo-jinja.or.jp
協力/宝泉堂 古田三哉子 HP:https://housendo.com
インスタグラム:https://instagram.com/housendo.kyoto
構成/菅原喜子(京都メディアライン)HP:https://kyotomedialine.com Facebook