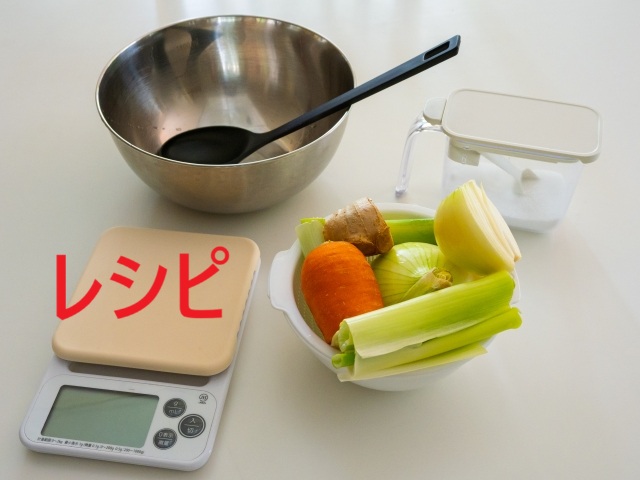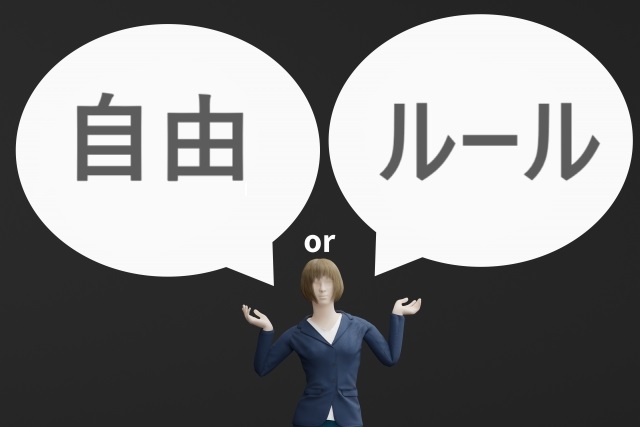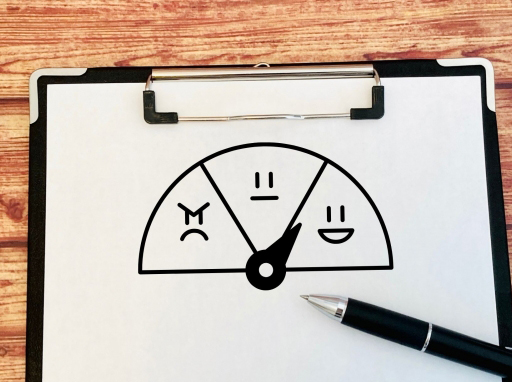先の見えない現代において、会社や組織にはどんなルールが必要なのでしょうか。マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)で、その知見を得ましょう。
* * *
組織を守り、成長させるための「ルールの明文化」
現代は「正解のない時代」と呼ばれるほど、変化のスピードが速く、かつての成功体験や経験則が通用しなくなってきています。このような環境下で組織を動かすために必要なものは、「柔軟性」ではなく、「共通の判断軸=ルール」です。
本記事では、識学の理論をもとに、「なぜ今、ルールが必要なのか」「ルールがどう組織を変えるのか」について解説します。
1.不確実な時代がもたらす「判断の分散」
テクノロジー、価値観、社会制度の変化が加速する現代では、「正解」が通用しない場面が増えています。昨日までの常識が今日には通じない。そんな状況で組織が陥りがちなのが、「各人が独自に判断して行動する」状態です。
この「判断の分散」は、一見すると自律性や柔軟性を重視しているように思えますが、実際には組織成果のバラつきや責任の不明瞭さを引き起こします。
上司ごとに指示内容が異なったり、部下が「どの行動が正解か」をその場の空気や雰囲気で測るようになったりすると、組織は次第に機能不全に陥っていきます。意思決定にかかるスピードも遅くなり、事後処理や感情でのマネジメントばかりが増えるのです。
このような状況下でこそ、組織には「判断の軸」が必要になります。それが、明文化された「ルール」です。
2.「ルール」の定義
ルールとは単なるマニュアルや規則とは異なります。ルールは、以下の3要素を備えたものです。
・明文化されていること
ルールは明文化され、誰でもそのルール内容を確認できる場所を認識できる状態でなければなりません。「暗黙の了解」や「なんとなくそうしている」は、ルールとして機能しないのです。
・そのルールではすべてのメンバーが同じ動きになること
特定の人だけに適用されるルールは「例外」を生み、不平等や感情的な摩擦の原因となります。ルールは「全員が守る」ものであり、だからこそ組織の統一性が保たれます。
・破った際に必ず「指摘」があること
ルール違反が放置されれば、ルール自体の信頼性が崩れ、組織は空気と感情で動くようになります。違反には必ず指摘を行うことで、「ルール=機能する基準」になります。
3.なぜ「今」ルールが必要なのか?
多くの企業が今、変革期にあります。新規事業への挑戦、DX化、組織再編、働き方改革など、従来の型が通用しない変化が求められています。その中で、「現場の判断に任せる」「自律性を重んじる」といった運営が称賛されがちですが、それは本来「判断軸が共有された後」に機能するものです。
ルールが存在しない中での自由は、単なる放任です。判断基準が個々人に委ねられると、組織として一貫性を失います。そして一貫性を失った組織には、責任の所在が曖昧になり、成果も偶発的なものになります。
変化の激しい時代だからこそ、組織はまず「ぶれない軸=ルール」を設けることで、メンバーが「どう動けばよいか」を迷わず行動できる状態をつくる必要があります。
つまり、「自由に動ける状態」とは、「ルールがあるからこそ実現できる」のです。
4.実践事例:「ルールの明文化」で組織が変わった
ある企業では、営業活動における報告方法が各人に任されていました。その結果、日報を出すタイミング、内容、頻度に大きなバラつきが生じ、上司の管理負荷も高く、正しい評価が難しい状況でした。
報連相に関するルールを「Slackで18時までに報告」「案件ステータスは週1で更新」などと期限と状態を明確にして明文化したところ、報告精度とタイミングが安定し、上司のマネジメントが格段に効率化されました。
さらに、評価基準も「訪問件数」「商談化率」など、行動に基づく定量指標に変更されたことで、部下が「どうすれば評価されるか」を理解しやすくなり、主体的な行動が増加しました。 このように、ルールの明文化は「管理が厳しくなる」のではなく、「自由に成果を出しやすくなる」ための基盤なのです。
5.ルールは「縛る」ものではなく、「自由にするための土台」
ルールというと、「堅苦しい」「縛られる」といったネガティブな印象を持たれがちです。しかし、ルールとはむしろ人を自由にするための仕組みです。
ルールが明確にあるからこそ、「どこまでが自由で、どこからが逸脱か」が分かるようになります。そして、そのルールの範囲内であれば、個人は自信を持って判断・行動できるのです。
言い換えれば、ルールがなければ自由は存在しない。ルールがあるからこそ、リーダーは部下に責任を委ねられ、部下は安心して挑戦ができるのです。
まとめ:ルールがある組織は、変化に強くなる
「正解がない時代」に最も危険なのは、各人が自分の価値観や感覚で判断してしまうことです。だからこそ、組織には「共通の判断軸=ルール」が不可欠です。
ルールの明文化とその上司が決めたルールを守らせることが、組織として上司側の意図が下せる環境となるため、組織の成長や成果につながると考えます。変化の時代において成果を出し続ける組織は、実は「自由な組織」ではなく、「ルールに基づいて自由に動ける組織」なのです。
自社のルールを見直すことこそが、あいまいな判断や空気で動く組織から脱却するチャンスとなります。
【この記事を書いた人】
識学総研 編集部/株式会社識学編集部です。『「マネジメント」を身近に。』をコンセプトに、マネジメント業務の助けになる記事を制作中。3,000社以上に導入された識学メソッドも公開中です。
引用:識学総研 https://souken.shikigaku.jp/
コンサルタント紹介はこちらから https://corp.shikigaku.jp/introduction/consultant