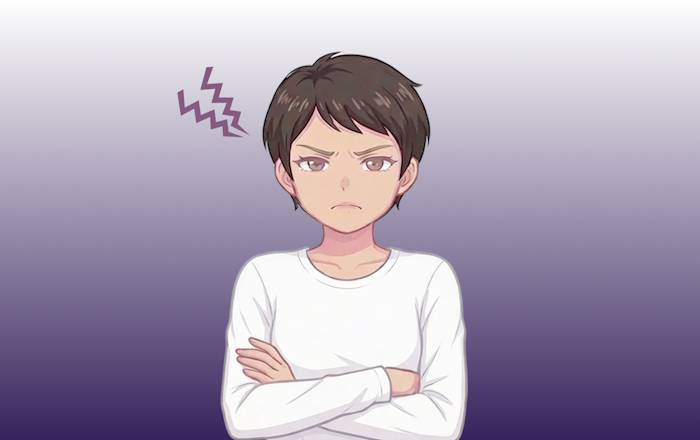壬生忠岑(みぶのただみね。9世紀半ば~10世紀前半頃)は平安時代の歌人で「三十六歌仙」の一人。身分の低い武官の家柄の出で、終生官位にはめぐまれなかったが、歌人としては早くから才能を認められ、紀貫之(きのつらゆき)とともに『古今集』の撰者に抜擢(ばってき)された。

画・菱川師宣 国立国会図書館蔵
壬生忠岑は叙情的な歌を多く残している。
「命にも まさりて惜しくあるものは 見果てぬ夢の覚むるなりけり」(命よりも惜しいと思うことは、愛する人との逢瀬(おうせ)の夢をおしまいまで見ぬうちに目が覚めてしまうことであった)
そんな歌をのこした忠岑ではあるが、老いを迎えると、身分が低いままに歳をとっていくのを嘆いて、次のように述べている。
「さすがに命は惜しいもので、越(こし)の国(北陸)の白山(しらやま)にあると伝え聞く不老不死の薬を手に入れて、何度も若返って帝の御代(みよ)を幾代(いくよ)にもわたって見たいものだ」。
この言葉から、平安時代の上流社会のなかで、不老不死の薬のありかが伝説的に語られていたことがわかる。
忠岑は官位が低いまま亡くなったが、その歌はいまも輝きをもって生き続けている。
文/内田和浩
※本記事は「まいにちサライ」2013年10月11日掲載分を転載したものです。