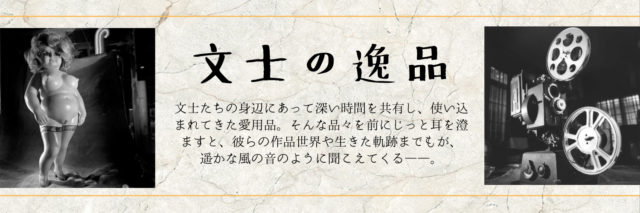
◎No.38:中勘助の匙

中勘助の匙(撮影/高橋昌嗣)
文/矢島裕紀彦
中勘助は、子どものころ、虚弱体質だった。生まれて間もなく、全身に吹き出物ができ、漢方医の処方した薬を飲まなければならなかった。その際、赤ん坊の勘助の口へ薬をすくい入れるのに、小さく平べったい銀の匙が使われた。
そんなエピソードから始めて、自らの幼少年期の思い出と、少年の目でとらえた美的世界を綴ったのが、いまに読み継がれる佳作『銀の匙』だった。勘助がその稿を起こしたのは、明治45年(1912)夏、満27歳の折。彼はまだ、一介の文学青年に過ぎなかった。
そんな勘助の作品が、翌年4月から6月にかけて、東京朝日新聞に連載された。夏目漱石の推挙によるものだった。漱石は、朝日の学芸部長の山本松之助に宛てた書簡(大正2年2月26日付)の中で、『銀の匙』の掲載を薦め、出来ばえについてこう讃美している。
「珍しさと品格の具(そな)はりたる文章と夫(それ)から純粋な書き振とにて優に朝日で紹介してやる価値ありと信じ候」
静岡市の中勘助文学記念館を訪れると、その銀の匙があった。全長、約8センチ。渋みのある銀色。
背丈180 センチ余りにまで成長した勘助が、この小さな匙を宝物のように愛蔵し、時々取り出しては眺めていた光景を思い浮かべると、なんとも微笑ましい気分になる。
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。『サライ.jp』で「日めくり漱石」「漱石と明治人のことば」を連載した。
写真/高橋昌嗣
1967年桑沢デザイン研究所 グラフィックデザイン科卒業後、フリーカメラマンとなる。雑誌のグラビア、書籍の表紙などエディトリアルを中心に従事する。
※この記事は、雑誌『文藝春秋』の1997年7月号から2001年9月号に連載され、2001年9月に単行本化された『文士の逸品』を基に、出版元の文藝春秋の了解・協力を得て再掲載したものです。


































