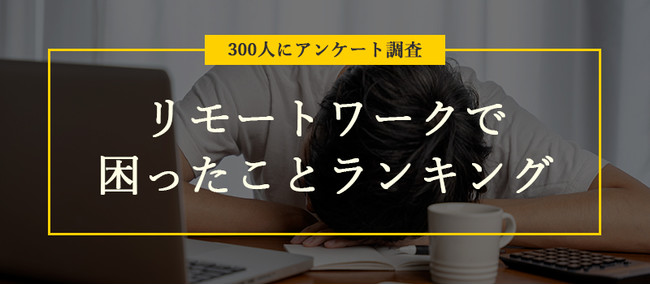千葉県鴨川市のワーケーション・シンポジウム(3月13日開催)に登壇し、「いつもと違う場所に身を置くことで、体も心もリフレッシュすることで元気になれる。新しいアイデアも生まれるんですよ」と語ったのは、旅行や航空業界に詳しい専門家・鳥海高太朗さん。国内外問わずテレビの中継を各地から行うなど、ワーケーションの達人でもある鳥海さんに、ワーケーション地の選び方について教えてもらった。
【ワーケーション地の選定ポイント1】一にも二にもインターネット環境。とくに速度が重要
ワーケーションをしながら、ZoomやTeamsなどでスムーズにオンライン会議をする場合は、上り100Mbps、下りでも100Mbpsだと完璧、と鳥海さん。
「普段のリモートワークとほぼ近い環境でやりたいですよね。僕は動画を送らなきゃいけないこともあるので、これくらいあると安心。ストレスなく仕事ができるようにしたいですね。100メガあれば嬉しいですが、最低ラインとしては上り・下りともに30メガ以上の速度です」
通信環境にもよるが、ワーケーション実施地のインターネット環境がイマイチなときは、スマホのテザリングを使うのも手だそう。
【ワーケーション地の選定ポイント2】東京から1.5時間。緊急時には帰れる距離がいい
たとえば鴨川市は自家用車であれば都内から約1.5時間で行くことができる。東京駅から高速バスで2時間強、特急で2時間弱なので、日帰り需要も十分に考えられるという。
「僕の場合は、急に仕事が入る場合もあるので、すぐに東京に戻れる距離というのは重要視しています。たとえば熱海だと、新幹線で40分あれば帰れる。車で移動できるなら鴨川は90分くらいだし、東京湾アクアラインも800円と安いですし(2025年4月1日より料金体制が改定)、交通費の面で考えるといいかも」
【ワーケーション地の選定ポイント3】誘惑に負けてしまうから、観光スポットは多すぎないほうが〇

仕事が終わった後は、出来立てのビールをいただきたい!
ワーケーションをする上で、たくさんの観光スポットがあると、仕事ができず本末転倒に。「これは大きいポイントですね。鴨川は、シーワールドとプラスちょこっとしかないのと、騒がしくないというか、静かなのは魅力です。『KAMOGAWA BREWERY』のテラスは海が綺麗に見えるし、海外っぽくていいワーケーションスポット。リゾート宿『ひだまりINN』もロケーションがいいですね。海に近いから、朝起きてすぐ海辺を散歩したり、波の音を聞きながら仕事をしたりもできます」
ワーケーションを実施する場所について、宿泊施設の客室で実行するのもいいけれど、ホテルのワーキングスペースがおすすめという話も伺った。鳥海さん曰く、「高級で泊まることができないホテルでも、ワーキングスペースやカフェなどを利用してみるとテンションが上がって仕事が捗りますよ」
【ワーケーション地の選定ポイント4】グルメは最大のリピート要素となる
グルメのために、ワーケーション実施地を選ぶことも大いにあるという鳥海さん。香川のうどんや岩手のウニ丼を目当てにワーケーションをしたりと、美味しいものには時間やお金の糸目をつけない。
「鴨川は魚料理がいいですよね。観光地価格ではないのもいいところ。僕は金目鯛の煮付け、なめろう、アジフライが好き。海鮮丼も好きです。ちなみに鴨川市の郷土料理で『おらが丼』というのがあるのですが、これは鴨川のブランド米『長狭米』を使い、鴨川産の食材を乗せたもので、お店ごとにオリジナルで出しているんです。だから、中華の丼もあればイタリアンの丼もあるので、イコール海鮮丼ではないことをご注意ください」

地元産品の育成に寄与する他、季節感を失わない、健康を意識するなどの掟がある。
また、鴨川でのおすすめ店舗については、「プライベートでよく行くのが『食事処 池田』。あと『まるよ』は、いわゆるデカ盛りグルメです!」とのこと。
鴨川ではこの春、「鴨川夜のまちあるきガイド」なるものが発行された。こちらもグルメ探しや夜の梯子酒の参考に。
【ワーケーション地の選定ポイント5】レンタルサイクルやカーシェアなど、二次交通が確保できる
いざワーケーションしてみると、鴨川のようにお店が点々としている地域も少なくないので、「レンタルサイクルやカーシェアなど、二次交通の確保を忘れずに」と鳥海さん。
今回シンポジウムを行った「鴨川市小湊さとうみ学校」では、電動マウンテンバイク(E-bike)のレンタルも行っているので、鴨川でのワーケーションの際には、ぜひ利用してみては。
* * *
鳥海高太朗さん(旅行、航空アナリスト)

1978年千葉県富津生まれ。帝京大学理工学部航空宇宙工学科、千葉商科大学サービス創造学部、共栄大学国際経営学部で非常勤講師を務める。航空、旅行業界の最新動向や、自身の体験談を中心に、SNSやテレビ、ラジオなどに多数出演し、情報を発信。著書に『コロナ後のエアライン』(宝島社)。YouTubeチャンネル「PTA鳥ちゃんねる」を配信中。
取材・文/株式会社都恋堂