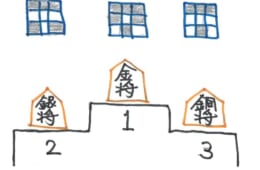昭和33年3月29日、長野の犀北館で行われた第7期王将戦の最終対局。前年、三冠を達成した升田(左)を大山が破り王将位に。写真:毎日新聞社
升田幸三が棋士になることを夢見て13歳11か月で家出をしたとき、母親が使っていた竹製の物差しの裏に墨書したことばがある。
名人に香車を引いて勝つ──。
名人を相手に香落ち(自分の方が香車1枚少ない状態)で勝とうというのだから、志や高し。そして後年、実際にこの空前のことを成し遂げた唯一の棋士となった。
大正7年3月21日、広島県双三郡三良坂町(現・三次市)の農家の生まれ。将棋好きの7つ年上の長兄に教わって小学2年で将棋を覚えた。両親は将棋も碁もやらず、とくに母親は子供が将棋を指すなんてとんでもないと考えていた。自分の夫が博打好きで苦労させられていたため、勝負事そのものを嫌っていたのだ。
その母に見つからないよう、兄は土蔵の中で弟に将棋を仕込んだ。弟はめきめき腕を上げ、棋士になりたい気持ちをふくらませてゆくが、母は聞く耳は持たない。かくて昭和7年2月、升田少年は家を飛び出した。
50km余り歩いて広島市内にたどり着くと、升田は大道詰将棋の賞金で飢えをしのぎ、天ぷら屋やクリーニング店で働いて汽車賃をためた。紹介してくれる人がいて大阪の木見金治郎の内弟子となったのは、家出から4か月後のことだった。
初め雑用ばかりで、升田は将棋の勉強もできないと不満を募らせる。そんなある日、買い物に出て凍りついた道路で足をすべらせ、鍋の中の豆腐を放り出してしまった。普段から気の抜けた升田の生活態度を見ていた木見夫人は、「使いっ走りも満足にできんどって、なにが将棋や」と叱しかりつけた。
はっと気づかされるものがあった。後年の升田のことば。《それからというものは、どんなことにも気持ちを集中させた。一生懸命すれば雑念がわかず、不平不満も起こらない》
意識を変えると、不思議と雑務をこなす合間に勉強ができるようになる。升田は順調に昇段を重ねた。
升田の将棋はこの頃から破格のものがあった。定跡にとらわれず、独創的な中飛車戦法などを考案し相手を打ち負かす。そんな升田に目をかけた阪田三吉は「あんたの将棋はいい将棋や。大けな将棋や」と応援してくれた。

升田幸三が盤箱の蓋裏に書いた「香一筋」(倉敷市大山名人記念館蔵)。升田は香車を「辺鄙なところで灯台守をしとるような駒」と表現した。
昭和14年11月には、時の名人である東京の木村義雄と交流試合で対局し、相手の香落ちながら完勝。次は平手で勝負だと、いやが上にも意気があがった。
そんな升田のもとに、昭和14年12月、召集令状が舞い込む。升田は3年間の軍隊生活を余儀なくされた。いったんの帰国後、昭和18年11月には二度目の召集。空襲の激しい南海の孤島ポナペに。歩哨に立って星空を見上げながら升田は思う。
《もう一度木村名人と指してみたい。月が連絡してくれるなら、通信将棋で戦ってみたい》
幸い命を長らえ、復員したのは昭和20年12月。この間、木村義雄は名人として地歩を固め、木見門の弟弟子だった大山康晴もぐんと力をつけていた。
意外なことに、升田の棋力も落ちるどころか強靱になっていた。最前線で死線をくぐった経験が、升田の精神力を逞しくしていたのである。
《続きは『サライ』本誌10月号の特集「将棋界「鬼才」列伝」をご覧ください》

『サライ』2017年10月号では「将棋界“鬼才”列伝」と題して、「鬼才」と呼ばれる、阪田三吉、升田幸三、
将棋盤上で繰り広げられた名勝負の逸話を、
※サライ10月号は下記より試し読みいただけます。
↓↓↓
https://shogakukan.tameshiyo.me/4910142111075
※この記事は『サライ』2017年10月号より一部転載しました(取材・文/矢島裕紀彦、撮影/宮地 工)