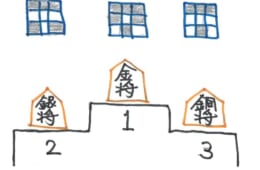昭和55年、山形県天童市で王将位復活に笑顔を見せる大山康晴。
大山康晴は大正12年3月13日、岡山県浅口郡西阿知町(現・倉敷市)に生まれた。父親は畳表の会社に勤務するサラリーマンだった。
少年期にこんな逸話がある。小学校に入学して最初の夏休み、大山は腸チフスに罹りひと月ほど床に寝ついた。見舞いにきた父親の仕事仲間が、退屈そうな大山少年に向かって「将棋指そうか」と言ってくれた。
将棋はこの正月に覚えたばかりだった。熱を計ってから、という父の許しが出て一番指した。終わって熱を計り直すと、不思議に下がっている。そんなことが1週間つづくうち、大山少年の体温は平熱に戻ってしまった。
喜んだ父親はこう言った。「そんなに好きなら、将棋指しになってもいいよ」全快祝いのプレゼントは将棋盤と駒。母手作りの毛糸の駒袋も添えられた。

小学生の大山が将棋を習った最初の師の元で使用していた小振りの盤と駒。
翌年の正月からは、父の知り合いの先生のもとに通い、本格的に将棋を習いはじめた。小学校6年になると、父親が、大阪の木見金治郎のもとに弟子入りする話をまとめてきてくれた。担任教師や学校側も理解があり、どうせなら早い方がいいと、卒業が決まると卒業式を待たずに大阪に行くことになった。
当日は駅に教師や同級生、応援の人々が駆けつけ、万歳の声と「若竹や苦節しのいで天をつけ」の幟のぼりで見送ってくれた。仕立て下ろしの絣の着物に小倉の袴をつけ、青白い顔に牛乳瓶の底のような分厚い眼鏡をかけた大山少年。大志を抱きつつ、走りだした列車の窓から身を乗り出し、蟻のように小さくなってゆく人の群れをいつまでも眺めていたという。
木見家ではすぐ上の兄弟子に升田幸三がいて、厳しく稽古をつけられた。そんな升田は昭和14年12月に召集令状を受け、広島の連隊に入隊。昭和19年4月、大山にも赤紙がきた。岡山の連隊に入り新兵としての基礎訓練のあと、体が丈夫でないため縫工に回された。
上官に将棋好きがいて、よく相手をさせられた。戦友の多くが前線に送られ戦死する中、大山は内地に留とどめられ命をとりとめた。

昭和33年3月29日、長野の犀北館で行われた第7期王将戦の最終対局。前年、三冠を達成した升田(左)を大山が破り王将位に。写真:毎日新聞社
終戦後の昭和23年2月、大山は名人戦への挑戦権をかけて升田と三番勝負をすることになった。新聞はこの同門対決を「宿命のライバル」と書き立てて盛り上げた。
対局場は高野山と決した。関係者は大阪で待ち合わせることになっていたが、定刻を過ぎても升田は現れない。列車の時刻があり、大山らはやむなく先発。升田は夜になってようやく新聞記者に伴われて粉雪の舞う高野山女人堂に到着した。連絡の行き違いがあったらしかった。対局前から荒れ模様の空気が漂ただよっていた。
1勝1敗で迎えた最終第3局、振り駒で先手となった升田が序盤から優勢で、大山は奮闘空むなしく必敗の局面を迎えた。残り1分の大山に対し、升田は1時間余りも持ち時間を余していた。だが、どうしたことか、升田がノータイムで悪手を指し一瞬のうちに逆転。
「錯覚いけない、よく見るよろし」
升田はおどけた顔で呟くしかなかった。大道詰将棋の口真似だった。時計の針は午前2時30分を指していた。大山は思いもせぬ拾い勝ちに、しばし茫然と盤上を見つめていた。
《続きは『サライ』本誌10月号の特集「将棋界「鬼才」列伝」をご覧ください》

『サライ』2017年10月号では「将棋界“鬼才”列伝」と題して、「鬼才」と呼ばれる、阪田三吉、升田幸三、
将棋盤上で繰り広げられた名勝負の逸話を、
※サライ10月号は下記より試し読みいただけます。
↓↓↓
https://shogakukan.tameshiyo.me/4910142111075
※この記事は『サライ』2017年10月号より一部転載しました(取材・文/矢島裕紀彦、撮影/宮地 工)