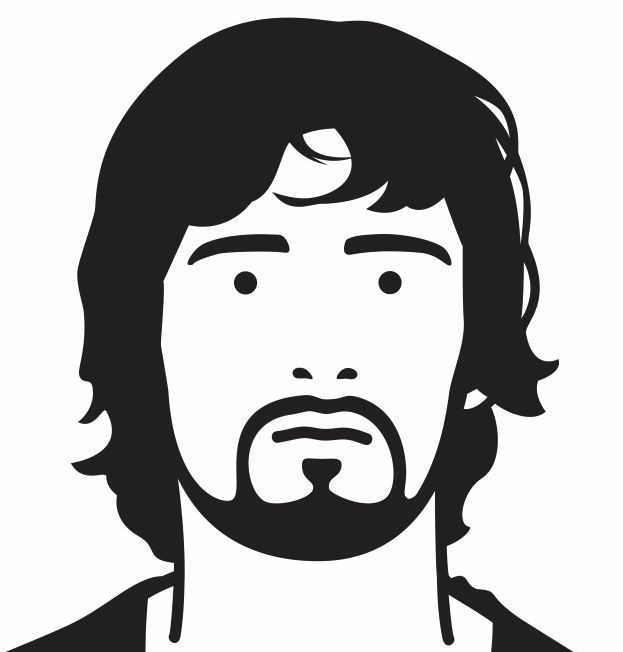ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)も第36回になりました。政権は田沼意次(演・渡辺謙)から松平定信(演・井上祐貴)に移り、それを受けて蔦重(演・横浜流星)らは『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくとおし)』に続いて『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』という黄表紙を刊行して、意気軒高な様子が描かれました。
編集者A(以下A):ところが、定信周辺では、ようやく蔦重らの真の思惑に気がついた! という体で物語が続いていきます。
I:その流れで老中の本多忠籌(ただかず/演・矢島健一)と定信との問答が展開されます。忠籌が賄賂(まいない)を受け取っているという報告があがったことを問いただします。
A:本多忠籌は、嫡流ではありませんが、2023年の『どうする家康』で山田裕貴さんが演じた「徳川四天王」本多忠勝の子孫になります。その本多忠籌が定信に対して、「なぜ賄賂を受け取るのか」ということを懇切に説明します。そして、よせばいいのに定信に対して『鸚鵡返文武二道』を渡してしまうのです。
I:これで一気に炎上するという設定ですね。なんと、蔦重は刊行した黄表紙を絶版にするよう命じられてしまいます。
A:出版社勤務の身としては、背筋が凍る思いがしました。「いや、現代にこんなことはさすがにおきませんよ」というかもしれませんが、まさにいまこのとき、アメリカでは、テレビ局の免許取り消しが話題になっています。
I:もしかしたら、いま、このときが実は正念場なのかもしれませんね。
A:いや、本当ですね。

兼業作家らが次々と……

I:さて、朋誠堂喜三次(平沢常富/演・尾美としのり)の殿様である佐竹義和(演・二宮慶多)が登場しました。
A:佐竹家は、源義家の弟新羅三郎義光を源流とする清和源氏の名門。もともとの本領は常陸国。源頼朝挙兵の際にもすぐには従わず、むしろ反目の立場を貫きました。歴史の表舞台に主要人物として登場することはないのですが、鎌倉時代から戦国時代にかけてしぶとく生き残ります。ところが、関ヶ原合戦の際に、旗幟を鮮明にせず、常陸国から出羽秋田に移封させられるのです。
I:2023年まで秋田県知事を務めていた佐竹敬久氏は、佐竹家分家の方なんですよね。石高は20万石ですが、将軍からの偏諱はなくて代々の藩主は「義」を通字とした名を名乗っています。25万石の阿波蜂須賀家は藩主が将軍の偏諱を受けていますから、「偏諱の分岐」は20万石から25万石までの間なのでしょうか。
A:その佐竹家で江戸留守居役を務めていた朋誠堂喜三二こと平沢常富。平沢家じたいも義光流の源氏の家系で、佐竹氏に仕える前は、愛洲氏を名乗っていた名門。1万石の大名の家臣である恋川春町(演・岡山天音)とは「格」が違うのですが、「作家活動」では、俗世の身分を超越して交流できるというのが楽しかったのでしょう。
I:思えば、大田南畝(演・桐谷健太)もこの頃は、どちらかといえば低位の幕臣ですし、蔦重の耕書堂で執筆した「作家陣」は武士としての本業を持つ人が多かった。いわば、兼業作家主流の時代だったわけですが、それぞれお家の事情でたいへんなことになったのですね。
A:なんだか、蔦重周辺が「暗いムード」に包まれます。まさに正念場ですね。
I:蔦重とともに、平秩東作(演・木村了)の見舞いに行った大田南畝が言った「戯れせんとや生まれけん、だ」は、平安時代末期の後白河法皇の『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』収録の歌「遊びをせんとや生まれけむ 戯れせんとや生まれけん 遊ぶ子どもの声聞けば 我が身さへこそ揺がるれ」からの引用だと思われます。
A:2012年の大河ドラマ『平清盛』のテーマ曲でも、このフレーズが使われていました。最終回のタイトルも「遊びをせんとや生まれけむ」でした。そんなことも思い出された方もいたのではないでしょうか。
荒唐無稽なストーリーに秘められた「定信批判」

I:『鸚鵡返文武二道』は、延喜の帝、菅原道真の子という設定の菅秀才と、鎮西八郎為朝、源義経などが、同時代に生きているというよくよく考えれば、荒唐無稽な黄表紙です。作者の恋川春町自身、菅秀才の台詞として、「時代違いも知っているが、ここが草双紙だから、うっちゃっておきやれサ」と言わせているくらいです。本来、そんなものは無視するのがふつうなのでしょうが、松平定信はそういう黄表紙までも、自分のことを揶揄しているものだと、取締りに乗り出すわけです。
A:黄表紙で一見荒唐無稽なあらすじのようにも見えますが、そもそもタイトルの『鸚鵡返』の個所が、松平定信が著した『鸚鵡言(おうむのことば)』を念頭においたものです。てい(演・橋本愛)が懸念していた通り、ギリギリを攻めている。物語に登場する平安時代の実在の有名学者・大江匡房が阿波出身ということになっていて、これは『べらぼう』劇中でも登場している阿波徳島藩出身の儒学者柴野栗山(演・嶋田久作)を穿っているわけです。
I:『鸚鵡言』では、経済について定信はこんなふうに記しています。「入るを量りて出すことをなすは経済の本なり。倹約は費を省きて、つつまやかにすることなるべし。惜しむにあらず」――。荒唐無稽といえば、同じく恋川春町執筆の『悦贔屓蝦夷押領(よろこんぶひいきのえぞおし)』は、以前にも紹介しましたが、「悦」の字を「よろこんぶ」と読ませ、蝦夷特産の「昆布」にかけているものです。登場人物の「奥蝦夷女王」は帝政ロシアの女帝、エカチェリーナ2世をモデルにしたといいます。お話も源義経一行の冒険譚という筋で、蝦夷特産の昆布などを雲に乗って運んでくるという内容です。
A:いずれにしても、自由にさせるか、倹約させるか否かというのは、現在でも議論される「懸案」ではあります。それこそ、いままさに政権党の総裁選挙が行なわれていますが、経済政策とはほんとうに難しいですね。

クナシリ・メナシの戦い

I:さて、今週は、家斉施政下の蝦夷地のことにも触れられています。蝦夷地といっても広大ですが、国後島や現在の道東を舞台に展開したクナシリ・メナシの戦いも家斉(演・城桧吏)が将軍になったばかりのころに発生しました。
A:『べらぼう』劇中でひょうろくさんが演じた松前廣年が出陣した戦いですね。松前廣年は、アイヌ分断をはかり、一部のアイヌは廣年に加勢します。そのために、松前方の圧勝という形で合戦は終了します。このときに、絵画にも通じていた松前廣年が自軍に味方したアイヌの首長を描いたのが、『夷酋列像(いしゅうれつぞう)』。絵師としては蠣崎波響(かきざきはきょう)の名乗りの方が著名です。現在はロシアが不法占拠している北方領土の国後島(くなしりとう)ですが、この頃の松前藩では、現在の北方領土はもちろん、カムチャツカ半島、樺太まで「松前領」と幕府に報告していたといいます。
I:この頃の蝦夷地の歴史、もっと知りたくなりますよね。
【恋川春町の死。次ページに続きます】