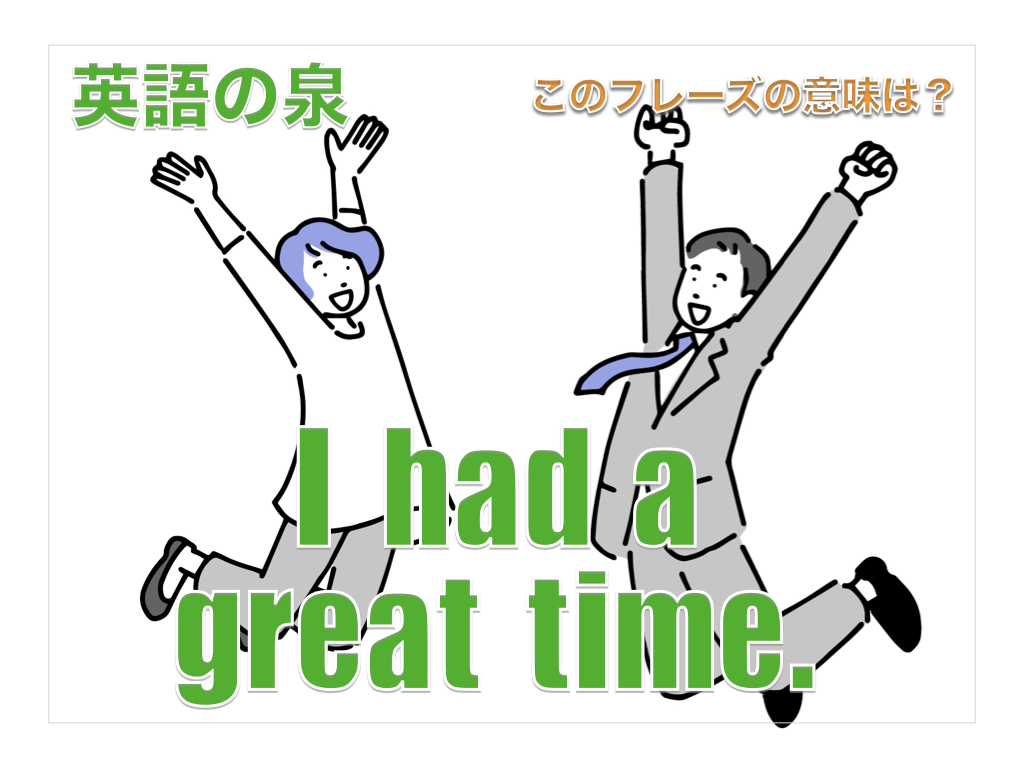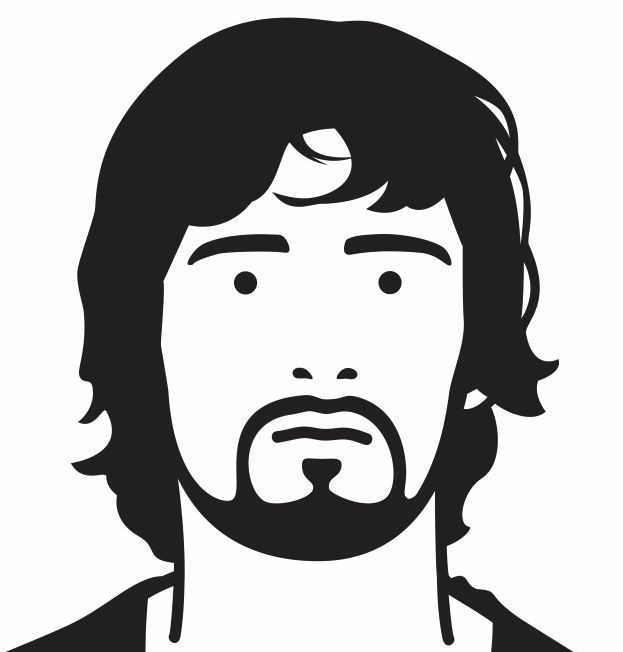恋川春町の死

I:さて、為政者が本気で取締りに乗り出せば、いとも簡単に素姓が暴かれる実態が描かれました。
A:朋誠堂喜三二が国元に異動させられ、今度は恋川春町が、藩主である松平信義(演・林家正蔵)に呼ばれます。恋川春町が仕えた駿河小島藩は、現在の静岡市の一部をおさめた一万石の藩。一万石といえば、現在でいえば、町長、村長のような感じです。加賀、能登など複数の国を版図として100万石を超える加賀藩や薩摩藩、仙台藩など大藩と比べれば、同じ大名とはいえ、格差はありました。
I:藩主の松平信義が恋川春町を庇おうと、病だということでやり過ごそうとしたのですが、松平定信はそうした動きを見透かしたのか、小島藩の屋敷まで実際に訪ねようとするわけです。さすがに武士として、主君にこれ以上の迷惑はかけられない――。恋川春町はそう思ったんですね。
A:恋川春町の死については、たしかに自害説もあります。豆腐の角に頭をぶつけて死んだというくだりは、最期の最期まで「戯作の世界に身を投じた」恋川春町こと倉橋格の生きざまを象徴的に描いた「胸に迫る」場面になりました。私はこの場面をみて、2011年に亡くなった立川談志師匠の「戒名エピソード」を思い出しました。師匠が亡くなった際、師匠が戒名を生前自らつけていたことが報じられました。その戒名が「立川雲黒斎家元勝手居士」。「雲黒斎=うんこ臭い」というフレーズを入れ込んだわけです(笑)。その「うんこ臭い」が入った「戒名」を「生前自らつけた戒名」だと、大真面目に新聞が報じました。談志師匠の「してやったり」という顔が浮かんでくるような「報道」でした。
I:『べらぼう』劇中では、当時の「読売」が登場していますので、2011年11月25日付の読売新聞「編集手帳」から引用します。「◆〈立川雲黒斎家元勝手居士〉。生前に自分で決めた戒名の通り、勝手の限りを尽くしつつ、落語に焦がれ死にした人――そんな気がする」。戒名にルビが振ってあったのが、すごく印象的でしたね。
平賀源内は生きているのか?
I:ところで、また怪しい「何か」が映りましたね。前回、鳥山石燕(演・片岡鶴太郎)が亡くなる直前に現れ、着物の柄などから、もしや平賀源内(演・安田顕)では、とネットでも騒がれました。
A:今回は、仲間だった東作の夢枕に立ったような設定でした。源内はもしかして生きて、娯楽などがことごとく奪われていく松平定信の時代の様子を冷ややかな目で見ているのかもしれないですよ。
I:そうだとしたら、それこそ「遊びをせんとや」の歌が切実に響いてきますね。
●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。
●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。
構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり