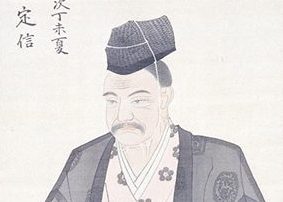ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)第42回です。前回の最後に、松平定信(演・井上祐貴)は「オロシヤの船がやってきた」との報を受けます。場所は蝦夷地のネモロ(根室)。オロシヤに流れ着いた日本人を送り返しに来たというのです。この場面だけみていると、ロシアの使節が突然やってきたという印象も受けたりしますが、実際はどうだったのでしょうか。
編集者A(以下A):『べらぼう』劇中でも『赤蝦夷風説考』という書物が登場していました。この本の著者工藤平助は仙台藩の藩医ですが、元文4年(1739)にロシアの船が仙台湾に入ってきた事件が執筆の動機になっています。この頃、ロシア帝国の船が日本近海にたびたび来航していることは周知の事実ですから、「ついにその時がきたか」という受け止めが正しいのでしょうか。当時のロシア皇帝は女帝のエカテリーナ2世ですが、7代前のピョートル大帝の時代から日本からの漂流民を「教師」とする日本語学校をつくって、虎視眈々と日本に視線を向けていたことが知られています。
I:なるほど。
A:このとき、根室にやってきたのはアダム・ラクスマン。ロシア皇帝エカテリーナ2世の命を受けた正式な使節でした。日本からの漂流民の引き渡しという「大義」を掲げての来航です。このときの漂流民が大黒屋光太夫と磯吉。伊勢国白子(三重県鈴鹿市)の船の船頭で、天明2年(1782)に白子から江戸に向けて出港した際に、荒天に巻き込まれ、7か月間の漂流の後、アリューシャン列島のアムトチカ島にたどり着いたという人物です。
I:大黒屋光太夫は、エカテリーナ2世に謁見しているのですよね。
A:そうです。漂流民を帰還させ、さらにロシアと日本の間で通商を結びたいということだったようです。大黒屋光太夫の聞き書きをまとめた『北槎聞略(ほくさぶんりゃく)』という本が医師で蘭学者である桂川甫周(かつらがわほしゅう)の手でまとめられています。岩波文庫に所収されているので、気軽に読むことができるのですが、漂流の経緯はもちろん、厠(かわや)、浴室などの風俗や、学校、病院、娼家の様子、さらには当時のロシアの年中行事など事細かに語られています。エカテリーナ2世は、歴代のロシア皇帝でもっとも長く在位した皇帝で、最大の版図を領した時代です。その頃のロシアの様子を日本人の視点で記録した貴重な史料です。
I:私も読みましたが、光太夫と磯吉と同じ船に乗っていた乗員の大半が異国の地で命を落していたこと、ロシア正教に改宗して現地で生きることを決意した日本人漂流民がほかにもいたこと、などに衝撃を受けました。
A:漂流の末、救助された漂流民もいたわけですが、そのまま大海のなかで命を落した人々も多かったのだろうと推察します。今回は後半でも漂流民について思いを馳せたいと思います。
I:さて、松平定信は、例によって、「オロシヤの船を江戸に入れるなど断じてならぬ!」とロシア船との交渉に難色を示します。大黒屋光太夫が通訳をするということについても拒絶します。私は、船頭上がりの光太夫に公儀の通訳をさせるのが嫌だったのかな、と思ったりしました。同時に、田沼意次(演・渡辺謙)だったら、どう対処したのだろうとも思いました。
A:歴史に「if」を持ち込むのはタブーなのですが、そこは考えてしまいますよね。
寛政三美人と漂流民
I:さて、劇中では、江戸の看板娘ブームが描かれました。いわゆる「寛政三美人」といわれる女性たちです。茶屋の難波屋、おきたの出す茶は1杯四十八文まで高騰、さらに五十文にまで跳ね上がりました。煎餅の高島屋では、六文の煎餅がおひさ渡しだと百文になり、吉原の見番大黒屋では芸者の豊ひなのご指名が殺到する始末。蔦屋では、商人たちが自分たちの娘を描いてくれと行列する様子が描かれました。
A:現代のアイドル商法もびっくりの様子が描かれたわけです。
I:おきたさんやおひささんなどは「寛政三美人」と称される女性ですが、どんな女性だったんですかね。当たり前の話ですが、喜多川歌麿(演・染谷将太)筆の絵は残っているのですが、写真は残っていないわけです。
A:劇中では寛政5年(1793)頃でしょうか。現状で日本人を撮影した最古の写真が撮影されたのが嘉永3年(1850)頃といわれますから、およそ60年後には、写真が登場するということになります。
I:日本人が撮影された最古の写真は紀州沖で遭難して南鳥島でアメリカの商船に救助された樽廻船栄力丸の乗員の人たちですね! 亀蔵、仙太郎ら5人の船員がサンフランシスコで撮影されたのですよね。
A:漂流してロシアに救助された大黒屋光太夫、漂流してサンフランシスコまでいって写真を撮影された日本人船員。漂流民が日本の国内外の歴史にあらゆる足跡を残しているのは感慨深いですね。
I:そして、「寛政三美人」から100年以上、日本人が初めて撮影されてからでも半世紀以上経過した明治41年(1908)、日本でも初めて写真による「ミス・コンテスト」が開催されます。主催したのは、福沢諭吉が創刊に関与した時事新報社。『全国美人写真審査』として全国から写真を募集したものでした。
A:芸妓など玄人の「美人帖」はそれまでにもあったようですが、一般の人に呼び掛けてのイベントでした。新聞の歴史、「ミスコン」の歴史、双方にとっての歴史的トピックスでしょう。このとき一位に輝いたのが、福岡県小倉市長の娘である末弘ヒロ子14歳。蔦重健在のころに写真が登場していたら、蔦重はどんな企画を考えたのでしょう。そんなことを思わずにはいられません。
I:さて、江戸城では、「これは恐ろしきものにございます。この娘の入れた茶はいっぱい百文、この娘の手渡す煎餅は一枚百二十文! この芸者会いたさに吉原では紙花のまきちらしが始まっておるそうにございます!」と、田沼病が息を吹き返したと幕閣らが松平定信に奉告します。なんだかなあ、という感じですね。

(時事新報社編『日本美人帖』より。国立国会図書館蔵)
●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。
●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。
構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり