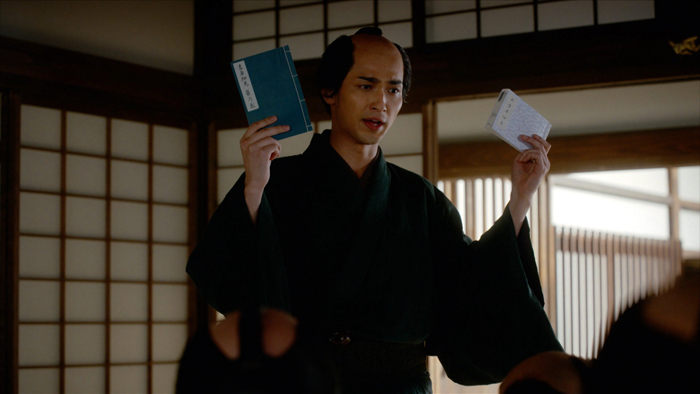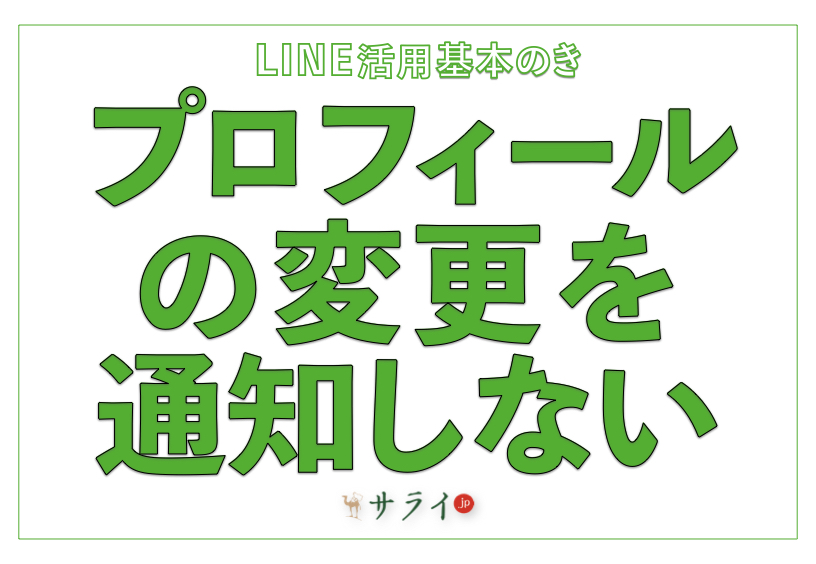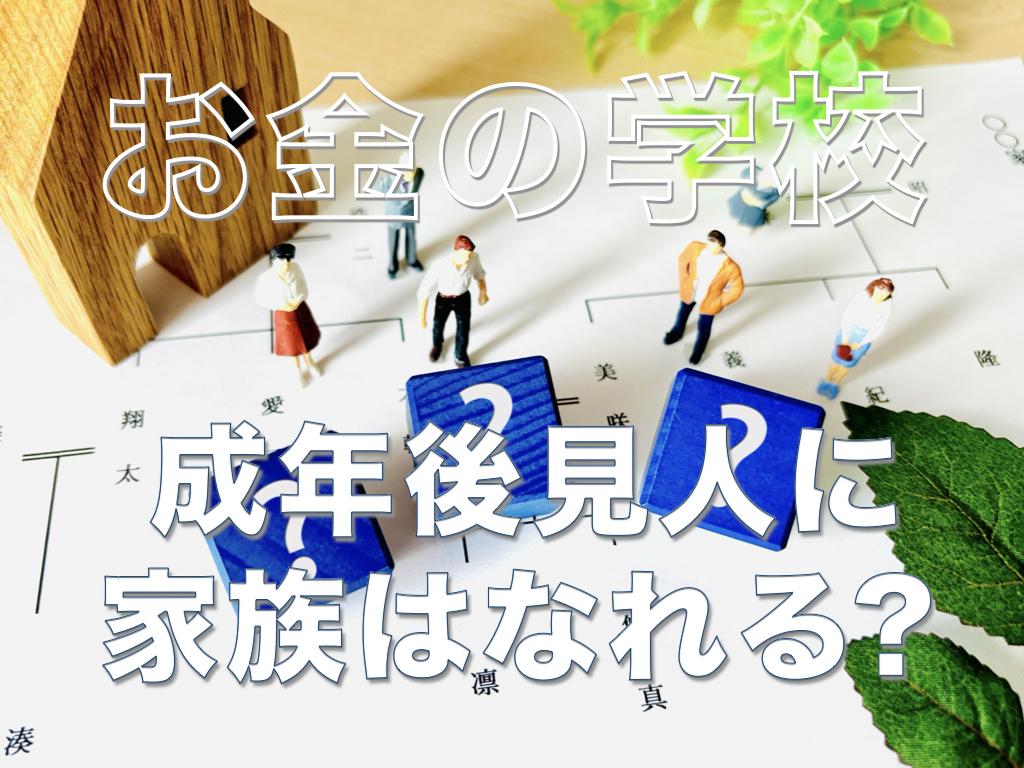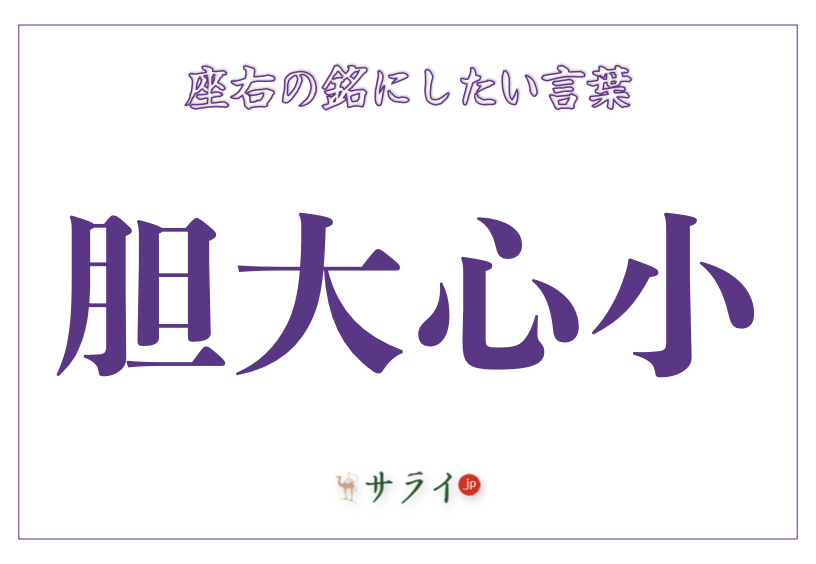ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)第34回では、天明の打ちこわしのその後が描かれました。天明の打ちこわしが起きたのが天明7年、西暦でいうと1787年にあたります。
編集者A(以下A):思えば、天明年間は、浅間山大噴火と噴火に起因する大飢饉、若年寄田沼意知刃傷事件、利根川の洪水、将軍家治の死と激動の日々が続いていました。「漢委奴国王印」で知られる金印が筑前の志賀島で見つかったのも天明4年という説があります。天明の打ちこわしは、浅間山大噴火→北日本を中心に大飢饉→江戸でも米不足という流れの中で発生した「民衆の決起」になります。『初めての大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺」歴史おもしろBOOK』(小学館)でも蔦重の時代と英国、米国、フランス、中国などの歴史を比較したページがありましたが、フランスでは天明の打ちこわしの2年後にバスティーユ監獄襲撃事件が勃発して、フランス革命へと突き進みます。
I:『べらぼう』の劇中では、新之助(演・井之脇海)が幟に檄文をかいていました。一橋治済(演・生田斗真)が市井の貧しい男に扮して、「米ではなく犬を食えというのか」と役人を罵倒する役割を担いました。その声をきっかけにして庶民が熱くなり、打ちこわしが激しさをました様が描かれました。
A:「犬を食え」で想起されるのは、昭和25年に当時の池田勇人大蔵大臣が「貧乏人は麦を食え」と発したとされますが、実はそのフレーズは新聞の見出しで、池田蔵相はそこまでひどい発言はしていなかったともいわれています。『べらぼう』劇中の「犬を食え」と同じで「扇動」って怖いなと思います。
I:「犬を食え」というフレーズは、町奉行の曲淵景漸という人物が発したとされる「米がなければ犬を捕まえて食べれば良い」との放言に庶民が怒り、打ちこわしに発展したという言説にヒントを得た演出だと思われます。
蔦重とていの胸打つやり取り

I:さて、今週はてい(演・橋本愛)と蔦重(演・横浜流星)とのやり取りがひときわ印象に残りました。世情は、「吉宗公の孫」である新老中松平定信(演・井上祐貴)を持ち上げるのに必死です。
A:読売配りや、そのほか定信のよい噂を流布する役割の人間も市井に放たれているという感じでした。中世とは異なり、民衆文化が成熟してきて、「世論」をまったく無視することができなくなっている世の中になっていることをよく表現してくれているという印象です。こうしたことは手を変え品を変え、現代でも行なわれているとみていいでしょう。
I:現代でいうと、SNSの普及で発信元の背景についてもしっかり吟味しなければならないのと似たようなものかもしれませんね。
A:「吉宗公の孫」という貴種性が喜ばれるに違いないということなのでしょうが、それから200年以上経過した現代でもそんなに変わらないのが不思議なところです。評論家の八幡和郎さんが『日本の政治「解体新書」:世襲・反日・宗教・利権、与野党のアキレス腱』(小学館新書)で指摘していますので、ざっくりと説明すると、日本の政界は平成の宮澤喜一首相が、官僚出身ながら父の宮澤裕が衆院議員だった二世議員でしたが、橋本龍太郎氏以降の自民党の首相のほとんどが世襲議員で占められているのです。しかも首相になる近道は、「父が早死にして若くして議席を得ること」というのです。
I:次期首相と人気を集める人の中にも世襲議員は多いですからね。
A:それはさておき、私の中での今回の一番のトピックは、渡辺謙さん演じる田沼意次が最後の登場となったことです。
I:蔦重とのやり取りが骨身にしみました。「皆が欲まみれでいいかげん。吉原の引手茶屋の拾い子が日本橋の本屋になれるような」という蔦重に対して、意次は「俺もお前と同じ成りあがり」と言をつなぎます。
A:あきらかに時代の空気を演出したのは田沼意次であるということが強調される場面になりました。成りあがりといえば、来年の大河ドラマ『豊臣兄弟!』に登場する豊臣秀吉も日本史上最大級の「成りあがり」。
I:さらに成りあがりといえば、昭和の大ベストセラー矢沢永吉さんの『矢沢永吉激論集 成りあがり』が思い出されます。1978年刊行の本ですが、私はずいぶんあとになって文庫版を読んだ記憶があります。
A:誰にも「成りあがれる」チャンスがあるという時代は、やはり歴史的にも「熱い」ですね。
I:今は、志ある人が「成りあがれる」時代なのでしょうか。蔦重と意次のやり取りをみて、そんなことを思いました。松平定信は、「悪の田沼政権」という印象操作を徹底します。なんか、そんな流れはイヤですね。
A:土山宗次郎(演・栁俊太郎)の斬首なんて、なぜここまで? という思いもします。公金を横領したとも伝えられますが、本当でしょうか。そして、意次への仕打ちがひどすぎます。相良城破却などその最たる例です。そこまでひどいことしましたか? 『初めての大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」歴史おもしろBOOK』の取材で相良城跡にも足を運びました。きっかけは同書にも掲載されている渡辺謙さんのインタビュー記事です。
渡辺謙さんの話を聞いて、いてもたってもいられずに静岡駅からバスで約1時間の相良城跡に足を運びました。
I:地元の学芸員の方にお話を聞いたのですよね。
A:はい。「田沼=悪」のレッテルをはられて地元でも人気がなかったそうです。新たな研究成果などで、徐々に復権へ向けた動きが出てきたそうです。城跡に田沼意次の銅像ができたのは、なんと令和になってから。復権に200年の歳月がかかったのです。
I:松平定信のネガティブキャンペーン恐るべしです。『べらぼう』を機に、そのあたりの研究が深化していけばいいですね。

【新たな政権の顔ぶれ。次ページに続きます】