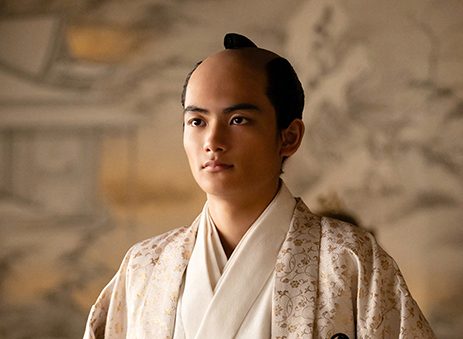53人の子どもをもうけた家斉。第一子は?
I:家斉政権が始動したわけですが、さっそく側室に子をもうけたことが紹介されました。
A:劇中で紹介されたのは、後に尾張藩主徳川斉朝に嫁ぐ淑姫のことですかね?
I:家斉は、自分のことを「子作りには長けている」ようなことをいっていましたが、側室ってどういう状況で選ばれていたんでしょうね。大奥のことがドラマになるといつもそう思います。
A:「将軍の側室になりたい」という願望はいかばかりだったのでしょうか。競争は激しかったのでしょうか。ちょっと振り返ると、第3代将軍徳川家光は、側室「お楽の方(後の宝樹院)」に第4代将軍徳川家綱、側室「お玉(後の桂昌院)」に第5代将軍徳川綱吉を生ませています。家光の時代は余裕があったのかどうかはわかりませんが、将軍生母になった側室の実家が大名に取り立てられます。
I:これが不思議なんですよね。お楽の方は、もともと下野国の農民の出と伝わります。父母の代に縁あって江戸に出て、お楽の方が少女のころに、母の再嫁先の商家で下働きをしていたところにたまたま訪れていた春日局の目に留まり大奥に召されたという異色の経歴の持ち主です。まるで「江戸のシンデレラ」のようなお話ですが、おそらく家光の好みを知っていた春日局が厳選したのでしょう。お楽の方に家光の手がつき、後の第4代将軍家綱が誕生するわけです。
A:ほかの将軍の際にはこんなことはなかったのですが、お楽の方の実弟増山正利は大名に取り立てられます。当初は1万石でしたが、後に伊勢長島藩2万石となり、幕末まで続きます。同じように、家光の側室「お玉」は、『徳川実紀』による「公式見解」では京都の公家の家臣の娘ということになっていますが、八百屋の娘という説も有力です。彼女も縁あって大奥に上がって、将軍家光のお手がつき、第5代将軍綱吉の生母として権勢を得ます。
I:桂昌院の実弟本庄宗資もまた、大名に取り立てられ、宗資の息子の代には7万石にまで加増されるという異例の厚遇を受けるのですよね。なんかびっくりです。
A:家光にはもうひとり綱重という男子がいますが、元は京都の町人だったという綱重生母の実家藤枝家は、大名にこそなりませんでしたが、4500石の大身旗本に立身します。藤枝家は蔦重の時代に改易されるのですが、その理由が、吉原の女郎と駆け落ちし、居場所を突き止められた末に心中したというのです。
I:『べらぼう』劇中でも新之助(演・井之脇海)とうつせみ(ふく/演・小野花梨)の足抜けが描かれましたが、大身旗本でもうまくいかないのが足抜けということなんですね。
A:さて、脱線してしまいましたが、ここでいいたかったのは、家光の時代は、将軍生母や男子を生んだ側室は実家ごと立身できたわけです。後の時代にも第9代将軍徳川家重の生母お須磨は実家の弟が5000石の旗本に取り立てられます。
I:お須磨の方は、1995年の大河ドラマ『八代将軍吉宗』では賀来千香子さんが演じていましたね。さすがに家斉の時代にはそういうわけにはいかなかったのでしょうが、期待はしますよね。将軍の子を身ごもったら、少なくとも実家が大身旗本になれるかもって。
A:いったい、家斉の子作り、どこまで描かれるのでしょうか!?

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。
●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。
構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり