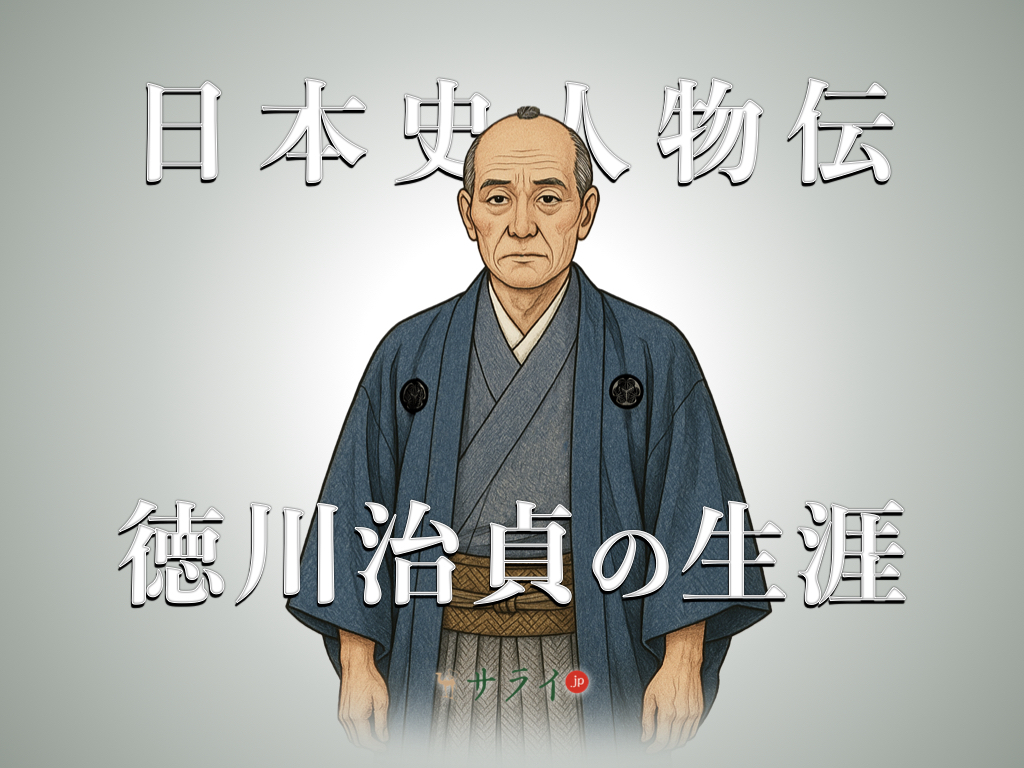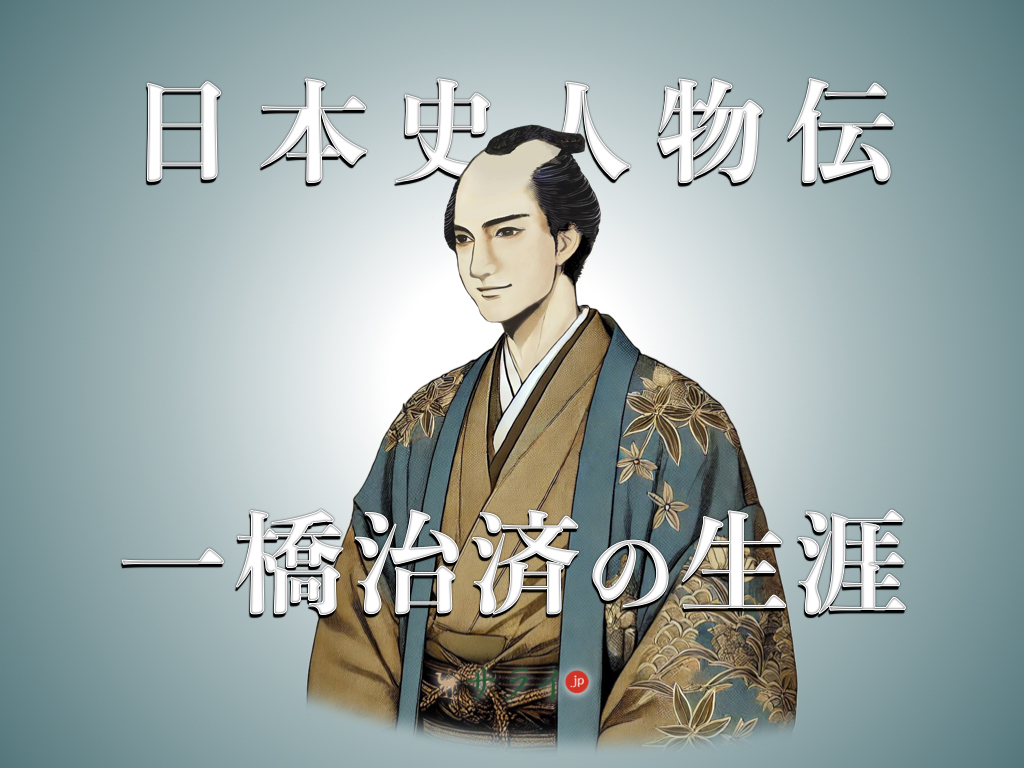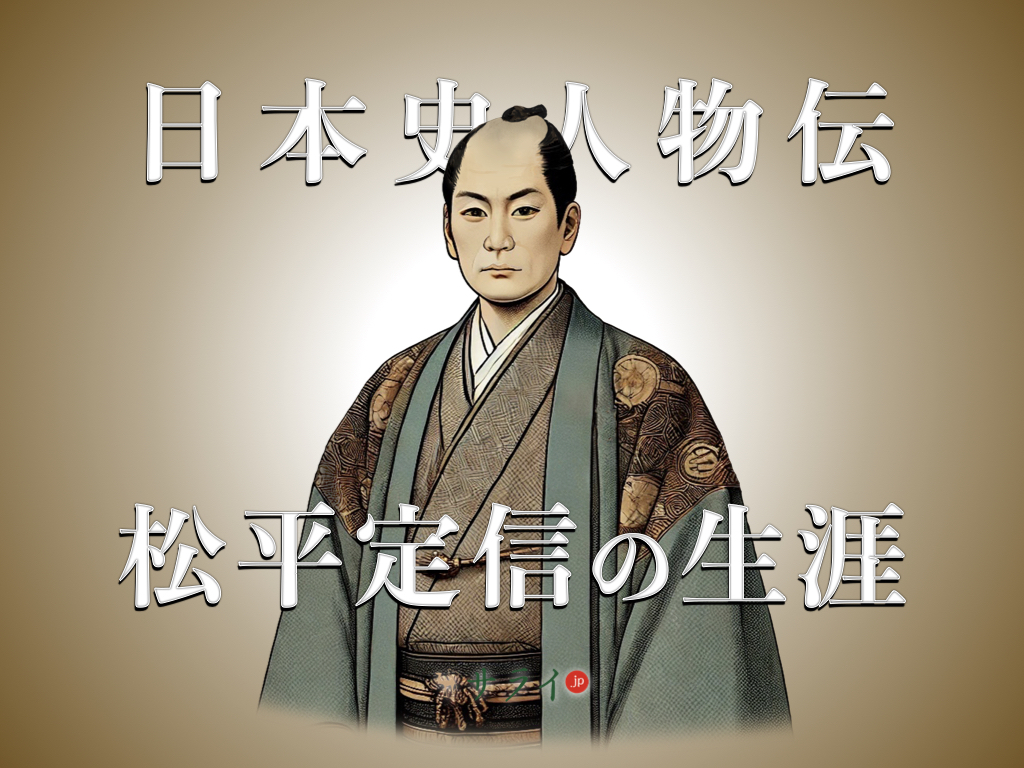はじめに-徳川家斉とはどんな人物だったのか?
江戸幕府第11代将軍・徳川家斉(とくがわ・いえなり)。わずか15歳で将軍となり、隠居後も実権を握り続けたその治世は、なんと約50年におよび、歴代将軍中で最も長いものとなりました。
その一方で、豪奢な生活ぶりや、側近政治による腐敗など、家斉の時代には江戸幕府の緊張が緩み、支配体制のほころびが目立ち始めます。文化文政期の華やかな町人文化の影で、何が起こっていたのでしょうか?
徳川家斉について、史実をベースに紐解いていきます。
2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、老中・松平定信とともに、財政再建や風紀の改善に取り組むが、時代の変化や内外の事情を背景に、次第に政務への姿勢に変化が現れていく人物(演:城桧吏)として描かれます。

徳川家斉が生きた時代
徳川家斉が将軍に就任したのは天明7年(1787)。天明の飢饉により社会不安が高まる中、10代将軍・家治の死を受けて、わずか15歳の若さで第11代将軍に就任しました。
以後、寛政の改革から大御所政治に至るまで、約50年にわたる政権を握り続けた家斉の治世は、江戸時代の後期にあたります。
この時代は、文化・文政(1804〜1830)期に象徴される町人文化が花開き、表面的には平穏に見えましたが、貨幣経済のひずみ、農村の疲弊、外国船の接近といった危機がじわじわと迫っていました。
徳川家斉の足跡と主な出来事
徳川家斉は、安永2年(1773)に生まれ、天保12年(1841)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。
一橋治済の子として誕生、10代将軍・家治の養子に
徳川家斉は、安永2年(1773)10月5日に御三卿(ごさんきょう)の一つ、一橋治済(ひとつばし・はるさだ)と母・於富之方 (おふくのかた、岩本氏)の長男として生まれました(※四男とする説もあり)。幼名は豊千代です。
天明元年(1781)に10代将軍・徳川家治(いえはる)の養子となって西の丸に移り、「家斉」と名乗ります。翌年、元服しました。

15歳で江戸幕府第11代将軍となる
天明7年(1787)、前将軍・家治の死去を受けて、15歳の若さで徳川家斉が第11代将軍に就任しました。前代から重用されていた田沼意次(たぬま・おきつぐ)を排し、父である一橋治済や、白河藩主・松平定信を老中首座に登用して政務を主導します。
寛政元年(1789)2月には、近衛経煕(このえ・つねひろ)の養女で、島津重豪(しまづ・しげひで)の娘である茂姫と婚姻しています。
定信は、家斉の後見役として「寛政の改革」を断行し、農村復興、文武奨励、倹約令、風紀の引き締め、異学の禁止などを通じて幕政の立て直しを図りました。しかし、風俗・出版・思想への過度な統制は、幕府内部に不満を蓄積させていきます。
やがて、光格天皇が実父・典仁(すけひと)親王に太上天皇の尊号を贈ろうとした「尊号事件」、さらに家斉が父・治済に「大御所」の称号を与えようとした「大御所事件」が発生。これらを契機に、大奥や朝廷との対立が表面化し、寛政5年(1793)に定信は老中職を辞任することとなりました。

【「大御所政治」の時代へ。次ページに続きます】