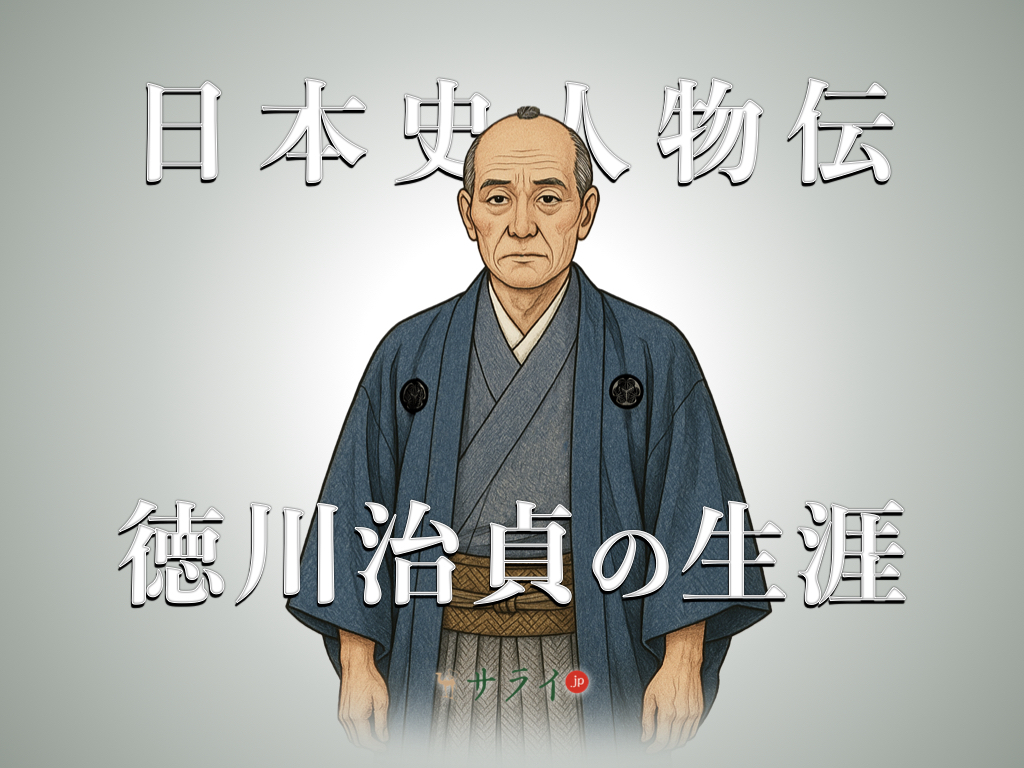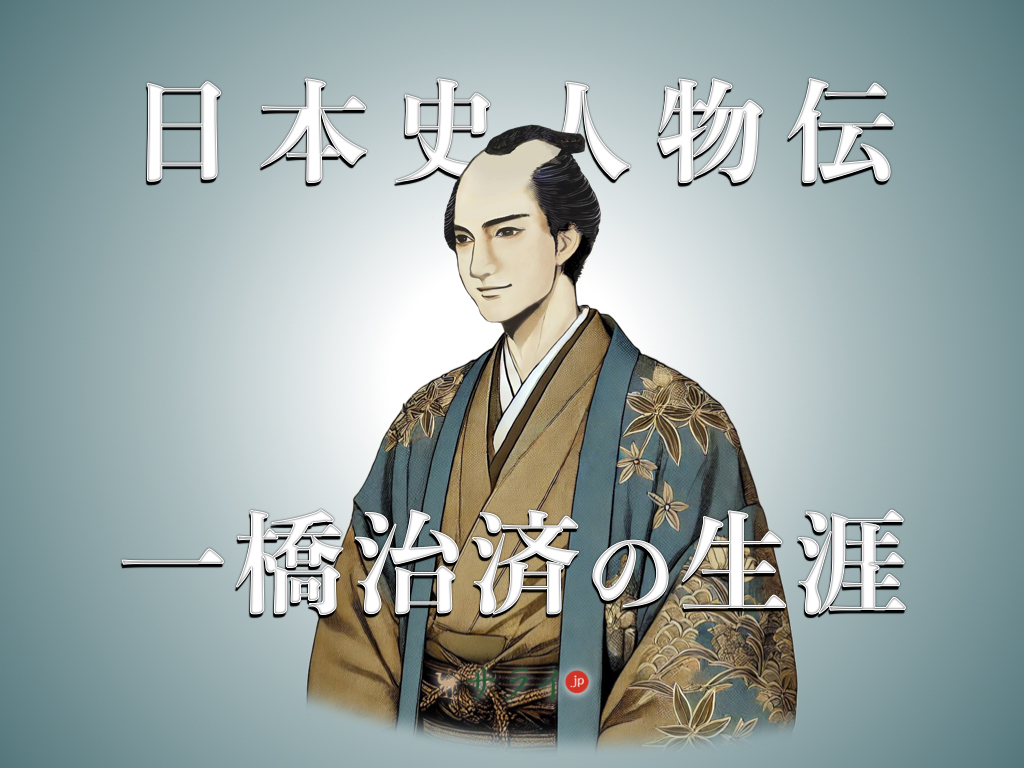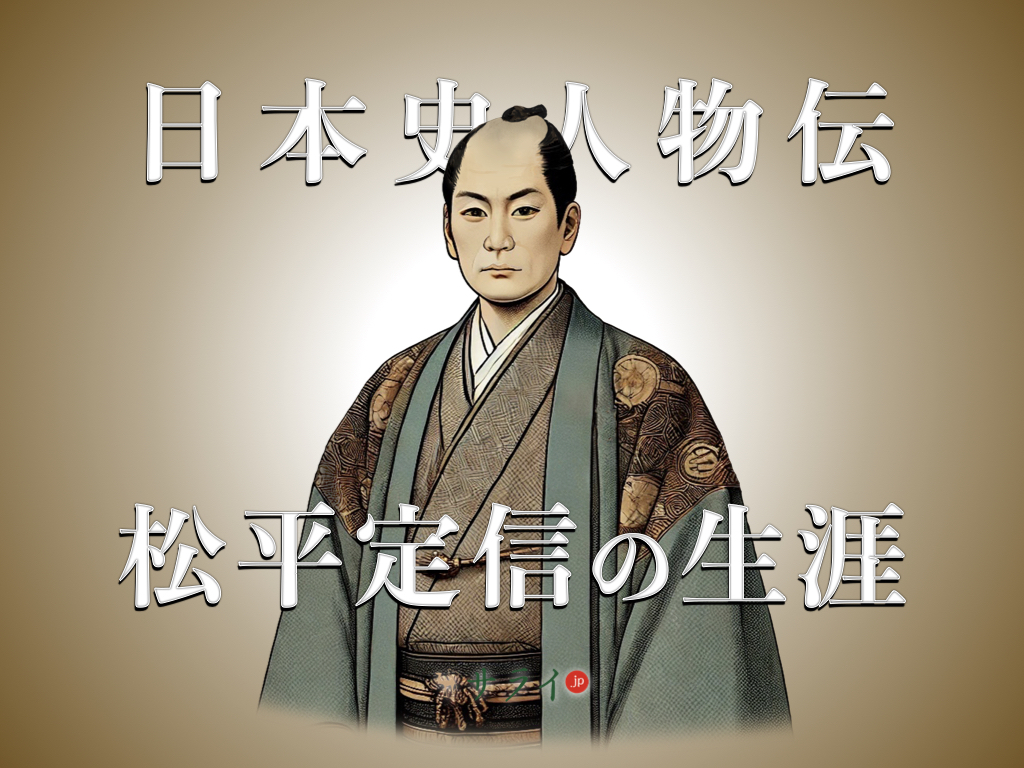「大御所政治」の時代へ
松平定信の退任後、将軍・家斉は政務における実権を徐々に強めていきます。それに伴い、再び田沼派の側用人たちが台頭。幕政を私物化していきます。特に文政期(1818〜1830)以降は、大奥の華美な生活を象徴とするように、幕政は次第に弛緩していきました。
家斉の側室は40人とされ、そのうち16人が子を出産。正室と合わせて計17人の女性から55人の子女が生まれたと伝えられます。これは、家斉の大奥における性生活の奔放さを象徴する逸話でもあり、幕政の中心が私的空間である大奥と一体化していたことを示しています。
このような状況から、家斉の治世後半は「大御所時代」とも呼ばれ、賄賂が横行する腐敗政治の時代でもありました。
こうした政治の緩みの裏で、町人文化が花開き、いわゆる化政文化が隆盛を迎えました。江戸を中心に文芸・美術・学問が大きく発展し、庶民の文化が成熟を見せた時代でもあります。
内憂外患、無策の代償
家斉が将軍職を子の家慶(いえよし)に譲ったのは天保8年(1837)のこと。しかし、隠居後も「大御所」として政権を握り続けます。
同年には大塩平八郎の乱が発生。天保の飢饉による百姓一揆や打ちこわしも多発し、国内は混乱を極めました。
また、ロシア・イギリスなど外国船の接近やアヘン戦争の勃発など、外交的な危機も押し寄せていましたが、家斉政権は抜本的な対策を打てず、幕府の信頼と威信は大きく揺らぎました。
しかし、家斉はそうしたことには無関心を貫いたまま、天保12年(1841)に69歳で長逝したのです。
まとめ
徳川家斉の治世は、約50年に及ぶ「最長政権」として、江戸幕府の中でひときわ異彩を放っています。若き将軍として始まった寛政の改革には引き締めの気概がありましたが、大御所時代には腐敗と贅沢が幕政を蝕みました。
表面的には平和だったものの、民衆の不満、政治の弛緩、対外的な危機が積み重なり、のちの天保の改革や幕末の動乱へとつながっていきます。
家斉の時代は、江戸幕府の転換点ともいえる存在だったのです。
※表記の年代と出来事には、諸説あります。
文/菅原喜子(京都メディアライン)
肖像画/もぱ(京都メディアライン)
HP: http://kyotomedialine.com FB
引用・参考図書/
『日本大百科全書』(小学館)
『世界大百科事典』(平凡社)
『日本人名大辞典』(講談社)
『国史大辞典』(吉川弘文館)