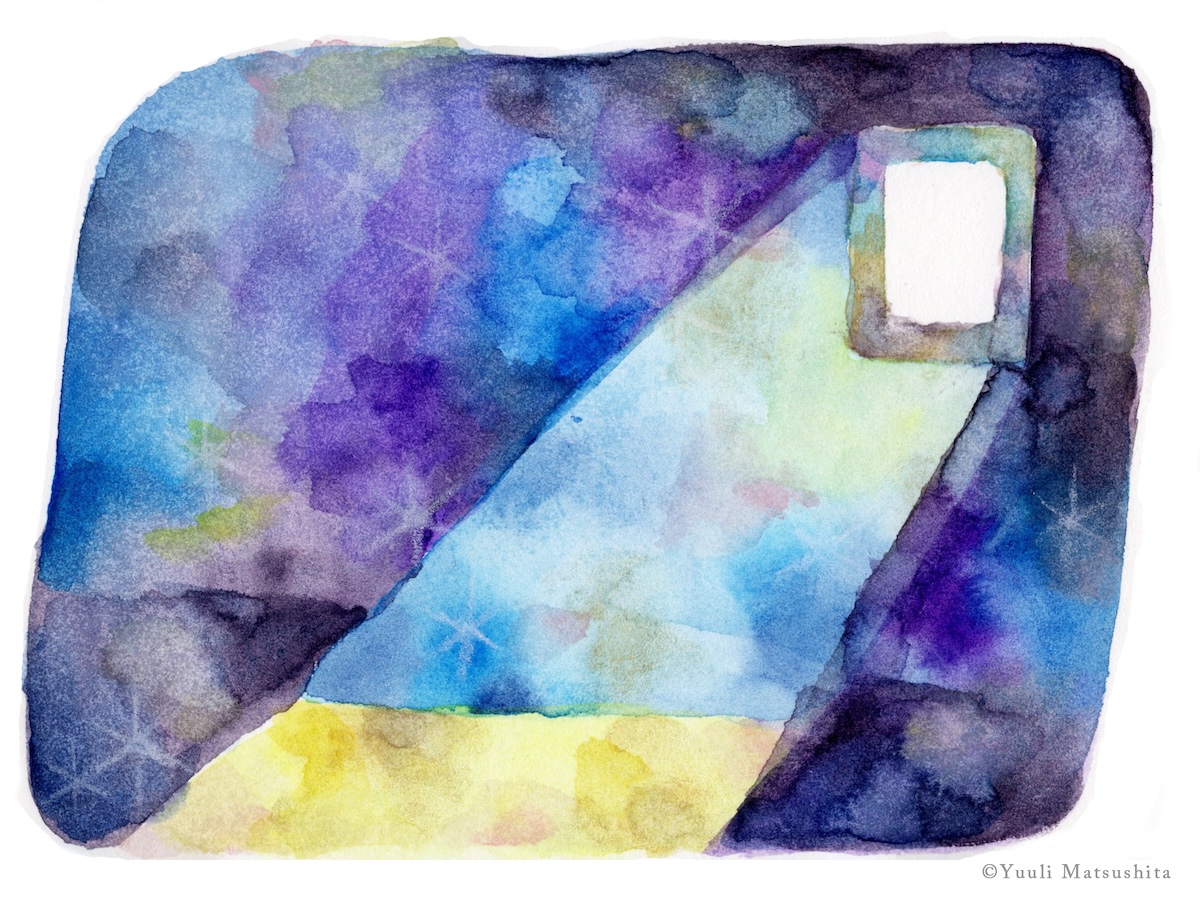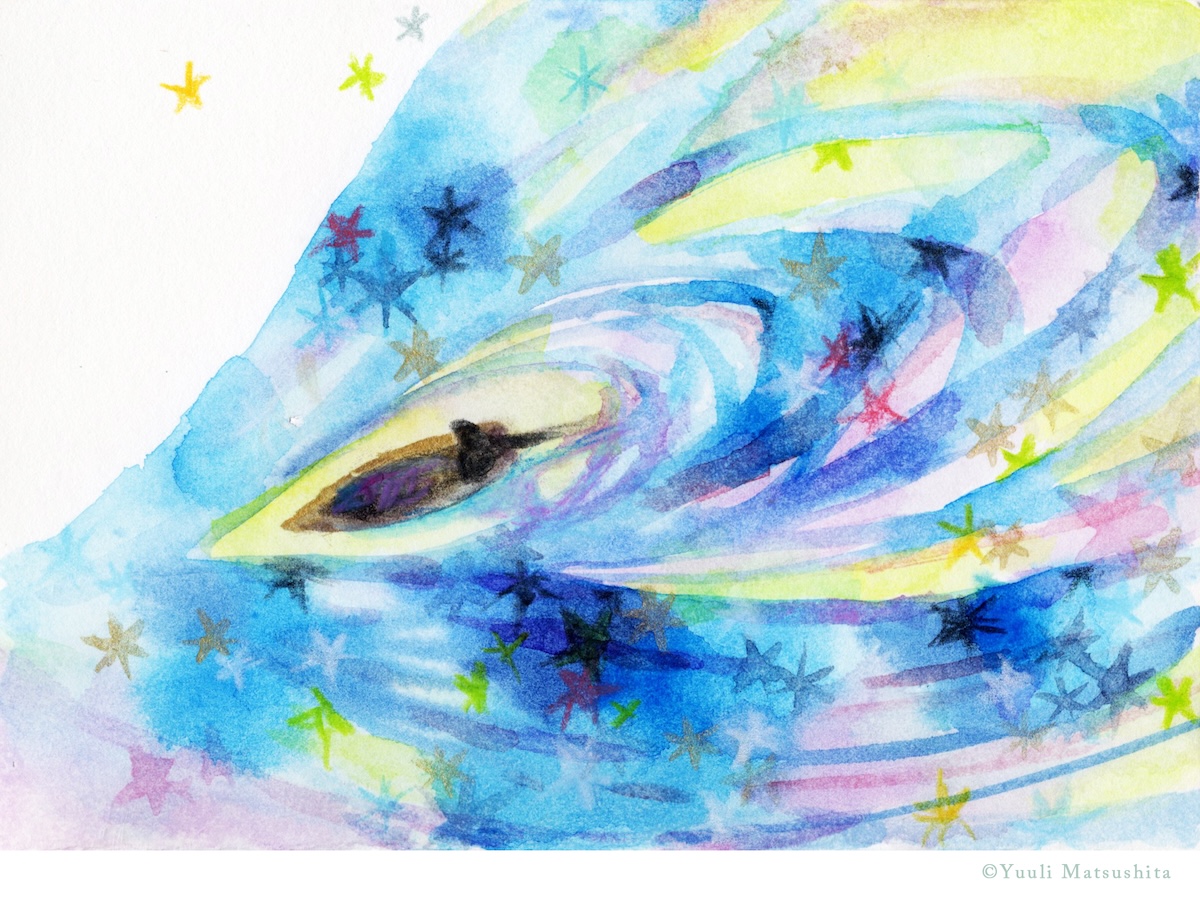草の葉に朝露が宿り始める頃になると、秋の気配がほんのりと感じられる、「白露(はくろ)」を迎えます。日中はまだ夏の名残がありながらも、朝晩には涼しさが訪れ、秋の足音が近づいてきます。
2025年の白露は9月7日(日)に始まり、約15日間続きます。その間に訪れる自然の変化や風習を知ることで、忙しい日常に「季節の彩り」を取り入れてみませんか? 和歌や行事、食などを通じて日本の暦文化を味わいましょう。
さて今回は、旧暦の第15番目の節気「白露」について下鴨神社京都学問所研究員である新木直安氏に紐解いていただきました。
白露とは?
「白露」という言葉は、露が凝って白く見える様子に由来します。古くは、秋の「陰気」が夏の「陽気」に交じり合う季節の交替点とされ、白露がその目印となっていました。野に咲く花に宿る露、耳に届く虫の音……ささやかな自然のサインが、確かな季節の移ろいを教えてくれます。
2025年の白露は【9月7日(日)】にあたり、次の節気「秋分(9月23日)」まで続きます。今年の夏は、気象庁が「130年近い観測史上の中でも異常」と指摘するほどの猛暑でした。だからこそ、朝晩に吹く風の涼しさや、草木に光る露の美しさに、例年よりも深く季節の移ろいを感じられるかもしれません。
参考:『日本大百科全書』(小学館)
七十二候で感じる白露の息吹
「白露」は二十四節気の第15番目で、例年9月8日〜9月22日ごろ。七十二候では以下のように分けられます。
■初候(9月8日〜9月12日頃)…草露白(くさのつゆしろし)
草に降りた朝露が白く輝くころ。朝夕の涼しさが際立ってきます。
■次候(9月13日〜9月17日頃)…鶺鴒鳴(せきれいなく)
鶺鴒(せきれい)という鳥が鳴き始めるころ。『日本書紀』にも登場する、秋を告げる鳥です。
■末候(9月18日〜9月22日頃)…玄鳥去(つばめさる)
春に渡ってきたツバメたちが、越冬地の南方へと帰っていくころ。
七十二候は動植物の変化を繊細にとらえた暦。白露の頃は、夏から秋への静かな移ろいを知らせてくれます。
白露を感じる和歌|言葉に映る処暑の情景
まだまだ暑いと思いつつも、この時期から夜が少しひやっとし始めてもいるかと思います。皆様こんにちは、絵本作家のまつしたゆうりです。 今月ご紹介するのは、秋といえば思い出すこの歌!
秋の野に 咲ける秋萩 秋風に 靡(なび)ける上に 秋の露置けり
(大伴家持『万葉集』1597)
《訳》秋の野原に咲いた秋萩が、秋風に靡いてるところに秋の露が置いているなあ
《詠み人》この歌は、『万葉集』を編纂したと言われている大伴家持(おおとものやかもち)が詠んだ歌です。貴族で歌人でもある彼は、心の機微を自然に喩えた歌をたくさん残しています。

「秋って言い過ぎじゃない?!」と思わずツッコミたくなりません!? 私は初めて読んだ時に噴き出してしまいました。他にこんな詠み方をしている人なんていない、ちょっと変わったこの歌は、どうやら当時流行っていた中国の漢詩に影響を受けているのだそう。漢詩は韻を踏んだ表現が美しいとされ、こうやって四季のいずれかの景物を並べて、褒め称えるような作品もあったりします。
なのできっと「唐の流行のスタイルを、日本の歌でもやってみた!」ということなのでしょう。でもこれ……スベってません? 私は完全にスベってると思うんですよ。いや、新しいことに挑戦している姿勢はすごくいいなと思うのですが、正直「秋、秋」言っている印象しか残らなくて、歌の内容や情景が全く頭に入ってこない。心に感情が1ミリも響いてこない。まさに「技におぼれる」という言葉が思い浮かんでしまう案件なんだと思うんです。
でもこういうことって、身近にありません? 例えば、絵を学んだりして、ちょっと技を知った頃なんかに、やたらとそれを使いたくなる。「こんなこと出来るんだぜ?」と自慢して、披露したくなる。けれどそんな「ドヤ感」が鼻につく作品になってしまっている……なんて経験、誰でもひとつふたつは思い浮かぶはず。
そんな思い出すだけで恥ずかしくなるような黒歴史。でもそんなエピソードを知った方が、その人物に親近感のようなものや、親しみやすさを感じたりすると思うのです。有名人の失敗エピソードも、「こんな凄い人に見える方にも、私と似たような経験あるんだ」知るだけで、そのヘッポコを知ったことで応援したくなる。
この歌も、私にとって「『万葉集』を編纂したとされる凄い人、大伴家持」から、「ヘンテコな歌をドヤって作るちょっとイタイ家持、改め『やかもっちゃん』→『もっちゃん』」へと認識が変化した歌なんです。
人は人のヘッポコを見て笑ったり馬鹿にしたりもするけれど、そこを可愛がったり愛しく思ったりもする。そう思うと、自分のヘッポコを出すことにも少しハードルが下がりませんか?
自分のヘッポコを出して誰かに愛された時、自分も自分のヘッポコを愛せるようになる。そうすると、他人のヘッポコも愛せるようになる。 そうやって、「吊るし合い」ではなく「ゆるし合い」の世界になればいいのになと願うこの頃。
大きな話に思えるかもしれませんが、「世界平和」の第一歩として「自分のヘッポコを出していく」、ぜひやってみませんか。私は全力で皆さまのヘッポコ出しを応援しております!
(「白露を感じる和歌」文/まつしたゆうり)
白露に行われる行事|秋を迎えるしつらえと祈りの時間
白露の時期には、秋の深まりとともに季節の節目を祝う行事がいくつか重なります。自然への感謝や、祖先・年長者を敬う心が大切にされてきたこの季節。日々の暮らしのなかに、古来の行事を取り入れてみることで、より豊かな秋の始まりを感じられるでしょう。
重陽の節句(ちょうようのせっく)
旧暦9月9日にあたる重陽の節句は、「陽」の数字である奇数「九」が重なることから、五節句の中でも最も縁起のいい日とされてきました。現在では新暦で祝われ、9月9日前後に各地で関連行事が行われます。
平安時代には宮中で、菊を愛でながら詩歌を詠んだり、菊花を浮かべた「菊酒(きくざけ)」を酌み交わしたりと、風雅な催しが行われていました。また、菊の花に真綿をかぶせて露を含ませ、身体を清める「被せ綿(きせわた)」の風習もありました。
さらに遡れば、この時期は収穫を祝う「栗の節句」とも呼ばれ、栗ご飯などを供えて自然の恵みに感謝したとも伝えられています。長寿と実りを祝う、豊かな秋の節句です。

敬老の日
白露の期間中には、長寿と人生の歩みに敬意を表す「敬老の日」もやってきます。平成15年(2003)からは9月の第3月曜日と定められ、2025年は9月15日(月・祝)にあたります。
敬老の日の由来は諸説ありますが、昭和22年(1947)9月15日に兵庫県のある村で「敬老会」を開催したのが始まりであるとされています。この会の活動の輪が広がりを見せ、発足から約20年後には、現在のように国民の祝日となったのでした。
贈り物や手紙、会いに行くなど、かたちにとらわれない「思いやり」が喜ばれる日。秋の空のもと、穏やかな時間を分かち合えるよき機会です。
白露に見頃を迎える花|秋の風情を映す草花たち
露に濡れる草花の姿は、白露の名にふさわしい風情を醸し出します。
芒(すすき)
白露は、秋の風情を感じさせる「秋の七草」が咲き始める季節になります。その内の一つが、芒です。芒の花穂はふわふわしており、種子に生えている白い毛のため、全体的に白く見えます。花期は7~8月ですが花を観賞するのではなく、秋に花穂を眺めることがほとんどです。

秋海棠(しゅうかいどう)
「秋」の名を冠する花のひとつ、秋海棠。その名は、花姿が春に咲く海棠(かいどう)に似ており、秋に花開くことから名付けられました。
大きな葉が目を引き、淡紅色の可憐な花が風に揺れる姿は、どこか儚く、秋の訪れをそっと告げるようです。涼やかな日陰にひっそりと咲く様子には、ひとしれぬ美しさと風情が漂います。古くから詩歌にも詠まれ、しっとりとした秋の庭にふさわしい風雅な花です。

白露の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む
秋の入り口である白露には、体調を整える旬の食材が多く登場します。
魚|太刀魚(たちうお)
白露の頃に旬を迎える魚は、太刀魚です。鱗がなく、ピカピカした光沢が特徴的な太刀魚は、夏から秋にかけて産卵期を迎えます。「たちうお」という名は、姿かたちが「太刀」に似ていることからその名前がついたとも、狩りの際に立って泳ぐ様子を指して「立ち魚」としたともいわれています。
クセが少なくどんな料理にも合わせやすい白身魚ですので、召し上がる際にはシンプルな塩焼きに加え、ソテーやムニエル、または竜田揚げなどにするのもおすすめです。
野菜・果物|秋茄子(あきなす)
白露に旬を迎える野菜は、茄子(なす)です。晩夏でもあり初秋でもある9月に収穫される茄子は、「秋茄子」と呼ばれます。実も締まり、種が少なく、美味しいのが特徴。また、秋茄子といえば「秋茄子は嫁に食わすな」ということわざが有名です。解釈は様々ですが、いずれも秋茄子が美味しいことを表しているといわれています。
京菓子|着せ綿(きせわた)

(写真提供/宝泉堂)
重陽の節句にちなんだ「着せ綿」は、は菊の花に綿を載せて露を集め、その綿で身を拭うと長寿になるという故事にちなんだものです。長寿や無病息災を祈る願いが込められています。
まとめ
朝晩に空気が冷やされ、草木に露が光る「白露」。朝の光にきらきらと輝く露の美しさが、その名前からも伝わってきます。秋の和歌、秋海棠、秋の七草、秋茄子など、秋を冠するものに触れ、季節の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。
●「和歌」部分執筆・絵/まつしたゆうり

絵本作家、イラストレーター。「心が旅する扉を描く」をテーマに柔らかで色彩豊かな作品を作る。共著『よみたい万葉集』(2015年/西日本出版社)、絵本『シマフクロウのかみさまがうたったはなし』(2014年/(公財)アイヌ文化財団)など。WEBサイト:https://www.yuuli.net/ インスタグラム:https://www.instagram.com/yuuli_official/
監修/新木直安(下鴨神社京都学問所研究員) HP:https://www.shimogamo-jinja.or.jp
協力/宝泉堂 古田三哉子 HP:https://housendo.com
インスタグラム:https://instagram.com/housendo.kyoto
構成/菅原喜子(京都メディアライン)HP:https://kyotomedialine.com Facebook