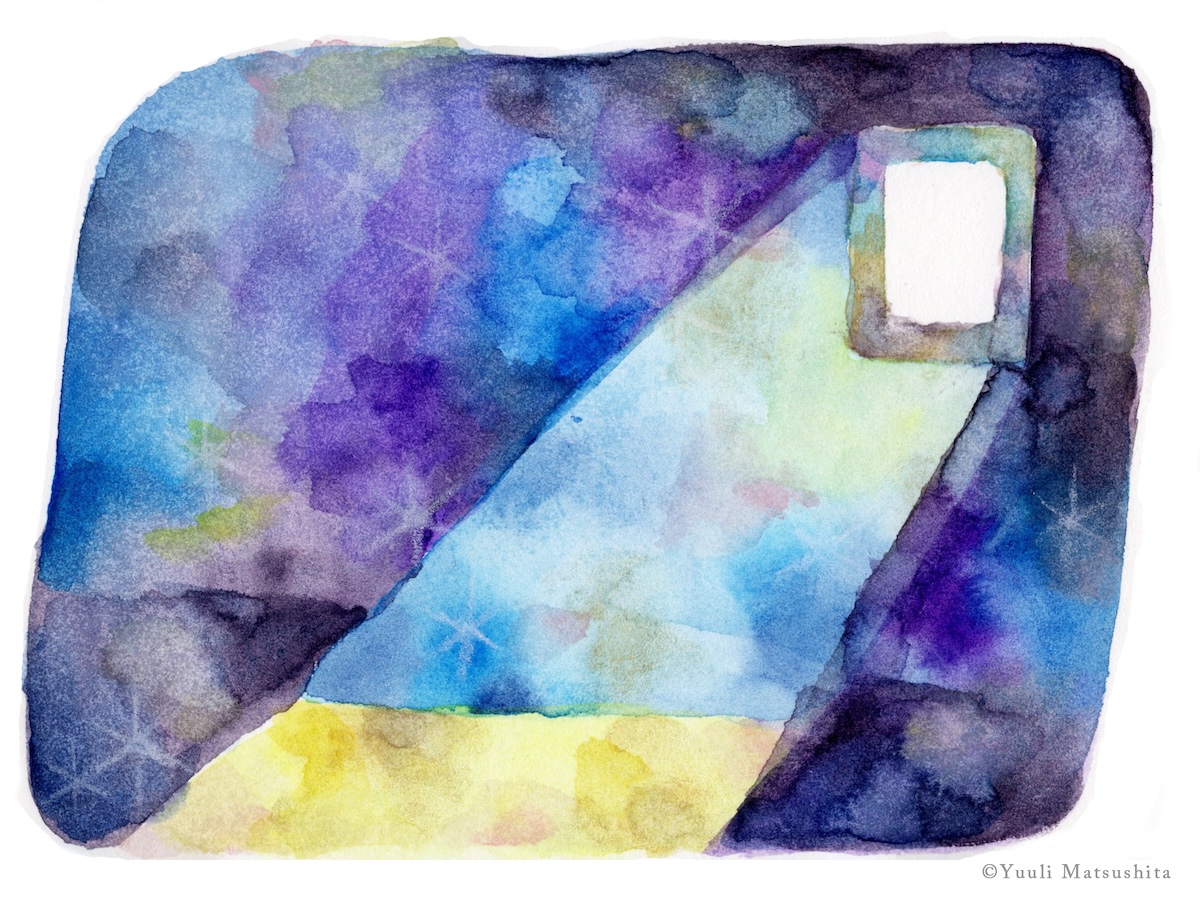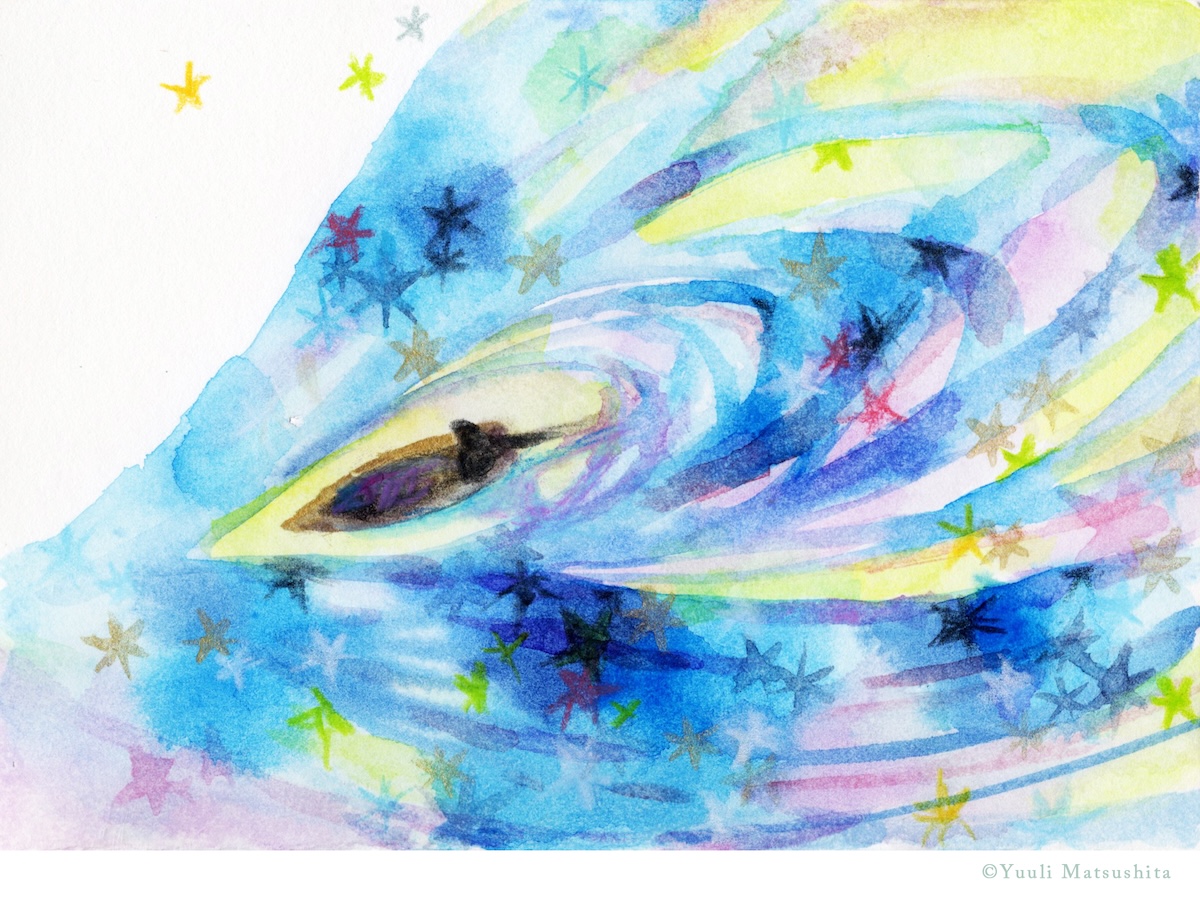新緑がいよいよ勢いを増し、木々の葉が陽射しにきらめく季節がやってきました。風には若葉の香りが混じり、身も心も軽やかに感じられる時期です。こうした自然の変化に気づく心を忘れずにいたいものです。
古来、日本人は自然の微細な変化を敏感にとらえ、一年を二十四節気・七十二候という暦で表現してきました。暦は、単なる日付ではなく「自然と寄り添って暮らす」ための知恵といえるでしょう。
今回は、そんな暦の中から旧暦の7番目の節気「立夏(りっか)」をご紹介します。
目次
立夏とは?|夏の兆しを知らせる節目
立夏を感じる和歌|言葉に映る立夏の情景
立夏に行われる行事|子どもの健やかな成長を願って
立夏に見頃を迎える花
立夏の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む
まとめ
立夏とは?|夏の兆しを知らせる節目
立夏は、春が終わり夏が始まることを告げる節気です。立春・立夏・立秋・立冬を総称して「四立(よんりつ)」と呼び、いずれも季節の節目とされています。
「立」は「始まり」の意味をもち、立夏から立秋の前日までが暦のうえでの「夏」となります。2025年の立夏は【5月5日】。この日を境に季節の区切りが変わるのです。
立夏の頃には、空気が一層澄み、薫風(くんぷう)と呼ばれるさわやかな風が吹き始めます。昼の長さを感じ、暑さが本格化する前の、最も過ごしやすい時期ともいえるでしょう。
七十二候に見る立夏|自然の声に耳をすます
立夏には、次の三つの七十二候(しちじゅうにこう)があてられています。
初候(5月5日〜5月9日頃)蛙始めて鳴く(かわずはじめてなく)
田んぼや川辺で蛙の声が聞こえ始めます。春の眠りから目覚めた命の営みを感じます。
次候(5月10日〜5月14日頃)…蚯蚓出ずる(みみずいずる)
土が温まり、ミミズが地表に現れるようになります。土の中の生命が動き始める合図です。
末候(5月15日〜5月19日頃)…竹笋生ず(たけのこしょうず)
たけのこが地面を突き破るように顔を出します。成長の勢いに、夏の力強さが感じられます。
自然の現象を、短い言葉で豊かに伝える七十二候。それぞれの時期に耳を澄まし、足元の動植物を見つめることで、暦の言葉が体験と重なっていきます。
立夏を感じる和歌|言葉に映る立夏の情景
皆さま初めまして。二十四節気に纏わる万葉歌をご紹介させていただく、まつしたゆうりです。水彩画の絵本作家ですが、15年ほど前から『万葉集』の沼にどっぷりハマり、書籍の執筆や講演活動もしています(『よみたい万葉集』共著・絵/西日本出版社)。
「そんな昔のことを知って何になるの?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。ですが、万葉歌を知れば知るほど、季節を見る時の新しいフィルターが増え、気持ちを現す言葉が増え、心のひだが増すことで世界をもっと豊かに見ることができるのです。美しい世界とのアンテナを、毎月2つずつ増やしてみませんか?
「立夏」の記事でご紹介するのは、夏の初めにぴったりなこの歌。
夏山の 木末(こぬれ)の茂(しげ)に 霍公鳥(ホトトギス) 鳴き響(とよ)むなる 声の遥けさ
(大伴家持『万葉集』1494)
(訳)夏山の木のてっぺんの茂みで、ホトトギスが鳴き響かせている声の遥かなことよ
(詠み人)大伴家持は、『万葉集』を編纂したといわれている奈良時代の貴族で歌人。日常の小さな幸せや悲しみを探して歌にする視線に親近感が湧きます。

新緑が目に鮮やかな初夏の山。木のてっぺんの茂みで、ホトトギスが鳴き声を遠く遠くまで鳴き響かせている、そんな爽やかさ最高潮の歌。ここから見えてくるのは、抜けるような青空の下、ぽかぽかの日差しに心地よい風。「もう寒の戻りは来ないんだなあ」という安心感と、すくすく稲や穀物が育っていく夏への期待感。
その訪れを予祝するように鳴いてくれる、ホトトギス。ちょっとマイナー調の切ない声なんですが、夏だけ飛来して鳴く習性から「夏の訪れを告げる鳥」として愛されていたよう(ぜひ動画で調べて聴いてみてください)。
現代人がクリスマスソングを聴いて冬を感じるように、ホトトギスの歌に夏を感じていた昔々の人々。今年、この鳴き声が聴こえたら、「この歌が、夏を運んできているんだな」とか「この歌が響くたび、夏がどんどん増えているんだな」という風にイメージしてみませんか? きっと木々も花も風も、いつもと違って見えてくるかもしれません。
(「立夏を感じる和歌」文/まつしたゆうり)
立夏に行われる行事|子どもの健やかな成長を願って

立夏の代表的な行事といえば、5月5日の「こどもの日」です。本来は男児の成長を祝う「端午の節句」でしたが、昭和23年(1948)に「こどもの日」として国民の祝日となり、子ども全般の幸福を願う日となりました。
鯉のぼりや兜を飾る風習も、古くから続いています。鯉が急流をのぼって龍になるという中国の故事にちなみ、「立身出世」や「力強く生きる」象徴として用いられてきました。
同じく5月5日、京都・下鴨神社では「更衣祭(ころもがえまつり)」が執り行われます。これは、神様の衣替えの神事です。この「更衣祭」は、立冬にも同様に行われるのが特徴です。立夏と立冬という二つの節目に、神々の神衣(もしくは神服)を新調する古来の習わしが受け継がれています。
なお、こうした神事は、他の神社にも見られます。伊勢神宮では「神御衣祭(かんみそさい)」、明治神宮では「御衣祭(おんぞさい)」などが挙げられます。
立夏に見頃を迎える花
立夏の頃は、花々の色もより鮮やかになります。代表的なものを紹介しましょう。
躑躅(ツツジ)
躑躅は、紅・白・紫など鮮やかな花を咲かせ、庭園や山道を彩ります。江戸時代には品種改良が盛んに行われ、多くの園芸品種が誕生しました。

(写真提供/宝泉堂)
菖蒲(あやめ)
立夏の頃、水辺や湿地ではさまざまな花々が彩りを添え始めます。菖蒲をはじめ、花菖蒲(はなしょうぶ)、杜若(かきつばた)、あさざ、河骨(こうほね)、菱の花などが次々と咲き揃い、涼やかな景を描き出します。
「菖蒲」は「文目」「綾目」とも書かれ、その名のとおり、葉に浮かぶ網目模様のような葉脈(文目)が特徴とされています。
立夏の訪れとともに咲くこの花は、古くから端午の節句とも関わりが深く、邪気を払う力を持つとされてきました。花の美しさだけでなく、その背景にある文化や信仰にも目を向けると、より深い季節の趣が感じられるでしょう。

立夏の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む
立夏の時期に旬を迎える野菜、魚、京菓子をご紹介します。
野菜|筍(たけのこ)
筍は香りが高く、若いうちに収穫されることで味に深みが出ます。筍ご飯や煮物、ホイル焼きなどでその魅力を存分に味わえます。
魚|鰹(かつお)
鰹は、黒潮に乗って南の海から北上する回遊魚。立夏の頃、鹿児島や高知の沖合を経て、関東近海へと姿を見せるのは、まさに青葉が芽吹く季節のこと。
なかでも江戸っ子が心待ちにしたのが「初鰹」。とりわけ珍重されたのは、皮目を残したまま薄く削ぎ切りにした「初鰹の銀皮造り」です。新鮮な身に添えられる薬味の香り、口に広がる初夏の味わいは格別でした。
京菓子|柏餅(かしわもち)・粽(ちまき)

(写真提供/宝泉堂)
柏餅は、新芽が出るまで古い葉が落ちない柏の葉に「家系が絶えない」という意味が込められた縁起物です。粽は中国から伝来し、邪気を払う供物として端午の節句に用いられてきました。

(写真提供/宝泉堂)
まとめ
立夏は、ただの「初夏の入り口」ではありません。自然界の息づかいや、人々の暮らしに根ざした文化が豊かに息づく時期です。
暦に耳を傾け、花に目をとめ、旬を味わう。そうした暮らしの中に、心を潤す喜びが潜んでいます。いま一度、暦の言葉と向き合いながら、立夏を「人生の楽しみ」として味わってみてはいかがでしょうか。
●「和歌」部分執筆・絵/まつしたゆうり

絵本作家、イラストレーター。「心が旅する扉を描く」をテーマに柔らかで色彩豊かな作品を作る。共著『よみたい万葉集』(2015年/西日本出版社)、絵本『シマフクロウのかみさまがうたったはなし』(2014年/(公財)アイヌ文化財団)など。WEBサイト:https://www.yuuli.net/ インスタグラム:https://www.instagram.com/yuuli_official/
監修/新木直安(下鴨神社京都学問所研究員) HP:https://www.shimogamo-jinja.or.jp
協力/宝泉堂 古田三哉子 HP:https://housendo.com
インスタグラム:https://instagram.com/housendo.kyoto
構成/菅原喜子(京都メディアライン)HP:https://kyotomedialine.com Facebook