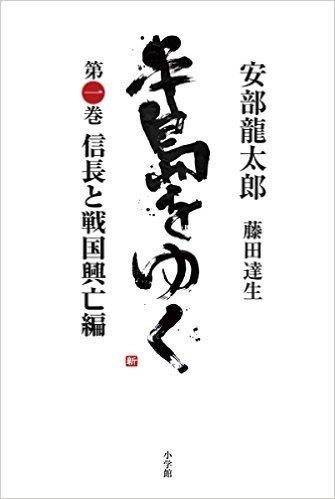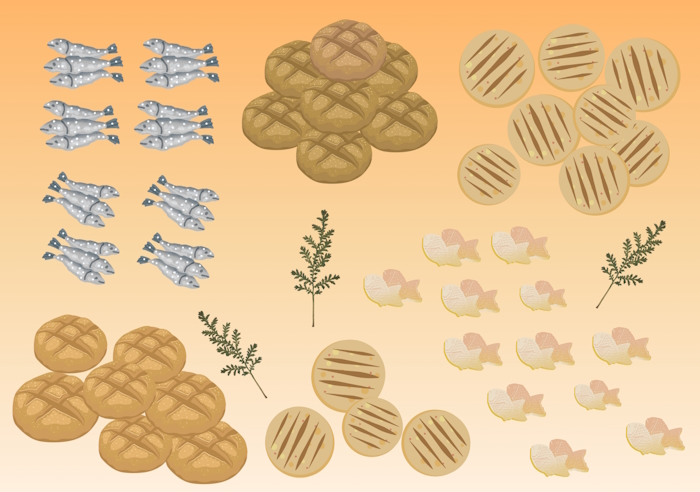『サライ』本誌で連載中の歴史作家・安部龍太郎氏による歴史紀行「半島をゆく」と連動して、『サライ.jp』では歴史学者・藤田達生氏(三重大学教授)による《歴史解説編》をお届けします。
文/藤田達生(三重大学教授)

石垣が残る原城跡で。
長崎県「潜伏キリシタン」関係遺跡を訪ねる旅の2日目である。私たちは、朝から天草・島原一揆の舞台、島原半島の南端に位置する原城跡(長崎県南島原市)をめざした。筆者は、仕事柄、何度もこの島原湾を見下ろす広大な城跡を訪れているが、その都度、遺跡整備が進んでいるのには驚かされる。
かつて、拙著『天下統一』のための取材旅行の一環として訪れた折りに、一揆に参加した老若男女の大量の遺骨(レプリカ)を資料館(現在の有馬キリシタン遺産記念館)で拝見し、衝撃を受けたことが記憶に新しい。

有馬キリシタン遺産記念館で再現される原城跡からの人骨出土現場。
当時は、確か入館してすぐに見ることができたのだが、現在は資料館がリニューアルされて一番奥に陳列され、遺骨の発掘状況がわかるように三層に分けて丁寧に展示している。本施設は、世界遺産登録推進のため平成26年4月にオープンしたそうだ。
城跡を発掘した結果、一体としてまとまった遺骨が見つからず、惨殺してバラバラに捨てられていたことが判明している。その上に石垣を崩して埋めたまま3世紀以上の年月が経過したのである。凄惨と言うほかないが、同じ取材で訪れた陸奥九戸城(岩手県二戸市)における発掘で発見された惨殺遺骨と同様だった。
天草・島原地域でキリシタン一揆が発生したのは、寛永14年(1637)10月のことだった。キリシタンに対する弾圧ときびしい年貢収奪に耐えかねた両地域の農民が一揆を企てたのである。近年の研究は、やむにやまれず民衆が暴発したというイメージではなく、改易されたキリシタン大名小西氏らの旧臣すなわち牢人や庄屋たちが頭目となって、談合のうえでつまり計画的に決起したことを指摘する。
岡本大八事件で有馬氏は国替

本丸跡にたつ天草四郎像。
天草四郎(益田四郎時貞、洗礼名フランシスコ)を大将とした一揆軍は、肥後本渡城(熊本県天草市)などの天草支配の拠点を攻撃し、11月14日に本渡の戦いでは、富岡城代の三宅重利(熊本藩重臣、明智秀満の子息)を討ち取った。勢いに乗った一揆勢は、唐津藩兵が籠もる肥後富岡城(熊本県苓北町)を攻撃したが、攻めきれなかった。島原の一揆勢は、松倉氏の島原城(森岳城)を攻撃したが、こちらも善戦するが落城には至らなかった。
この段階で天草と島原の一揆勢は、前任大名有馬氏の支城だった原古城に目を付けて入城した。戦国大名有馬氏は、かつて島原半島一帯に勢力を誇ったが、龍造寺氏の南下によって半島南部に領国を縮小していた。有馬晴信は、朱印船による海外交易で巨万の富を築いており、居城日野江城(南島原市)とその城下町は繁栄していた。

原城から指呼の距離ある日野江城
豊かな経済力を背景に旧領を回復しようとした晴信は、家康の謀臣として権勢を誇っていた本多正純に目を付け、その家臣岡本大八に賄賂をもって接近したが、トラブルに巻き込まれ処罰されてしまう。有名な岡本大八事件である。
幸運にも、子息直純は家康の養女を正室としていたため連座せず日野江藩主となり、慶長19年(1614)7月には日向延岡藩5万3千石に国替となった。この後任として入国したのが、元和2年(1616)に4万3千石を預けられた松倉重政だった。
重政は一旦は日野江城に入るが、同年から島原城の築城を開始する。寛永7年に重政が急逝して後は、子息勝家によって工事は強硬に進められた、小藩にふさわしからぬ大規模城郭の普請が、一揆勃発の要因の一つとして数えられている。
一揆勢が抵抗拠点として原古城を選択したのは、元和元年発令の一国一城令によって廃城になっており、入城が容易だったからとみられてきた。ところが関係史料と発掘調査をあわせて検討すると、その理由は変更せざるをえない。
ポルトガルの援軍を待っていた天草軍
原城は、有馬晴信時代には日野江城と併存していた。正確には、晴信は原城を築城して、本城を移転しつつあったとみられる。両城は距離にしてわずか3キロしか隔たっていないのである。これほどの規模の城郭が近接しているのは、不自然だ。事実かどうか確認はできないが、往時の両城は海上を橋で結ばれていたというから(『有馬氏系図』)、一体的に利用していたのかもしれない。
日野江城跡からは、直線的な立派な石段遺構をはじめ、金箔瓦や野面積みの大規模石垣などが確認されており、晴信の時代に戦国城郭を立派な織豊系城郭へと改修したことがうかがわれる。晴信は、雲仙山麓の地味が豊かではない領地に依存するよりも、至近の口之津を利用した南蛮貿易による繁栄に傾注しようとしたのである。
そうすると、周囲が遠浅の日野江城よりも、直接海に面しており、口之津を把握することができる原城に拠点を移そうとしたと理解される。原城には天守とみられる三重櫓が海側にそびえていたが、ここからは口之津方面がよく見通せる。
服部英雄氏(九州大学名誉教授)は、一揆側が各地のキリシタンに対して次々と使者を派遣して一緒に決起するように呼びかけたこと、天草四郎の父親甚兵衛が、一揆が始まった時点でキリシタンの多い長崎に向かったことなどから、国内に内乱状況をおこそうとした形跡を指摘された。
さらに、幕府軍の総大将松平信綱の「追付け南蛮より加勢に指し越し候(まもなくポルトガルから援軍が派遣されます)」(『綿考輯録』)との認識から、一揆はポルトガルからの援軍を待っていたと推論される(『原城発掘』)。
そうだとすると、信綱がオランダに沖から原城を攻撃してほしいと依頼したのは、もしもポルトガルが援軍に来たとしても、新教国(プロテスタント)であるオランダが応戦することを一揆側に示すものだったとみることも可能である。
以上からは、一揆側が島原湾に面する原古城をめざしたのは、ポルトガルからの援軍を意識してのものと考えることができる。それに加えて、一揆側は防戦のための現実的な対応として原古城を選択したと、筆者は考えている。
文/藤田達生
昭和33年、愛媛県生まれ。三重大学教授。織豊期を中心に戦国時代から近世までを専門とする歴史学者。愛媛出版文化賞受賞。『天下統一』など著書多数。
※『サライ』本誌の好評連載「半島をゆく」を書籍化。
『半島をゆく 信長と戦国興亡編』
(安部 龍太郎/藤田 達生著、定価本体1,500円+税、小学館)
https://www.shogakukan.co.jp/books/09343442