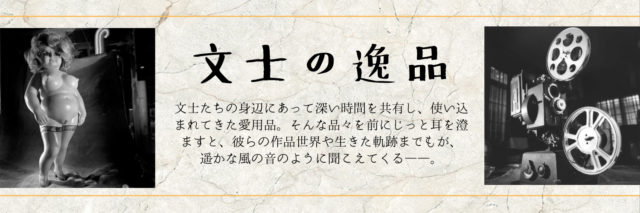
◎No.21:谷崎潤一郎の長襦袢

谷崎潤一郎の長襦袢(撮影/高橋昌嗣)
文/矢島裕紀彦
長襦袢と呼ぶには、余りにも絢爛豪華な姿であった。兵庫県芦屋市の谷崎潤一郎記念館の一隅に再現された潤一郎の書斎、中央に据えた衣桁に掛けると、その背に染め抜かれた雲上の雷神がいまにも叫びを上げて動き出さんばかりの迫力が伝わってくる。
反自然主義の旗手として、耽美的な物語の数々を紡ぎ出す一方で、日本の伝統文化や古典文学への回帰を示した潤一郎は、もちろん、自らが身に纏(まと)う着物にも、雅びやかな趣味を貫いていた。結城の袷に唐桟(とうざん)の羽織で芝居見物に出かけるなんぞは、その最たるもの。ついには、人目にはけっしてさらされることのない羽織の裏地や長襦袢にまで、凝りに凝ったのである。
実は、背に雷神が踊るこの羽二重地の長襦袢には、さらなる曰(いわ)く因縁がある。潤一郎の3人目の妻となる松子の父から譲り受けたものであった、というのである。
潤一郎といえば、佐藤春夫とのいわゆる細君譲渡事件でも物議を醸したが、松子への思慕の度合いもなんとも並外れたものであった。
「どんな難題でも御出し下さいまし、きつときつと御気に入りますやうに御奉公」云々とは、潤一郎がまだ結婚前の松子へ出した手紙の一節。
こんな手紙を想起すると、『痴人の愛』や『鍵』にも通ずる倒錯したエロティシズムの世界までもが、眼前の雷神の背後に垣間見えてくる。
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。『サライ.jp』で「日めくり漱石」「漱石と明治人のことば」を連載した。
写真/高橋昌嗣
1967年桑沢デザイン研究所 グラフィックデザイン科卒業後、フリーカメラマンとなる。雑誌のグラビア、書籍の表紙などエディトリアルを中心に従事する。
※この記事は、雑誌『文藝春秋』の1997年7月号から2001年9月号に連載され、2001年9月に単行本化された『文士の逸品』を基に、出版元の文藝春秋の了解・協力を得て再掲載したものです。


































