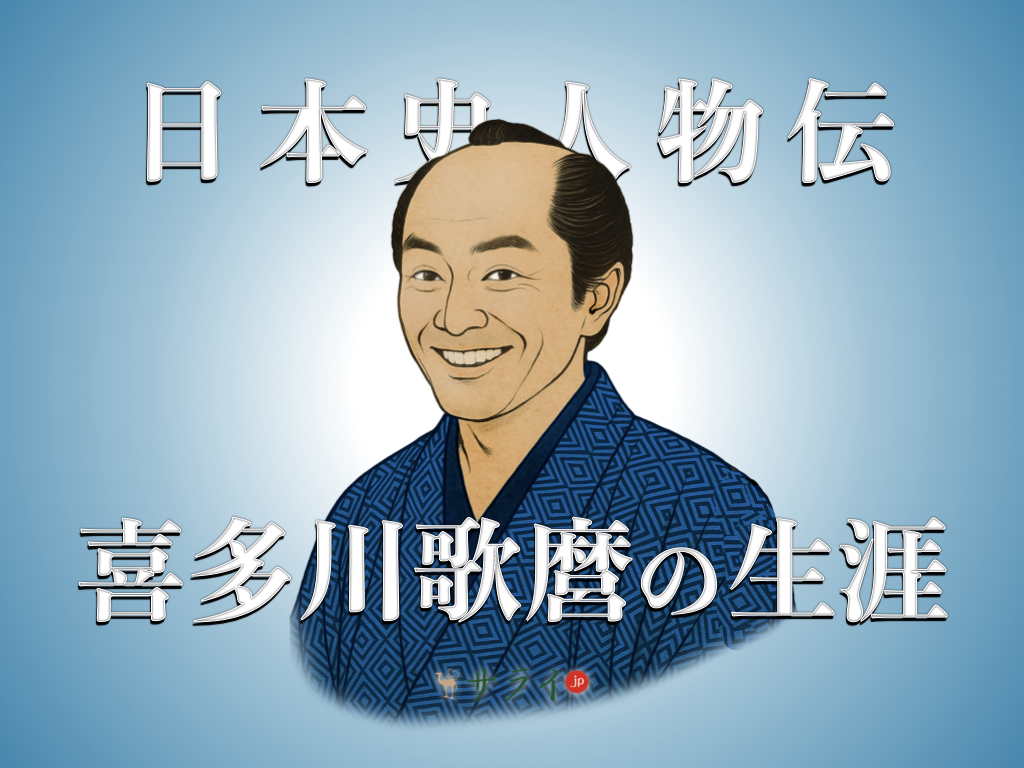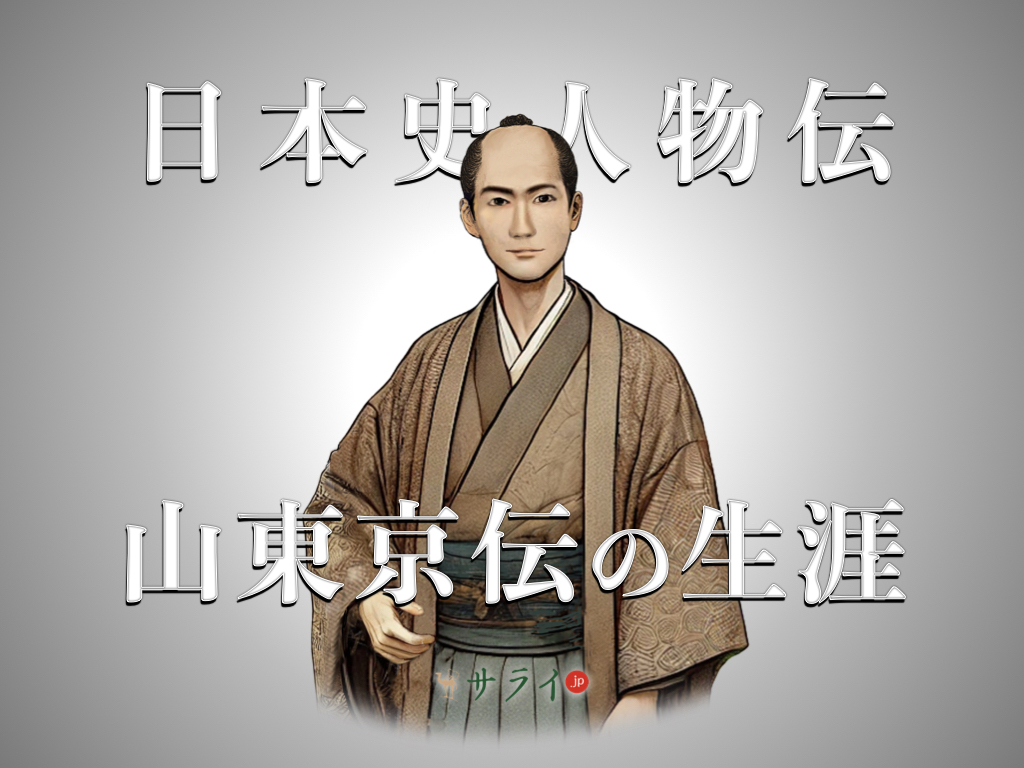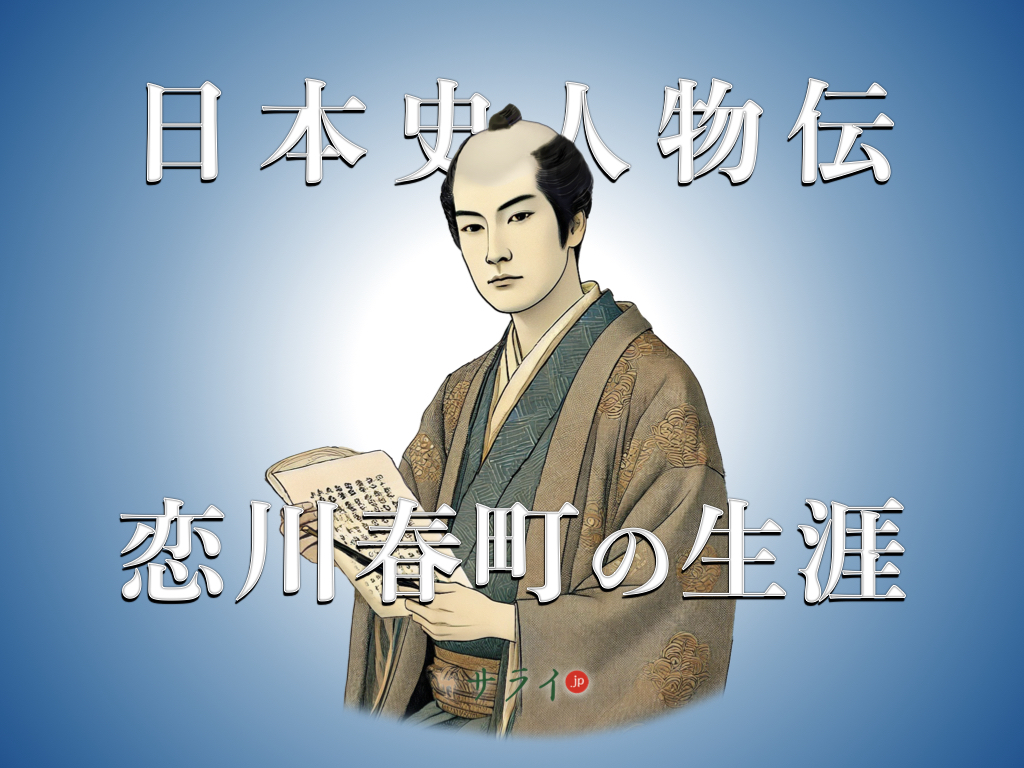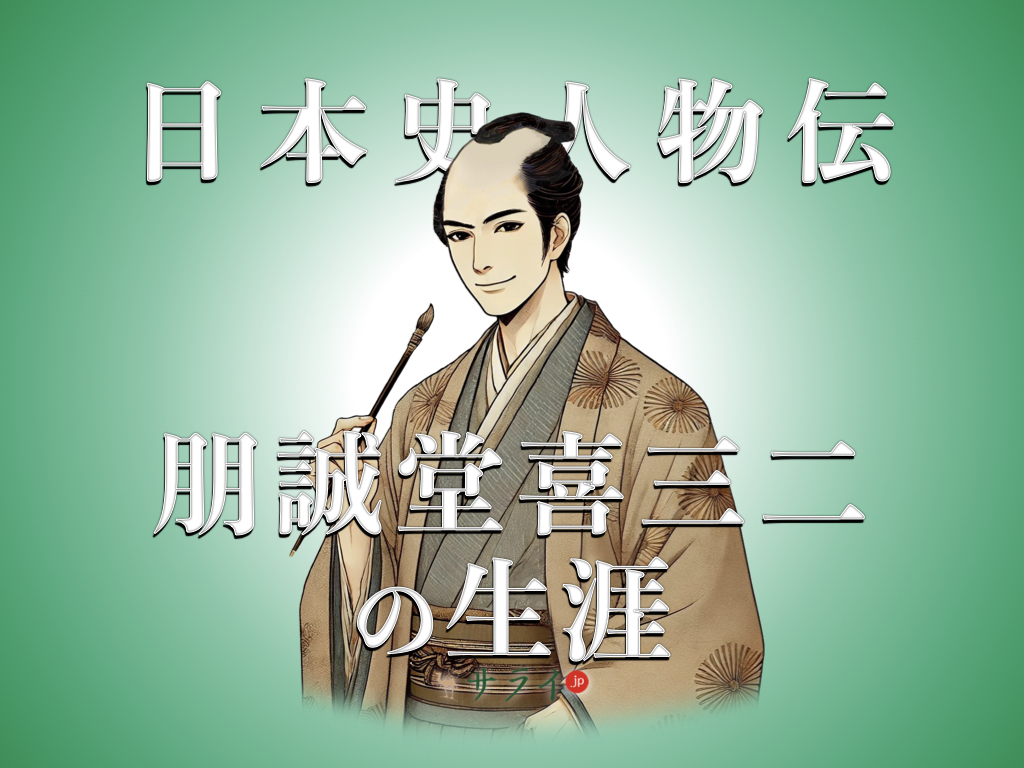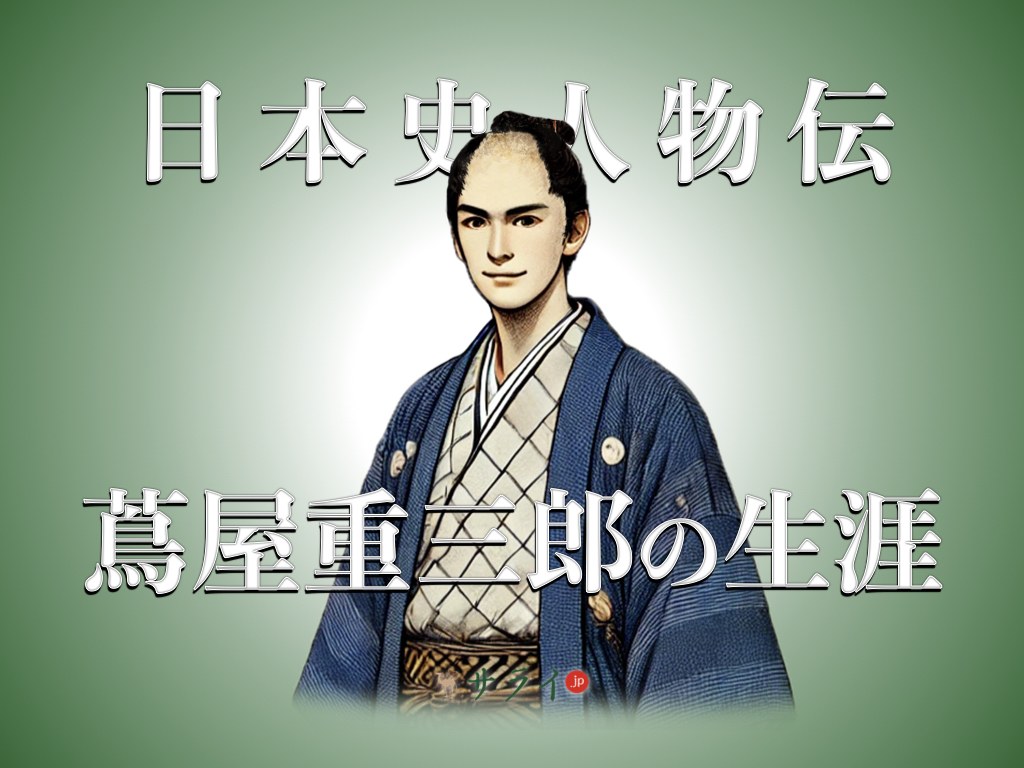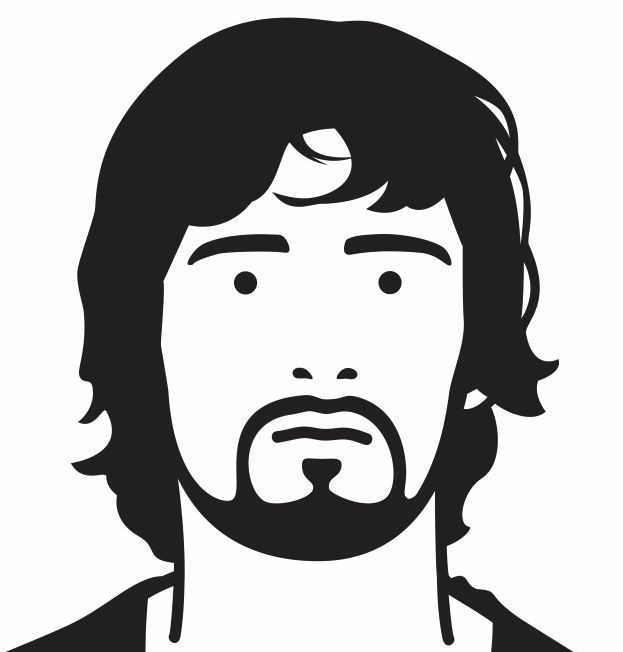大河ドラマや時代劇を観ていると、現代では使うことなどない言葉が多く出てきます。その言葉の意味を正しく理解していなくとも、場面展開から大方の意味はわかるので、それなりに面白くは観られるでしょう。
しかし、セリフの中に出てくる歴史用語をわかったつもりで観るのと、深く理解して鑑賞するのとでは、その番組の面白さは格段に違ってくるのではないでしょうか?
【日本史ことば解説】では、「時代劇をもっと面白く」をテーマに、“大河ドラマ”や“時代劇”に登場する様々な言葉を取り上げ、具体的な例とともに解説して参ります。時代劇鑑賞のお供としていただけたら幸いです。
江戸の知性と風刺が光る「黄表紙文学」。今回はその中でも寛政の改革を真っ向から茶化した作品として語り継がれる、恋川春町(こいかわ・はるまち)の『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』をご紹介します。
幕府の新政に対する庶民の疑問や風刺心をユーモアで包み込んだこの作品は、時の為政者・松平定信の怒りを買い、作者に悲劇的な運命をもたらしました。

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892636
『鸚鵡返文武二道』とは?
『鸚鵡返文武二道』は、寛政元年(1789)に刊行された黄表紙作品で、作者は黄表紙の第一人者・恋川春町、画は北尾政美(きたお・まさよし)が担当、出版者は蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)です。
物語の舞台は古代・延喜の御代。帝が、文と武の両道を国の柱として奨励し、補佐役の菅秀才(菅原道真を連想させる人物)が人々に文武の修行を推進します。
ところが人々はこれを誤解し、武勇を競って洛中で騒動を起こしたり、たとえ話を真に受けて凧あげに熱狂したりと、世の中は空回り。万民こぞって文武二道に狂奔する――という筋立てです。
この寓話的なストーリーの背後には、作者が当時の「寛政の改革」とその精神主義的な政策に対する痛烈な風刺を込めていたことは明らかです。

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892636
作品に込められた風刺と時代背景
本作のタイトル『鸚鵡返文武二道』は、前年に出版された朋誠堂喜三二(ほうせいどう・きさんじ)の『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくどおし)』を踏まえたものであり、また松平定信が書いた教訓書『鸚鵡言(おうむのことば)』への皮肉を暗示しています。
定信の政治は「文武奨励」と「風俗粛正」を柱とし、武士たちには清貧と精神修養を求めましたが、それが空疎な理想論に見えることも多かったのです。
春町の作品では、登場人物たちが主君の言葉を鸚鵡返しのように繰り返しながらも、本質を理解せず行動だけが空回りする様子が描かれています。これは、形式ばかりが先行し実効性を伴わない幕府の改革を痛烈に揶揄したものといえるでしょう。
幕府の弾圧と作者・恋川春町の最期
このような風刺の鋭さから、『鸚鵡返文武二道』は幕府の怒りを買いました。
幕府は作者・恋川春町に出頭を命じましたが、春町はこれに応じることなく、寛政元年(1789)7月7日、46歳で急死します。
死因については「病死」と記録されていますが、幕府への出頭を避けるための自殺だったという説も根強く残されています。この一件は、寛政の改革下における言論統制の象徴的な事例としても知られています。
同時に、幕府批判の筆を止めなかった春町の姿勢は、江戸文学史における「表現の自由」と「風刺文化」のあり方を考える上で重要な示唆を与えているともいえるでしょう。
最後に
『鸚鵡返文武二道』は、文芸を通じて為政者の政治や社会の空気に問いを投げかけた作品です。
そして、作者・恋川春町は、黄表紙という新しい文芸ジャンルを確立し、江戸庶民の笑いや知性を支えた立役者でもありました。
改革と弾圧の時代。そこに生きた人々の声に耳を傾けることで、私たちは現代に通じる表現の力や、社会に対するユーモアと批判精神の大切さを改めて感じることができるのではないでしょうか。
※表記の年代と出来事には、諸説あります。
文/菅原喜子(京都メディアライン)
HP:http://kyotomedialine.com FB
引用・参考図書/
『世界大百科事典』(平凡社)
『日本国語大辞典』(小学館)