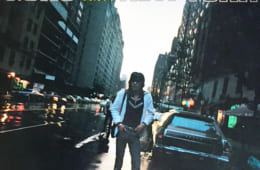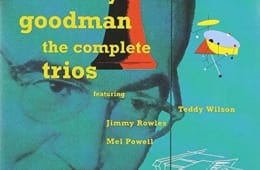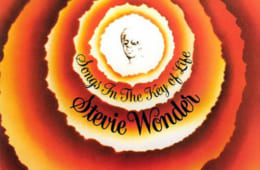文/池上信次
前回(https://serai.jp/hobby/1090796)に続き、めずらしいジャズ・ドキュメンタリー映画を紹介します。今回はオーネット・コールマン「トリオ」の映像作品。どうしてトリオにカギカッコをつけたかというと、トリオによるものだからこそ面白いものなので。その作品とは1966年(または65年秋。諸説あり)に撮影された『David, Mofett & Ornette』という短編映画。監督は多くのジャズ・ドキュメンタリー映画で知られるディック・フォンティーン。これはオーネット・コールマン(アルト・サックス、トランペット、ヴァイオリン)・トリオの、映画『Who’s Crazy』のサウンドトラック録音現場の映像とインタヴューで構成されたドキュメンタリーであり、またオーネット、そしてチャールズ・モフェット(ドラムス)、デヴィッド・アイゼンゾン(ベース)による「オーネット・コールマン・トリオ」のおそらく唯一の映像でもあります。
オーネットのこのトリオは62年末のコンサート以降活動を停止しており、65年は再び活動を始めた時期で、トリオは同年12月には代表作となる『ゴールデン・サークルのオーネット・コールマン・トリオ』を録音しています。まだまだオーネットの「フリー・ジャズ」のスタイルには賛否両論がやかましかった時期、わずか28分の映画ですが、当事者の「生の声」が聞けるという興味深い内容になっています。

演奏:オーネット・コールマン(アルト・サックス、トランペット、ヴァイオリン)、デヴィッド・アイゼンゾン(ベース)、チャールズ・モフェット(ドラムス)
録音:1965年12月3日、4日
ストックホルムのジャズ・クラブ「ゴールデン・サークル」でのライヴ盤。オーネットは『vol.1』ではアルト・サックスだけですが、『vol.2』ではトランペットとヴァイオリンも演奏します。
映画『Who’s Crazy』は1966年公開。監督はトーマス・ホワイト。撮影はベルギーで、オーネットらによるサウンドトラック録音はパリで行なわれました。ドキュメンタリーはスタジオの演奏シーンから始まります。トリオはスタジオ内に用意されたスクリーンを見ながら「サドネス」を演奏し、1シーン1曲を完奏。しかし監督は「入るタイミングが早すぎる。映画のシーンと合わない」とやり直しを命じます。その反応が三者三様で、まず怒ったのがモフェット。「途中でカットと言ってくれ。2日前に完璧な音はすでに録音してあるから、それを使えばいいだろう」。リーダーのオーネットはどうしたかというと、「まあまあ、待てよ」とやんわりとそれをなだめるのでした。そしてアイゼンゾンはふたりを笑って見ているだけ。このトリオはこういうバランスなのですね。
そしてもう1曲。スクリーンはクレイジーな行為をする人たちのシーン。オーネットはアルトのほか、ヴァイオリン、トランペットを持ち替えて演奏しながらもスクリーンから目を離しません。モフェットも同様。しかしアイゼンゾンだけはスクリーンではなく、じっとオーネットを注視し続けています。トリオは映画と「ライヴ共演」しているのでした。
それら演奏シーンに挟まれるのが3人のインタヴュー。当時の「当事者たちのフリー・ジャズ観」が語られています。興味深い発言をそこから紹介します。(日本語版ビデオ『オーネット・コールマン・トリオ』[バップ廃盤/字幕:神代知子]から引用・編集)
●アイゼンゾン「ある日突然、自分がやりたいようにやっていいんだと気づいた」「オーケストラは音楽と指揮者が第一だが、多くの指揮者は自分が一番だと思っている。(トリオの活動休止中に)私がNBCシンフォニーで演奏していたときは、好きなようにやるために契約は結ばなかった」
●モフェット「オーネットは好きなようにやらせてくれる。完全にフリーだ」「他人の音楽のための演奏は十分やった。今は自分のための音楽をやっていきたい」
●オーネット「デヴィッド(アイゼンゾン)とモフェットのふたりに共通しているのは、自分の信条を曲げずに腕を磨き、可能性を追求する願望だ。自分を裏切らずに完璧を目指す。俺は大賛成だ」
●オーネット「弦楽四重奏を書いたら、バルトークに似ていると言われた。彼らはそうやって自分がなじめる形にはめたいんだ。自分の教養の範囲内に収まればとりあえず安心できるからだ。でも的外れということもけっこうある」
●モフェット「オーネットの音が耳に入らない人がいる。ライヴに来てもなぜか本気で音楽を聴いていない。自分が期待していた音じゃないと受けつけないんだ。でもオーネットの音に本気で耳を傾ければメッセージが伝わる」
●オーネット「アメリカでは痛い目にあって人間不信に陥った。だからいろいろと悩むのを諦めた。食べていけないことは今さら怖くない。自分がやっていることの価値とか、その善悪を考えずにとりあえずやることにした」
●アイゼンゾン「どんな強い人間でも傷つくようなことを彼(オーネット)は人から言われてきた。だから自分の周りに壁を作るのも当然だ」
●オーネット「男にとって大切なことは、誠実さや哲学ではない。自分の好きなようにやって、それがそいつのやり方だと人に納得させることだ」
「自分の音楽に求めるものは今この瞬間だ。これは生涯の夢だ。今を捉えた曲がこの場で書けたら昨日の演奏は関係ない。過去が欲しければ機械がある(注:レコーダーのことか)。過去は機械に任せて、俺たち人間は今を体現する」
そして最後に、空港で飛行機に乗り込む映像に重なるオーネットの言葉でドキュメンタリーは終わります。「俺は永遠というものに恋をしてる。そこにどんな変化が起ころうと、無限に続くという流れに」。
これらは会話ではなくすべて独白です。3人とも意識が同じ方向を向いています。個々の強い意志と固い結束がこのトリオの音楽を作っているのですね。
でもこれってフリー・ジャズではなくても、ジャズであれば成り立つ話でもあります。と考えれば、オーネットは人とは違う新しいことをやってシーンを変えようという意識ではなく、ただひたすら自分の音楽をやっているだけという、ミュージシャンとしては当たり前の感覚だったともいえます。周りが騒ぎすぎただけというのは極端かもしれませんが、オーネットにとってはいい迷惑だったということでしょう。
なお、このサウンドトラック音源は『フーズ・クレイジー』のタイトルで1983年にアルバム化されています。これはこのトリオによる唯一のスタジオ・セッションとなりました。映画『Who’s Crazy』の方はといえば、1966 年のカンヌ国際映画祭で上映されたあと、ずっとフィルムが行方不明とされていて「幻」の映画となっていましたが、2016年に監督の家のガレージから発見され、17年に公開、ソフト化されました。オフィシャル予告編はYouTubeで観ることができます。
文/池上信次
フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。ライターとしては、電子書籍『サブスクで学ぶジャズ史』をシリーズ刊行中(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz)。編集者としては『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『ダン・ウーレット著 丸山京子訳/「最高の音」を探して ロン・カーターのジャズと人生』『小川隆夫著/マイルス・デイヴィス大事典』(ともにシンコーミュージック・エンタテイメント)などを手がける。また、鎌倉エフエムのジャズ番組「世界はジャズを求めてる」で、月1回パーソナリティを務めている。