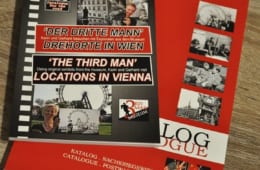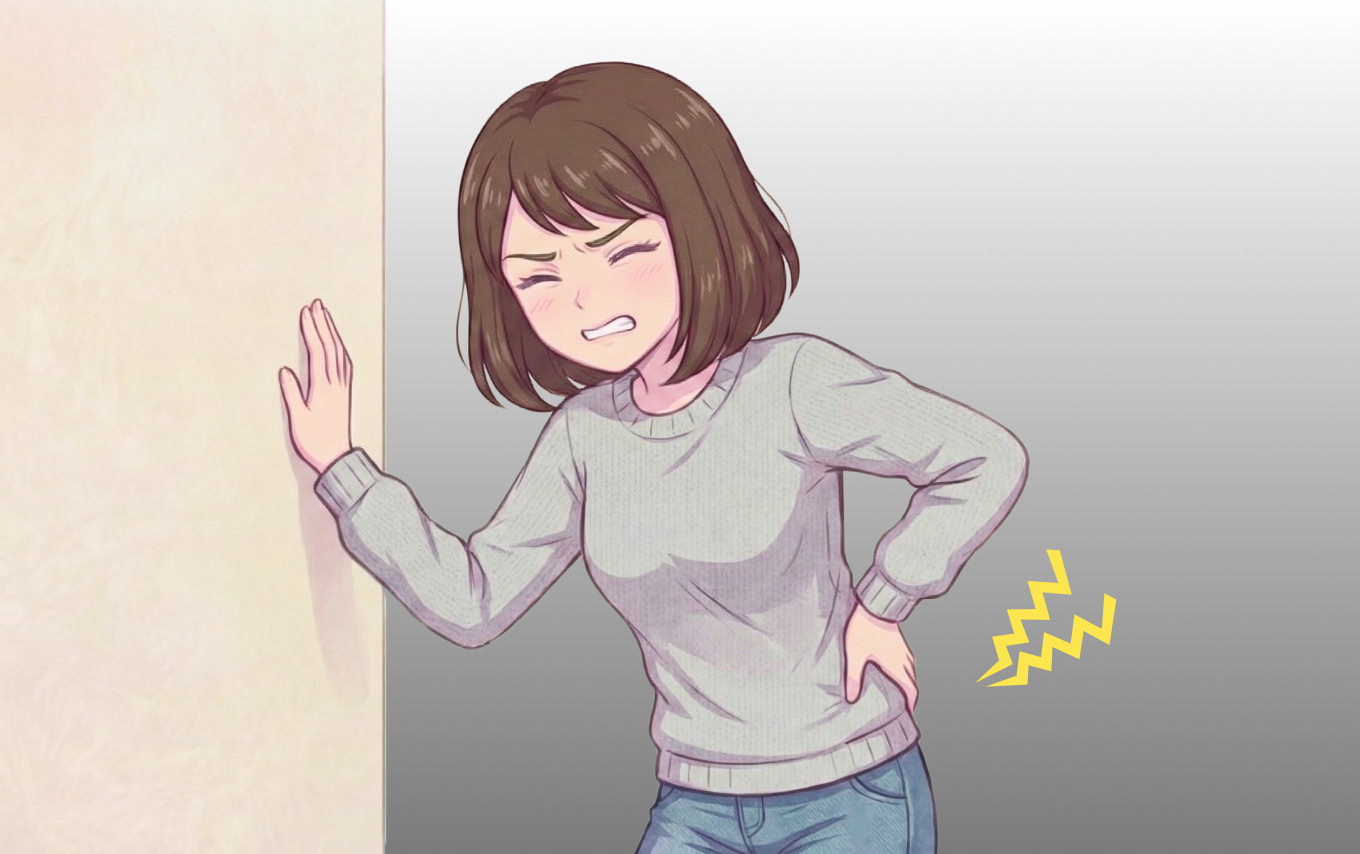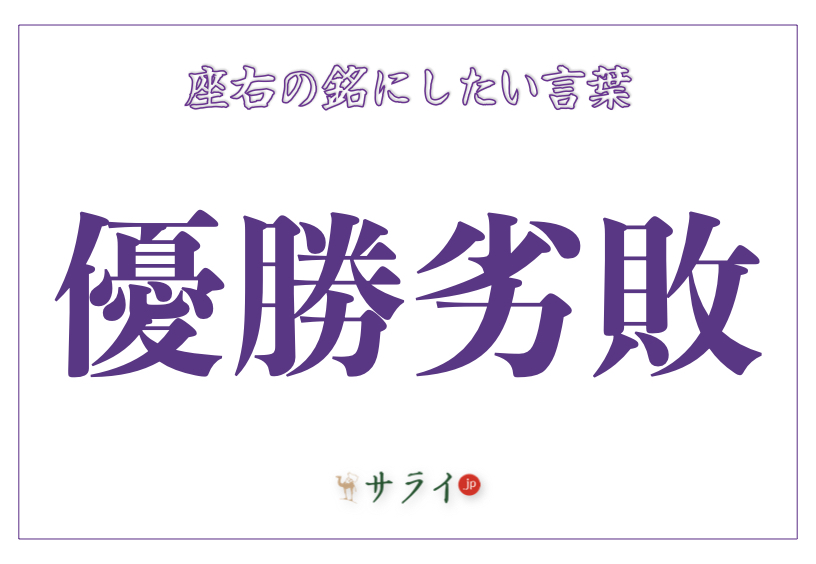文・写真/バレンタ愛(海外書き人クラブ/ウィーン在住ライター)
オーストリアの首都ウィーンより郊外に約1時間ほど行った場所に、ロースドルフというお城(https://www.piatti.at/schloss-loosdorf)がある。11世紀からの歴史があるイタリアの貴族家系、ピアッティ家が北イタリア、ドレスデンと移動してこの地に城を構えたのは1834年のことだった。それ以来、農業や林業に携わっていて、現在の当主は8代目となる。そんなピアッティ家の住居となっているロースドルフ城には、多くの人に知られていない陶磁器の物語があった。その物語を順を追ってひも解いてみよう。
ピアッティ家の陶磁器コレクション
ピアッティ家では、1760年頃から陶磁器を集め始め、日本の古伊万里を含む世界の貴重な陶磁器のコレクションが代々受け継がれていた。第二次大戦末期に、この辺りはロシア軍に占領され、ピアッティ家もお城から逃げることを余儀なくされた。大切な陶磁器コレクションは地下に隠して行ったのだが、戦争が終わりロシア軍が撤退し、ピアッティ家の人々がお城に戻ってみると、陶磁器コレクションの大部分は無残な姿に破壊されてしまっていたという。

陶片はお城の中だけではなく、庭のあちらこちらにも散らばっているという痛ましい状況だった。ピアッティ家の人々と地元の人たちは協力して、1片1片拾い集めて行ったのだという。ピアッティ家にとっては破片になってしまったとはいえ、18世紀の始めから代々受け継ぎ、家族が大切にしてきたコレクションであることは変わらなかった。家族の思い出が詰まった陶磁器コレクションを、壊れてしまったからといって捨てることは出来なかったのだ。そして戦争の無意味さを訴えていくことと、戦争は破壊にしか繋がらないことの象徴としたいとして破片を保存することにした。


当時の当主フェルディナンドは、ロシア軍が執務室として使っていた城内の1部屋を「陶片の間」とし、拾い集めた破片を床に敷き詰めて展示室にした。その後長い年月をかけ、ピアッティ家の人々と地元の人は協力して破片を集め、洗い、分類して、保存作業を進め続けた。「陶片の間」の壁には、今でもロシア軍が使用していた当時の看板がそのまま残されている。

そこまでしても「戦争の嫌な記憶を思い出させる」とか「粉々になってしまった陶磁器には価値がない」という声も多く、この陶片のことは広く知られることはなかったのだった。
お茶の心により再び日本と繋がった陶片
時は流れ2015年。当時の駐日オーストリア大使だったベルナルド・ツィンブルグ氏が、初来日する妹夫婦の為にお茶会を開いて欲しいと言ったことからこの陶片の物語は大きな動きを見せる。実は大使の妹というのが、当時のロースドルフ城城主夫人であったヴェレーナ氏だった。彼女は「陶片の間」の管理を引き継いでいた人物だった。
大使公邸において、催された茶会の場で、茶の心、茶器、陶磁器、陶磁器の繕い文化と話は広がっていき、ピアッティ夫妻はロースドルフ城にある陶片の話をはじめたのだった。その陶片をなんとか出来ないか、日本の専門家とも話がしたいということから、話は進んでいった。茶会を主催した保科氏とピアッティ夫妻は連絡を取り続け、保科氏は2017年に初めてロースドルフ城を訪れることになった。「陶片の間」を実際に目にした保科氏は、1万ピースにも及ぶ膨大な陶片の様子に衝撃を受け、これをこのまま埋もれさせてはいけないと考えた。その後、有志を集め2018年に「ロースドルフ城 古伊万里再生プロジェクト(https://www.roip.jp/)」を立ち上げた。
故郷へ戻った古伊万里の陶片
2019年は日本とオーストリアの外交樹立150周年という節目の年で、このプロジェクトは在日オーストリア大使館より日墺友好150周年事業の認定も受け進行していくことに。紆余曲折は多々あったものの、結果的には多くの協力者を得て、2018~2019年には日本の専門家による学術調査がロースドルフ城で行われることとなったのだった。
調査を経て陶片コレクションの一部を日本に送り、修復することになった。しかし「過去の痛ましい破壊の史実が消されてしまうのは望まない」というヴェレーナの意向で、完璧に修復し美しい元の姿に戻すのではなく部分的な修復をすることになった。そして698点の破片が、約400年振りに故郷日本に戻ったのだった。

ヨーロッパでは日本の古伊万里の収集も盛んで、多くの古伊万里が海を渡った。今でもヨーロッパの多くの城や宮殿では、古伊万里のコレクションを見ることが出来る。だが、海を渡った古伊万里が日本の専門家の手に触れることは少なかったという。その為、帰国した古伊万里に触れることは、日本の専門家にとってもすごく貴重な機会になった。陶磁器は断面を見ると、多くの情報が分かるようだが、美しく保存されてきた陶磁器の断面を見るのは壊さない限り不可能だ。はるか昔に海を渡った古伊万里を手に取れるだけでも貴重なのに、断面まで見ることが出来たのは、学術的にも大きな意味があったという。

修復された陶磁器は「海を渡った古伊万里〜ウィーン、ロースドルフ城の悲劇〜」として、日本各地の美術館で巡回展を開催。東京「大倉集古館(https://www.shukokan.org/)」で2020年11月~2021年3月、名古屋「愛知県陶芸美術館(https://www.pref.aichi.jp/touji/index.html)で2021年4月~6月、萩「山口県立萩美術館・浦上記念館(https://hum-web.jp/)」で2021年9月~11月、そしてついには古伊万里の故郷、有田にある「佐賀県立九州陶磁文化館(https://saga-museum.jp/ceramic/)で2022年5月~7月に特別展が開催されたのだった。
有田での特別展には、2021年にピアッティ家の家督を継いだ若き当主、ガブリエルも来展。有田の次世代を担う学生たちや地元の人も含めた、講演やシンポジウムも行った。単なる国際感覚を養う国際交流というだけではなく、ピアッティ家が持ち続けている戦争の無意味さや悲しさ、平和への想いを伝え、壊されても美しい魂が宿っている陶磁器、古伊万里の歴史や素晴らしさを再認識し未来へ繋げていくというとても深く有意義なものになった。
修復された破片は再びオーストリアへ
日本での修復と展示を終えた陶片は、2022年9月に再びロースドルフ城に戻った。2023年5月には修復された陶片やその歴史、残りの陶片が展示してある「陶片の間」を見られる特別展「Comeback for more」がウィーン応用美術大学主催で開催されたのだった。





同時にピアッティ家の陶片の物語が動き出すきっかけになった茶席も、ロースドルフ城で催された。その時に保科氏が掲げたのは「千里同風」という書。「遠く離れた土地で思いが繋がる」ことを表すそうだが、このロースドルフ城の古伊万里の物語にピッタリの言葉だ。

2023年は日本が初出展した1873年開催のウィーン万博から数えて150周年の記念の年。多くの記念イベントあるなか開催されたこの特別展には、日本からの茶道関係者27名も和服で参加。美しい着物を着てのお点前を披露、政府関係者や大学関係者、地元の人なども含む約200名を超える参加者にお茶をふるまっていたのは圧巻だった。オーストリア国営放送の取材も入り、ヴェレーナや当主ガブリエルは特別展のガイドツアーを行った。書道や折り紙などの紹介もあり、参加者はロースドルフ城の陶片の歴史と、日本文化を知ることが出来たのだった。

2023年7月から9月には、ウィーンにある世界遺産のシェーンブルン宮殿でも茶会が開催された。ロースドルフ城 古伊万里再生プロジェクトが協力したウィーン工科大学による「茶室プロジェクト」で、学生たちが作ったポータブル茶室が宮殿敷地内の日本庭園に設置された記念式典でのことだった。このポータブル茶室は、2024年6月にロースドルフ城で開催されたイベントでも設置された。茶会だけではなく、書道や弓道も披露され再び日本文化を通じて、ロースドルフ城の破片の歴史と、そこに込められた平和への想いが多くの参加者の心に響いたのだった。

2025年大阪万博でも紹介
2025年4月から10月にかけて開催される大阪万博。そこに出展するオーストリアパビリオンでも、このピアッティ家の陶磁器の物語が映像で紹介される。400年前に海を渡りヨーロッパで大切にされ続けている古伊万里、それが戦争によって壊された無意味さや平和の大切さ、目に見えるものだけが美しいというわけではないこと、長い時を超えて日本の茶の心が繋げた距離と人の心、そして完全には修復されなかった陶片を通して訴える平和への想い。これらが紹介映像を通じて、1人でも多くの人に届くことを願うのだった。そしてこの想いが、時と距離を越えて日本とオーストリアを繋ぎ続けるだけでなく、さらには世界中の人々にも届き、未来にも受け継がれていくことを願って。

文・写真/バレンタ愛(ウィーン在住ライター)
2004年よりウィーン在住。うち3年ほどカナダ・オタワにも住む。長年の海外生活と旅行会社勤務などの経験を活かし、2007年よりフォトライターとしても多数の媒体に執筆、写真提供している。著書に「カフェのドイツ語」「芸術とカフェの街 オーストリア・ウィーンへ」など。世界100ヵ国以上の現地在住日本人ライターの組織「海外書き人クラブ」(https://www.kaigaikakibito.com/)会員。