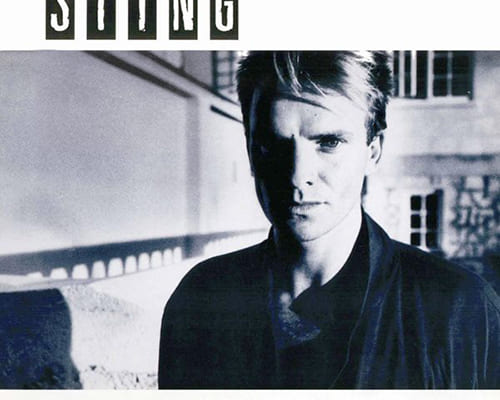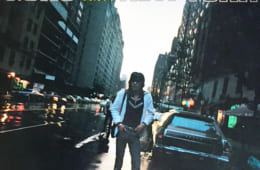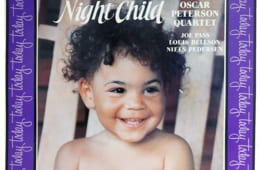文/池上信次
ポップスのシンガーが、ジャズマンをフィーチャーして作品を作ることは珍しくありません。個性や演奏技術など、ジャズマンに求めるものはさまざまでしょうが、多いケースはソロイストとしてのフィーチャー(これはあらためて紹介します)。ときにはバック・バンド全部をジャズマンにしてしまうことも、また珍しくありません。たとえば、ジョニ・ミッチェル。1970年代のアルバム『シャドウズ・アンド・ライト』では、人気絶頂のジャコ・パストリアスやパット・メセニーらフュージョンのスター・プレイヤーが参加していました。またスティングのソロ・デビューのバックでは、ブランフォード・マルサリスとケニー・カークランドがバリバリのジャズのソロを展開していました。そのふたつのバンドの顔ぶれは、当時ジャズの分野にはなかったスーパー・ジャズ・バンドとしてジャズ・ファンからも大きな注目を集めました。
(1)ジョニ・ミッチェル『シャドウズ・アンド・ライト』(アサイラム)
演奏:ジョニ・ミッチェル(ヴォーカル、ギター)、マイケル・ブレッカー(テナー・サックス)、ライル・メイズ(キーボード)、パット・メセニー(ギター)、ジャコ・パストリアス(ベース)、ドン・アライアス(ドラムス)
録音:1979年9月
ジョニ・ミッチェルの70年代半ばからこの時期のアルバムにはジャズマンが多数参加しています。とくにジャコとラリー・カールトン(ギター)の存在感は突出しています。今の耳で聴くと、それらは「ジャズ」といっていいサウンドではないでしょうか。
(2)スティング『ブルー・タートルの夢』(A&M)
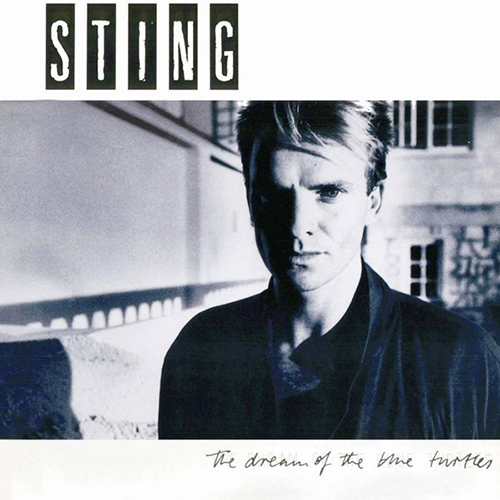
スティング『ブルー・タートルの夢』
演奏:スティング(ヴォーカル、ギター)、ブランフォード・マルサリス(ソプラノ&テナー・サックス)、ケニー・カークランド(ピアノ、キーボード)、ダリル・ジョーンズ(ベース)、オマー・ハキム(ドラムス)、ほか
発表:1985年
ブランフォードとケニーは当時大注目の新進ジャズマン。ダリルはマイルス・デイヴィスのグループ、オマーはウェザー・リポートを経ての参加。翌年リリースのライヴ盤『ブリング・オン・ザ・ナイト』(A&M)ではよりジャズ度の高い(というかジャズ)演奏が展開されています(サブスクでは、一部楽曲が未収録で残念)。
いずれも、ジャズマンの参加がそのサウンドを決定づけています。ジャズマンの「個性」を重視していることは音楽を聴けば明白です。その姿勢はジャズともいえるものですし、当然ながら出てきた音のジャズ濃度はたいへんに高いといえます。
ただ、ジャズマンが参加すればそうなるかというと、必ずしもそうではない場合もあります。ここで紹介するのはオルネラ・ヴァノーニ(Ornella Vanoni)が1986年にリリースしたアルバム『愛を歌う…』。オルネラは34年イタリア、ミラノ生まれ。イタリアン・ポップスを代表する歌手のひとりで、60年代に多くのヒットがあり、70年の「逢いびき」は最大のヒット曲で、73年のイタリア・フランス合作映画『ビッグ・ガン』や、2004年のアメリカ映画『オーシャンズ12』で使われているほどです。
(3)オルネラ・ヴァノーニ『Ornella &…』(CGD)

オルネラ・ヴァノーニ『Ornella &…』
演奏:オルネラ・ヴァノーニ(ヴォーカル)、参加ミュージシャンは下記参照。
発表:1986年
初発売当時はLP2枚組の大作でしたが、イタリアではヒット・チャートの6位にまでなりました。オルネラは現在までに50枚以上のアルバムをリリースしている、イタリアの国民的シンガーなのです。
この『愛を歌う…』はかつてリリースされた日本盤のタイトルで、原題は『Ornella &…』。つまり「オルネラと誰か」の共演というのがテーマなのですが、これがすごいのです。バックはみんなジャズマンでしかもトップクラス。ジャズ界隈で1枚のアルバムにこれだけの顔ぶれが揃っているのはちょっと例がありません。
マイク・アベネ(ピアノ、アレンジ)が中心となり、そこに集結したのはハービー・マン(フルート)、マイケル・ブレッカー(テナー・サックス)、ランディ・ブレッカー(トランペット)、クリス・ハンター(アルト・サックス)、リー・コニッツ(アルト・サックス)、ハービー・ハンコック(ピアノ)、ギル・エヴァンス(ギル・エヴァンス)、ジョージ・ベンソン(ギター)、ジョン・バシーリ(ギター)、ロン・カーター(ベース)、トム・バーニー(ベース)、スティーヴ・ガッド(ドラムス)、ジョーイ・バロン(ドラムス)などなど。
このメンバーが入れ替わり立ち替わり全20曲やっているのですが、驚くのは出来上がった音楽が「まるでジャズじゃない」こと。これだけのジャズマンのバックにもかかわらず、オルネラはイタリアン・ポップスの女王のスタイルを少しも崩すことなく、自身の歌唱を披露しています。一方、ジャズマンのほうはというと、「どうして?」となるくらい、みなジャズ濃度が薄く感じられるのです。というわけで、ジャズを聴くということではお勧めしませんが、ここでは「オルネラ&」とはいうものの、主役オルネラの世界を作ることが、参加ミュージシャンの最大のミッションなのですね。ジャズは「俺が俺が」の音楽ではありますが、これもできることが「演奏の上手さ」なのです。豪華ジャズマンとみるよりは、一流スタジオ・ミュージシャンの立ち位置というべきですね。
そんな中、ひとりだけ「ジャズ」をまきちらしているのがリー・コニッツ。さすが孤高のインプロヴァイザー。それもギル・エヴァンスとともに歌伴なんて(ふたりのデュオ・アルバムはありましたが)、いったいどういういきさつだったのか。いろんな面で「ジャズでは聴けない」ジャズマンのスーパー・セッションなのでした。
文/池上信次
フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。先般、電子書籍『プレイリスト・ウィズ・ライナーノーツ001/マイルス・デイヴィス絶対名曲20 』(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz/)を上梓した。編集者としては、『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『小川隆夫著/伝説のライヴ・イン・ジャパン』、『村井康司著/あなたの聴き方を変えるジャズ史』(ともにシンコーミュージックエンタテイメント)などを手がける。