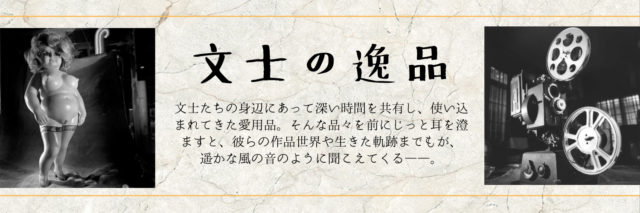
◎No.19:川端康成の土偶

川端康成の土偶(撮影/高橋昌嗣)
文/矢島裕紀彦
「深夜の中空に一つ冴えている、鬼気をおびた寒月の光」
川端康成をそうたとえたのは、中山義秀であった。幅も厚みもある文壇交遊、周囲に見せるさりげない温情の奥に、孤独な魂を持していた。
もの心つくかつかぬかの幼児期に父母を亡くし、続いて姉や祖父母にも先立たれ、満十五歳を目前にして孤児となる寂しい来歴。実質的な処女作『十六歳の日記』は、最後の肉親である祖父の死を看とった記録だった。
そこには、尿を受ける溲瓶(しびん)の底に谷川の清水の音を聞く、といった場面も描かれる。後年の康成作品に通じる、酷薄なほどの直視と、醜なるものを美に昇華させていく感覚が、すでに宿っているのである。
よく晴れた新春の一日、鎌倉の居宅跡の川端康成記念会を訪れ、康成遺愛の土偶と対面した。
ハート型の顔面。細く横に伸びた目。大きな鼻と、棒線状の鼻孔。欠け残った左胸のとがりが「女」という性別を示し、体部の文様から縄文期、紀元前2000年ころの国内産という出自が特定されている。
一見、なんともユーモラスな姿形。だが、康成の目線を借りて凝視すれば、幽玄の時を超えて今ここにある土偶に、「女のなまめかしさ」や「滅びの美学」までも感じとることができる。
文/矢島裕紀彦
1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。『サライ.jp』で「日めくり漱石」「漱石と明治人のことば」を連載した。
写真/高橋昌嗣
1967年桑沢デザイン研究所 グラフィックデザイン科卒業後、フリーカメラマンとなる。雑誌のグラビア、書籍の表紙などエディトリアルを中心に従事する。
※この記事は、雑誌『文藝春秋』の1997年7月号から2001年9月号に連載され、2001年9月に単行本化された『文士の逸品』を基に、出版元の文藝春秋の了解・協力を得て再掲載したものです。




































